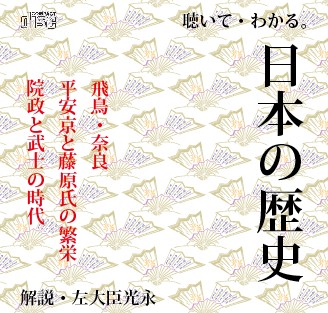風姿花伝第二 物学(ものまね)条々
原文
物まねの品々、筆に尽くしがたし。さりながら、この道の肝要なれば、その品々を、いかにもいかにもたしなむべし。およそ、なに事も残さず、よく似せんが本意なり。しかれども、また、事によりて、濃き淡(うす)きを知るべし。
まづ、国王・大臣より始め奉りて、公家の御たたずまひ、武家の御進退(ごしんだい)は、及ぶべき所にあらざれば、十分ならん事かたし。さりながら、よくよく言葉を尋ね、品を求めて、見所(けんじよ)の御意見を待つべきをや。
その外、上職の品々、花鳥風月の事わざ、いかにもいかにも細かに似すべし。田夫・野人の事に至りては、さのみに細かに卑しげなるわざをば似すべからず。仮令(けりやう)、木樵(きこり)・草刈・炭焼・汐汲(しほくみ)などの、風情にもなりつべきわざをば、細かにも似すべきか。それよりなほ卑しからん下職(げしよく)をば、さのみには似すまじきなり。これ、上方(じやうほう)の御目に見ゆべからず。もし見えば、あまりに卑しくて、面白き所あるべからず。
この宛(あ)てがひを、よくよく心得べし。
現代語訳
能の演技の種類について、文章で説明し尽くすのは難しい。しかしながら、申楽の世界では最も大切なことで、その各種類についてよくよく工夫し練習しなければならない。だいたい、なにごとをも写実的に演じるのが本来のやり方である。しかし、また、演技の種類によっては細部まで徹底的に似せるか、簡単に似せるかの使い分けをする必要があるということを知っておくこと。
まず、かしこくも天皇や大臣をはじめ、貴族の方々のご様子や、高位の武家方の立ち居振舞は、下々の我々には想像することもできないので、十分に似せる事は難しい。しかしながら徹底的に言葉遣いや行動様式を研究した上で演技を組み立て、観客のご批評をうかがうがよかろう。
そのほか、高位の方々の物まね、花鳥風月に事寄せた詩歌管弦などのことは、おおいに具体的に似せるがよい。農夫や無位無冠の民衆のこととなると、むやみに詳しく卑賎な生活や仕事を再現してはならない。たとえば、樵・草刈り・炭焼き・汐汲みなどの、風情を感じる演技になる仕事の様子などは、詳しくその様子を真似る必要があります。しかし、それら以下の卑しい職業については、やたらに詳しく似せてはならない。そういうことは、貴人のご鑑賞に備えるべきではないからである。もしもお目に掛ければ、あまりに下品で面白い所がなく感興を催されるどころではなくなってしまう。
以上、真似る度合いの案配を、十分注意しておかねばならない。
語句
■物学-漢字書きは巻名のみで使用し、ふつうは「物まね」と表記するのが、世阿弥の語例。「物まね」とは、能の演技の事で、ある人物に扮してその役を演じることを言うが、現代の「物真似」とは相違し、滑稽の要素は無い。■肝要-最も大切なこと。最も必要なこと。■たしなむ-工夫し練習すること。心がけること。■本意-ここは本来のあり方の意。■事によりて濃き淡きを-物まねの内容により、演技の程度に差があること。■たたずまひ-姿。様子。■御進退-立ち居振る舞い■言葉を尋ね、品を求めて-言葉使いや行動様式を調査すること。■見所-見物席、転じて観客の事。ここはかなり身分の高い観客を想定した文言。■見所の御意見を待つべきをや-見物衆の御批判を待つがよろしかろう。■をや-『風姿花伝』序にも見える、婉曲(えんきょく)的な言い回し<遠回しな言い方>。■上職の品々-高貴な人の身分職業。■花鳥風月の事わざ-自然の美しい風物にこと寄せた詩歌管弦などの遊び。■細かに-具体的に。■田夫-農夫。■野人-いなかの人。礼儀作法もわきまえない人。また、教養のない人。ぶこつもの。■わざ-仕事。また、姿や振舞。■仮令-たとえば。仮に。よしんば。■木樵(きこり)・草刈・炭焼・汐汲(しほくみ)-いずれも和歌の題材になる職業。■風情にもなりつべきわざ-見所のある所作(1.しわざ。ふるまい。身のこなし。2.踊り。)・演技。■卑しからん下職-和歌の題材にも成り得ない、より卑賎な職業。ただし登場を禁じたわけではなく、乞食となった老婆小町を描く<卒塔婆小町>のような作品もある。■上方-貴人。■見ゆ-他動詞で「見す」と同じ。■御目に見ゆべからず-お目にかけてはいけないものである。■宛てがひ-物まねの濃淡の案配。まねる度合いの見当。
原文
女
およそ、女がかり、若き為手(して)のたしなみに似合ふ事なり。さりながら、これ、一大事なり。
まづ仕立(したて)見苦しければ、さらに見所なし。女御(にようご)・更衣(かうゐ)などの似せ事(ごと)は、たやすくその御振舞(おんふるまひ)を見る事なければ、よくよくうかがふべし。衣(きぬ)・袴(はかま)の着様(きやう)、すべて私ならず。尋ぬべし。
ただ世の常の女がかりは、常に見慣るる事なれば、げにはたやすかるべし。ただ衣・小袖(こそで)の出立(いでたち)は、おほかたの体、よしよしとあるまでなり。
舞・白拍子(しらびようし)、または物狂(ものぐるひ)などの女がかり、扇にてもあれ、かざしにてもあれ、いかにもいかにも弱々と、持ち定めずして持つべし。
衣・袴などをも長々と踏み含(くく)みて、腰・膝(ひざ)は直(すぐ)に、身はたをやかなるべし。顔の持ち様(やう)、あをのけば見目悪(みめわろ)く見ゆ。うつぶけば後姿悪し。さて、首持ちを強く持てば、女に似ず。いかにもいかにも袖の長き物を着て、手先をも見すべからず。帯などをも弱々とすべし。
されば、仕立をたしなめとは、かかりをよく見せんとなり。いづれの物まねなりとも、仕立悪くてはよかるべきかなれども、ことさら女がかり、仕立を以(も)て本とす。
現代語訳
そもそも女の演技は、若い役者が稽古するのに適当である。若い役者に適当だというと、簡単に思うかもしれないが、これが、なかなか難しい。
まず、扮装がみっともないと、まったくよいところがない。最も幽玄な女御・更衣などの貴婦人の真似事は、申楽者ふぜいでは宮中奥深く婦人たちの生活をのぞき見することはできないから、よくよく調査研究して真似るがよい。宮中の夫人は衣や袴の着方についてもすべてきちんとした決まりがあるので勝手にはできないからよく問いただすことだ。
ただ世間一般の女子の姿は、常に見慣れていることであるから、その扮装を真似るのは、まことに容易であろう。ただ、ほぼすべての女姿の衣や小袖の扮装は、まずまずの風情がある程度でよい。曲舞(くせまい)舞や白拍子、または狂女の演技は、扇でも、そのほかの持ち物であっても、なんとしても柔らかに、握りしめたりせず持つのがよい。衣や袴なども長々と裾長に着て、腰や膝はまっすぐにし、体つきはしとやかでなければならない。
顔の角度は、上を向けば不器量に見える。うつむくと、背中が丸くなって後姿がよくない。そうかといって、顎を引きすぎると、女には見えない。なるたけ袖の長いものを着て、手先も見せてはならない。帯なども弱々しげに締めるがよい。
さて、扮装を工夫せよとは、姿を美しく見せよという意味である。どんな役になろうとも、扮装が悪くてはいいはずがないけれども、特に女姿については扮装を第一とするのである。
語句
■女がかり-女の演技様式。女姿。■たしなみ-稽古。実演。■一大事-非常にむつかしいこと。■仕立-扮装。身ごしらえ。■見所-見た目の魅力。■女御(にようご)・更衣(かうゐ)-貴人の女性(天皇に近接する女官)の服装。■似せ事-物まね・演技の事だが、実質的には演技の対象となる人物の扮装が中心。■うかがふ-調査・研究すること。■私ならず-きちんとした方式があるのをゆるがせにしてはならない。勝手にできない。着用の次第(きまり)がある。■小袖-袖口の狭い下着。それを上着として着用することが室町時代に一般化。■おほかたの体-ほぼすべての扮装。■よしよしとあるまでなり-まずまずであればよい。なんとなく趣がある程度でよい。■舞-曲舞(くせまい)の女芸人のこと。曲舞は南北朝時代に流行した歌謡に合わせて立って舞う芸能で、観阿弥もこれを得意とした。■白拍子-平安末期に起こり、流行した女流の歌舞。ここはそれを舞う遊女のこと。■物狂-狂人のことだが、能では芸人の意もある。愛別離苦に狂乱して、旅芸人に身をやつした人物として描かれることが多い。■扇-能の登場人物が必ず携える持ち物。■かざし-手に持った花の枝や榊の枝など。■持ち定めずして持つべし-やんわりと持つがよい。■踏み含みて-裾長に足先が隠れるほどに着ること。■たをやか-美しくしとやかなこと。■見た目悪く-器量・見た目がよくない。■さて-そうかといって。■首持ちを強く持てば-首の据え方で、顎を引きすぎることを警告したもの。■かかり-ここでは姿の美しさをいう。■よかるべきかなれども-よいというはずはないけれども。
原文
老人
老人の物まね、この道の奥義なり。能の位(くらゐ)、やがてよそ目にあらはるる事なれば、これ第一の大事なり。
およそ、能をよきほど極めたる為手も、老いたる姿は得ぬ人多し。たとへば、木樵(きこり)・汐汲(しおくみ)のわざ物などの翁形をし寄せぬれば、やがて上手と申す事、これ誤りたる批判なり。冠(かぶり)・直衣(なをし)・烏帽子(えぼし)・狩衣(かりぎぬ)の老人の姿、得たらむ人ならでは似合ふべからず。稽古の功入りて、位上らでは似合ふべからず。また、花なくば面白き所あるまじ。
およそ、老人の立振舞、老いぬればとて、腰・膝をかがめ、身をつむれば、花失(う)せて、古様(こやう)に見ゆるなり。さるほどに、面白き所稀(まれ)なり。ただ、おほかた、いかにもいかにもそぞろかで、しとやかに立ち振舞ふべし。
ことさら、老人の舞がかり、無上の大事なり。花はありて年寄りと見ゆるる公案、くはしく習ふべし。ただ、老木に花の咲かんがごとし。
現代語訳
老人の物まねは、申楽道の奥義である。能芸の実力が、そのまま外形に現れるものだから、老人の物まねは一番難しい。
だいたいにおいて、能をかなりの程度に習熟した役者であっても、老人の芸をうまくやれない人が多い。たとえば、木こりや汐汲みなどが登場するわざのいる作品の老人の姿を一通りやってみせると、すぐに上手とほめるのは、これこそが誤った批評である。冠・烏帽子・狩衣の老人の姿は奥義を体得した人でなくては演じられないだろう。稽古の経験を多く積んで、芸の格が上がらなくては似合うはずがない。また、芸に魅力がなければ、老人の物まねは面白くない。
そもそも、老人の立ち居振舞について、年老いたからといって、腰や膝をかがめ、体をちぢこませると、魅力は無くなり、古くさく見えるものである。したがって、面白い所は多くはない。ただ、だいたいにおいて、決してもじもじそわそわせず、しとやかに演じるのがよい。
とりわけ、老人の舞姿は、このうえなく難しいものである。芸の魅力を感じさせつつも、年寄りと見えるよう工夫すべき研究題目であり、詳しく研究せねばならない。たとえて言えば、枝葉の無い老木に花を咲かせるようなものである。
語句
■奥義-もっとも大事なもの。■能の位-芸の品等。■やがて-すぐにそのまま。■よそ目-観客の目。■よきほど極めたる為手-かなりの程度に習熟した役者。■得ぬ人-体得していない人。■わざ物-わざのいる曲。■翁形-老人姿。■し寄せぬれば-やりおおせると。一通りやってみせると。■冠・直衣-貴人の正装。実際には神体などの場合か。■烏帽子・狩衣-貴人の略装。■功-年功。経験。■花-見物人が美しいと感じる舞台効果。■立ち振舞-演技。■つむれば-かがめれば。■古様-古くさいこと。古風。観阿弥が新しく始めた新風申楽に対して、古風なやり方。卑近な写実的な所作を誇張して演じた滑稽申楽のやり方を古風という。■そぞろかで-落ち着いて。■舞がかり-舞の演技。■見ゆるる-「見ゆ」の連体形の慣用表現。■公案-禅語。工夫すべき研究課題の意。■老木-『別紙口伝』第三条参照。
原文
直面(ひためん)
これまた大事なり。およそ、もとより俗(ぞく)の身なれば、やすかりぬべき事なれども、ふしぎに、能の位(くらゐ)上らねば、直面は見られぬものなり。
まづ、これは、仮令(けりやう)、その物その物によりて学ばん事、是非なし。面色をば似すべき道理もなきを、常の顔に変へて、顔気色をつくろふ事あり。さらに見られぬものなり。
振舞・風情をばその物に似すべし。顔気色をば、いかにもいかにも己(おのれ)なりに、つくろはで直(すぐ)に持つべし。
現代語訳
直面(ひためん)でやる申楽もまた難しい。そもそも、直面物は真似る対象がたいてい俗人であるから、俗人である役者にとって、易しいはずであるが、不思議なことに、芸が上手でない役者が演じる直面は見られたものではない。
だいたい、この直面の能は、演じる役柄それぞれについて真似てゆくほかはない。顔の表情を似せる必要もないのに、いつもの表情を変化させて表情を作ることがあるが、これは、ますます見られたものではない。
演技・所作をそのものに似せるべきである。顔の表情は自分本来の顔のままで、特に作らず自然な表情を保つのがよい。
語句
■直面-仮面を着用せず、素顔で演じる事。役者が素顔で演じる現在身(生身)の成人男子の役以外は、すべて仮面をつけるのが能の原則。■俗-一般の成年男子のこと。能役者はもともと俗体の男なのだから、の意。■見られぬ-見ていられない。■仮令(けりやう)-だいたい。■その物その物-演じるべき役柄それぞれ■学ばんこと、是非なし-まねてゆくほかはない。■面色-顔の表情。顔つき。■顔気色をつくろふ-表情をつくること。■振舞・風情-演技・所作のこと。■己なりにつくろはで-自分本来の顔のままで。■直ぐに持つ-自然な表情を保つ。
原文
物狂
この道の第一の面白づくの芸能なり。物狂の品々多ければ、この一道に得たらん達者は、十方へわたるべし。くり返しくり返し、公案の入るべきたしなみなり。
仮令(けりやう)、憑物(つきもの)の品々、神・仏、生霊(いきりよう)・死霊(しりよう)の咎(とが)めなどは、その憑物の体を学べば、やすく、便りあるべし。
親に別れ、子を尋ね、夫に捨てられ、妻(め)に後(をく)るる、かやうの思ひに狂乱する物狂、一大事なり。よきほどの為手も、ここを心に分けずして、ただ一遍に狂ひはたらくほどに、見る人の感もなし。思ひゆゑの物狂をば、いかにも物思ふ気色を本意にあてて、狂ふ所を花にあてて、心を入れて狂へば、感も面白き見所も、定めてあるべし。かやうなる手柄にて人を泣かする所あらば、無上の上手と知るべし。これを心底によくよく思ひわくべし。
およそ、物狂の出立、似合いたるやうに出で立つべき事、是非なし。さりながら、とても物狂に言寄せて、時によりて、なにとも花やかに出で立つべし。時の花を挿頭(かざし)に挿(さ)すべし。
また曰(いは)く、物まねなれども、心得べき事あり。物狂は憑物の本意を狂ふといへども、女物狂などに、あるいは修羅闘諍(とうじやう)・鬼神などの憑く事、これ、なによりも悪(わろ)き事なり。憑物の本意をせんとて、女姿にて怒りぬれば、見所(みどころ)似合はず。女がかりを本意にすれば、憑物の道理なし。また、男物狂に女などの寄らん事も、同じ料簡(れうけん)なるべし。
所詮(しよせん)、これ体なる能をばせぬが秘事なり。能作る人の料簡なきゆゑなり。さりながら、この道に長じたらん書き手の、さやうに似合はぬ事を、さのみに書く事はあるまじ。
この公案を持つこと秘事なり。
また、直面の物狂、能を極めてならでは、十分にはあるまじきなり。顔気色をそれになさねば、物狂に似ず。得たる所なくて顔気色を変ゆれば、見られぬ所あり。物まねの奥義とも申しつべし。大事の申楽などには、初心の人、斟酌(しんしやく)すべし。直面の一大事、物狂の一大事、二色を一心になして、面白き所を花に宛てん事、いかほどの大事ぞや。よくよく稽古(けいこ)あるべし。
現代語訳
申楽の中で一番面白い芸である。物狂いの種類は多方面に渡るので、この道を極めた役者は、ほかのあらゆる分野の物まねでも通じることになろう。物狂いの稽古は繰り返し繰り返し工夫をこらさなければならない。
たとえば、色々な憑物、神・仏、生霊・死霊のたたりなどは、その憑物のすがたをまねてやれば、やりやすい手がかりがあるというものだ。
親と生き別れ、子供を探しもとめ、夫に捨てられ、妻に先立たれるなど、このような悲嘆の情によって狂乱する物狂いの演技は大変に難しい。かなり演技上手の役者でも憑物の故なのか悲嘆の故なのか判別せずに、ひたすら一本調子で狂乱の演技をするので観客の共感も得られない。悲嘆を原因とする物狂いの演技は、いかにも思いつめた様子を役作りの基調として、狂乱の場を見せ場として、登場人物の心理に分け入った狂乱の演技をすれば、観客の共感も、面白味も、きっと生じるであろう。こういう作品を巧みに演じて観客の涙を誘うような役者であれば、このうえない達人と認識すべきである。物狂いの演じ分けの極意をよくよく心のうちで分別せよ。
およそ物狂いの扮装は、演じる物狂いの種類に応じて、それに似合った扮装をするべきことは勿論である。しかしながら、いっそ物狂ということにかこつけて、たいそう華やかにに演じる方がよい場合がある。そういう場合は季節の代表的な花を髪に挿すのもよいだろう。
また言う。物まねとはいっても心得ておかなければならないことがある。物狂は憑物の本体の性格に応じて狂乱の演技をするとはいっても、女物狂など、あるいは修羅道に堕ちた怨霊の演技・鬼人などがついた物狂いはなによりも悪い。憑物の本体を表現しようとして、女姿の扮装で怒りを現せば、女は優しいものだと思っている見物客の思いなしに合わない。反対に女姿を基本に演じれば憑物の意味がなくなってしまう。また男物狂に女などが憑いてしまう設定も、同じように考えることができる。結局、この類の能は演じないのが秘訣である。能作家の無見識の結果、こんな能ができあがるのである。しかしながら、この道に長じた作者が、このように不相応なことを書くはずがない。
こうした考え方をすることが先ほど述べた秘伝なのである。
また、直面で演じる物狂の能は、能を極めた役者が演じるものでなければ満足できるものでない。何故かというと、顔つきをそれらしくしないと、物狂には見えない。
未熟な役者が顔つきを変えたりするのは見られたものではない。物まねのもっとも奥深い秘伝とも言うべきである。大切な申楽興業などでは、直面での物狂いの演技は初心者は遠慮すべきであろう。直面の難しさ、物狂いも難しい。直面で演じる物狂いは二つの難事を同時に解決し、しかも狂乱の場を面白い見せ場に仕立てて観客を引き付けるようとすることはどれほど難しい事であろうか。こうした演技をするにはよくよく稽古を重ねる必要がある。
語句
■面白づくの芸能-面白づくしの芸。面白さの限りをつくした芸。■物狂の品々-物狂の種類。■一道-一方向。■十方へわたるべし-あらゆる方面の芸に通暁(つうぎょう(すみずみまで非常にくわしく知ること))すること。■公案の入るべきたしなみ-工夫の必要な稽古の意。■憑物-霊などが憑依するもの。■咎(とが)め-たたり。■憑物の体-憑依したものの本体。■便り-面白く見せる手がかり。■体を学べば、やすく便りあるべし-姿をまねてやれば、やりやすい手がかりがあるというものだ。■ここを心に分けずして-憑物物狂か悲嘆で狂乱する物狂か分別せず。狂乱する原因をしかとつきとめないで。■一遍に狂ひはたらくほどに-どんな役でも一本調子に、狂乱の演技をすること。■思ひゆゑの物狂-愛別離苦の思いにより狂乱する狂人の役のこと。物思いがもとで起った物狂をば。■もの思ふ気色をば本意にあてて-悩みの様子をしんにしっかりとつかんでおいて。■狂ふ所を花にあてて-狂乱の場面を作品の山場に配当すること。■心を入れて-配慮・工夫して。■感-見物の感動・喝采。■手柄-技量。てぎわ。■是非なし-論はない。■とても-とてものことに。いっそのこと。■出立(いでたち)-扮装。■言寄せて-かこつけること。■時の花-季節の花。■挿頭に挿す-手に持つのではなく、髪の毛に挿すこと。■また云々-追記的な記事。■憑物の本意を狂う-憑物の本体の性格に応じて狂乱する意。■修羅闘諍-修羅道に堕ちた怨霊。■なにも-何でも。■怒り-狂乱など荒々しい演技をすることが「怒る」。■見所(みどころ)似合はず-見物の思いなしに合わない。
■寄らん-憑物が憑くこと。■同じ料簡なるべし-同じ考えでよい。同じであると理解してよい。■所詮-結局。つまるところ。■これ体なる-こういうような。同じ類の。■能をばせぬが云々-ここでいう「能」は分野名の「能楽」の意。■この道に長じたらん書き手-申楽の道に通暁した作者。作者として熟練している意味ではなく、能の上演に長じている意味であろう。■それになさねば-それらしくせねば。ここは以下の部分、「直面」の条の指摘とは矛盾する。■顔気色を変ゆれば-顔の表情を変えると。顔つきを変えると。■斟酌-遠慮。■二色を一心にして-二つの難事を同時に解決すること。
原文
法師
これは、この道にありながら、稀(まれ)なれば、さのみの稽古(けいこ)入らず。
仮令(けりやう)、荘厳(しやうごん)の僧正、ならびに僧綱(そうがう)等は、いかにも威儀(ゐぎ)を本として、気高き所を学ぶべし。それ以下の法体(ほつたい)・遁世(とんせい)、修行の身に至りては、抖櫢(とそう)を本とすれば、いかにも思ひ入りたる姿かかり、肝要たるべし。
ただし、賦物(ふしもの)によりて、思ひの外の手数(てかず)の入る事もあるべし。
現代語訳
法師の能は、物まねの中にあるにはあるが、僧が為手である能は少ないので、さほど稽古の必要はない。
仮に、美々しく正装した最高位の僧、並びに僧正・僧都・律師などの高位の僧の物まねは、いかにも作法にかなった服装・振舞を基本として、気品のある様子をまねればよい。それ以下の僧形とかただの世捨て人、修行者などの身分になると、乞食修行を本来の姿とするから、その行脚姿を手本にし、いかにも一途に思い入れ、仏道に向かおうとする姿や風情に見せることが肝要である。
ただし、物まねの対象によっては、思いのほか手の込んだ演技を必要とする場合があろう。
語句
■この道にありながら-物まねの中にあるにはあるが。■稀-僧が為手である能は少ない。■荘厳の僧正-美々しく正装した最高位の僧。■僧綱-僧正・僧都・律師などの高位の僧。■威儀-作法にかなった服装・振舞。■法体-僧のこと。■遁世-寺院に帰属せず、極楽往生を目指して世間を逃れ、修行している者。■抖(と)そう-衣食住の欲望を去るための心身の修行。行脚のこと。煩悩を振り払う。■思ひ入りたる-一途に思いつめる。■姿かかり-扮装と様子。■賦物-作品の主題。物まねの対象。■手数-演技の数々。
原文
修羅(しゅら)
これ又、一体のものなり。よくすれども、面白き所稀(まれ)なり。さのみにはすまじきなり。
ただし源平などの名のある人の事を、花鳥風月に作り寄せて、能よければ、何よりもまた面白し。これ、ことに花やかなる所ありたし。
これ体なる修羅の狂ひ、ややもすれば、鬼の振舞いになるなり。それも、曲舞(くせまひ)がかりあらば、少し舞がかりの手づかひ、よろしかるべし。
弓・箙(えびら)を携(たづさ)へて、打物(うちもの)を以(も)て厳(かぎり)とす。その持ち様・使い様をよくよくうかがひて、その本意をはたらくべし。
あひかまへてあひかまへて、鬼のはたらき、また舞の手になる所を用心すべし。
現代語訳
これも又、物まねの一分野である。しかし上手に演じたとしても、面白い場面は少ない。従って普通にはむやみに演じてはならない。
ただし、源氏や平家の名のある武将の事を自然の美しさに関連付けて作詞し、作品として出来上がり、それが良ければ、何よりも又面白いものである。こうした能には、ことに華やかな場面があった方がよい。
修羅能で、修羅道の苦しみを演じる狂乱の演技は、ややもすると鬼の演技になってしまう。そんな場合でも、作品中に曲舞風の謡があれば、それに合わせて多少は舞踊的な演技があっても悪くない。
修羅の扮装は、弓・箙を携えて、太刀を持って飾りとする。その武器の持ち様・使い様をよくよく調査・研究し、その武器本来の使い方で演技しなければならない。
よくよく気をつけて、鬼の演技と同じになったり、また舞の所作になったりする、その境目に、注意せねばならない。
語句
■修羅-帝釈天との戦闘に明け暮れる。阿修羅王の世界。ここは、修羅道に堕ちて苦しむ亡者を指す。■一体のもの-一風体のもの。一分野。■よくすれども云々-上手に演じても。鬼の場合と同様の扱い。■源平などの名ある人-『平家物語』に登場する源氏や平氏の著名な武将。■花鳥風月に作り寄せて-自然美にかこつけて。■能よければ-作品がよければ。■これ-源平などの名将に取材した修羅の、狂乱の演技。物狂いも修羅も鬼も、すべて「狂い」という演技が共通していたらしいが、「面白きところまれ」な修羅を度外視した文言。■鬼の振舞-鬼の演技。■舞の手-舞踊の所作。■曲舞-曲舞音曲の謡。いわゆる「クセ」と呼ばれる部分、それに合わせて舞うわけである。■弓・箙(えびら)-弓と箙(矢を入れて背に負う道具)。現在では弓は持たぬ場合が多い。■打物-太刀。長刀(なぎなた)も打物だが、世阿弥時代初期にシテが長刀を持つ能の例未見。■巌(かぎり)-装飾の意だが、文字使いが特異。■うかがひて-調査・研究すること。■その本意をはたらくべし-その武器本来の正しい使い方で演技すること。
原文
神
およそ、この物まねは鬼がかりなり。なにとなく怒れるよそほひあれば、神体によりて、鬼がかりにならんも苦しかるまじ。ただし、はたと変れる本意あり。神は舞がかりの風情によろし。鬼には更に舞がかりの便りあるまじ。
神をば、いかにも神体によろしきやうに出(い)で立ちて、気高(けたか)く、ことさら、出物(でもの)にならでは神といふ事はあるまじければ、衣装(いしやう)を飾りて、衣文(ゑもん)をつくろひてすべし。
現代語訳
たいたいにおいて、この物まねは鬼系列の演技である。どことなく荒ぶる様子があるので、神の性質によっては、鬼風になっても問題はあるまい。ただし、まったく異なる本質がある。神は舞踊系の演技に向いている。鬼にはまったく舞踊系の演技の手がかりはない。
神を、なるべく神姿にふさわしいように扮装して、気高く、とりわけ舞台上の登場人物以外には、神というのは現実に姿を現すはずがないので、衣装を飾り、衣服が着崩れしないようにきちんと着付けをして演じるべきである。
語句
■鬼がかり-鬼能の演技様式。■なにとなく怒れるよそほひ-どことなく荒ぶる雰囲気。神という存在のイメージを言ったもの。■神体-神の姿。軍神でもある住吉明神が、老体の鬼神面である悪尉(あくじょう)<面の一。強く恐ろしい表情をした尉(老翁)の面。多く老神・怨霊 (おんりょう) などに用いる。 >の面で登場する。「住吉の遷宮の能」■風情-演技。所作。■神体によろしきように-神姿にふさわしいように。■出立て-扮装して。■出物-舞台に登場する霊的な役柄。単に登場人物の意にも用いる語。■衣文をつくろひ-きちんと着付けをして。
原文
鬼
これ、ことさら大和(やまと)のものなり。一大事なり。
およそ、怨霊(をんりやう)・憑物(つきもの)などの鬼は、面白き便りあれば、やすし。あひしらひを目がけて、細かに足・手をつかひて、物頭(ものがしら)を本にしてはたらけば、面白き便りあり。
まことの冥途(めいど)の鬼、よく学べば恐ろしきあひだ、面白き所、更になし。まことは、あまりの大事のわざなれば、これを面白くする者、稀(まれ)なるか。
まづ、本意は、強く恐ろしかるべし。強きと恐ろしきは、面白き心には変はれり。
そもそも鬼の物まね、大きなる大事あり。よくせんにつけて、面白かるまじき道理あり。恐ろしき所、本意なり。恐ろしき心と面白きとは、黒白の違ひなり。されば、鬼の面白き所あらん為手は、極めたる上手とも申すべきか。さりながら、それも、鬼ばかりをよくせん者は、ことさら花を知らぬ為手なるべし。されば、若き為手の鬼は、よくしたりとは、見ゆれども、更に面白からず。鬼ばかりをよくせん者は、鬼も面白かるまじき道理あるべきか。くはしく習うべし。ただ、鬼の面白からむたしなみ、巌(いはほ)に花の咲かんがごとし。
現代語訳
これは、大和申楽が最も得意とする芸で、もっとも難しい物まねである。
だいたい、怨みを抱えた怨霊や憑物などの鬼の演技は、面白く演じる手がかりがあるので容易である。相手役に向かって、、細かに足踏みと身振りをして、頭にいただいたかぶり物の種類に応じて動作をすれば、それが面白く演じる手がかりとなる。
本当の地獄の鬼は、そっくりまねると恐ろしいものだから、見世物としてはまったく面白くない。ほんとうは、あまりにむずかしい芸なので、これを面白く演じることができる役者は少ないのだ。
まず、地獄の鬼の本質は、強く恐ろしいものであるとするべきである。強さと恐ろしさというのは面白さとは異なるものである。
そもそも鬼の物まねは、大変難しいものである。上手に演じようとすればするほど、面白くないのである。鬼は恐ろしいのが本質である。恐ろしさと面白さとは正反対の違いがある。それで、鬼が面白く演じられるような役者は、この道を極めた上手と言えるであろう。しかし、そうはいっても、鬼ばかりを上手に演じる者は、とりわけ芸の魅力の何たるかを知らぬ役者であろう。さて、若い役者の演じる鬼は、上手に演じているように見えても、なおさら面白くない。鬼だけをうまくこなすような役者が、鬼をやっても面白いはずがない。微に入り際に渡って稽古せよ。要するに、鬼が面白くできるような稽古の心得は、大岩に花が咲くようなものであろう。
語句
■大和のものなり-観阿弥の得意芸であったことを示唆するか。■怨霊・憑物-妄執を抱えてこの世に出現する亡者。幽霊として登場する場合と、憑物の形で表現される場合とがある。■面白き便り-面白く演じる手がかり。■あひしらひ-相手役。ワキやツレなど。■細かに云々-精細に足踏みを繰り返すのが、砕動風鬼(形は鬼でも心は人間であるように演じること。身心に力を入れず、軽やかに細かく身を動かす。)の演技の特色で、ここはそれに近い演技様式か。■足・手を使ひて-足踏みと身振りをして。■物頭-頭に被る仮髪や、冠の台に装着する鬼畜を表す飾り物のことか。■まことの冥途の鬼-亡者を責める地獄の冥官。こちらは後年の力動風鬼(姿も心も鬼人で、亡者を呵責する役)にほぼ対応するらしい。■本意-鬼の本質。■面白き心-面白さ。面白いということ。■大きなる大事-「一大事」、「第一の大事」、「いかほどの大事」などと同じ言い回しか。■黒白の違いなり-正反対であること。■たしなみ-ここは、稽古というより工夫の意か。■巌に花の咲かんがごとし-恐ろしさと美しさが共存する、珍しさの例え。岩に根付いた桜の花とも、岩に降り敷く雪を花に見立てたとも考えられる。
原文
唐事(からごと)
これは、およそ、格別(かくべち)の事なれば、定めて稽古(けいこ)すべき形木(かたぎ)もなし。ただ、肝要、出立(いでたち)なるべし。また、面をも、同じ人と申しながら、模様の変はりたらんを着て、一体異様(いつていいやう)したるやうに、風体を持つべし。功(こう)入りたる為手(して)に似合ふものなり。ただ、出立を唐様(からやう)にするならでは、手立(てだて)なし。なにとしても、音曲もはたらきも、唐様といふ事は、まことに似せたりとも、面白くもあるまじき風体なれば、ただ一模様心得んまでなり。
この、異様したると申す事など、かりそめながら、諸事にわたる公案なり。何事か異様してよかるべきなれども、およそ唐様をば何とか似すべきなれば、常の振舞に風体変はれば、何となく、唐びたるやうによそ目に見なせば、やがてそれになるなり。
おほかた、物まねの条々、以上。この外、細かなる事、紙筆に載せがたし。さりながら、およそ、この条々をよくよく極めたらん人は、おのづから細かなることをも心得べし。
現代語訳
中国人の物まねは、だいたい特別の演目なのでこうと決めて稽古する形というものはない。ただ、大事なのは、その扮装である。また、面においても唐人も我々と同じ人間とはいいながら、日本人とは異なるデザインの衣服を着て、どこかひとところ、普通と違う印象を与えるように唐人風を演じるがよい。
経験を積んだ役者に似合う物まねである。ただ、扮装を中国風にするほかは、方法はない。なにとしても、音曲も所作も中国風に似せて演じても、面白いはずもない姿なので、ただ一点の雰囲気上の工夫を心がけておけばいいのである。
この普通と違う印象を与えるということなどは、かりそめにも、万事に応用可能な工夫である。どんなことでも普通と違えるのはいいはずはないのだが、そもそも、中国風というのを似せても無意味なのであるから、ふつうと姿が変わっていて、何となく中国風に見せれば、やがて観客にはそのように映るものである。
だいたいのところ、物まねの心得は以上である。詳しい事は紙筆では言い尽くせないが、だいたい、この心得をよく研究して達人になった人は、おのずと細かな点も会得してしまうものである。
備考・補足
■唐事-中国人の物まね。中国種の能は少なくない。■格別なこと-特殊なこと。■定めて-こうと決めて。■形木-印刷のための版木のこと。転じて、稽古の見本・規範。■肝要-大事なのは、の意。■同じ人と申しながら-同じ人間とはいいながら。■模様-様子。デザイン。着物の図案ではあるまい。■一体(いってい)-ひとところ。■
異様したる-異装をした。■風体を持つ-能を演じること。■功入りたる為手-ベテランの役者。様々な紛争の経験を生かせるためか。■唐様(からよう)-中国風。■手立て-方法。■一模様-一体とほぼ同じ意味。一点。■常の振舞に風体変はれば-普通の能の時の演技と姿が変わっていること。■何事か云々-反語体や確定条件文を圧縮してたたみかける、世阿弥の文体の特色の一つ。■唐びたるやうに-中国めいている。■よそ目-観客の目。
原文
(結語)
おほかた、物まねの条々、以上。この外、細かなる事、紙筆に載せがたし。さりながら、およそ、この条々をよくよく極めたらん人は、おのづから細かなることをも心得べし。
現代語訳
だいたいのところ、物まねの心得は以上である。詳しい事は紙筆では言い尽くせないが、だいたい、この心得をよく研究して達人になった人は、おのずと細かな点も会得してしまうものである。
備考・補足
<参考文献>
・風姿花伝・三道 現代語訳付き 世阿弥・竹本幹夫訳注
・花伝書(風姿花伝) 世阿弥編 川瀬一馬校注、現代語訳
・風姿花伝 世阿弥編 野上豊一郎・西尾実校訂
・現代語訳 風姿花伝 世阿弥著 水野聡訳
・風姿花伝 世阿弥 現代語訳:夏川賀央
前の章「第一 年来稽古条々(ねんらいけいこでうでう)」|次の章「風姿花伝第三」