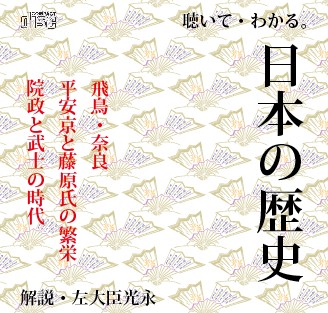風姿花伝第三 問答条々
■【古典・歴史】メールマガジン
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
原文
問答条々(1)
問ふ。そもそも申楽(さるがく)を始むるに、当日(たうにち)に臨んで、まづ座敷を見て、吉凶をかねて知る事は、いかなる事ぞや。
答ふ。この事、一大事なり。その道に得たらん人ならでは心得べからず。
まづ、その日の庭を見るに、今日は能よく出(い)で来べき、悪(あ)しく出で来べき、瑞相あるべし。これ、申しがたし。しかれども、およその料簡(れうけん)を以(も)て見るに、神事(じんじ)、貴人(きにん)の御前(ごぜん)などの申楽に、人群集(くんじゆ)して、座敷いまだ静まらず。さるほどに、いかにもいかにも静めて、見物衆(けんぶつしゆ)、申楽を待ちかねて、数(す)万人の心一同に、遅しと楽屋を見るところに、時を得て出でて、一声(いっせい)をも上(あ)ぐれば、やがて座敷も時の調子に移りて、万人の心、為手(して)の振舞に和合して、しみじみとなれば、なにとするも、その日の申楽ははや良し。
さりながら、申楽は、御出(おんい)でを本とすれば、もし早く御出である時は、やがて始めずしてはかなはず。さるほどに、見物衆の座敷いまだ定まらず、あるいは後れ馳(ば)せなどにて、人の立ち居しどろにて、万人の心、いまだ能にならず。されば、左右(さう)なくしみじみとなる事なし。さやうならむ時の脇の能には、物になりて出づるとも、日ごろより色々と振りをもつくろひ、声をも強々(つよづよ)とつかひ、足踏みをも少し高く踏み、立ち振舞ふ風情をも、人の目にたつやうに生き生きとすべし。これ、座敷を静めんためなり。さやうならんにつけても、ことさら、その貴人の御心(みこころ)に合ひたらん風体をすべし。されば、かやうなる時の脇の能、十分によからん事、返すがへすあるまじきなり。しかれども、貴人の御意(ぎょい)にかなへるまでなれば、これ、肝要(かんえう)なり。なにとしても、座敷のはや静まりて、おのずからしみたるには、悪(わろ)きことなし。
されば、座敷の競(きほ)ひ後(おく)れを勘(かんが)へて見る事、その道に長ぜざらん人は、左右(さう)なく知るまじきなり。
また曰(いは)く、夜の申楽は、はたと変はるなり。夜は、遅く始まれば、定まりて湿るなり。されば、昼二番目によき能の体(てい)を、夜の脇にすべし。脇の申楽湿り立ちぬれば、そのまま能は直らず。いかにもいかにも、よき能をとくすべし。夜は、人音怱々(そうそう)なれども、一声にてやがて静まるなり。しかれば、昼の申楽は後(のち)がよく、夜の申楽は指寄(さしよ)りよし。指寄(さしよ)り湿(しめ)り立ちぬれば、直る時分左右(さう)なくなし。
秘儀に曰(いは)く、そもそも、一切は、陰陽(いんやう)の和(くわ)する所の境を、成就とは知るべし。昼の気は陽気なり。されば、いかにも静めて能をせんと思ふ工(たく)みは、陰気なり。陽気の時分に陰気を生ずる事、陰陽和する心なり。これ、能のよく出で来る成就の始めなり。これ、面白しと見る心なり。夜はまた陰なれば、いかにも浮き浮きと、やがてよき能をして、人の心花めくは、陽なり。これ、夜の陰に陽気を和する成就なり。されば、陽の気に陽とし、陰の気に陰とせば、和する所あるまじければ、成就もあるまじ。成就なくば、なにか面白からん。また、昼の内にても、時によりて、なにとやらん、座敷も湿りて寂(さび)しきやうならば、これ陰の時と心得て、沈まぬやうに心を入れてすべし。昼は、かやうに、時によりて陰気になる事ありとも、夜の気の陽に成らんこと、左右なくあるまじきなり。
座敷をかねて見るとは、これなるべし。
現代語訳
問。そもそも申楽興業を始めるのに、演技当日、まず会場を覗き見て、その日の公演の成否をあらかじめ予見するとはどういうですか。
答。これは大変難しい事だ。陰陽道-占いの分野に熟達した人でなけれわからないことだ。
まず、その日の観客席を覗いて見ると、今日は能がうまくいくか、うまくいかないかの前触れ現象を認識することができるはずである。これは言葉ではうまく説明できない。しかし、だいたいのところを推測してみると、神社の祭礼や身分の高い人の前で演じる能で、観客が大勢集まり、客席がなかなか静まらないことがある。そういう時には、出来る限り観客のざわめきを静めるべく、公演開始後、わざと為手の登場を引き延ばし、観客が能の進行を待ちかねて、全員の気持ちが一つになって、今か今かと楽屋の方を見るちょうどその時の、絶妙な瞬間を捉えて登場し、一声謡いあげると、そのまま会場もその場の音曲に魅了されて、全員の気持ちが主演者の演技と一体となり、能に集中する。そうなればもうどのよう演じようと、その日の公演は成功したも同然である。
しかしながら、申楽は貴人のご臨席を基本とするので、もし、早めにご隣席の場合はすぐに開演しなくてはならない。そういう場合は、観客たちはまだ着席しきっておらず、あるいは遅れて入場したりして、人がいつまでも立ったり座ったりと落ち着かず、全員の気持ちがまだ能に集中しきれない。それでなかなか見物席全体が静かにならないのである。
そういう時の最初の祝言能では、何かに扮して登場したとしても、いつも以上に色美しく身なりを飾って、声も大きく張り上げ、足踏みも少し高めに踏んで色々な所作も見物人の気をひきつけるように生き生きと演じるのがよい。これは皆、座敷を静めるためである。そうなった場合はなおのこと、その日の貴人の好みに合うような演能をするべきである。しかし、このような時の最初の能が十分にうまくいくということは、容易にないものだ。
しかしながら貴人のお気持ちに添うことが先決なのであるから、この心得が大切なのである。どんな場合でも、座敷が早く静かになって、自然に静まっていくのは悪い事ではない。こういうわけだから、観客の気が乗っているかいないかを考えてみることは、陰陽道に熟達した人でなくては、容易に知ることはできないのである。
もう一つ言うと、夜の申楽は昼のそれとはまったく違ったものになり、遅い時間に始まるので、静かで、沈みがちな雰囲気になるものである。だから、昼の二番目にやって丁度良い能の類を、夜の最初にやるが良い。最初の能が陰鬱な感じで始まってしまうと、そのまま会場の雰囲気は立ち直らないものだ。そこで、夜の催しでは、出来る限り、よい作品をキビキビとやるがよい。夜は観客席がざわめいていても、為手の登場の一声ですぐに静まってしまう。
要するに、昼の催しでは後半が良く、夜の催しでは前半が良いのである。最初に陰鬱な始まり方をすれば立ち直る機会はめったにない。
秘儀に言う。そもそも、すべての事で、陰陽和合する境地を成功と考えるべきである。昼の雰囲気は能動的な陽気である。これに対し、できる限り観客席の静まるのを待って能を演じようとするのは、受動的な陰の働きである。陽気の時間帯に陰気を発生させるのは、陰陽を調和させることである。これは演能を成功させるためのいとぐちでもあり、また観客が演能を面白いと思うのである。
夜は逆に、陰の時なのであるから、できるだけにぎやかに、すぐによい作品を演じて、観客の心が花やいで明るくなるのは陽の運気である。これは夜の陰に陽の働きを和合させて成功させるということだ。
したがって陽の気のある時期に陽気なことをし、陰の気のある時期に陰気なことをすれば、和合する所がなく、うまくいかないであろう。うまくいかないものがどうして面白かろうか。また、昼でも時間帯によっては、何かしらん、会場も湿っぽく寂しいようなら、これを陰の時と考えて、会場が沈みこまないようにしっかり気を入れてやるがよい。昼は、このように、時間帯によっては陰気になる事があっても、夜の雰囲気が陽に転じることは、なかなかないのである。
観客席を覗いてあらかじめ予見するというのは、このようなことであろう。
語句
■申楽-神事能や勧進帳などの猿楽の催し。■当日に臨んで-興業当日の開始直前になって。■座敷-観客席のこと。演能の会場全体。■吉凶-興業の成否。■かねて-(副)前もって。あらかじめ■その道-占いの分野。陰陽道。■庭-演能会場。演能の場。■能-ここは演能のことか。以下もほぼ同様。■瑞相-前兆。■申しがたし-言葉では説明できないこと。■料簡-考えて判断すること。■貴人の御前-必ずとも貴人主催の能とは限らず、神事能にも貴人の来臨はありえた。■静めて-観客席を静かにさせ。■いかにもいかにも-〔「いかにも」を重ねて強めた語〕どうにもこうにも。いずれにしても。 なるほど。そのとおり。 ■時を得て-その瞬間を捉えて。■時の調子-その時の調子。■はやよし-もう大丈夫。もはやしめたものだ。■一声をもあぐれば-一声謡いだせば。■時の調子-その時や時節にふさわしい音楽の調子。■和合して-一つになること。■さるほどに-その一方で。■定まらず-静まらない事。■しどろ- 乱雑なこと。■左右なく-たやすく。■能にならず-舞台に集中しないこと。■脇の能-翁の次に演じられる最初の能。■物になりて出づる-何かに扮して登場すること。曲中の人物になって登場すること。■日ごろより-いつも以上に。■振りをもつくろひ-動作を飾ること。身なりや所作を引き立つようにし。■足踏み-足の運び方。■立ち-演技の型。■風体-能のこと。■おのずからしみたるには-自然としみじみとなってきた場合には。■競ひ後れ-意気込みとしらけ。■また曰く-以下、増補とする説もある。後年の追記と言えるかどうかは微妙。■夜の猿楽は-明治以前は能は昼に演じるのが普通であったが、夜間に行われる催しも少なくなかった。■湿るなり-雰囲気が湿りがちになること。めいって湿っぽくなる。■利かすべし-きびきびと演ずべきである。■昼二番目に-次の条で脇能の必須条件を祝言の能であることとするのと整合しない所説。ただし第二条にも類似の説がある。■体(てい)-姿。■とくすべし-早い段階で演じるがよい。■人音怱々-観客席がざわついていること。■指寄り-はじめ。最初。■左右なくなし-簡単にはやってこない。■秘儀に曰く-秘伝を延べるときのことわり。特定の書物ではない。■陰陽-全宇宙の相反する二要素。この二気の和合が世界の調和を保つとするのが陰陽説。■和する-和合する。■成就-成功。■陽気の時分に陰気を生ずる事、陰陽和する心なり-以下、何らかの陰陽道の所説に基づく見解であろうが典拠不明。■はじめ-きっかけ。■面白しと見る心なり-(見物人が)面白いと感じる心のもとである。■花めく-華やぐ。■心を入れて-工夫すること。■左右なくあるまじきなり-決してないのである。■座敷をかねて見るとは云々-興業の成否を占うのが、「座敷をかねて見る」ことの実質。問に対応する結語。
原文
問答条々(2)
問ふ。能に、序破急(じよはきふ)をばなにとかさだむべきや。
答ふ。これ、やすき定めなり。一切の事(じ)に序破急あれば、申楽(さるがく)もこれ同じ。能の風情を以(も)て定むべし。
まづ、脇の申楽には、いかにも本説正しき事の、しとやかなるが、さのみに細かになく、音曲・はたらきもおほかたの風体にて、するすると、安くすべし。第一、祝言なるべし。いかによき脇の申楽なりとも、祝言欠けてはかなふべからず。たとひ能は少し次なりとも、祝言ならば苦しかるまじ。これ、序なるがゆゑなり。二番・三番になりては、得たる風体のよき能をすべし。ことさら、挙句急なれば、揉(も)み寄せて、手数(てかず)を入れてすべし。
また、後日(ごにち)の脇の申楽には、昨日(きのふ)の脇に変はれる風体をすべし。泣き申楽をば、後日などの中ほどに、よき時分を勘(かんが)へてすべし。
現代語訳
問い。能の催しに、序破急ということをどのように決めたらよいのでしょうか。
答え。これは簡単なことである。世の中のすべての事に序破急ということがあり、申楽についても同様だからである。申楽の場合は、能の曲の趣(おもむ)きによってそれを決めるがよい。
まず、最初に演ずる能には、出来る限り権威ある正統的な説話に典拠を求め、上品な内容ながら、むやみに手が込んでおらず、謡や所作もそれほど個性が強くない能を、すらすら、楽々と演じるのがよい。そして第一に大切な要素は、めでたさであろう。どんなに脚本がよくできている脇の申楽でも、めでたさの要素が欠けていてはふさわしくない。たとえ作品としては多少劣っていても、めでたい内容であれば問題はない。これは、はじめの神を祝う序の能であるからである。二番目・三番目と番数が重なったら、役者が得意とする演目で、よい作品を演じるとよい。特に最後は、急で、急迫したテンポであるから、激しく身体を動かして、手数をかけてやることだ。
また、続けて幾日も興行する場合には、後の日の最初の能には、前日の最初の能とは違った姿の能をやり、泣き申楽は、後の日の破の順番のところに、格好の潮時を判断して演じるがよい。
語句
■序破急-三幕構成。三段構成のこと。本来は雅楽の楽曲構成の三区分。中世には連歌論にも応用され、世阿弥もその影響を受けたか。■一切の事に-万事に。■能の風情-能の演技内容。■まづ-「花伝第六花修」第一条前半部分参照。■本説正しき事-典拠となる由緒正しい説話である事。「本説正し」で、権威のある正統的な説に則(のっと)っていることを意味する。■おほかたの風体-それほど個性の強くない穏当な姿の能。■するすると-手の込んでいない様。■祝言-めでたい事。■次なる-劣ること。■二番・三番-一日の演目を五・六曲とするか。「番」は能や狂言の演目の数え方。■挙句-百韻連歌のような鎖連歌の最終の七七の句を言い、転じて最後の事。■揉み寄せて-たたみかけるように急迫すること。■手数-見せ所の型などの演技の数々。■後日-二日目のこと。二日目の脇の猿楽では、初日のようには祝言性にはこだわっていなかったらしい。■泣き申楽-観客の涙を誘う内容の能。
原文
問答条々(3)
問ふ。申楽の勝負の立会の手立てはいかに。
答ふ。これ、肝要なり。まづ、能数(のうかず)を持ちて、敵人(てきじん)の能に変(かは)りたる風体(ふうてい)を、違(ちが)へてすべし。
序(じよ)に云ふ。「歌道(かだう)を少し嗜(たしな)め」とは、これなり。この芸能(げいのう)の作者別(さくしやべち)なれば、いかなる上手(じやうず)も心(こころ)のままならず。
自作(じさく)なれば、言葉(ことば)・振舞(ふるまひ)、案(あん)の内なり。されば、能(のう)をせんほどの者(もの)の、和才(くあさい)あらば、申楽(さるがく)を作(つく)らん事、やすかるべし。これ、この道(みち)の命(いのち)なり。
されば、いかなる上手も、能を持たざらん為手(して)は、一騎当千の強者(つはもの)なりとも、軍陣にて兵具(ひやうぐ)のなからん、これ同じ。
されば、手柄のせいれひ、立合に見ゆべし。敵方(てきほう)色めきたる能をすれば、静かに、模様変はりて、詰め所(どころ)のある能をすべし。かやうに、敵人の申楽に変へてすれば、いかに敵方の申楽よけれども、さのみに負くる事なし。もし能よく出で来れば、勝つ事は治定(ぢぢやう)あるべし。
しかれば、申楽の当座においても、能に上中下の差別(しやべつ)あるべし。本説正しく、めづらしきが、幽玄にて、面白き所あらんを、よき能とは申すべし。よき能をよくしたらんが、しかも出で来たらんを、第一とすべし。能はそれほどになけれども、本説のままに咎(とが)もなく、よくしたらんが、出で来らんを、第二とすべし。能はえせ能なれども、本説の悪(わろ)き所をなかなか便りにして、骨を折りて、よくしたるを第三とすべし。
現代語訳
問。申楽能において、他座の役者との優劣を競う競演に勝つ方法とは、どのようなものでしょうか。
答。これは大切なことである。まず、第一にたくさんの上演可能演目数を保有して、相手方の能とは異なった姿の能を違えてやるがよい。
「序」でも述べているように、「和歌を少し稽古せよ」と言ったのは、このためである。申楽能の作者が役者と別人だと、どんなに演技上手の役者でも、心のままに演技することはできない。
自分で作った曲があれば、せりふやしぐさも自分の思い通りにやれる。それゆえに、能を演じようとするほどの者が、和歌に対する知識があれば、申楽を作るのは簡単なことだ。役者が能を作れるということは、申楽道の命である。
要するに、どんな上手でも、自作の能を持たない役者は、単騎で千人に向かえるような勇者であっても、、戦陣において、武器を持たないに等しいのだ。
自作の能での手際の優れ具合を、競演の舞台上で見せるがよい。相手方が華やかで派手な能を演じた場合は、しんみりした雰囲気の異なる山場のある能をするがよかろう。このように、相手方の猿楽とは雰囲気の異なる演技をすれば、どんなに相手方の猿楽が優れていようとも、簡単に負ける事はないであろう。もし、その時の能の演技が上出来であれば、勝ちは確定したと言えるであろう。
そこで、脚本のよしあしの外に、それを申楽の実際の舞台にかける場合に於いても、上・中・下の区別がでてくる。典拠が権威ある古典で、作品に新鮮味があり、優美で、しかも面白く感じさせるというように、種々の条件がよく備わったものを良い作品というのである。こうした良い作品を、上手に演じて、しかも上々の出来であるのを第一の上の舞台とする。能としては大したことはないが、典拠通りの無難な作風で変なところもない作品を、上手に演じて、上々の出来であったものが第二の中の舞台だ。作品性の劣る能ではあるが、典拠の悪い所をかえってうまく利用し、役者がうまく直して、いい作品に仕上げたものを上手に演じたのを第三の下の舞台とするのだ。
語句
■勝負-複数の役者が交互に競演して芸の優劣を競う興業のこと。■能数を持ちて-得意に演じ得る能の種類を多く持つ事。■変はりたる風体-重複による強調表現。■この-猿楽の作品のこと。■案の内-考えの通り。計画通り。■和才-和歌についての知識。■これ-能が作れるということは。■能を持たざらん為手-自作の能を持っていない役者。上演可能演目の少ない役者の意味ではあるまい。■兵具-武器。■手柄のせいれひ-手際の優れ具合。■色めきたる能-華やかで派手な能。■詰め所-山場。観客を引き付ける場面。■しかれば-ところで。■治定-確定。必定。■当座-実際の舞台。■本説-典拠。出典。■幽玄-美しい事。■咎-他人が非難するのももっともな、欠点・過ち。■えせ能-不出来な能。作品性の劣る能。■なかなか便りにして-かえって工夫のてがかりとして。
原文
問答条々(4)
問ふ。これに大きなる不審あり。はや功入りたる為手(して)の、しかも名人なるに、ただ今の若き為手の、立合(たちあひ)に勝つ事あり。これ、不審なり。
答ふ。これこそ、先に申しつる三十以前の時分の花なれ。古き為手ははや花失せて古様なる時分に、めづらしき花にて勝つ事あり。真実の目利きは見分くべし。さあらば、目利き・目利かずの、批判の勝負になるべきか。
さりながら、やうあり。五十以来まで花の失せざらんほどの為手には、いかなる若き花なりとも、勝つ事はあるまじ。ただこれ、よきほどの上手の、花の失せたるゆゑに、負くる事あり。いかなる名木(めいぼく)なりとも、花の咲かぬ時の木をや見ん。犬桜(いぬざくら)の一重(ひとへ)なりとも、初花(はつはな)の色々と咲けるをや見ん。かやうの譬(たと)へを思ふ時は、一旦(いったん)の花なりとも、立合に勝つは理(ことわり)なり。
されば、肝要(かんやう)、この道はただ花が能の命なるを、花の失するをも知らず、もとの名望ばかりを頼まん事、古き為手の、返すがへす誤りなり。物数をば似せたりとも、花のあるやうを知らざらんは、花咲かぬ時の草木を集めて見んがごとし。万木千草において、花の色もみなみな異なれども、面白しと見る心は、同じ花なり。物数は少なくとも、一方の花を取り極めたらん為手は、一体の名望は久しかるべし。
されば、主(ぬし)の心には随分花ありと思へども、人の目に見ゆるる公案なからんは、田舎(でんじや)の花、藪梅(やぶうめ)などの、いたづらに咲き匂はんがごとし。
また、同じ上手なりとも、その内にて重々あるべし。たとひ随分極めたる上手・名人なりとも、この花の公案なからん為手は、上手にては通るとも、花は後まではあるまじきなり。公案を極めたらん上手は、たとへ能は下がるとも、花は残るべし。花だに残らば、面白きところは一期(いちご)あるべし。されば、まことの花の残りたる為手には、いかなる若き為手なりとも、勝つ事はあるまじきなり。
現代語訳
問。申楽について大きな疑問点が一つあります。それは、経験豊かな役者で、しかも名人と言われていながら、たった今駆け出しの若い役者が、競演に勝つ事があります。これはどういうことでしょうか。
答。これこそ、「年来稽古条々」二十四伍の条で述べた、三十以前の若さによる一時的な魅力のことである。ベテランの役者は、すでに魅力もなくなり、古臭くなっている頃で、若い役者が珍しさの魅力によって勝つ事がある。しかし、真実の目利きは、時分の花と真の花を見分ける鑑識眼を持っていなければならない。そうなると、目利きか目利かずかの鑑識眼の優劣の勝負になるであろう。
しかしこれにも問題がある。、五十過ぎまで魅力の失せない名人の役者には、どんな若さの魅力を持った役者も勝つことはないであろう。ただ、若手が勝つ場合というのは、、かなりの程度の上手の古株の役者が、芸の魅力が失われたために負けることもあるのである。どんな名木といえども、花が咲いていない時の木を鑑賞するだろうか。つまらない一重桜であろうとも、初花が色とりどりに咲いているのなら誰でも鑑賞するというものだ。こういう例えを考えて見れば、その場限りの若さの花と言えども競演に勝つのは当たり前なのである。
であれば、大事なことは、この申楽の道は、ただ芸の魅力こそが最重要であるのに、その魅力は失せるものであることを認識せず、以前の名声ばかりを頼りにすることが、古参役者のとんでもない誤りである。多くの物まねを、どれほど、似せて演じようと、魅力が失せるものであることを知らないのは、花の咲かない時期の草木を集めて見ているようなものである。すべての樹木・草類において、花の色は、それぞれに異なるが、人が咲く花を面白いと思う心理は、皆それが同じ美しい花だからだ。自分がこなし得た芸の種類は少なくても、ある一芸の花を極めた役者は、それがうまいという名声を久しく持ち続けることができるであろう。
一方、本人としては多くの自作演目を持っていて、自分は多くの花を持っているんだと思っていても、他人から見れば、その魅力を観客に見せる工夫をしない役者は、田舎の花や藪に咲く梅などが、見る人もないのに無駄に咲き誇っているようなものだ。
また、同じ上手と言っても、その中では段階がある。たとえ、かなりの程度に芸を極めた上手・名人といえども、この芸の魅力を引き出す工夫をしない役者は、上手とは言われても、その魅力は後々までは残らないであろう。この花の工夫を極めた上手は、たとえ、技量的には衰えても、その魅力さえ残れば、面白い所は生涯あり続けるであろう。だから、本当の芸の魅力の残っている役者には、どんな若さの魅力いえども、勝つはずはないのだ。
語句
■功入りたる為手-経験の豊かな役者。年功を積んだ役者。■名人-名声を博した役者。名にある役者。■ただ今の若き為手-全くの新人。デビューしたての役者。
■先に-「年来稽古条々」二十四伍の条をいう。■三十以前の-三十以後の「真の花」と対比した言い方。■古き為手-ベテランの役者。■古様なる-古くさくなる。■めづらしき花-新人の珍しさの魅力。■真実の目利き-時分の花と真の花を見分ける鑑識眼の持ち主。■批判-鑑識眼の優劣。■やう-子細。事情。■若き花-若さの魅力。■よきほど-よほど。かなりの程度であること。■犬桜-桜の一種だが、花が見劣りするのでこのように呼ばれる。■肝要(かんやう)-「肝要は」の意味で、直後の文に続く。■花が能の命-花が能を成り立たせている意。■物数-上演可能演目の数。■物数をば似せたりとも-たくさんの物まねをそれなりに演じて見せたとしても、の意。■花のあるやう-魅力の引き出し方。見せ方。■取り決めたらん-それだけに熟達しているような。■一体の名望-特定演目に対する名声。■主-本人。■田舎の花-風雅を解する人の見ることもない田舎の桜。■藪梅-藪で咲く見る人もない梅。■重々-段階。■能は下がるとも-能の力は下がっても。技量はさがっても。■一期-生涯にわたって。■されば-以下、前文の趣旨の再説。
備考・補足
■万木千草-「別紙口伝」第一条を踏まえるか。
■また-「年来稽古条々」五十有余の条の補説。
原文
問答条々(5)
問ふ。能に得手得手(えてえて)とて、ことの外に劣りたる為手(して)も、一向き上手に勝りたる所あり。これを上手のせぬは、かなはぬやらん。また、すまじき事にてせぬやらん。
答ふ。一切の事(じ)に、得手得手とて、生得得たる所あるものなり。位(くらゐ)は勝りたれども、これはかなはぬ事あり。さりながら、これもただ、よきほどの上手の事にての料簡(れうけん)なり。まことに能と工夫との極まりたらん上手は、などかいづれの向きをもせざらん。されば、能と工夫とを極めたる為手、万人が中にも一人もなきゆゑなり。なきとは、工夫はなくて、慢心あるゆゑなり。
そもそも、上手にも悪き所あり、下手にも良き所必ずあるものなり。これを見る人もなし。主(ぬし)も知らず。上手は、名を頼み、達者に隠されて、悪しき所を知らず。下手は、もとより工夫なければ、悪き所をも知らねば、良き所のたまたまあるをもわきまへず。されば、上手も下手も、たがひに人に尋ぬべし。さりながら、能と工夫とを極めたらんは、これを知るべし。
いかなるをかしき為手なりとも、良き所ありと見ば、上手もこれを学ぶべし。これ、第一の手立なり。もし、よき所を見たりとも、我より下手をば似すまじきと思ふ情識(じやうしき)あらば、その心に緊縛(けばく)せられて、我が悪き所をも、いかさま知るまじきなり。これすなはち、極めぬ心なるべし。
また、下手も、上手の悪き所もし見えば、「上手だにも悪き所あり。いはんや初心の我なれば、さこそ悪き所多かるらめ」と思ひて、これを恐れて、人にも尋ね、工夫をいたさば、いよいよ稽古になりて、能は早く上がるべし。もし、さはなくて、「我はあれ体(てい)に悪き所ををばすまじきものを」と慢心あらば、我が良き所をも、真実知らぬ為手なるべし。良き所を知らねば、悪き所をも良しと思ふなり。さるほどに、年は行けども、能は上がらぬなり。これすなはち、下手の心なり。
されば、上手にだにも、上慢あらば能は下がるべし。いはんやかなはぬ上慢をや。よくよく公案して思へ。「上手は下手の手本、下手は上手の手本なり」と工夫すべし。下手の良き所を取りて、上手の物数(ものかず)に入るる事、無上至極の理(ことわり)なり。人の悪き所を見るだにも、我が手本なり。いはんや良き所をや。「稽古は強かれ、情識はなかれ」とは、これなるべし。
現代語訳
問。能にはそれぞれ得意芸というものがありますが、とりわけ下手な役者も、特定の出し物については上手の役者より優れたところがあるものです。この芸を上手な役者が演じようとしないのはできないのでしょうか。あるいは、してはいけないということでしないのでしょうか。
答。あらゆる物事に、それぞれの得意芸といって、生まれつき上手に出来るものがある。芸の実力は優れていても、こういう他人の得意芸は上手にもできないということがある。しかしながら、そんな考えも、それなりの上手という程度の人間の考えである。本当に能と芸の工夫を極めた上手は、どうして、どんな芸もできないことがあろうか。上手が下手のよい芸をまねないのは、本当に実力のある役者が、万人の中に一人もいないからである。それがないというのは、実力を発揮する工夫はしないのに、慢心ばかりがあるからである。
そもそも上手にも悪いところがある。下手にも必ずいいところがあるものだがこれを見つける人もいない。本人にもその自覚が無く、上手は、その名声を頼みとし、そのことに隠されて、自分の悪い所が見えなくなっているのだ。下手はもともと、工夫もしないので、自分の悪い所も自覚していないので、自分のよい部分も稀にあるのに気づかない。それで、上手も下手も、お互い他の人の評価を聞いてみるべきである。そうはいっても、実力を備え、それを発揮する工夫を極めたような者は、自ら反省してこのことを知るだろう。
どんなおかしな役者であっても、いいところがあるのを見つけたら、上手であってもこれを学ぶべきである。これが上達する最善の方法だ。もし、他人のいいところを見出したとしても、自分より下手な役者の真似はすまいと思う慢心で相手を見くびる気持ちがあれば、、その心に束縛されて、自分の悪い所をも、きっとわからないであろう。これが言い換えれば芸を極めない心情というものだ。
また、下手も、上手の悪い所がもしわかったならば、上手といえども欠点がある。いわんや未熟な自分であれば、さぞかし多くの欠点があるだろうと思って、それに気を付けて、人にも尋ね、工夫をすれば、それがますます稽古になって、芸は速やかに上達するであろう。もし、そうではなくて「自分はあんな風に欠点をさらすことはないであろう」という慢心があれば、自分の良い所も、本当に知らない役者ということになる。良い所を知らないから悪い所をも良い所と思うのである。そうだから年齢は重ねても能の上達はないのである。これがすなわち下手の心情である。
であれば、上手といえども、慢心あれば能の技能は下がっていくのだ。まして、下手の思い上がりの慢心ならばなおさらである。
そこでだれも皆よくよく反省するがよい。「上手は下手の手本、また下手は上手の手本である」と考え、下手の良い点を取り入れて、上手の得意芸に取り入れる事は、最高の境地に達するための真理である。人の欠点を見る事さえ、自分にとっては手本となるのである。まして、良い所を見るのはなさらである。「稽古は一生懸命にやれ、慢心にもとづく争い心を持ってはならぬ」と序文で言ったのは、このことだ。
語句
■得手得手-それぞれの得意芸。■ことのほか-特別。とりわけ。■一向き-一方面。特定の出し物。■すまじき事-下手の演目を学ぶことを禁忌とする発想があったか。■位-芸の格。■これはかなはぬ事あり-芸位が高くても下手の得意わざはできないこと。■よきほどの上手の事にて料簡-ある程度の熟達者の場合の見識。■能と工夫-芸力とそれを生かす工夫。■向き-芸風・演目。■されば-上手が下手のよい芸をまねないのは、を略す。■達者に隠されて-芸達者であることに我を忘れて。■能と工夫-芸力とそれを生かす工夫。■これを知るべし-上手の欠点や下手の美点を知っていよう、の意。■をかしき為手-変な役者。笑うべき下手さの役者。■第一の手立て-最善の方法。■情識-慢心して相手を見くびる事。■縛縛(けばく)-束縛。■いかさま-きっと。■極めぬ-芸を極めぬということ。■上手の悪き所-上手の欠点を見つけた意にも、上手が欠点を見せた意にもとれる。■初心-未熟者。■恐れて-自己の欠点の多さを恐れ慎んで。■上がる-上達する。■あれ-あのざま。■されば-以下、冒頭の序文を踏まえるなど、後年の増補か。内容は前文の再説による強調。■上慢-増上慢。慢心。■かなはぬ上慢-下手の思い上がり。■上手の物数-上手な役者の演目。■無上至極の理-最高の境地に達するための真理。■稽古は強かれ、情識はなかれ-序文参照。
原文
問答条々(6)
問ふ。能に位(くらゐ)の差別(しやべち)を知る事は、如何(いかん)。
答ふ。これ、眼利きの眼(まなこ)には、やすく見ゆるなり。およそ、位の上がるとは、能の重々の事なれども、不思議に、十ばかりの能者(のうじや)にも、この位おのれと上がれる風体あり。ただし、稽古(けいこ)なからんは、おのれと位ありともいたづら事(ごと)なり。
まづ、稽古の功(こう)入りて位のあらんは、常の事なり。
また、生得の位とは、長(たけ)なり。嵩(かさ)と申すは別のものなり。多く、人、長と嵩とを同じやうに思ふなり。嵩と申すは、ものものしく、勢ひのある形なり。また曰(いは)く、嵩は一さいにわたる義なり。
位・長は別(べち)のものなり。たとへば、生得幽玄なる所あり。これ、位なり。しかれども、さらに幽玄にはなき為手の、長のあるもあり。これは幽玄ならぬ長なり。
また、初心の人思ふべし。稽古に位を心がけんは、返すがへすかなふまじ。位はいよいよかなはで、あまさへ、稽古しつる分も下がるべし。所詮(しよせん)、位・長とは生得の事にて、得ずしてはおほかたかなふまじ。また、稽古の功入りて、垢(あか)落ちぬれば、この位、おのれと出でくる事あり。稽古とは、音曲・舞・はたらき・物まね、かやうの品々を極むる形木(かたぎ)なり。
よくよく公案して思ふに、幽玄の位は生得のものか。長けたる位は功入りたる所か。心中に案を廻(めぐ)らすべし。
現代語訳
問。能に実力の差があることを知るにはどうしたらよいでしょうか。
答。このことは、目の利く批評家には簡単にわかるものだ。だいたい、位が上がっていくというのは、稽古を重ねて芸の段階が次第に上がっていくことをいうが、不思議なことに、十歳ばかりの芸達者な子役にも、この位が自ずと備わっている芸風を見る事がある。ただし、稽古修練を行わないのであれば、生まれつき備わった芸の位があったとしても、それが無駄になってしまう。
まず、稽古の年功を積んだうえで、芸位が備わるというのが、普通のことである。それを「嵩(かさ)」という。
それに反して、生まれつき備わっている位とは、「長(たけ)」である。「嵩(かさ)」というのはこれとは別物である。たいていの人は「長(たけ)」と「嵩(かさ)」を同じように考えている。「嵩(かさ)」というのは重々しく、迫力のある演技のことを言い、勢いのある芸のことである。さらに言うと、「嵩(かさ)」はどんな芸でもこなすという意味である。
「位」と「長(たけ)」とは別のものである。たとえば、生まれつき舞台姿が美しい場合がある。これが、「位」ということだ。しかし、まったく優美とは無縁の役者で、「長(たけ)」のある場合もある。これは優美とは異質の「長(たけ)」である。又、未熟な者は心得ておかねばならぬことがある。稽古によって、芸の「位」を学び取ろうとしても、それは不可能である。芸の「位」はますます遠ざかり、そればかりか、今まで稽古をして持っていた芸の「位」も下がるであろう。所詮、位・長とは生まれながらに備わっている才能で、もともと持っていない場合には、決して身につくものではない。
また、稽古を重ねて、その効果が出、洗練されてくると、この「位」が自然と出てくる場合がある。稽古とは、音曲・舞・演技・役づくりといったような基礎技術の数々をきちんと極めるための規範となるものである。よくよく考えると、幽玄の位というものは生まれつき持っているものであろうか。長という位は稽古の賜物か。このことはよく心のなかでよく考えてみるがよい。
語句
■位-芸の格(実力)であるが、経験を経た後に獲得されるものばかりでなく、生まれつき備わった器用さも含める。■重々-段階を経ての事であるが。■能者-よくできる役者。才能ある役者。■おのれと上がれる-自然に位の上がった。■おのれと位あり-自然に生まれつき身に備わった位。■また云々-もともと備わっている位と稽古の成果としての位との相違を説明する前提となる補説。■長(たけ)-強々として品格のある芸位。すっきりした感じ。センスの良さを意味する。■嵩(かさ)-積み重ねた感じで、どっしりと重みがあること。■ものものしく-重々しく、迫力のある演技。■一さいにわたる義-どんな演目でもこなせるという意味。■幽玄-美しさを意味する一般語。ここでは単純な容姿の美しさではなく、舞台姿の美しさを言うか。■幽玄ならぬ長-美しさとは別種の芸格。■稽古に位を心がけんは-稽古によって、その位自体を演技の目標とすること。■あまさへ-「あまつさへ」の文字脱落したもので、「そればかりか」、「それどころか」、「そのうえ」の意。■生得のことにて得ずしては-生まれつきそなわったものとして持っていなければ。■垢落ちぬれば-不器用さが無くなると。あかぬけがすると。■形木-版木のことで、稽古の基準となる技術の比喩。
原文
問答条々(7)
問ふ。文字(もんじ)に当たる風情とは、なに事ぞや。
答ふ。これ、細かなる稽古(けいこ)なり。能にもろもろのはたらきとは、これなり。体拝(たいはい)・身づかひと申すも、これなり。
たとへば、言ひ事(ごと)の文字にまかせて心をやるべし。「見る」といふ事には物を見、「指す」「引く」などいふには手を指し引き、「聞く」「音する」などには耳を寄せ、あらゆる事にまかせて身をつかへば、おのづからはたらきになるなり。第一、身をつかふ事、第二、手をつかふ事、第三、足をつかふ事なり。節とかかりによりて、身の振舞を料簡(れうけん)すべし。これは筆に見えがたし。その時に至りて、見るまま習ふべし。
この文字に当たる事を稽古し極めぬれば、音曲・はたらき、一心になるべし。所詮(しよせん)、音曲・はたらき一心と申す事、これまた得たる所なり。堪能(かんのう)と申さんも、これなるべし。
秘事なり。音曲とはたらきとは、二つの心なるを、一心になるほど達者に極めたらんは、無上第一の上手なるべし。これ、まことに強き能なるべし。
また、強き・弱き事、多く、人、紛らかすものなり。
能の品(しな)のなきをば強きと心得、弱きをば幽玄なると批判する事、をかしき事なり。なにと見るも見弱りのせぬ為手(して)あるべし。これ、強きなり。なにと見るも花やかなる為手、これ幽玄なり。されば、この文字に当たる道理をし極めたらんは、音曲・はたらき一心になり、強き・幽玄の境、いづれもいづれも、おのづから極めたる為手なるべし。
現代語訳
問。謡の文句にかなった所作とは、どのようなものでしょうか。
答。これは、具体的な物まねに関する稽古のことを指すのであるが、能の色々な身のこなしとは、謡の文句に合った動作でなければならぬ。
それには謡の文句に従って心を使うことだ。例えば、「見る」という文句では、物を見る動作をし、「指す」、「引く」などという言葉では、手を指したり引いたり、「聞く」、「音する」などのときには、耳を近づけるなど、あらゆる事で、その文句の通りに演技をすれば、自然な動きになるのである。所作を大きく分けると、第一に体を動かす場合、第二には手を使う場合、第三には足を動かす場合である。その身のこなしは、謡の節と言葉の響きによって、加減することが大切である。これは文章では説明しきれない。必要に迫られて、師の演技を見るままに学び取る必要がある。
この文字に対応した動作を稽古し極めたならば、謡と演技とが一体となり、これまたすばらしいものだ。堪能というのもこのことを言うのであろう。
秘伝である。謡と演技とは別の物であるが、これが、同化するほど芸達者になった役者は、このうえなく最高の上手である。これが、真に安定感のある芸なのであろう。
また、「強い事」、「弱い事」とにつき、多くの場合、人は混同しがちである。能芸に上品さの無い事を「強い能」と思いこみ、弱々しい芸を「幽玄である」と批評することは、おかしなことだ。どこから見ても見飽きない役者というのがいるであろう。これが「強い」というものだ。どから見ても華やかな役者というのが「幽玄」なのである。さて、先の「言葉に対応する」という演技理論を徹底的にやり抜いた役者は、謡と演技が同化し、「強き」と「幽玄」の二つの演技の境地のいづれについても、すべて、自然に申楽の道を極めた役者ということであろう。
語句
■文字にあたる風情-言葉(詩章の意味内容)に対応した所作。■細かなる稽古-具体的な物まねに関する稽古。■はたらき-動き・所作。■体拝(たいはい)-定型的な身のこなし。■身づかひ-身体動作。■言ひ事-謡の文句。■心をやる-振舞うこと。■事にまかせて-文句通りに。■はたらき-演技。■身をつかふこと-演技をすること。■手をつかふこと-型を演じること。■足をつかふ-足踏み。■節-謡の曲節。■かかり-言葉のひびき。■筆に見えがたし-文章ではうまく説明できない、意。■この文字に云々-以下、「花修」第二条の所説の展開。■音曲・はたらき、一心になる-謡と演技が一体化する境地。■堪能(かんのう)-十分に満足すること、飽きるまで満足すること。■二つの心-二つのこと。■強き能-安定感のある芸。
■また云々-以下、「花修」第三条の所説の展開。■能の品-演技や芸の品格。ここは作品内容が下品なことではあるまい。■見弱り-見飽きること。見ている中に欠点が露呈すること。■おのづから極めたる云々-文字に当たる風情を極めることで自然と、の意。
原文
問答条々(8)
問ふ。常の批判にも、「しほれたる」と申す事あり。いかやうなる所ぞや。
答。これは、ことに記すに及ばず。その風情あらはれまじ。さりながら、まさしく、しほれたる風体はあるものなり。これも、ただ、花によりての風情なり。よくよく案じて見るに、稽古(けいこ)にも振舞にも及びがたし。花を極めたらば知るべきか。されば、あまねく物まねごとになしとも、一方の花を極めたらん人は、しほれたる所をも知る事あるべし。
しかれば、この「しほれたる」と申す事、花よりもなほ上の事にも申しつべし。花なくては、しほれ所無益(どころむやく)なり。
それは「湿(しめ)りたる」になるべし。花のしほれたらんこそ面白けれ。花咲かぬ草木のしほれたらんは、なにか面白かるべき。されば、花を極めん事、一大事なるに、その上とも申すべき事なれば、しほれたる風体、返すがへす大事なり。
さるほどに、譬(たと)へにも申しがたし。
古歌に曰(いわ)く、
薄霧の籬(まがき)の花の朝じめり秋は夕(ゆふべ)と誰かいひけん
また、曰く、
色見えで移ろふものは世の中の人の心の花にぞありける
かやうなる風体にてやあるべき。心中にあてて公案すべし。
現代語訳
問い。よく聞く批評でも、「しほれたる」などということがありますが、それはどういうことですか。
答え。これは、とりたてて説明するほどのこともない。というのは、「しほれたる」風情というものは目に見える具体的な演技としてあるわけではないからだ。しかし、まさしく「しほれたる」と批評される芸風はあるものである。それもただ花があった上での風情である。よくよく考えてみると、「しほれたる」ということを実現する稽古もないし、それを著す演技もない。能芸の魅力を極めたならば、自然にこの境地を会得できるのだ。
それ故に、ひろくすべての演目に花を極めていなくても、ある一面の花を極めたような人は、この「しほれたる」という趣も理解できるかもしれない。
つまり、この「しほれたる」ということは、「花」よりもっと上位の概念とも言わねばならない。花が無くては、「しほれたる境地」は無意味なのである。花が無ければ、「しめりたる」になってっしまうであろう。盛りを少し過ぎた花がしっとりとしている姿こそ、趣あるものといえよう。
花の咲かない草木が少し枯れかかっているのなど、どうして面白い事があろうか。さて、花を極めることだけでも難しいのに、さらにその上の境地ともいうべきことであるので、「しほれたる能姿」というものは達成するのが非常に困難な境地なのである。
であるから、たとえにも言い表しにくいのである。
古歌にいう、
うっすらと漂う秋霧の向こうに見える垣根の花が、朝霧にしっとりと濡れている美しさよ。秋は夕方がすばらしいとは誰が言ったことか。朝だってこんなにすばらしいではないか。
また、いう。
はっきりとはわからずに散ってしまうのは、この世間の人心という花であったなあ。
これらの歌にうたわれた美に類似した、能の姿であろうか。心の中にこれを当てはめてよくよく工夫するがよい。
語句
■しほれたる-盛りを過ぎていっそう美しさを増す花に比喩される境地。転じてしみじみとした情感があること。■ことに-とりわけて。■その風情あらはれまじ-目に見える所作や演技に「しほれ」ということがあるわけではない。■しほれたる風体-趣ある芸風。■花によりての風情-花によって生じる美的感興。■あまねく物まねごとになしとも-ひろくすべての演目に花を極めていなくても。■湿りたる-「しほれ」から美しさを除いた形容。魅力のない陰気な印象。■薄霧の・・・-『新古今』秋上、藤原清輔の歌。薄霧の中に咲く籬(まがき)の菊のしっとりとした風情を「しほれ」に例えたものか。■色見えで・・・-『古今』恋五、小町。美女が失恋の涙に沈んでいる様を「しほれ」に例えたものか。
原文
問答条々(9)
問ふ。能に花を知る事、この条々を見るに、無上第一なり。肝要なり。または不審なり。これ、いかにとして心得(こころう)べきや。
答ふ。この道の奥義を極むる所なるべし。一大事とも秘事とも、ただ、この一道なり。
まづ、大かた、稽古、物まねの条々にくはしく見えたり。時分の花、声の花、幽玄の花、かやうの条々は、人の目には見えたれども、そのわざより出で来る花なれば、咲く花のごとくなれば、またやがて散る時分あり。されば、久しからねば、天下に名望少なし。ただ、まことの花は、咲く道理も散る道理も、心のままなるべし。されば、久しかるべし。この理を知らむ事、いかがすべき。もし、別紙の口伝にあるべきか。
ただ、わづらはしくは心得まじきなり。まづ、七歳よりこのかた、年来稽古の条々、物まねの品々を、よくよく心中にあてて分かち覚えて、能を尽くし、工夫を極めて後、この花の失せぬ所をば知るべし。この物数を極むる心、すなはち花の種なるべし。されば、花を知らんと思はば、まづ種を知るべし。花は心、種はわざなるべし。
古人曰く、
心地(しんじ)に諸(もろもろ)の種(たね)を含(ふく)み、 普(あまね)き雨(あめ)に悉(ことごと)く皆(みな)萌(きざ)す。
頓(とみ)に花(はな)の情(こころ)を悟り已(をは)れば、菩提の果(くわ)自(おのずか)ら成(な)る。
現代語訳
問い。能芸の花を知るということは、この「風姿花伝」三編の項目を見ると、最も大事なことであり、一つには又肝要なことでもある。またその一方でわからない部分がある。この花を知るというのは、どのようにして実現できるのでしょうか。
答え。花を知るということこそ、この道の奥義を極めるということであろう。最も難しいことと言おうか、秘訣と言おうか、要するに、ただ、この花を知るという一つの事に関わるのである。
まづ、大体のところは、「年来稽古条々」や「物学条々」に詳しく書いてある。一時的な若さの魅力、若々しい声の魅力、若々しい姿の魅力。このような花は、観客の目にははっきりと見えるが、どれも皆、一時的な若々しい振舞から生じる魅力なので、自然に咲く花のようなものであり、また、やがて散る運命にもあるのだ。
つまりは、永く続かないものなので、それだけでは都で名声を博するのは難しい。これに対して、真実の芸の力から生じる花というのは咲かせることも散らせることも自分の意のままであろう。であるから、永遠の魅力となろう。このような花を咲かせたり散らせたりする方法を知るには、どのようにすべきであろうか。あるいは「別紙口伝」にて詳しく述べるべきでろうか。
ただし、花を知ることを面倒なことだと思い込んではならない。まずは七歳以降の「年来稽古条々」説いた教えの数々、「物学条々」に記した各条を、何度も心の中で理解して覚え、あらゆる演目を演じ、芸の工夫を極めた後に、どうしたら花を失わずにすむかがわかってくる。このようにあらゆ演目の芸を極める心がけというのが、すなわち花の種というものである。だから、花を理解しようとするには、まず花の種を理解することだ。さて花は心の工夫の問題、種は芸の技というわけである。
慧能(えのう)という禅の高僧も、
人の本質には仏になるべきすべての条件(種)が備わっており、仏の慈雨に応じてその仏種はすべて芽吹くのである。
すみやかに花の咲く道理を悟ったならば、悟りという成果は自ずから達成されるのである。
と言っている。
語句
■能に花を知る事-能芸において、花とは何かを知る事。すなはち花の大切さを認識すること。■この条々-「花伝」三篇の条々。■または-一つには又の意。■いかにとして-どのようにして。■時分の花-若さの魅力。■声の花-若々しい声の魅力。■幽玄の花-若々しい姿の魅力。■条々-項目。■そのわざ-若々しいふるまい。■咲く花-自然の花。■別紙の口伝-「別紙口伝」の花の理論を漠然と指す。■わずらわしくは心得まじきなり-面倒なことだと思い込んではならない。■わかつ-判断する。理解する。■能を尽くし-あらゆる演目を行い。■花は心、種はわざなるべし-芸の花は工風によって咲かせるものであり、その種となるのは、能の数々である。■古人-禅宗の始祖である達磨大師から数えて第六祖の慧能(えのう)禅師の偈文(げもん)。■偈文(げもん)-仏典のなかで、仏の教えや仏・菩薩の徳をたたえるのに韻文の形式で述べたもの。■心地-人間の本心・本性をいう。■普(あまね)き雨(あめ)に悉(ことごと)く皆(みな)萌(きざ)す-仏法の恵みの比喩。■花(はな)の情(こころ)を悟り-花の開く道理。■菩提の果(くわ)-悟りという成果。
原文
問答条々 (結句)
およそ、家を守り、芸を重んずるによって、亡父の申し置きし事どもを、心底にさしはさみて、大概を録する所、世のそしりを忘れて、道のすたれん事を思ふによりて、まつたく他人の才学に及ばさんとにはあらず。ただ子孫の庭訓(ていきん)を残すものなり。
風姿花伝条々 以上
時に応永(おうえい)七年 庚辰(かのえたつ) 卯月(うづき)十三日
従五位下左衛門大夫(たいふ) 秦(はだの)元清(もときよ)書(かく)
現代語訳
そもそも申楽の家を守り、芸を大切に思うがゆえに、亡き父、観阿弥が言い残した事などを、心にとどめて、そのほとんどを記録したのが本書であるが、それは世間の非難を顧みず、申楽の道が廃(すた)れてしまうことを憂えるあまり、あえて筆を執ったものであり、まったく他人に何かを教えようなどという意図はない。ただ、子孫に対して教訓を残すばかりである。
風姿花伝条々は以上である。
時に応永七年庚辰の年 四月十三日
従五位下左衛門大夫 秦の元清 これを記す。
語句
■亡父-観阿弥のこと。■心底にさしはさみて-心にとどめること。■世のそしりを忘れて-世間の非難を顧みず。
備考・補足
<参考文献>
・風姿花伝・三道 現代語訳付き 世阿弥・竹本幹夫訳注
・花伝書(風姿花伝) 世阿弥編 川瀬一馬校注、現代語訳
・風姿花伝 世阿弥編 野上豊一郎・西尾実校訂
・現代語訳 風姿花伝 世阿弥著 水野聡訳
・風姿花伝 世阿弥 現代語訳:夏川賀央
前の章「風姿花伝第二 物学(ものまね)条々」|次の章「風姿花伝第四 神儀(じんぎ)に云(い)はく」