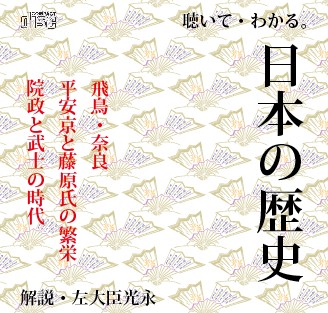風姿花伝 奥義に云はく
■【古典・歴史】メールマガジン
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
原文
風姿花伝 奥義に云はく
そもそも、風姿花伝の条々、おほかた、外見のはばかり、子孫の庭訓(ていきん)のため注(しめ)すといへども、ただ望む所の本意とは、当世、この道のともがらを見るに、芸のたしなみはおろそかにて、非道のみ行(ぎやう)じ、たまたま当芸に至る時も、ただ、一夕(いつせき)の戯笑(けせう)、一旦(いつたん)の名利に染(そ)みて、源を忘れて流れを失ふ事、道すでにすたる時節かと、これを嘆くのみなり。
しかれば、道をたしなみ、芸を重んずる所私(わたくし)なくば、などかその徳を得ざらん。ことさら、この芸、その風を継ぐといへども、自力より出(い)づる振舞あれば、語にも及びがたし。その風(ふう)を得て、心より心に伝ふる花なれば、風姿花伝と名づく。
現代語訳
いったい、この『風姿花伝』の項目内容はすべてが他人に読まれてはならない秘伝であり、子孫の教育のためにのみ執筆したのであるが、ただ、望む本来の執筆動機は何かというと次のようなものである。すなわち、最近、能の世界の仲間を見ていると、芸の稽古をおろそかにし、本芸以外のことばかりに熱心で、たまたま、能の世界で成功した時も、ただ、その場限りの喝采に喜び、一時的な名誉や利益に感化され、本芸を忘れて伝統を見失ってしまう有様は、能の道はすでに廃絶してしまったかと、これを嘆かわしく思うばかりに筆を執ったのである。
だから、能の稽古に務め、私心なく芸を重んじれば、どうして、能の道が興隆しないことがあろうか。とくに、この芸は古来の猿楽の伝統を継ぐといっても、私の努力・工夫によって発明した、伝統に相違する演技もあるので、そのいちいちを言葉による説明をしきれない。猿楽の伝統を受け継ぎながら、言葉では伝えきれない部分までも、心から心へと伝える猿楽の花であるので、『風姿花伝』と名付けるのである。
語句
■奥義-最奥の秘伝の意で、風姿花伝の末尾に配置するにふさわしい見出し。本書の第五巻に相当するが、もともと巻序が脱落していた可能性も指摘されてる。■そもそも-さて。いったい。■おほかた-ここは「すべて」に近い意味か。■外見の-「外見を」の連声。■はばかる-恐れ慎む。遠慮する。■子孫の庭訓-子孫の教育のためのみに、の意。■庭訓-家庭の教訓。しつけ。■本意-本来の執筆動機は何かというと。「これを嘆くのみなり」にかかる。■この道-能の世界。田楽も含むらしいことが後の十体論からわかる。■たしなみ-稽古。■非道-能以外の事柄の意らしいが、具体的にいかなる行いを非難したのかは不明。むしろ正しい習道の道筋を踏まえていないことを問題視するような内容。■行じ-修行し。■当芸に至る-能の世界で成功する意。■一夕の戯笑-その場限りの喝采。■一旦の-一時的な。■名利-名誉と利益。■染まる-感化される。■しかれば-だから。■その徳-私心を捨てた功徳。能の道が興隆すること。■ことさら-わざわざ。とくに。■自力より出づる振舞-己の努力・工夫によって発明した、伝統に相違する演技。■その風-猿楽の伝統。■語-言葉による説明。
原文
風姿花伝 奥義に云はく
およそ、この道、和州(わしう)・江州(がうしう)において風体変はれり。江州には、幽玄の境を取り立てて、物まねを次にして、かかりを本とす。和州には、まづ物まねを取り立てて、物数を尽くして、しかも幽玄の風体ならんとなり。しかれども、真実の上手は、いづれの風体なりとも洩(も)れたる所あるまじきなり。ひと向きの風体ばかりをせん者は、まこと得ぬ人の技なるべし。
されば、和州の風体、物まね・義理を本として、あるいは長(たけ)のあるよそほひ、あるいは怒れる振舞、かくのごとくの物数を、得たる所と人も心得、たしなみもこれもつぱらなれども、亡父の名を得し盛り、静(しづか)が舞の能、嵯峨の大念仏の女物狂(ものぐるひ)の物まね、ことにことに得たりし風体なれば、天下の褒美・名望を得し事、世以(も)て隠れなし。これ、幽玄無上の風体なり。
また、田楽(でんがく)の風体、ことに格別の事にて、見所(けんじよ)も、申楽(さるがく)の風体には批判にも及ばぬと、みなみな思ひ慣れたれども、近代にこの道の聖(ひじり)とも聞こえし、本座の一忠(いつちゆう)、ことにことに物数を尽くしける中にも、鬼人の物まね、怒れるよそほひ、洩れたる風体なかりけるとこそ承りしか。しかれば、亡父はつねづね、一忠が事を、「我が風体の師なり」と、まさしく申ししなり。
されば、ただ、人ごとに、あるいは情識(じやうしき)、あるいは得ぬゆゑに、ひと向きの風体ばかりを得て、十体(じつてい)にわたる所を知らで、よその風体を嫌ふなり。これは、嫌ふにはあらず、ただかなはぬ情識なり。されば、かなはぬゆゑに、一体(いつてい)得たるほどの名望を、一旦(いつたん)は得たれども、久しき花なければ、天下に許されず。堪能(かんのう)にて、天下の許されを得んほどの者は、いづれの風体をするとも、面白かるべし。風体・形木(かたぎ)は面々各々なれども、面白き所はいづれにもわたるべし。
この面白しと見るは花なるべし。これ、和州・江州、または田楽の能にも洩れぬ所なり。されば、洩れぬ所を持ちたる為手(して)ならでは、天下の許されを得ん事、あるべからず。
また云はく、ことごとく物数を極めずとも、仮令(けりやう)、十分に七八部極めたらん上手の、その中にことに得たる風体を、我が門弟の形木にし極めたらんが、しかも工夫あらば、これまた、天下の名望を得つべし。さりながら、げには、十分に足らぬ所あらば、都鄙(とひ)・上下において、見所の褒貶(ほうへん)の沙汰(さた)あるべし。
現代語訳
そもそも、この申楽の芸は、大和(やまと)と近江(おうみ)では芸風を異にしている。近江申楽では、まづ幽玄の境地を取り上げて、物まねを次とし、姿の美しさを基本とする。一方、大和申楽では、まず物まねを取り上げて、あらゆる演目を数多くこなして、そのうえで幽玄をを実現しようとするのである。けれども、どちらの芸風も、幽玄と物まねの二つの要素を欠いてはいない。そこで、ある一方向の芸しかしない者は、能の神髄を理解していない人だというべきであろう。
さて、大和申楽の芸風は、写実的な人体やそうした役柄によるせりふ回しの面白さを基本として、たとえば、いかめしく堂々とした能姿、あるいは、荒々しい鬼の演技、といった演目を、得意芸であると観客も考え、芸人たちの稽古ももっぱらこればかりであるけれども、亡き父観阿弥が名声を博していた絶頂期に演じた「静が舞の能」や嵯峨の大念仏の女物狂いの物まね」は特に得意な演目だったので、京都人からの称賛・名声を博したことは世上に紛れもなく有名であった。これこそが、この上ない幽玄な芸風であったろう。
また、田楽の芸風は、特に猿楽とは異質な芸能であり、観客も、申楽と同列には評価できないと、皆、思い、慣れていたけれども、近代にこの道の聖と聞えた、田楽本座の一忠は、あらゆる演目・人体をすべて演じ尽した中でも、鬼人の物まねや、荒々しい鬼の演技についても、演じ洩れの芸はなかったと聞いている。
だからこそ、亡父観阿弥はいつも流派の異なる一忠のことを、「我が芸の師である」と本当に言っていたものである。
さて、ただ、どんな人でも、あるいは心から、あるいはできないものだから、一方向の演技ばかりを行い、あらゆる芸を演じこなすという境地の素晴らしさを認識せず、他座の芸を嫌うのである。これは嫌うのではなく、ただ、実力不相応のいさかい心である。
さて、できないものだから、一つ得意芸があるという程度の評判を、一時的には得たとしても、永続する魅力は無いので、京の都で名声を博することがあるはずがないのである。
さらに付け加えると、すべての演目を極めなくても、たとえば、七八部の演目を十分極めた上手が、その中でも特に得意な演目の能を、自分の一座の代表演目として習熟し、しかもそれに工夫が加味されていれば、これもまた、京都で名声を博することができるであろう。しかし、完璧ではない部分があれば、観客毎の住居地・身分の違いによって、評価が分かれ、安定した評価は得られないであろう。
語句
■和州-大和猿楽。とくに観世の座の猿楽を指す。■江州-近江猿楽。とくに犬王の座の猿楽を指す。■幽玄の境-優美な境地。具体的には歌舞の芸。■取り立てて-第一義として。■物まね-扮装に応じた写実的な演技。■かかり-姿の美しさ。■本とする-基本とする。■物数を尽くして-どのような役でもこなすこと。■ひと向き-一方面。■まこと-本当には。■義理-文句の面白さ。■長のあるよそほひ-いかめしく堂々とした能姿。■怒れる振舞-荒々しい鬼の演技。■亡父-観阿弥。■静が舞の能-散逸曲。静御前が登場して舞を舞う能で、『三道』に「静、本風あり」とあり、『五音』上にも「静 亡父曲」として謡の一節を引用。「吉野静」あるいは「二人静」の原曲に比定<比較して(成立年代などを)推定すること。>される。■嵯峨の大念仏の女物狂い-散逸曲。『三道』に「昔の嵯峨物狂いの狂女、今の百万、これなり」とあり、「百万」の翻案原曲。■世以て-世上に。「世に」の強意。■田楽-平安末期以来、大流行を続けた人気芸能で、新座・本座の両座があり、観阿弥時代以前より能を演じるようになっていた。応永二十年(1413)以後、新座の名人増阿弥が活躍。■各別の事にて-猿楽とは別芸能の意。能の芸風も大きく相違していたらしい。■見所-観客。■申楽(さるがく)の風体には-猿楽と同列には。■本座-京白河を本拠とした田楽座。■一忠-石松とも呼ばれた名人で、文和三年(1354)没(常楽記)。■我が風体の師-一忠没時、観阿弥二十二歳。猿楽役者でありながら私淑(直接に教えは受けないが、ひそかにその人を師と考えて尊敬し、模範として学ぶこと。)していたのでああろう。■十体にわたる所-あらゆる風体の能。■嫌ふ-自流の演目と差別して演じない事。■かなはぬ情識-実力不相応のいさかい心。■仮令-たとえば。■形木-文字や模様をすり付けるための版木。転じて基準となる様式の事。■面々各々-各人各様。■面白き所-面白さの意。■洩れぬ所を持ちたる為手-十体にわたり、花を供えた為手の事。■我が門弟の形木-自流の様式。■都鄙(とひ)・上下-地域差と身分差。■褒貶(ほうへん)の沙汰-安定して高い評価を得られないことをいう。
備考・補足
■散逸曲-散りうせてしまった曲。■褒貶-ほめることと、けなすこと。■沙汰-評判。うわさ。
原文
風姿花伝 奥義に云はく
およそ、能の名望を得る事、品々多し。上手は目利かずの心にあひかなふ事難し。下手は目利きの眼に合ふ事なし。下手にて目利きの眼にかなはぬは、不審あるべからず。上手の目利かずの心に合はぬ事、これは目利かずの眼の及ばぬ所なれども、得たる上手にて工夫あら為手ならば、また、目利かずの眼にも面白しと見るやうに能をすべし。
この工夫と達者とを極めたらん為手をば、花を極めたるとや申すべき。されば、この位(くらゐ)に至らん為手は、いかに年寄りたりとも、若き花に劣る事あるべからず。されば、この位を得たらん上手こそ、天下(てんが)にも許され、また、遠国(をんごく)・田舎(でんじや)の人までも、あまねく面白しとは見るべけれ。
この工夫を得たらん為手は、和州(わしう)にも江州(がうしう)へも、もしは田楽の風体までも、人の好み・望みによりて、いづれにもわたる上手なるべし。このたしなみの本意をあらはさんがため、風姿花伝を作するなり。
現代語訳
そもそも、能芸において名声と人気を博することについては、公演地の違いや観客の身分の上下の違いなどでいろいろな場合がある。。演技上手な者が、鑑識眼のない観客の気に入る事は難しい。下手な役者が、鑑識眼の優れた観客には問題にもされない。下手な役者が目利きに気に入られないのは、別に不思議なことではない。上手が鑑識眼の無い観客に気に入られない事、これは、目利かずの観客の至らなさの結果ではあるが、能芸を極めた上手でもあり、しかも芸の工夫があるような役者であれば、そういう場合でもまた、鑑識眼のない観客にも「面白い」と見られるように能を演じることができるであろう。
この工夫と技術を極めた役者を、能の花を極めたと言うべきであろうか。こういう境地に達した役者は、どんなに年を取っていようとも、一時的な若さの魅力に劣る事はないのである。それで、こういう境地を獲得した上手な役者は、京の都でも名声を博し、また、都を離れた遠国や田舎などに住む鑑識眼の低い観客までもが、すみずみまで広く面白いと感じるはずであろう。
こういう芸の工夫を会得した役者は、大和申楽の出し物でも、近江申楽の出し物でも、または田楽の能までをも、観客の好みや希望に応じて、どんな芸をもこなす上手なのであろう。こういう芸の稽古のやり方を明らかにするため、『風姿花伝』を作ったのである。
語句
■名望-名声と人気。■品々多し-都鄙(とひ)・上下により、十体にわたる役者の風体の多様さに対応して、名望の内容も種々に渡る事。特定の催しに集まったすべての観客の好みに対応せよというのではなく、興行地や主要な客の身分等に応じて演能し、どんな相手からも喝采を博すべきことを書く。■目利かず-鑑識眼のない観客。■眼に合ふ-鑑識眼に適うこと。■得たる上手-能の奥義を体得した上手。■工夫と達者-観客を満足させる演出の工夫と練達の演技術。■この位に-「年来稽古条々」の五十有余で言及した晩年の観阿弥の至芸が念頭にある表現。■天下-後文の「遠国・田舎」に対して、京都のこと。■このたしなみの云々-以下、執筆動機を説明。「風姿花伝」の書名が奥義編の段階で確定したことを思わせる。「このたしなみ」とは十体にわたる上手として、都鄙(とひ)・上下のあらゆる観客の間に名声を博することで、「問答条々」にも片鱗が見えるが、体系的な所説としては奥義編で初めて説かれる稽古目標。本編の全体がこの論で一貫する。■本意-本当の心。真の意味。
原文
風姿花伝 奥義に云はく
かやうに申せばとて、我が風体の形木(かたぎ)のおろそかならむは、ことにことに能の命あるべからず。これ、弱き為手なるべし。我が風体の形木を極めてこそ、あまねき風体をも知りたるにてはあるべけれ。
あまねき風体を心にかけんとて、我が形木に入らざらん為手は、我が風体を知らぬのみならず、よその風体をも、確かにはまして知るまじきなり。
されば、能弱くて、久しく花はあるべからず。久しく花のなからんは、いづれの風体をも知らぬに同じかるべし。しかれば、花伝の花の段に、「物数を尽し、工夫を極めて後、花の失せぬ所をば知るべし」と言へり。
現代語訳
このように述べたからと言って、基本となる自分本来の芸がいい加減なものなら、決して、自流の能を永続させることはできないであろう。このようなものは、その場限りの芸しかできない役者である。自流の芸の基本を確立させてこそ、近江猿楽や田楽といったようなすべての芸風・演目をも知っているということになるのであろう。
ひろくすべての芸風を目標にしようとして、自分の基本芸が確立していない役者は、自分の能について未熟であるばかりでなく、ましてや他流の芸をも、しっかりと習得できるはずがないのである。
こんなことでは、芸に力強さはなく、芸の魅力も長続きするはずがない。花が長続きしないのは、どのような芸風をも会得していないのと同じである。だから、『花伝』の「第三問答条々」の「花」の段で、『あらゆる演目を演じ尽し、演出の工夫を徹底的にやりぬいて後に、永遠の芸の魅力を獲得できよう』と述べたのである。
語句
■かやうに云々-以下、十体説の補足説明。■我が風体の形木-基本となる自分本来の芸の様式。■能の命-自流の能を永続させるための要件。伝承されるべき確立された芸風。■弱き為手-伝えるべき芸風が確立していない役者。その場限りの芸しかない役者。■あまねき風体-近江申楽や田楽の演目をも包摂した芸風。実際に田楽能を改作して自演することがあった。■我が形木に入らざらん為手-自分の基本芸が確立していない役者。■能弱く-能の命がないこと。永続性のない芸。
備考・補足
■包摂-一定の範囲の中に包み込むこと。
原文
風姿花伝 奥義に云はく
秘義に云はく、そもそも、芸能とは、諸人の心を和らげて、上下の感をなさむ事、寿福増長のもとゐ、遐齢延年(かれいえんねん)の方(ほう)なるべし。極め極めては、諸道ことごとく寿福延長ならんとなり。ことさらこの芸、位(くらゐ)を極めて、家名を残す事、これ、天下の許されなり。これ、寿福増長なり。
しかれども、ことに故実あり。上根上智(じやうこんじやうち)の眼(まなこ)に見ゆる所、長(たけ)、位の極まりたる為手(して)におきては、相応至極なれば、是非なし。およそ、おろかなるともがら、遠国(をんごく)、田舎(でんじや)の卑しき眼(まなこ)には、この長・位の上がれる風体、及びがたし。
これをいかがすべき。この芸とは、衆人(しゆにん)愛嬌(あいぎやう)を以(も)て、一座建立の寿福とせり。ゆゑに、あまり及ばぬ風体のみなれば、また諸人の褒美欠けたり。このために、能に初心を忘れずして、時に応じ、所によりて、おろかなる眼にもげにもと思ふやうに能をせん事、これ寿福なり。よくよくこの風俗の極めを見るに、貴所・山寺、田舎・遠国、諸社の祭礼に至るまで、おしなべてそしりを得ざらんを、寿福達人の為手とは申すべきをや。されば、いかなる上手なりとも、衆人愛嬌欠けたる所あらむをば、寿福増長の為手とは申しがたし。しかれば、亡父は、いかなる田舎・山里のかたほとりにても、その心を受けて、所の風儀を一大事にかけて、芸をせしなり。
かやうに申せばとて、初心の人、それほどはなにとて左右(さう)なく極むべきとて、退屈の儀はあるべからず。この条々を心底にあてて、その理(ことわり)をちちと取りて、了簡(れうけん)を以て、我が分力(ぶんりき)に引き合はせて、工夫をいたすべし。
およそ、今の条々・工夫は、初心の人よりはなほ上手におきての故実・工夫なり。たまたま得たる上手になりたる為手も、身を頼み、名に化かされて、この故実なくて、いたづらに名望ほどは寿福欠けたる人多きゆゑに、これを嘆くなり。得たる所あれども、工夫なくてはかなはず。得て工夫を極めたらんは、花に種を添へたらんがごとし。
たとひ、天下に許されるを得たるほどの為手も、力なき因果にて、万一少しすたるる時分ありとも、田舎・遠国の褒美の花失(う)せずは、ふつと道の絶ふる事はあるべからず。道絶えずば、また天下の時に合ふ事あるべし。
一、この寿福増長のたしなみと申せばとて、ひたすら世間の理にかかりて、もし欲心に住(ぢゆう)せば、これ、第一、道のすたるべき因縁なり。道のためのたしなみには、寿福増長あるべし。寿福のためのたしなみには、道まさにすたるべし。道すたらば、寿福おのづから滅すべし。正直円明(ゑんみやう)にして世上(せじやう)万徳(ばんとく)の妙花(めうくわ)を開く因縁なりと、たしなむべし。
現代語訳
秘伝に言う。そもそも、芸能とはあらゆる人々の心を豊かにし、あらゆる階層の観客に同じ感動を生み出させるのである。そして、それが、長寿と幸せを増大する基となり、長寿の方策となるのである。究極的には、あらゆる芸道はすべて、寿福延長を達成させるものであろう、とも言われている。特に申楽の芸で、最高の芸位に達して子孫に家名を残す事こそが天下に名手として認められることである。これこそが能役者にとっての寿福延長にもなるのである。
しかし、この身分の違いを超えて感動を与えることについて、経験上考えなければならないことがある。身分高く鑑識眼のある観客が鑑賞するのが、品格や芸位が最高の役者である場合は、眼識と芸位が釣り合った組み合わせなので問題はない。ところが、愚かな連中、地方人の教養不足の眼では、この品格の高い芸は理解できない。
こういう場合どうしたらいいだろうか。能芸というものは、多くの人に愛され親しまれてこそ一座が成り立っていくものである。それで、あまりにも観客に理解できない高尚な芸のみでは、やはり多くの人の賞賛を得ることはできない。それを防ぐためには、能をやる場合に、それまでに演じてきた演目を忘れずに、時に応じ、場所によって、鑑識眼の無い観客にも”すばらしい”と思わせるような芸を演じることが一座繁栄の基本である。
よくよく、この芸能鑑賞における演者と観客との究極的なあり方を考えると、貴人の御前や山寺、田舎・遠国、諸国の神社の祭礼にいたるまで、あらゆる場所での演能で悪評を蒙らない者を、一座に寿福の増長をもたらす練達の役者というべきではなかろうか。したがって、どんなに上手であっても、多くの人々に愛され、親しまれるという点で欠けたところのあるような役者を、福徳を招く達人とは言いがたいのである。だからこそ亡父は、どんな田舎や山里の辺鄙な所であっても、その土地の人心・好みに合わせ、土地柄やその土地の人々の気質を重視して能を演じたのである。
このように言ったからといって、未熟な役者が、そこまではどうやってたやすく極める事が出来ようか。簡単には到達できないからといって意欲を失ってはならない。『風姿花伝』に述べられている種々の能芸に関する項目を心に刻み、その意味する所を少しづつ取り入れ、思いを巡らせて自分の力量に応じて、工夫をしなければならない。
だいたい、今、述べた内容や工夫の数々は、初心の役者向けというのではなく、もっと格上な役者の場合の心得・工夫である。たまたま芸達者になった役者も、自分の芸に自惚れ、名声に惑わされて、この衆人愛嬌という心得がなくて、空名ばかりで評判ほどには福徳の薄い人が多いために、このことを嘆くのである。得意な演目があっても、工夫というものがなければだめである。得意な演目があってなおかつ工夫がこらされていれば、花に種を添えて持っているようなものである。
たとえ、京の都で名声を博した役者であっても、いかんともしがたい不運に見舞われ、まんがいち、落ちぶれることがあっても、田舎や遠国で培った演技を失くさなければ、完全に能芸の道を絶たれるということがあるはずがない。
芸能の道が絶えなければ、いつかまた、京の都の名声を取り戻すことがあるであろう。
一、この寿福増長の稽古が大切だからといって、ひたすら理財ということにこだわって、もしも私利私欲に走れば、これこそ、芸道がすたれる第一の原因である。芸道精進の稽古には、福徳の増進という利益があろう。福徳自体を目指した稽古では、芸道は必ずや断絶するであろう。、芸道が断絶すれば、寿福は自ずから消滅するであろう。心正しく明らかであることが、この世にあらゆる福徳をもたらすはずの、能芸のすばらしい魅力を花開かせる要因であるということを心して、稽古に励むがよい。
語句
■芸能-ここは能の意味ではなく、諸芸一般を広く言っている。■すべての感-すべての観客の感動。■寿福増長-長寿と幸福を増長。■遐齢延年-「遐齢」、「延年」とも長生きを意味する語。■方-方策。■諸道ことごとく寿福延長ならん-あらゆる芸道。いかなる芸道においても寿福延長が達成されるとの意。■なさむ事-後に「にてなどが省略された縮約文体。■寿福延長-寿福増長と同じ。それを見る者の歳をも延ばすという意識を反映した表現。■この芸-申楽の芸。能芸。書き出しは芸能の社会的効用を説きながら、この一文で芸能に関わる目的に話題が展開する。■位を極めて-最高の芸位に到達して。■家名-「佳名」とも解釈できる。後継者に伝承する意義を強く意識する世阿弥としては、「家名」が適当か。■これ-ここは「天下の許され」を得たことによってもたらされる、役者個人の「寿福増長」。■ことに-「ここに」の誤りか。■上根上智-優れた資質と智慧。ここは身分高く鑑識眼のある観客の事。■長・位-芸の格と位。■相応至極なれば-役者と観客のレベルが極めてよく一致すること■是非なし-問題がない。■おろかなるともがら-身分が低く無見識な連中。■卑しき-無教養な観客。■上がれる-高度なこと。■衆人愛敬-多くの人に愛され親しまれること。■一座建立の-座の経営が成り立っていくこと。■及ばぬ風体-観客に理解できない高踏(俗世間を離れて高尚な世界に生きること)的な芸風。■初心-この「初心」は「別紙口伝」第四条に説く十体論を踏まえる。今まで習得したあらゆる演目を忘れぬ事。■寿福-「寿福増長のもとゐなり」の意。具体的には、一座繁栄の基本である、の意。■風俗の極め-芸能鑑賞における演者と観客の究極的なあり方。■寿福達人-一座に寿福の増長をもたらす練達の役者。■田舎・山里のかたほとり-都を遠く離れた辺鄙な場所の事。■その心-その土地の人心・好み。■所の風儀-土地柄やその土地の人々の気質。■左右なく-そうなく たやすく、ためらいなく、直ちに。■退屈の儀-気持ちが萎えること。意欲を失うこと。■ちちと-すこしづつ。ここは適当にの意に近いか。■了簡-思いをめぐらすこと。考え。思案。■我が分力-自分の力量。■たまたま-運よく。■いたづらに名望ほどは寿福欠けたる人-空しい名声ばかりで繁栄には程遠い人。■得たる所あれども-得意な演目があっても。■力なき因果-いかんともしがたい不運。■褒美の花-褒美が獲得できるだけの(芸の)花。■ふつと-完全に。■道の絶ふる事-芸人として立ちゆかなくなること。■一、前条の追記であることを示すもの。書状などによくある形式。■世間の理-営利重視の原則。■因縁-原因。■円明-明らかで方正(心や行いが正しい事)なこと。■万徳の妙花-芸人としての最高の栄誉。この前後は、誠実でまっすぐな心が、世間で最高の名声を博する原因となる、の意。
原文
風姿花伝 奥義に云はく
およそ、花伝の中、年来稽古より始めて、この条々をしるす所、まつたく自力より出(い)づる才学ならず。幼少よりこのかた、亡父の力を得て人と成りしより、二十余年が間、目に触れ、耳に聞き置きしまま、その風を受けて、道のため、家のため、是を作する所、私(わたくし)あらむものか。
現代語訳
そもそも、「花伝」のうち、年来稽古から始まって、この各条を記したのは、まったくもって、自分の力から出てきた知識ではない。幼少より、これまで亡き観阿弥の力を頼りに成人したが、二十余年の間、父の芸に触れ、耳で聞き、その芸風を受けて、能芸の道のため、観世の家のために、これを執筆したものであり、いささかも私心は無いのである。
語句
■花伝-本書本来の書名。■才学-学識。知識。■二十余年-世阿弥は二十二歳で父と死別した。
備考・補足
<参考文献>
・風姿花伝・三道 現代語訳付き 世阿弥・竹本幹夫訳注
・花伝書(風姿花伝) 世阿弥編 川瀬一馬校注、現代語訳
・風姿花伝 世阿弥編 野上豊一郎・西尾実校訂
・現代語訳 風姿花伝 世阿弥著 水野聡訳
・風姿花伝 世阿弥 現代語訳:夏川賀央
前の章「風姿花伝第四 神儀(じんぎ)に云(い)はく」|次の章「花伝第六 花修(くわしゆ)に云はく」