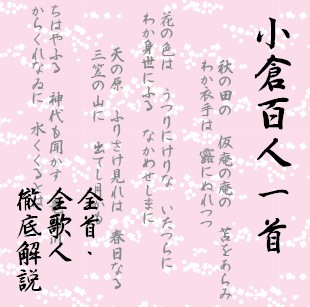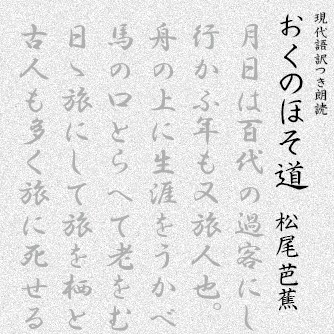宇治拾遺物語 1-3 鬼に瘤を取られる事
【無料配信中】福沢諭吉の生涯
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
これも昔、右の顔に大きなる瘤(こぶ)ある翁ありけり。大柑子(おほかうじ)の程なり。人に交じるに及ばねば、薪をとりて世を過ぐる程に、山に行きぬ。雨風ははしたなくて帰るに及ばで、山の中に心にもあらずとまりぬ。また木こりもなかりけり。恐ろしさすべき方(かた)なし。木のうつほのありけるにはひ入りて、目も合はず屈(かが)まりゐたる程に、遥(はる)かより人の音多くして、とどめき来る音す。
いかにも山の中にただ一人ゐたるに、人のけはひのしければ、少しいき出(い)づる心地して見出(みいだ)しければ、大方(おほかた)やうやうさまざまなる者ども、赤き色には青き物を着、黒き色には赤き物を褌(たふさぎ)にかき、大方目一つある者あり、口なき者など、大方いかにもいふべきにあらぬ者ども百人ばかりひしめき集りて、火を天の目のごとくにともして、我がゐたるうつほ木の前にゐまはりぬ。大方いとど物覚えず。
宗(むね)とあると見ゆる鬼横座(よこざ)にゐたり。うらうへに二ならびに居並みたる鬼、数を知らず。その姿おのおの言ひ尽くしがたし。酒参らせ、遊ぶ有様、この世の人のする定(ぢやう)なり。たびたび土器(かはらけ)始(はじま)りて、宗(むね)との鬼殊(こと)の外(ほか)に酔(よ)ひたる様(さま)なり。末より若き鬼一人立ちて、折敷(をしき)をかざして、何(なに)といふにか、くどきくせせる事をいひて、横座の鬼の前に練り出でてくどくめり。横座の鬼盃を左の手に持ちて笑(ゑ)みこだれるさま、ただこの世の人のごとし。舞うて入りぬ。次第に下より舞ふ。悪(あ)しく、よく舞ふもあり。
あさましと見る程に、横座にゐたる鬼のいふやう、「今宵(こよひ)の御遊びこそいつにもすぐれたれ。ただし、さも珍しからん奏(かな)でを見ばや」などいふに、この翁物の憑(つ)きたるけるにや、また然(しか)るべく神仏(かみほとけ)の思はせ給(たま)ひけるにや、「あはれ、走り出でて舞はばや」と思ふを、一度(いちど)は思ひ返しつ。それに何(なに)となく鬼どもがうち揚げたる拍子(ひやうし)のよげに聞えければ、「さもあれ、ただ走り出でて舞ひてん、死なばさてありなん」と思ひとりて、木のうつほより烏帽子(えぼし)は鼻に垂(た)れかけたる翁の、腰に斧(よき)といふ木伐(き)る物さして、横座の鬼のゐたる前に躍(をど)り出でたり。
この鬼ども躍りあがりて、「こは何(なに)ぞ」と騒ぎ合へり。翁伸びあがり屈(かが)まりて、舞ふべき限り、すぢりもぢり、ゑい声を出(いだ)して一庭(ひとには)を走りまはり舞ふ。横座の鬼より初めて、集りゐたる鬼どもあさみ興ず。
横座の鬼の曰(いは)く、「多くの年比(としごろ)この遊びをしつれども、いまだかかる者にこそあはざりつれ。今よりこの翁、かやうの御遊びに必ず参れ」といふ。翁申すやう、「沙汰(さた)に及び候(さぶら)はず、参り候ふべし。この度(たび)にはかにて納(をさ)めの手も忘れ候ひにたり。かやうに御覧にかはひ候はば、静かにつかうまつり候はん」といふ。横座の鬼、「いみじく申したり。必ず参るべきなり」といふ。
奥の座の三番にゐたる鬼、「この翁はかくは申し候へども、参らぬ事も候はんずらんと覚え候ふに、質(しち)をや取らるべく候ふらん」といふ。横座の鬼、「然(しか)るべし、然るべし」といふて、「何をか取るべき」と、おのおの言ひ沙汰(さた)するに、横座の鬼の言ふやう、「かの翁が面(つら)にある瘤(こぶ)をや取るべき。瘤は福の物なれば、それをや惜(を)しみ思ふらん」といふに、翁がいふやう、「ただ目鼻を召すとも、この瘤は許し給ひ候はん。年比(としごろ)持ちて候ふ物を故(ゆゑ)なく召されん、すぢなき事に候ひなん」といへば、横座の鬼、「かう惜しみ申すものなり。ただそれを取るべし」といへば、鬼寄りて、「さは取るぞ」とてねぢて引くに、大方(おほかた)痛き事なし。さて、「必ずこの度(たび)の御遊びに参るべし」とて、暁に鳥など鳴きぬれば、鬼ども帰りぬ。翁顔を探るに、年比(としごろ)ありし瘤跡なく、かい拭(のご)ひたるやうにつやつやなかりければ、木こらん事も忘れて家に帰りぬ。妻の姥(うば)、「こはいかなりつる事ぞ」と問へば、しかじかと語る。「あさましきことかな」といふ。
隣にある翁、左の顔に大きなる瘤ありけるが、この翁、瘤の失(う)せたるを見て、「こはいかにして瘤は失せ給ひたるぞ。いづこなる医師(くすし)の取り申したるぞ。我に伝へ給へ。この瘤取らん」といひければ、「これは医師の取りたるにもあらず、しかじかの事ありて、鬼の取りたるなり」といひければ、「我(われ)その定(ぢやう)にして取らん」とて、事の次第をこまかに問ひければ、教へつ。この翁いふままにして、その木のうつほに入りて待ちければ、まことに聞くやうにして、鬼ども出(い)で来(き)たり。
ゐまはりて酒飲み遊びて、「いづら、翁は参りたるか」といひければ、この翁恐ろしと思ひながら揺(ゆる)ぎ出(い)でたれば、鬼ども、「ここに翁参りて候(さぶら)ふ」と申せば、横座の鬼、「こち参れ、とく舞へ」といへば、さきの翁よりは天骨(てんこつ)もなく、おろおろ奏(かな)でたりければ、横座の鬼、「この度(たび)はわろく舞うたり。かへすがへすわろし。その取りたりし質の瘤返し賜(た)べ」といひければ、末(すゑ)つ方(かた)より鬼出で来て、「質の瘤返し賜(た)ぶぞ」とて、今方々(かたかた)の顔に投げつけたりければ、うらうへに瘤つきたる翁に翁にこそなりたりけれ。物(もの)羨(うらや)みはすまじき事なりとか。
現代語訳
これも昔、右の顔に大きい瘤のある爺さんがいた。大きなみかんぐらいのものである。そのため人と交わることができないので、薪をとって生活しているうちに、ある日、山に行った。雨風がひどいので帰ることができなくなり、山の中に、やむをえず泊まることになった。他に木こりもいなかった。どうしようもなく恐ろしい。空洞のある木に這入って、眠ることもできずにうずくまっている間に、遥か向こうから人の声が多くして、どやどやとやってくる音がする。いかにも山の中にただ一人でいるところに、人の気配がしたので、少し正気づいた感じがして外を見ると、およそあれこれさまざまな者たちが、赤い色には青い物を着て、黒い色には赤い物をふんどしにして、およそ目が一つある者もあり、口のない者など、およそなんとも言いようのない者たちが百人ほどひしめき集まって、火を太陽のようにともして、爺さんが座っている空洞の木の前を取り囲んで座った。まねで正気でもいられない。
その中の首領であると見える鬼が上座に座っている。左右二列に並んで座っている鬼は数もしれぬほど多い。その姿はそれぞれ言い尽くしがたいほど異様である。酒を持ってこさせ、音楽の遊びをするようすは、この世の人がするのとかわらない。たびたび盃をくみかわして、首領格の鬼は格別に酔っているようすである。末座から若い鬼が一人立って、お盆を頭上にかざして、何といっているのか、しきりに口説きたて、何か節のついた言葉を言って、上座の鬼の前にゆらりと歩み出て、なにかくどくどいっているようだ。上座の鬼が盃を左の手に持って笑いくずれるさまは、まったくこの世の人のようである。若い鬼は舞い終わって退いた。下座の鬼から順番に舞う。まずく舞う者もあればうまく舞う者もある。呆れて見ているうちに、上座に座っている鬼の言うことに、「今宵の御遊びはいつもより特に素晴らしい。ただし、もう少し珍しい舞を見たいものだ」など言うので、この爺さんは何かに取り憑かれでもしたか、またはそのように神仏が思わせなさったことか、「ええい、走り出して舞ってやろう」と思うのを、一度は考え直した。それでも何となく鬼たちが上げた拍子がよい感じに聞こえたので、「そうはいっても、とにかく走り出して舞おう。死ぬならそれはその時だ」と心を決めて、木の空洞から、烏帽子が鼻に垂れかけた爺さんが、腰に手斧という木を伐る物をさして、上座の鬼の座っている前に躍り出たのである。この鬼たちは飛び上がって驚いて、「これは何だ」と騒ぎ合った。爺さんは伸び上がりうずくまって、舞える舞はすべて、体をくねくねさせて、「えい」という掛け声を出してその場を走り回って舞う。上座の鬼から始めて、集まっている鬼たちは目をみはっておもしろがった。
上座の鬼が言うことに、「長年この遊びをしてきたが、いまだにこのような者に逢ったことがないぞ。今後はこの爺さんよ、こうした御遊びには必ず参るがよい」という。爺さんが言うことに、「ご命令されるまでもなく、参りましょう。今回は急なことで、舞い納めの手も忘れてございます。こうしてお気に召していただけますなら、次はじっくりと舞って御覧に入れましょう」という。上座の鬼は、「立派に申したことよ。必ず参るのだぞ」という。奥の座の三番目にすわっている鬼が、「この爺さんはこう申しておりますが、参らぬこともございましょう。そう思いますので、質草を取っておかれるべきでございましょう」という。上座の鬼は、「そうだ、そうだ」といって、「何を質草に取ったらいいだろう」と、おのおの議論するに、上座の鬼の言うことは、「あの翁の顔にある瘤を取ればよい。瘤は縁起物なので、それを惜しいと思うだろう」というと、爺さんが言うことに、「ただ目鼻を取られるとしても、この瘤はお許しくださいませ。長年つけてございます物を理由なく取られるのは、筋の通らない事でございます」と言えば、上座の鬼は、「このように惜しんで申しているものである。ただそれを取るがよい」と言えば、鬼が寄って、「それでは取るぞ」といってねじって引っ張ると、少しも痛くない。そうして、「必ず次の御遊びに参るがよい」といって、明け方に鳥など鳴いたので、鬼たちは帰った。翁が顔を探ると、長年ついていた瘤は跡もなく、拭い取ったように、まったく無くなっていたので、木こりのしごとをする事も忘れて家に帰った。妻である婆さんが、「これはどうした事か」と質問すると、これこれだと語る。「呆れたことよ」と言う。
隣に住んでいる爺さんが、左の顔に大きな瘤があったが、この爺さんの瘤が無くなったのを見て、「これはどうやって瘤をなくされたのですか。どこにいる医者がお取り申したのですか。私にお教えください。この瘤を取りたいので」と言ったので、「これは医者が取ったのではありません。これこれの事があって、鬼が取ったのです」と言ったので、「私もその通りにして取りましょう」といって、事の次第をこまごまと質問したので、教えた。この爺さんは言うままにして、その木の空洞に入って待っていると、ほんとうに聞いたとおりで、鬼たちが出てきた。木のまわりに座って酒を飲んで音楽の遊びをして、「どこだ、爺さんは参ったか」といったので、この爺さんは恐ろしいと思いながら震えて出ていくと、鬼たちは、「ここに爺さんが参ってございます」と申せば、上座の鬼は、「こちらへ参れ。はやく舞え」と言うと、前の爺さんよりは不器用で、たどたどしく舞ったので、上座の鬼は、「今回はまずく舞ったものだ。返す返すもまずい。あの質に取っておいた瘤を返して与えよ」といって、もう片方の顔に瘤を投げつけると、顔の両側に瘤のついた爺さんになってしまった。だから人をうらやましがるのは良くないことだとか。
語句
■柑子-こうじみかん。今のみかんより小さく酸味が強い。■及ばず-できない。■世を過ぐる-生活をたてる。■はしたなし-激しい。■うつほ-(岩や木の)中が空洞になっている所。ほら穴。■ありけるに-「ける」が過去の助動詞の連体形であり、「ありける」つまり「あった」の下に「場所」とか「所」といった位置を示す語が省略されていると見る。■目も合はず-一睡もしないで。眠れないままに。■とどめく-がやがやと騒ぐ。■少しいき出(い)づる心地して-恐怖感から少し解放されて、ほっと一心地のついたさま。■やうやうさまざまなる者ども-種々様々な姿・形をした者ども。後代のいわゆる赤鬼・青鬼のような姿の鬼だけでなく、百鬼夜行と呼ばれた多様な怪物ども。■褌(たふさぎ)-さるまた・褌の類。■かき-「掻き」で締めるの意。■天の目-日輪・太陽のこと。■いとどもの覚えず-まったくわけがわからない。■宗(むね)-主要な者。中心人物。首領。■横座-正面の座席。上座。■うらうへに二並びに-「うらうへ」は裏と表。ここは、「左右」二列に向かい合って。■ゐ並みたる-並んで座っている。■おのおの言ひ尽くしがたし-どれも言葉では言い尽くしにくい。■酒参らせ-酒をさしあげ。■する定なり-するとうりである。「定」は、連体語を受けて、「・・・とうりである」の意。■土器(かはらけ)-素焼きの土器。ここでは、盃のやり取りを指す。■宗との鬼-首領にあたる鬼。■ことのほかに-格別に。■折敷(をしき)-縁の付いた四角い盆■何と言ふにか-何を言っているのか。■くどきくせせることを言ひて-くどくどと同じことを繰り返しながら、べらべらと勝手にしゃべりまくる様子。「くどく」はくどくどと。「くせせる」は、早口に述べる事か。■練り出でて-ゆっくりと歩み出て。■くどくめり-くどくどと述べ立てるようである。■笑みこだる-笑い転げる事。「こだる」は倒れかかること。■ただ-ひとえに。■舞ひて入りぬ。-舞って退いた。■次第に下より-順を追って下座から。■あしく、よく舞ふもあり-下手に舞うのもいれば、上手に舞うのもいる。■あさましと-あきれたことだと。■言ふやう-言うには。■いつにもすぐれたれ-いつもより勝っている。■さも-いかにも。■奏(かな)で-楽を奏して舞いを舞うこと。ここでは舞そのものを指す。「奏づ」の連用形の名詞化。■見ばや-見たいものだ。■ものの憑きたるけるにや-何かの霊が乗り移ったのだろうか。■しかるべく-そのように。■あはれ-ああ。■舞はばや-舞いたい。■それに-それでも。■うちあげたる拍子の-手や物をたたいて歌いはやす様子が。■よげに-よさそうに。■さもあれ-ええままよ、ひとつやってみよう。「さもあらばあれ」と同意。何かを思い切ってする時にいう言葉。■舞ひてん-舞ってやろう。■死なばさてありなんと思ひとりて-死んだら死んだでそれまでのことよと思い定めて。■烏帽子-元服した男のかぶりもの。古くは、黒の紗(しゃ)または帛(はく)で作ったが、後には紙で作って、黒の漆で塗り固めた。平安中期からは、貴人は平服だけに用いたが、無官の者は晴れの時にもかぶった。■斧(よき)-斧の小さなもの。手斧。木を伐る道具。■踊り出でたり-飛び出した。■踊りあがりて-飛び上がって。■こは何ぞ-これは何だ。■舞ふべき限り-舞えるだけ。■すぢりもぢり-さまざまに身をよじらせること。■えい声-「えい」という掛け声。■一庭-庭全体。庭じゅう。■あさみ興ず-驚きあきれて面白がる。■言はく-言うには。■多くの年頃比-長い年月にわたって。■かかる-このような。■つれ-完了の助動詞「つ」の已然形。■かやうの-このような。■御遊びにかならず参れ-自分の遊宴に「御」という尊敬の語を用いるとともに、相手に「参れ」という謙譲の語を用いるのは、話者が絶対の地位にあることを示す。いわゆる絶対敬語の一つの例にあたる。■沙汰に及び候はず-仰せには及びません。「沙汰」は指令・命令。ここでは、「参れ」という指図。■にはかにて-急なことで。■候はんずらんと覚え候ふに-あるかもしれませんと思われますので。■質-約束の保証として預かる物品。■取らるべく候ふらん-お取りになるのがよいでしょうか。■しかるべし-もっともだ。■取るべき-取ったらよいだろうか。■沙汰するに-相談していると。■瘤は福の物-当時の俗信と思われる。■許し給ひ候はん-お許しいただきとうございます。■年比-長年。■故なく召されん-理由もなくお取りになるのは。■すぢなきことに候ひなん-筋の通らないむちゃくちゃなこと。「術(すぢ)なき事」と読み、途方に暮れてしまう(ほどに悲しい事)、と解する説もある。■さは-それでは。■ねぢて-ねじって。■おほかた-まったく。■たびの-次の。■暁-夜半過ぎから夜明け近くまでをいう。夜の明ける前のまだ暗い時分。鳥が鳴くことによって、夜が明けるのを知ると、鬼はこの世に留まる事が出来ない。■かい拭(のご)ひたるやうに-拭い去ったように。「かい」は接頭語で、「かき」の音便。「のごふ」は、「ぬぐふ」と同じ意。■つやつや-少しも。下に否定の言葉を伴って、いささかも、少しもの意。■木こらんこと-木をきること。■その定にして-そのとおりにして。前の翁のしたようにして。■ゐまはりて-輪になって座って。■天骨-生まれつきの才能。器用さ。■おろおろ-不完全に。不十分に。■うらうへに-両方の頬に。