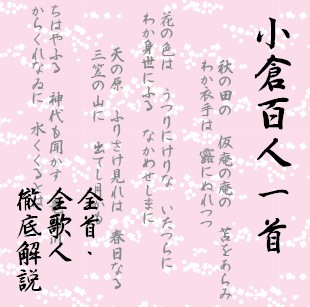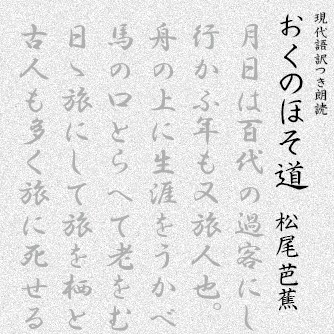宇治拾遺物語 1-7 龍門(りゆうもん)の聖(ひじり)、鹿(しし)に代(かは)らんとする事
大和国(やまとのくに)に龍門(りゆうもん)といふ所に聖(聖)ありけり。住みける所を名にて龍門の聖とぞいひける。その聖の親しく知りたりける男の、明け暮れ鹿(しし)を殺しけるに、照射(ともし)といふ事をしける比(ころ)、いみじう暗かりける夜、照射(ともし)に出(い)でにけり。
鹿(しし)を求め歩(あり)く程に、目を合せたりければ、「鹿ありけり」とて押しまはし押しまはしするに、たしかに目を合せたり。矢比(やごろ)にまはし取りて、火串(ほぐし)に引きかけて、矢をはげて射んとて弓ふりたて見るに、この鹿の目の間(あひ)の、例の鹿の目のあはひよりも近くて目の色も変りたりければ、あやしと思ひて、弓を引きさしてよく見けるに、なほあやしかりければ、箭(や)を外(はづ)して火取りて見るに、「鹿の目にはあらぬなりけり」と見て、「起きば起きよ」と思ひて、近くまはし寄せて見れば、身は一定(いちじやう)の皮にてあり。
「なほ鹿(しし)なり」とて、また射んとするに、なほ目のあらざりければ、ただうちにうち寄せて見るに、法師の頭(かしら)に見なしつ。「こはいかに」と見て、おり走りて火うち吹きて、「ししをり」とて見れば、この聖目を打ちたたきて、鹿の皮を引き被(かづ)きてそひ臥(ふ)し給へり。「こはいかに、かくてはおはしますぞ」といへば、ほろほろと泣きて、「わ主(ぬし)が制する事を聞かず、いたくこの鹿を殺す。我(われ)鹿に代わりて殺されなば、さりとも少しはとどまりなんと思へば、かくて射られんとして居(を)るなり。口惜(くちを)しう射ざりつ」とのたまふに、この男、臥し転(まろ)び泣きて、「かくまで思(おぼ)しける事を、あながちに侍りける事」とて、そこにて刀を抜きて、弓たち切り、やなぐひみな折りくだきて髻(もとどり)切りて、やがて聖に具して法師になりて、聖のおはしけるが限り聖に使はれて、聖失(う)せ給ひければ、またそこにぞ行ひてゐたりけるとなん。
現代語訳
大和国の竜門という所に一人の聖がいた。住んでいるところの名を名前にして竜門の聖と称していた。その聖の親しく知っていた男が、明けても暮れても鹿を殺すのを生業としていたが、照射という狩猟法を使う夏のかなり暗い夜、狩りに出かけて行った。
鹿を探し回るうちに、ふと鹿の目が松明の光を受けて光ったので、「鹿がいたぞ」と、馬を乗り回し乗り回ししていると、確かに鹿の目が松明を反射している。よく矢の届く距離まで近づき、火串に松明をひっかけ、矢をつがえて射ようと弓を振りたてて見ると、この鹿の目と目の間が、普通の鹿の目の間隔よりも近くて、目の色も変わっていたので、変だと思った。弓を引くのをやめてよく見ると、やはり変だったので、矢をはずして火を取ってみると、「どうもこれは鹿の目ではないぞ」と見て、「起きるなら起きろ」と思い、近くまで寄ってみると、確かに疑いようのない鹿の皮である。
「やはり鹿だ」と思い、また矢を射ようとするが、やはり目の様子が違っていたので、もうどんどん近寄ってみると、法師の頭であることがわかった。「これはどうしたことか」と思って、馬から下りて走り寄って、火を吹いて明るくして、「鹿が居る」と言って見ると、この聖の目がまばたきして鹿の皮を引きかぶって寝ておられた。「これはどうしたことですか。どうしてこんな格好をなさっているのですか」と聞くと、聖ははらはらと涙を流して、「お前は、私が止めるのも聞かず、むやみにこの鹿を殺す。だから、私が鹿に成り代わって殺されたなら、いくらなんでも少しは鹿を殺すのを止めるだろうと思うので、このように射られようとしてここに居るのだ。しかし残念なことにお前は私を射殺さなかった」とおっしゃるので、この男は転げまわって泣いて、「これほどまでにお考えになっていたのを、聞こうともせず、強情に殺生をいたしまして」と言い、その場で刀を抜き、弓の弦を断ち切り、「やなぐい」をみな打ち壊し、髻を切って、そのまま聖に従って法師になった。その後、その猟師は聖が生きておられる間、聖に仕え、聖が亡くなったあともずっと同じ所で勤行をしていたということである。
語句
■龍門-奈良県吉野郡吉野町。近くの龍門岳には奈良時代の義淵(ぎえん)僧正の創建とされる龍門寺があった。■聖-日本において諸国を回遊した仏教僧をいう。その語源は仏教伝来以前 の民間信仰の司祭者とされ、特にこれを指して民俗学上では「ヒジリ」とも表記される。■鹿(しし)-「しし」は肉の意で、古くから食用としてきた鹿や猪を「しし」と呼んだ。■照射(ともし)-火串に灯した火に近寄る鹿を射る狩猟法。■目を合せたり-視線を合わせた。■押しまはし-(松明を)振り回し。■やなぐい-矢を入れ、右腰につけて携帯する道具。奈良時代から使用され、状差し状の狩(かり)やなぐいと幅の広い平(ひら)やなぐいとがある。また、古製の靫(ゆき)が発展したものを平安時代からは壺(つぼ)やなぐい)といい、公家の儀仗用となった。ころく。■矢比(やごろ)-矢を射るのに具合のいい近距離。格好の射程距離。■火串-松明をはさむ木。■一定の皮-疑いようもなく確かな鹿皮。■わ主-おまえ。対等の相手か目下の者を呼ぶ人称代名詞。■口惜しう射ざりつ-残念なことにおまえは私を射てくれなかった。■あながちにし侍りける事-あなたの日頃の制止を押し切って、強情に鹿狩りを続けておりましたことの、何たる無分別。■やなぐひ-矢を入れて背負うための道具。■髻を切る-出家すること。