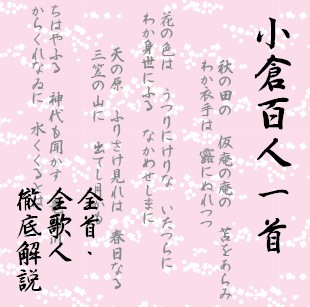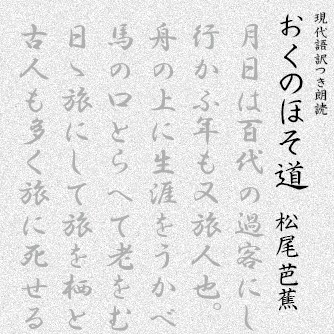宇治拾遺物語 1-18 利仁(としひと)、芋粥(いもがゆ)の事
今は昔、利仁の将軍の若かりける時、その時の一(いち)の人の御許(もと)に恪勤(かくご)して候(さぶら)ひけるに、正月に大饗(だいきやう)せられけるに、そのかみは、大響はてて、とりばみといふ者を払ひて入れずして、大饗のおろし米とて給仕したる恪勤の者どもの食ひけるなり。その所に年比になりて給仕したる者の中には、所得たる五位ありけり。そのおろし米(ごめ)の座にて、芋粥(いもがゆ)すすりて舌打(したうち)をして、「あはれ、いかで芋粥に飽かん」といひければ、利仁これを聞きて、「大夫殿いまだ芋粥に飽かせ給わずや」と問ふ。五位、「いまだ飽き侍らず」といへば、「飽かせ奉りてんかし」といへば、「かしこく侍らん」とてやみぬ。
さて四五日ばかりありて、曹司住(ざうしず)みにてありける所へ利仁(としひと)来ていふやう、「いざさせ給へ、湯浴(あ)みに。大夫殿(たいふどの)」といへば、「いとかしこき事かな。今宵(こよひ)身の痒く(かゆ)く侍りつるに。乗り物こそは侍らね」といへば、「ここにあやしの馬具(ぐ)して侍り」といへば、「あなうれし、うれし」といひて、薄綿(うすわた)の衣(きぬ)二つばかりに、青鈍(あをにび)の指貫(さしぬき)の裾(すそ)破(や)れたるに、同じ色の狩衣(かりぎぬ)の肩少し落ちたるに、したの袴(はかま)も着ず。鼻高なるものの、先は赤みて穴のあたり濡(ぬ)ればみたるは、洟(すすばな)をのごはぬなめりと見ゆ。狩衣の後(うし)ろは帯に引きゆがめられたるままに、ひきも繕(つくろ)はねば、いみじうみぐるし。
をかしけれども、先に立てて、我も人も馬に乗りて川原ざまにうち出でぬ。五位の供には、あやしの童(わらは)だになし。利仁が供には、調度懸け、舎人(とねり)、雑色一人(ざふしきひとり)ぞありける。川原うち過ぎて、粟田口(あはたぐち)にかかるに、「いづくへぞ」と問へば、ただ、「ここぞ、ここぞ」とて、山科(やましな)も過ぎぬ。「こはいかに。ここぞ、ここぞとて、山科も過(すぐ)しつるは」といへば、「あしこ、あしこ」とて、関山(せきやま)も過ぎぬ。「ここぞ、ここぞ」とて、三井寺に知りたる僧のもとに行(い)きたれば、「ここに湯沸かすか」と思ふだにも、「物狂ほしう遠かりけり」と思ふに、ここにも湯ありげもなし。
「いづら、湯は」といへば、「まことは敦賀(つるが)へ率(ゐ)て奉るなり」といへば、「物狂ほしうおはしける。京にてさとのたまはしかば、下人(げにん)なども具すべかりけるを」といへば、利仁あざ笑ひて、「利仁一人侍らば、千人と思(おぼ)せ」といふ。かくて物など食ひて急ぎ出でぬ。そこにて利仁胡簗(やなぐひ)取りて負ひける。
かくて行く程に、三津(みつ)の浜に狐の一つ走り出でたるを見て、「よき使ひ出(い)で来(き)たり」とて、利仁狐をおしかくれば、狐身を投げて逃ぐれども、追ひ責められて、え逃げず。落ちかかりて、狐の後足(しりあし)を取りて引き上げつ。乗りたる馬、いとかしこしとも見えざりつれども、いみじき逸物(いちもつ)にてありければ、いくばくも延ばさずして捕へたる所に、この五位走らせて行き着きたれば、狐を引きあげていふやうは、「わ狐、今宵のうちに利仁が家の敦賀にまかりていはんやうは、『にはかに客人(まらうど)を具し奉りて下(くだ)るなり。明日(あす)の巳(み)の時に高嶋辺にをのこども迎へに、馬に鞍(くら)置きて二疋具(ひきぐ)してまうで来(こ)』といへ。もしいはぬものならば。わ狐、ただ試みよ。狐は変化あるものなれば、今日(けふ)のうちに行き着きていへ」とて放てば、「荒涼(くわうりやう)の使ひかな」といふ。「よし御覧ぜよ。まからではよにあらじ」といふに、早く狐、見返し見返して前に走り行く。「よくまかりめり」といふにあはせて走り先立ちて失(う)せぬ。
かくてその夜は道にとまりて、つとめてとく出(い)で行く程に、まことに巳(み)の時ばかりに三十騎ばかりこりて来(く)るあり。何(なに)にかあらんと見るに、「をのこどももうで来たり」といへば、「不定(ふぢやう)の事かな」といふ程に、ただ近(ちか)くに近くなりてはらはらとおるる程に、「これ見よまことにおはしたるは」といへば、利仁うちほほゑみて、「何事ぞ」と問ふ。おとなしき郎等(らうどう)進み来て、「稀有(けう)の事の候(さぶら)ひつるなり」といふ。まづ、「馬はありや」といへば、「二疋(にひき)候ふ」といふ。食物(くひもの)などして来ければ、その程におりゐて食ふついでに、おとなしき郎等のいふやう、「夜部(よべ)、稀有(けう)の事の候(さぶら)ひしなり。戌(いぬ)の時ばかりに、台盤所(だいばんどころ)の胸をきりにきりて病(や)ませ給ひしかば、いかなる事にかとて、にはかに僧召さんなど騒がせ給ひし程に、手づから仰せ候ふやう、<何か騒がせ給ふ。おのれは狐なり。別(べち)の事なし。この五日、三津(みつ)の浜にて殿の下(くだ)らせ給ひつるにあひ奉りたりつるに、逃げつれど、え逃げで捕へられ奉りたりつるに、『今日(けふ)のうちに我が家に行き着きて、客人(まらうど)具し奉りてなん下(くだ)る。明日巳(あすみ)の時に、馬二つに鞍(くら)置きて具して、をのこども高嶋の津に参りあへといへ。もし今日(けふ)のうちに行き着きていはずは、からき目見せんずるぞ』と仰せられつるなり。をのこどもとくとく出で立ちて参れ。遅く参らば我は勘当蒙(かんだうかうぶ)りなん>と、怖(お)じ騒がせ給ひつれば、をのこどもに召し仰せ候ひつれば、例ざまにならせ給ひにき。その後(のち)鳥とともに参り候ひつるなり」といへば、利仁(としひと)うち笑(ゑ)みて五位に見合(みあは)すれば、五位あさましと思ひたり。物など食ひ果てて、急ぎ立ちて暗々(くらぐら)に行き着きぬ。「これ見よ。まことなりけり」とあさみ合ひたり。
五位は馬よりおりて家のさまを見るに、賑(にぎは)はしくめでたき事物にも似ず。もと着たる衣(きぬ)二つが上に利仁が宿衣(とのゐもの)を着せたれども、身の中(うち)しすきたるべければ、いみじう寒げに思ひたるに、長炭櫃(ながすびつ)に火を多うおこしたり。畳(たたみ)厚らかに敷きて、くだ物、食物(くひもの)し設けて、楽しく覚ゆるに、「道の程寒くおはしつらん」とて、練色(ねりいろ)の衣(きぬ)の綿厚らかなる、三つ引き重ねて持て来てうち被(おほ)ひたるに、楽しとはおろかなり。物食ひなどして事しづまりたるに、舅(しうと)の有仁出で来ていふやう、「こはいかでかくは渡らせ給へるぞ。これにあはせて御使(つかひ)のさま物狂ほしうて、上にはかに病(や)ませ奉り給ふ。稀有の事なり」といへば、利仁うち笑ひて、「物の心みんと思ひてしたりつる事を、まことにまうで来て告げて侍るにこそあなれ」といへば、舅も笑ひて、「稀有の事なり」といふ。「具(ぐ)し奉らせ給ひつらん人は、このおはします殿の御事か」といへば、「さに侍り。『芋粥にいまだ飽かず』と仰せらるれば、飽かせ奉らんとて、率(ゐ)て奉りにたる」といへば、「やすき物にもえ飽かせ給はざりけるかな」とて戯(たはぶ)るれば、五位、「東山に湯沸かしたりとて、人をはかり出(い)でて、かくのたまふなり」など言い戯れて、夜少し更(ふ)けぬれば舅も入りぬ。
寝所(ねどころ)と思(おぼ)しき所に五位入りて寝(ね)んとするに、綿四五寸ばかりある宿衣(とのゐもの)あり。我がもとの薄綿はむつかしう、何(なに)のあるにか痒(かゆ)き所も出で来る衣(きぬ)なれば、脱ぎ置きて、練色(ねりいろ)の衣(きぬ)三つが上にこの宿衣(とのゐもの)引き着ては臥(ふ)したる心、いまだ習はぬに気(き)もあげつべし。汗水(あせみづ)にて臥したるに、また傍(かたは)らに人のはたらけば、「誰(た)そ」と問へば「『御足(みあし)給へ』と候(さぶら)へば、参りつるなり」といふ。けはひ憎からねば、かきふせて風の透(す)く所に臥せたり。
かかる程に、物高くいふ声す。何事ぞと聞けば、をのこの叫びていふやう、「この辺の下人(げにん)承れ。明日の卯(う)の時に、切口(きりくち)三寸、長さ五尺の芋、おのおの一筋(すぢ)づつ持(も)て参れ」といふなりけり。「あさましうおほのかにもいふものかな」と聞きて、寝入りぬ。
暁方(あかつきがた)に聞けば、庭に筵(むしろ)敷く音のするを、「何(なに)わざするにかあらん」と聞くに、小屋当番(こやたうばん)より始めて起き立ちてゐたる程に、蔀(しとみ)あけたるに、見れば長筵(ながむしろ)をぞ四五枚敷きたる。「何の料(れう)にかあらん」と見る程に、下種男(げすをとこ)の、木のやうなる物を肩にうち掛けて来て、一筋置きて往(い)ぬ。その後(のち)うち続き持(も)て来つつ置くを見れば、まことに口三寸ばかりなるを、一筋づつ持て来て置くとすれど、巳(み)の時まで置きければ、ゐたる屋と等しく置きなしつ。夜部(よべ)叫びしは、はやうその辺にある下人(げにん)の限りに物いひ聞かすとて、人呼びの岡(をか)とてある塚の上にていふなりけり。ただその声の及ぶ限りのめぐりの下人の限り持て来るにだにさばかり多かり。まして立ち退(の)きたる従者(ずさ)どもの多さを思ひやるべし。あさましと見たる程に、五石(ごこく)なはの釜(かま)を五つ六つ舁(か)き持(も)て来て、庭に杭(くひ)ども打ちて据ゑ渡したり。「何の料(れう)ぞ」と見る程に、しほぎぬの襖(あを)といふもの着て帯して、若やかにきたなげなき女どもの、白く新しき桶(をけ)に水を入れて、この釜どもにさくさくと入る。「何(なに)ぞ、湯沸(わ)かすか」と見れば、この水と見るはみせんなりけり。若きをのこどもの袂(たもと)より手出(い)だしたる、薄らかなる刀の長やかなる持(も)たるが、十余人ばかり出で来て、この芋をむきつつ透(す)き切(ぎ)りに切れば、「はやく芋粥(いもがゆ)煮るなりけり」と見るに、食ふべき心地もせず、かへりては疎(うと)ましくなりにけり。
さらさらとかへらかして、「芋粥出でもうで来にたり」といふ。「参らせよ」とて、まづ大(おほ)きなる土器具(かはらけぐ)して、金(かね)の提(ひさげ)の一斗(とう)ばかり入りぬべきに三つ四つに入れて、「かつ」とて持(も)て来たるに、飽きて一盛(ひとも)りをだにえ食はず。「飽きにたり」といへば、いみじう笑ひて集りてゐて、「客人(まらうど)殿の御徳に芋粥食ひつ」と言ひ合へり。かやうにする程に、向ひの長屋の軒(のき)に狐のさし覗(のぞ)きてゐたるを利仁見つけて、「かれ御覧ぜよ。候(さぶら)ひし狐の見参(げんざん)するを」とて、「かれに物食はせよ」といひければ、食はするに、うち食ひてけり。
かくて万(よろづ)の事、たのもしといへばおろかなり。一月ばかりありて上(のぼ)りけるに、けをさめの装束(さうぞく)どもあまたくだり、またただの八丈、綿、絹など皮籠(かはご)どもに入れて取らせ、初めの夜の宿衣(とのゐもの)はた更(さら)なり。馬に鞍置きながら取らせてこそ送りけれ。
きう者なれども、所につけて年比(としごろ)になりて許されたる者は、 さる者のおのづからあるなりけり。
現代語訳
今では昔の事になりますが、利仁という将軍が若かった時、その当時の摂関家の屋敷に侍としてお仕えしていたが、正月に御主人が大臣就任の披露大饗宴を催された。
その当時は、饗宴が終わった後、お下がりものにありつこうとする乞食たちを追い払い、中に入れず、大響のお下がりものの米だとして、給仕をした屋敷に仕える侍たちがそれを食べた。その屋敷に長年仕える給仕をした者の中には、古参者として大きな顔をしてる五位がいた。そのおろし米の座で、芋粥をすすり、舌打ちをして、「ああ、何としても芋粥を腹いっぱい食いたいものだ」と言ったので、利仁はこれを聞いて、「大夫殿、まだ芋粥を腹いっぱい召しあがったことはないのか」と問う。
五位が、「まだ腹いっぱい食べたことがない」と言うと、「では、腹いっぱい食べさせてあげましょう」と言う。五位が「ありがたいことだ」と言ってその場は終わった。
さて、四五日ほど過ぎて、五位が自分の部屋に下がっていたところへ、利仁が来て、「さあご一緒に参りましょう。お湯を浴びに。大夫殿」と言うと、「それはとてもありがたいことですな。今夜は体が痒かったところですから。ところで乗り物がありませんが」と言うと「ここに見苦しいですが馬を用意しております」と言うと、「おお、うれしや、うれしや」と言って、薄い綿入れの着物二枚ほどを重ね、青鈍色の指貫袴の裾が破れたものをはき、同じ色の狩衣の肩が少し落ちたものを着て、下袴もはいていない。鼻は高いものの、先の方は赤らんでいて、穴のあたりが濡れているように見えるのは、鼻水を拭(ぬぐ)わないのであろうと見える。狩衣の後ろは帯に引っ張られて歪んだままで、直そうともしないのでひどくみっともない。
滑稽ではあるが、この五位を先に立て、利仁も五位も馬に乗って賀茂の川原の方向に向かって乗りだした。五位の供には賤しい召使の小者さえいない。利仁の供には、武具持ち、馬の口取り、雑役夫が一人ずついた。川原を過ぎて粟田口を通りかかると、五位が「何処へですか」と聞くので、利仁はただ、「ここだ、ここだ」と言いながら山科も通り過ぎてしまった。「これはどうしたことだ。ここだ、ここだと言いながら山科も通り過ぎましたぞ」と五位が言うと、「あそこ、あそこ」と言って、関山も通り過ぎてしまった。「ここだ、ここだ」と言って、三井寺にいる利仁の知り合いの僧の所へ行ったので、五位は、「ここで湯を沸かしているのか」と思うのだが、「なんと馬鹿げて遠くへ来たものかな」と思う。ところが、ここにも湯はありそうにもなかった。五位が、「どこです。湯は」と言うと、「本当は敦賀へお連れ申すのです」と言うと、五位は、「まったく正気ではない。京でそう言ってくだされば、下男なども連れて来るはずでしたのに」と言うと、利仁は嘲笑って、「利仁一人いれば、千人力とお思いください」と言う。こうして、食事をしたりして急いで出発した。そこで利仁は胡簗(やなぐい)を取って背負った。
このようにして進んでいくと、三津の浜で狐が一匹一行の前に走り出たのを見て、利仁は「いい使いがやってきたものだ」と言って、狐を追いかけると、狐は身を翻して逃げようとするが、追い詰められて逃げることが出来ない。利仁は馬の腹のあたりまで状態を低く下げた状態で狐の後足を掴んで引き上げた。利仁が乗った馬はそれほど立派にも見えなかったが、すばらしい駿馬だったので、狐がいくらも逃げないうちの捕らえたのだった。そこへ五位が馬を走らせて行き着いたので、利仁が狐を引き上げて言うのは、「おい狐よ、今夜のうちに利仁の家がある敦賀へ行って、『急に客人を連れて下る。明日の午前十時ごろ高嶋辺りに男達を迎えに、馬に鞍を置いて二頭連れて来い』と言え。もし言わぬものならひどい目に逢おうぞ。こりゃ狐、ともかくわしのいいつけどうりやってみよ。狐は神通力があるので、今日のうちに行き着いて言え」と言って放してやると、五位が、「頼りない使いだな」と言う。利仁は、「よろしい。見ておいでなさい。行かないはずは絶対にありませんから」と言ううちに、なんと狐は後ろを何度も振り返りながら先を走って行く。利仁が「ちゃんと行きそうだ」と言うのに合わせて走り去り見えなくなってしまった。
こうして、その夜は途中で泊まり、翌朝早く出発したが、確かに午前十時頃に三十騎ほどがひとかたまりになって来る者がある。五位が「何だろう」と見ていると、利仁が「男どもがやって来た」と言うので、五位が「驚きましたね」と言ううちに、ただもうどんどん近くなって大勢の者たちが威勢よく馬の背からぱらぱらと路上に降り立つ。お供の者たちが、「ほれ見よ、ほんとうにお出でになったわ」と言うと、利仁は微笑んで、男たちに向かって、「何事か」と問う。分別のありそうな年配の侍が進み来て、「変わったことがございまして」と言う。まず、利仁が、「馬はいるか」と言うと、「二頭連れております」と言う。食べ物など用意してきたので、その辺りで馬から降りて食べ始めていると、先の侍が言うには、「昨夜、変わったことがございましたのです。夜の八時ごろに、奥方の胸がきりきりと痛み出し、苦しまれたので、どうしたことかと、急いで祈祷の僧を招こうなどと大騒ぎになりましたが、自分からおっしゃいますには、<何をお騒ぎなさるか。我は狐である。格別なことはない。この五日、三津の浜で殿がお下りになったのにお会い申した際、逃げたのだが、逃げ切れず捕らえられてしまった折に、『今日の内に自分の家に行き着いて、客人をお連れして下る。明日の午前十時ごろ、馬二頭に鞍を置いて引き連れ、男どもは高嶋の津に来て出会えと言え。もし今日のうちに着いて言わないと、ひどい目に遭わせるぞ』とお命じになられたのである。男どもよ大急ぎで出立してそこへ向え。遅れて来たなら我は殿の御咎めを受ける事になろう>と恐ろしそうにしておられるので、舅殿が男どもにその旨仰せつけますと、奥方様はいつもの平常な状態に戻られた。その後、鳥が鳴くと同時に出立して参りました」と言うと、利仁は笑って五位と顔を見合わせると、五位は「あきれたことだ」と思った。食事など食べ終わり、急いで出立して、暮方に敦賀の家に着いた。「ほれ見よ、本当の事だったのだ」と家人たちは驚き合った。
五位が馬からおりて利仁の家の様子を見ると、豊かそうで立派なさまは比類がない。もと着ていた着物二枚の上に利仁の夜着を重ねて着たけれども、もともと下袴もはかず薄着だったのでかなり寒い感じがしたが、見ると、長火鉢に火をたくさんおこしてある。畳を分厚く敷いて果物や食物が用意してあって喜ばしく思われたが、「道中お寒くいらっしゃったでしょう」と言って、綿の厚い薄黄色の着物を三枚重ねて持ってきて、五位の上にかけてくれたので、その快適なことと言ったら言葉では言い尽くせない。食事などをして、一段落した時に、舅の有人が出てきて言うには、「これはどうしてこのようにお出でなされたのですか。それにつけて、お使いの様子が奇妙で奥様が急に御病気で苦しまれ、驚いた事でした。」と言うと、利仁は笑って、「狐の心を試そうと思ってした事だが、本当にやって来て報告したというのですね」と言うと、舅も笑って、「奇妙なことだな」と言う。「お連れ申しあげたというお方は、ここにおいでになる殿の事か」と言うと、「さようです。『芋粥をまだ腹いっぱい食べたことがない』とおっしゃるので、存分にご馳走してあげようということでお連れいたしました」と言うと、「それはまた何でもない物を、満腹なさるほどお食べにならなかったのですね」と軽口をたたく。五位は「東山に湯を沸かしたと言って、人をだまして連れ出し、このようにおっしゃるのですよ」などと応酬しているうちに夜が少し更けたので舅も奥に入った。
寝所と思われるところに五位が入って寝ようとすると、綿四五寸ほどもある厚い夜着がある。自分がもとから着ている薄綿は着心地が悪く、何がいるのか、痒い所も出てくる夜具だったので、脱ぎ捨てて、薄黄色の着物三枚の上に、この夜具類を引き重ねて寝た気分というものは、まだ、経験したことがないので、のぼせ上がってしまいそうだ。汗びっしょりで寝ていると、また傍らに人が動いているので、「誰か」と問うと、「お足をもんでさしあげよと仰せつけられましたのでやってまいりました」と言う。その物腰がいとおしかったので、かき抱いて、風通しのよい所に寝た。
こうしていると、大声で何か言う声がする。何事かと聞くと、男が叫んで、「この辺りの下人どもよく聞け。明日の朝六時に、切口三寸、長さ五尺の芋をそれぞれ一本ずつ持って参れ」と言うのであった。「大げさにも言うものだな」とあきれて聞いているうちに寝入ってしまった。
明け方に聞くと、庭に筵を敷く音がする。「何をするのだろうか」と耳をすました。やがて小屋当番を始めとして、みなが起きだした時分に蔀戸(しとみど)を開けてみると、長い筵が四、五枚敷いてある。「何に使う物か」と見ていると、下種男が、木のような物を肩にかついで来て、一本置いて立ち去った。その後、次から次へと持って来ては置いていくのを見ると、本当に切口三寸ばかりのものを一本づつ持って来ては置いていくだけだが、十時ごろまで置き続けたので、五位のいる家と同じ高さになった。昨夜叫んだのは、早くその辺りにいる限りの下人達に伝達しようとして、人呼びの岡と呼ばれている塚の上で叫んだのである。「ただ、その声が届く範囲の周囲の下人たちが芋を持ってくるのでさえそれほど多いのである。ましてや遠くに住む従者の多さを考えれば・・・・。あきれたことだ」と思って見ているうちに、五石も入る釜を五つも六つもかついで持って来て、庭に杭などを打って据え並べた。「何のためか」と見ていると、白布の襖(あを)というものを着て、帯を締め、若々しくこぎれいな女たちが、白く新しい桶に水を入れて、これらの釜にざあざあと入れる。「何だ。お湯を沸かすのか」と見ていると、なんと、この水に見える物は、味煎(みぜん)なのであった。若い男たちが袂から手を出して、薄手の長い刀を持って、十数人ほど出て来て、この芋を剥きながら薄切りにしていくので、「なんとこれは芋粥を煮るのであったか」と思って見ていると、もう食う気もなくなり、かえって見るのも嫌になってしまった。
さらりと煮上げて、「芋粥が出来ました」と言う。「さしあげなさい」と言うので、まず、大きなどんぶりを抱え、一斗ほども入りそうな金の提三つ四つに入れて、「すぐに、どうぞ」と持ってきたのに、もう胸いっぱいでそれ一杯でさえ食べられなかった。「もう十分いただきました」と言うと、大笑いして、集まって座り、「お客様のおかげで芋粥をいただけますな」と言い合っている。こうしているうちに、向かいの長屋の軒に狐がのぞいているのを利仁が見つけて、「あれを御覧なさい。昨日の狐が来ていますぞ」と言って、「あれに食わせよ」と命じたので、芋を食わせるとぺろりと食べてしまった。
こうして万事につけて裕福なことは、言葉に出来ないほどである。一月ほど経った後、京へ上った時には、五位は普段着と晴れ着を幾揃えも、又、普通の八丈、綿、絹などを幾行李(こうり)も贈られた。最初の夜に出した夜具類はむろんである。利仁は鞍を置いた馬を五位に与え送り届けたのであった。
身分は低い者だが、同じ所に仕えて長年になり、世間から認められた者には、たまたまこういう果報を得る者がいるものであった。
語句
■利仁-藤原利仁。常陸助・鎮守府将軍時永の子。民部卿山蔭中納言は伯父。上野介(かうずけのすけ)・上総介(かずさのすけ)を経て、延喜十五年(915)鎮守府将軍。さらに武蔵守を歴任。生没年未詳。■一(いち)の人-摂政・関白の異称。朝廷の席次の第一の人の意。一説に藤原基経(836~891)が擬せられている。■恪勤(かくご)-摂政・大臣などの家に侍として仕える事。恪(つつし)んで勤める、の意。■大饗-毎年正月に行われる恒例の大臣饗宴。左右の大臣が、それぞれ四日と五日に次位以下の上達部・殿上人たちを招待する習わし。■そのかみ-その当時。■とりばみ(取り食み)といふ者-宴会の料理の残り物を庭上に投げ捨て、下衆(げす)や乞食(こじき)に拾って食べるにまかせたこと。また、それを食べる下衆・乞食。 ■払ひてえ入れずして-追い払って中に入れず。■おろし米-おさがりものの米。神仏や貴人の前からおろしさげた米。■給仕したる恪勤の者どもの-給仕し近くに仕える侍の者どもが。■その所に-その屋敷に。■年ごろになりて-長年にわたって。■所得たる五位-古参者として大きな顔をして振舞っている五位の男。■芋粥(いもがゆ)-山芋を薄切にしたものを甘葛(あまずら)の汁で煮た粥。宴会の終わりに出されるデザート風の食べ物。■あはれ-ああ。■いかで-何とかして。■飽かん-腹いっぱい食べたい。■大夫-五位の人物の通称。職の長官の場合は「だいぶ」。■いまだ芋粥に飽かせ給わずや-まだ芋粥を腹いっぱい召しあがったことがないのか。■いまだ飽き侍らず-まだ腹いっぱい食べておりません、■飽かせ奉りてんかし-「飽かせ奉らむかし」の強調形。きっと、必ずの気持ちがこもる。存分に御馳走してあげましょうよ。■かしこく侍らん-ありがたいことです。■止みぬ-そのままになった。
■曹司住(ざうしす)み-貴族の部屋住みの子弟。また、部屋住みの身分。またはその部屋。■いざさせ給へ-「いざせさせ給へ」の略形。さあご一緒にお出で下さい。■いとかしこきことかな-本当にありがたいことですよ。■痒く侍りつるに-痒かったところですのに。■侍らね-ありませんが。■あやしの馬-粗末な馬。■具して侍り-連れております。■青鈍(あをにび)-青みが勝った紺に近い色。■指貫-指貫袴。直衣や狩衣などとともに着用する。裾のまわりにひもが通してある。■破れたるに-破れたものに。■狩衣-本来は公家が狩りに着用した服。後に日常服となった。丸首の襟で、袖先に括りひもが通り、わきの下は縫い合わせない。■濡(ぬ)ればみたるは-濡れて見えるのは。■のごはぬなめりと見ゆ-ぬぐわないのであろうと見える。■帯に引きゆがめられたるままに-帯によってひき曲げられたままで。■繕わねば-直しもしないのは。
■をかしけれども-滑稽ではあるが。■川原ざまに-賀茂の河原すなわち鴨川の方角へ向かって。■あやしの童-以下の利仁の側との対照で、五位には誰一人付き従っていないことを強調したもの。■調度懸け-武具などを持つ従者。■舎人-馬の口取りなどをする従者。■粟田口ー京都市東山区。東海道・東山道より三条通への出入り口にあたる交通上、軍事上の重要拠点。■山科-京都市山科区。山科盆地東山の南東部。■関山-関所のあった山。逢坂町。京都府と滋賀県との境に位置する。■三井寺-滋賀県大津市にある天台宗寺門派の総本山。長等山園城寺。貞観元年(859)、円珍が延暦時の別院として再興、正暦四年(993)以後、延暦時と対立、抗争を繰り返した。■物狂ほしう-常識では考えられないほどとてつもなく、の意。■敦賀-福井県敦賀市。三井寺からはまだはるかな遠方(二十里以上の距離)。このあたりで休憩をとっておく必要があった。『尊卑分脈』には、利仁の生母は、越前の国人秦豊国の娘とあり、本話後出の義父有仁との関係も、その母方の縁によるものと見られる。■さとのたまはしかば-そうと言ってくだされば。敦賀へ出かけるということ。■胡簗(やなぐい)-矢を入れて背負うための道具。さまざまの形のものがあった。
■三津の浜-大津市下坂本の辺り。琵琶湖畔。■落ちかかりて-馬の腹あたりまで状態を低く下げた状態で。■いくばくも延ばさずして-いくらも逃げ延びさせずに。■高嶋辺-滋賀県高島郡高島町。琵琶湖の西岸、古くは勝野津と呼ばれた古来からの交通の要衝。大津市の北端から約十一里強の距離。■もしいはぬものならば-「ただではすまないぞ」という含意。■ただ試みよ-ともかくわしの言いつけどおりやってみよ、とけしかけた。■変化-神変不思議の力。神通力。■荒涼-茫漠としていて、不確かで頼りないさま。■まからではよにあらじ-行かないでは絶対にいられまい。「よにあらじ」とは「この世にはいない」と言うことで、「もし行かなければお前はこの世にはいられないぞ」と脅かしているようす。
■早く-「早くも」の意にも解し得なくはないが、ここは『今昔』に頻出する感嘆の意を表す「なんと(・・・なのであった)」の意とみる見解に従う。
■つとめて-翌朝。■とく-早く。■不定の事-「定めがたい事」の意から、「どうだか、怪しいもの」とも解されるが、前後の文脈から、「常識的判断を超えたこと、思いがけなく意外なこと」の意と見る。■はらはらとおるる-大勢の者たちが威勢よく馬の背から路上に降り立つさま。■をとなしき郎党-分別のありそうな年配の侍。■台盤所-台盤(大きな食卓)を置く女房の詰めている部屋の意から転じて、高貴な人物の正室をいう敬称。御台所とも、ここは利仁の妻。■胸をきりにきりて-胸がきりきりともみ込むように痛み出したこと。狐の霊がとり憑いたさまを表す。昔話に関係話が多いが、詳しくは、吉野裕子『狐』(法政大学出版局)など参照。■手づから仰せ候ふやう云々-台盤所の突然の苦しみぶりに周囲の者たちがあたふたしているのに、そのことをまるで関知しないかのように、問題の張本人である台盤所ご自身が以下のようなことを突然語り始めた。「おのれは狐なり」と名乗ったうえでの語りなので、台盤所に狐がとり憑いて言わせているということを人々はただちに了解し、その言葉に従う。■勘当-本来は犯した罪について勘(かん)がえ、法に当てて処罰する意。ここは殿(利仁)様から必ずおとがめを受けることになりましょうから、というおののきの気持ち。■召し仰せ候ひつれば-このとき、家の子・郎等たちに対して、狐のもたらした指令に応ずる指図をしたのは、利仁の妻の父親である有仁と推測される。■例ざま-ふだんの状態。つまり狐の憑き物が落ちたいつものありさま。■鳥とともに-鳥が鳴きだすと同時に。夜が明けるか明けないかという早暁の薄暗い時に。通常朝日が昇るのに先んじて鳥が鳴き始める。■暗々(くらぐら)-郎等たちが鶏鳴(陰暦の正月ならば、五時ごろか)に発ったとして五時間で来た道を、五位を伴った一行は「暗々に(陰暦の正月の日没時は、十七時半ごろ)」到着しているので、十時半の出発とすれば、七時間を要したことになる。■あさみ合ひたり-驚きあきれている。
■身の中しすきたるべければ-前に「下の袴も着ず」とあったように、五位がほとんど下着を着けていない様子。身体には隙間ができたようであるから。■長火櫃-長方形の室内に置く火鉢。■畳厚らかに敷きて-床のついた厚手の畳ではなく、薄縁(うすへり)のようなものを何枚か厚ぼったく敷き重ねた状態をいうか。■おろか-「疎そか」で表現が十分でない。の意。■有仁-利仁の妻の父親。越前敦賀を根拠地とした士豪かと思われる。■上-貴人の妻。自分の娘に敬称を用いたのは、話し相手の利仁の妻であったのと、それが呈内での日常慣用的な呼び方であったため、という二つの理由が考えられる。■物の心みんと思ひてしたりつる事-野狐が自分に従うかどうか、その心を見極めて見ようと、軽い気持ちでした事であったのに。■東山-京都市の鴨川の左岸一帯。■宿衣-書陵部本は「直垂」とする。ここは「直垂衾」のことと解したい。襟と袖の付いた直垂のような形で、綿を分厚く入れてある夜具。長方形の衾(きん)に比べて隙間風をよく防ぐので、冬季、資産のある貴族や武家の間に愛用された。■臥したる心-寝ている気分。■今だ習はぬ-まだ経験したことがない。■気もあげつべし-のぼせあがってしまいそうだ。■むつかしう-「むさ苦しい、薄汚い」などの解釈もあるが、大系が注するように、「綿が古くなって感じの悪い事」、着古したもので着心地が悪い、の意であろう。■何のあるにか-着古した薄綿入れであれば、おそらく縫い目にかなりの数の虱(しらみ)が住みついていたと想像される。■はたらけば-もぞもぞ動く気配がするので。これではすでに人が夜具の中に入り込んでいるように読めるが、『今昔』では、「人ノ入(イ)ル気色有リ」と、その時に入ってきた気配を五位が感じたことになっている。■御足給へ-「客人の御足をいただきなさい」とは、客人の御足をおさすりせよ、夜の御伽(とぎ)の相手をしなさい、ということ。そうして大事な客をもてなした風習。■切口(きりくち)三寸、長さ五尺の芋-直径約一〇センチ、長さ約一・六メートルの長大な山芋。
■小屋当番-夜警の詰所にいた当番の侍。■蔀(しとみ)-格子の片面に板を張った戸。多くは上下二枚から成り、上を吊り上げるようにしてある。強い日差しや風雨を防ぐために使われたもの。■料-材料、用品。■五石なはの釜-五石納の釜。すなはち五石入りの大釜。「なは」は「納(なふ)」の訛った言い方。■しほぎぬ-「しろぎぬ」の誤伝か。『今昔』には、「白キ布ノ襖」とある。とすれば、白い布の袷(あわせ)・綿入れのこと。■さくさくと-水を釜にそそぐ音。ざあざあと。■みせん-味煎(みぜん)。甘葛煎(あまずらせん)ともいう。つる草の一種である甘葛の茎や葉の汁を煮詰めて作る甘味料。■食ふべき心地もせず-あれほど満腹してみたいと願っていた芋粥であったが、あまりに大量な仕込みぶりを目のあたりにした結果、食欲をそそられるどころか逆に、五位はもううんざりして食欲を失ってしまった。■さらさらとかへらかして-さらりと煮え返らせて。ぐつぐつと煮込むのではなく、短時間で煮上げる様子。■大きなる土器-芋粥をたっぷり盛りつけるための大ぶりの素焼きの陶器。■金の提-金属製の巨大な提。一般には取っ手のつるとそそぎ口のついた形状のつくりであるが、ここのは一斗(十八リットル)も入るような特別に大きな鍋状のものか。■かつ-すぐに、ただちに、の意か。とすれば「すぐに(どうぞ)召し上がれ」と勧めたことになる。■御徳に-おかげで。客人をもてなした残り物を「おろし物」としてその屋敷に仕える関係者たちがふるまわれる慣習があったものらしい。■八丈-「八丈絹」。美濃・尾張・信濃から産する長さ八丈の絹織物。■きう者-給者すなはち、①給仕の者、②恪勤(かくごん)<精勤>の侍、の両義が考えられる。本話全体の印象からすれば、②の利仁とみたいが、本話の冒頭近くの「その所に年比になりて給したる者のなかには、所得たる五位ありけり」により①とみておく。■けをさめの装束-普段着と晴れ着。■皮籠(かはご)-皮で張った籠。■あまたくだり-一そろいの多くの装束。(くだり)は一そろいの装束を数える数え方。■取らせ-贈らせ。■はた更なり-また言うまでもなく。■置きながら-置いたまま。■取らせてこそ送りけれ-贈って「家に」送り届けた。■所につけて-同じ所に仕えて。■年比になりて-長い年月を経て。■許されたる者-世間から認められた者。■おのづからあるなりけり-たまたまいるものであった。