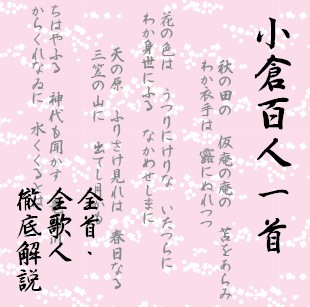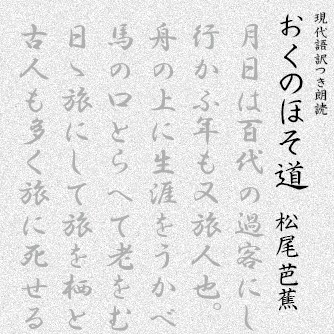宇治拾遺物語 3-9 伯(はく)の母の事
【無料配信中】福沢諭吉の生涯
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
今は昔、多気(たけ)の大夫(たいふ)といふ者の、常陸(ひたち)より上(のぼ)りて愁(うれ)へする比(ころ)、向ひに越前守(ゑちぜんのかみ)といふ人のもとに経誦(ず)しけり。この越前守は伯(はく)の母とて世にめでたき人、歌よみの親なり。妻は伊勢の大輔(たいふ)、姫君たちあまたあるべし。多気の大夫つれづれに覚ゆれば、聴聞(ちやうもん)に参りたりけるに、御簾(みす)を風の吹き上げたるに、なべてならず美しき人の、紅(くれなゐ)の一重(ひとへ)がさね着たるを見るより、「この人を妻(め)にせばや」といりもみ思ひければ、その家の上童(うへわらは)を語らひて問ひければ、「大姫御前の、紅は奉りたる」と語りければ、それに語らひつきて、「我に盗ませよ」といふに、「思ひかけず、えせじ」といひければ、「さらば、その乳母(めのと)を知らせよ」といひければ、「それは、さも申してん」とて知らせてけり。
さて、いみじく語らひて金(かね)百両取らせなどして、「この姫君を盗ませよ」と責め言ひければ、さるべき契(ちぎ)りにやありけん、盗ませてけり。やがて、乳母(めのと)うち具(ぐ)して常陸へ急ぎ下りにけり。跡に泣き悲しめど、かひもなし。程経て乳母おとづれたり。あさましく心憂(こころう)しと思へども、いふかひなき事なれば、時々うちおとづれて過ぎけり。伯の母、常陸へかくいひやり給ふ。
匂ひきや都(みやこ)の花は東路(あづまぢ)にこちのかへしの風のつけしは
返し、姉、
吹き返すこちのかへしは身にしみき都の花のしるべと思ふに
年月隔りて、伯(はく)の母、常陸守(ひたちのかみ)の妻(め)にて下(くだ)りけるに、姉は失(う)せにけり。女(むすめ)二人(ふたり)ありけるが、かくと聞きて参りたりけり。田舎(ゐなか)人とも見えず、いみじくしめやかに恥づかしげによかりけり。常陸守の上(うへ)を、「昔の人に似させ給ひたりける」とて、いみじく泣き合ひたりけり。四年が間(あひだ)、名聞(みやうもん)にも思ひたらず、用事(ようじ)などもいはざりけり。
任果てて上(のぼ)る折に、常陸守、「無下(むげ)なりける者どもかな。かくなん上(のぼ)るといひにやれ」と男にいはれて、伯の母、上(のぼ)る由(よし)いひにやりたりければ、「承りぬ。参り候(さぶら)はん」とて、明後日(あさって)上(のぼ)らんとての日、参りたりけり。えもいはぬ馬、一つを宝にする程の馬十疋(ぴき)づつ、二人して、また皮籠(かはご)負ほせたる馬ども百疋づつ、二人して奉りたり。何(なに)にも思ひたらず、かばかりの事したりとも思はず、うち奉りて帰りにけり。常陸守の、「ありける常陸四年が間(あひだ)の物は何ならず。その皮籠の物どもしてこそ万(よろづ)の功徳(くどく)も何(なに)もし給ひけれ。ゆゆしかりける者どもの心の大きさ広さかな」と語られけるとぞ。
この伊勢の大輔(たいふ)の子孫は、めでたきさいはひ人多く出で来(き)給ひたるに、大姫君のかく田舎人になられたりける、哀れに心憂(こころう)くこそ。
現代語訳
今は昔、多気大夫といふ者が、常陸国から上京して、訴訟をしている頃、向いの越前守という人の家でよく経が詠まれていた。この越前守は、神祇伯康資王の母といって、世に名高い女流歌人の親である。妻は伊勢の大輔(たいふ)で娘たちもたくさんいたようだ。多気の大夫は退屈でしかたないので、経を聞きにやって来たとき、ちょうど風が御簾を吹き上げ、その奥に紅の単衣を着た人並み以上の美人がいるのを見るなり、「この人を妻にしなくては」と心を砕き思いこがれたので、その家の上童を手なづけて尋ねると、「大姫御前が紅をお召しです」と話したので、その上童を説得し、「私にその姫を盗ませてくれ」と言うと、「とんでもない。できません」と言うので、「では、その人の乳母を教えてくれ」と言うと、「それはお教えしましょう」と言って取り次いでくれた。
そこで、その乳母をすっかり口説き落として金百両など与えたりなどして、「この姫君を自分に盗ませてくれ」と言い責めたてると、そうなるべき宿縁でもあったのか、ついに盗ませてしまった。多気の大夫はそのまま乳母をも連れて常陸へ急いで下った。その後で、越前守の家では、残った家の者たちが泣き悲しんだがどうしようもない。しばらくしてから、乳母が手紙をよこした。情なく辛い事だと思ったが言っても仕方がない事なので、時々、便りをして過ぎていった。伯の母は常陸へこう言っておやりになる。
西風につけて送った都の花の香りは、東路の方に匂ったでしょうか
(姉からの返事)
吹き返してきた西風は、ほんとうに身に染みたことです。なつかしい都の花にゆかりあるものと思いますと
長い年月が過ぎて、伯の母が、常陸守の妻として常陸に下ったが、姉はすでに亡くなっていた。姉には二人の娘がいたが、こうして叔母が来たと聞いて常陸の国司の館に訪ねて来た。田舎の人とも見えず、まことにしとやかで、気品もありこちらが恥ずかしくなるほどの美貌であった。二人は常陸守の奥方である伯の母を見て、「亡き母によく似ていらっしゃる」と言ってたいそう泣きあうのであった。といって国守の任期の間、叔母が国守の妻である事を名誉にも思っていない様子で、頼み事なども言ってこなかった。
任期が満了となり、上京する時に、夫の常陸守から、「あきれた娘たちだなぁ。こうして今や上京すると言ってやれ」と言われ、伯の母が、上京することを伝えにやると、「わかりました。私たちも参ります」と言って、明後日上京するという日になって、やって来た。何ともいえない立派な一頭だけでも宝と思える馬を十頭づつ、二人の名で、それに合せ、行李を背負った馬百頭づつを二人名で差し出した。これほどの贈り物をしても格別豪勢なことをしたとも思わぬさまで、届け終えて帰っていった。常陸守は、「これまでの常陸での四年間の収入はこの餞別に比べたらまるで問題にならない。その行李の中の品々を使えば、仏に功徳を施すことでも何でもできようというものだ。豪勢きわまる者たちの心は大きく、広いものだなぁ」と語られたということだ。
この伊勢の大輔の子孫には、たいそう出世した人が続いて多く出たが、大姫君が、こうして田舎人になられたということは、哀れに気の毒なことであった。
語句
■多気(たけ)の大夫(たいふ)-平惟幹(これもと)。常陸平氏の祖。国香の孫、繁盛(一説には貞盛)の子。常陸国多気(茨城県つくば市北条)に居住した常陸大掾の祖。従五位下であったので、平大夫とも称した。ただし、彼は以下に登場する高階成順と伊勢大輔の婚姻する以前、寛仁元年(1017)没した。■憂へする-訴訟する。■むかひに-向いの家で。■誦す-経や漢詩などを朗詠する。吟じる。■越前守-高階成順、万寿二年(1025)筑前守。越前は誤伝。正五位下。慈悲深く信心深い人という(今昔・巻一五-三五話)。長久元年(1040)没。法名乗蓮。■もとに-所に。■経-書陵部本『古本説話集』上二〇では「ぎやくす(逆修)」とする。逆修ならば、死後の安楽のために生前に行う仏事、の意。■伯の母-高階成順の娘。神祇伯康資王(?~1090)の母。『後拾遺集』以下に入集の歌人。四条宮寛子に仕えた。女房名は筑前。■世にめでたき人-世に名高い人。■伊勢の大輔-神祇伯・祭主大中臣輔親の娘、祖父は大中臣能宣。一条天皇の中宮彰子に仕えた。『後拾遺集』以下に入集の歌人。家集がある。■あまたあるべし-たくさんいたようだ。■つれづれに覚ゆれば-退屈でしかたがないので。■聴聞(ちやうもん)-説教や読経を聞く事。■なべてならず-なみなみでなく。人並み以上。■一重がさね-上着の下に単衣(ひとえ)を重ねて着るもの。■いりもみ思ひければ-激しく心をくだいて思いこがれたので。■姫君-伯の母、藤原通宗の母、藤原季綱の母、藤原成尹・正季の母、源兼俊の母になった娘たちがいた。■上童-貴族の邸宅に仕える少女のうち、奥向きの雑用に従う者。■語らひて-説得して。手なづけて。■紅は奉りたる-紅をば召しておいでになる。■思ひかけず-とんでもない。■えせじ-できませんよ。■乳母-その姫君の赤ん坊の時からの養育者で、後見をしている女房。■さも申してん-それはお教えしましょう。■知らせてけり-教えてしまった。
■匂ひきや云々-この歌は、『後拾遺集』雑五に源兼俊の母の作として見える。■姉-成順の娘たちの中では、伯の母が最年長者であったように考証されるので、その姉の存在は疑問。とすれば、「匂ひきや」の歌は兼俊の母、その返しの吹き返す」の歌は「康資王の母」すなわち伯の母の作とする『後拾遺集』の記載が理にかなっており、本話の人物伝承には誤伝があることになるが、ここではそれを問わない。■常陸守の妻-伯の母が常陸守の妻になったという確証はないが、常陸介藤原基房(中納言朝経の子)との関係は指摘されている。源兼俊の母の夫ということならば、源経宗。が、経宗は筑前守で、常陸には赴任していない。■参りたりけり-常陸の国司の館に。国府は現在の石岡市内。■恥づかしげによかりけり。-こちらが恥ずかしくなるくらいの美貌であった。■昔の人-亡くなった自分たちの母親。■四年-伯の母の夫の在任期間。■名聞(みやうもん)にも思ひたらず-叔母が常陸守の北の方だということを自慢げに思ってもおらず。■無下なりける者どもかな-自分たちを頼る事も、なつかしく思うこともないような疎遠な対応ぶりにあきれた思い。■一つを宝にする程の馬-一頭一頭がそれぞれ逸物で財物になりそうな立派な馬。■何ならず-まるで問題にならない。取るに足らないようなものだ。■ゆゆしかりける者ども-(経済的に)並大抵ではない、豪勢きわまる者たち。「無下なりける者どもかな」と対照的なほめ言葉。薄情な者どもという非難が一転して讃嘆に変わった。
前の章「宇治拾遺物語 3-8 木こり歌の事」|次の章「宇治拾遺物語 3-10 同人仏事(ぶつじ)の事」
宇治拾遺物語