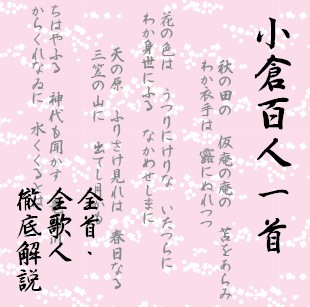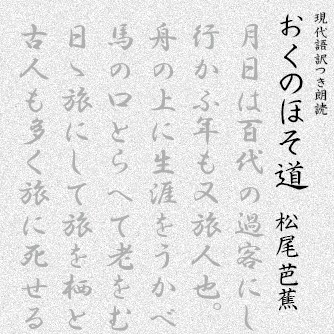宇治拾遺物語 6-1 広貴(ひろたか)、閻魔(えんま)王宮へ召さるる事
これも今は昔、藤原広貴といふ者ありけり。死にて閻魔の庁(ちやう)に召されて、王の御前と思しき所に参りたるに、王のたまふやう、「汝(なんぢ)が子をはらみて、産をしそこなひたる女死にたり。地獄に落ちて苦を受くるに、愁(うれ)へ申す事のあるによりて汝をば召したるなり。まづさる事あるか」と問はるれば、広貴、「さる事侍(さぶら)ひき」と申す。王のたまはく、「妻の訴へ申す心は、『我(われ)男に具(ぐ)して共に罪を作りて、しかもかれが子を産みそこなひて、死して地獄に落ちて、かかる堪えへがたき苦を受け候へども、いささかも我(わ)が後世をも弔(とぶら)ひ候はず。されば、我一人(われひとり)苦を受け候ふべきやうなし。広貴をももろともに召して、同じやうにこそ苦を受け候はめ』と申すによりて、召したるなり」とのたまへば、広貴が申すやう、「この訴へ申す事、もっともことわりに候ふ。おほやけわたくし、世を営み候ふ間、思ひながら後世をば弔ひ候はで、月日はかなく過ぎ候ふなり。ただし、今におき候ひては、共に召されて苦を受け候ふとも、かれがために苦の助かるべきに候はず。されば、この度(たび)は暇(いとま)を賜(たまは)りて娑婆(しやば)にまかり帰りて、妻のために万(よろづ)を捨てて、仏教を書き供養して弔ひ候はむ」と申せば、王、「しばし候へ」とのたまひて、かれが妻を召し寄せて、汝が夫広貴が申すやうを問ひ給へば、「げにげに経仏(きやうほとけ)をだに書き供養せんと申し候はば、とく許し給へ」と申す時に、また広貴を召し出でて、申すままの事を仰(おほ)せ聞かせて、「さらば、この度(たび)はまかり帰れ。たしかに妻のために仏教を書き供養して、弔ふべきなり」とて帰し遣はす。
広貴、かかれども、これはいづく、誰(だれ)がのたまふぞとも知らず。許されて、座を立ちて帰る道にて思ふやう、「この玉の簾(すだれ)の内にゐさせ給ひて、かやうに物の沙汰(さた)して、我を帰さるる人は誰にかおはしますらん」と、いみじくおぼつかなく覚えければ、また参りて、庭にゐたれば、簾のうちより、「あの広貴は、帰し遣はしたるにはあらずや。いかにしてまた参りたるぞ」と問はるれば、広貴が申すやう、「計らざるに御恩を蒙(かうぶ)りて、帰りがたき本国へ帰り候(さぶら)ふ事を、いかにおはします人の仰(おほ)せとも、え知り候はで、まかり帰り候はん事の、きはめていぶせく、口惜しく候へば、恐れながらこれを承(うけたまは)りに、また参りて候ふなり」と申せば、「汝(なんぢ)不覚なり。閻浮提(えんぶだい)にしては我を地蔵菩薩(ぢざうぼさつ)と称す」とのたまふを聞きて、「さは閻魔王と申すは地蔵にこそおはしましけれ。この菩薩に仕(つかまつ)らば、地獄の苦をばまぬかるべきにこそあめれ」と思ふ程に、三日といふに生きかへりて、その後(のち)、妻のために仏教を書き、供養してけりとぞ。日本(につぽん)の法華験記に見えたるとなん。
現代語訳
これも今は昔、藤原広貴という者がいた。死んで閻魔庁に召されて、閻魔大王の御前と思われる所に行くと、大王が、「おまえの子を孕んで、それを産みそこなった女が死んだ。それが今、地獄に落ちて苦痛を味わっているが、嘆き訴える事があるというのでお前を呼び寄せたのだ。まず、「そういう事実があるのか」と聞かれる。広貴は「そういうことがございました」と申し上げる。大王が、「妻が訴え出た気持ちというのは、『自分は男に連れ添って、共に罪を作りました。しかも夫の子を産みそこなったので、死んで地獄に落ち、このような堪えがたい苦痛を受けておりますが、我が夫はいささかも私の後世を弔おうとしません。それで、私一人が苦しみを蒙る謂れはありません。ですから広貴も一緒に召し寄せて、共に苦しみを受けたいと思います』と申すので、お前を召し出したのだ」とおっしゃると、広貴は、「妻が訴えて申し上げていることはもっともなことでございます。公私につけて暮らしをたてるのに忙しく、そう思いながらも妻の後世の弔いをしておりませんが、月日ははかなく過ぎてしまいました。しかし、今となっては共に召されて苦しみを与えられようとも、妻の苦しみを免れるというわけにもまいりません。それで、この度は暇を賜り、人間界に帰って妻の為にすべてを投げ打ち、お経を書き、供養し弔いをしましょう」と申し上げると、大王は、「しばらく待て」とおっしゃられて、彼の妻を召し寄せ、夫の広貴の申し開きを告げて意見をお聞きになると、「まことにまことに法華経を写経し、供養しますと申しておりますのでしたら、早くお許しください」との事であった。そこでまた広貴を呼び出して、妻が申すままの事を言ってお聞かせになり、「それでは、今度は帰るがよい。間違いなく妻の為にお経を書き供養し弔わなければならないぞ」と言って帰るのを許した。
広貴は、そうは言っても、ここはどこか、誰がおっしゃっているのかわからない。許されて、裁きの庭から立ち帰る道すがら、思ふには、「この立派な簾の内においでになられて、このような裁定を下され、自分を人間界にお帰しになられた人はどなたであろうか」と、大変気がかりに思われたので、また引き返して、元の庭に居た。すると簾の内側から、「あの広貴は帰してやったのではないか。どうしてまた帰って来たのだ」と聞かれたので、広貴は、「思いがけず、このたびは御恩を蒙り、帰ることの難しい人間界へ帰ることになりましたが、どういうお方の仰せとも分らず、帰って行くことがたいそう気がかりで、口惜しく、恐れながら、それをお聞きするために、また舞い戻って来たのでございます」と申し上げると、「お前は迂闊な者よな。人間界では、わしを地蔵菩薩と言うのだ」と仰せられた。それを聞いて、「では、閻魔大王と申されるのは地蔵でいらっしゃったのだ。この菩薩にお仕えすれば地獄の苦をまぬかれることができるのだ」と思ううちに、三日たって生き返り、その後、妻の為にお経を書き供養をしたという事である。日本法華経験記に見えているという。
語句
■藤原広貴-伝未詳。本話と同文話である『日本霊異記』下九話には、藤原朝臣広足とあり、以下は神護景雲二年(768)二月十七日、大和国免田郡真木原(奈良県宇陀榛原町檜牧)の山寺での出来事とする。■閻魔-閻魔大王。地獄の主催者。本話では、後出のように地蔵菩薩と同一者とみる。「閻魔の庁」は地獄に到来した死者について大王がその生前の罪業を地獄の鏡と記録簿によって点検、裁きを下す役所。『日本霊異記』には、重(かさな)れる楼閣(たかどの)に有り。炫(て)り輝(かがや)きて晃(ひかり)を放つ。四方に珠(たま)の簾(すだれ)を懸(か)け、其(そ)の中に人居り。面貌(かほ)を覲(み)ず」と述べられる。■おぼしき-思われる。■のたまふやう-おっしゃるには。■産をしそこなひたる女死にたり-出産に失敗して死亡した女は地獄に落ちるとされていたことを物語るか。ちなみに服部敏良『王朝貴族の病状診断』によれば、平安時代には村上天皇の女御安子、花園天皇の女御てい子、一条天皇の皇后定子らも出産で死亡している。この分娩に伴う死亡率は、奈良時代にはさらに高いものであったであろう。■愁(うれ)へ申す-嘆き訴える。■さることあるか-そのようなことがあるのか。■男に具して-男と連れ添って。■かれ-夫。■後世をも弔(とぶら)ひ-死者の死後の平安を祈って、仏寺などにおいて法要する事。■受け候ふべきやうなし-受けなければならないいわれはありません。■受け候はめ-受けさせてください。■もっともことわりに候ふ-まことにもっともです。■世を営み候ふ間-暮らしを立てておりますので。■今におき候ひては-今となりましては。「私が公私の忙しさにかまけてボウサイノ供養をせずにおったのは事実としても、それはすでにすでにすんだことでありまして」という合意。■かれがために-妻のために。■助かるべきに候はず-助かるはずのものではありません。■娑婆-梵語sahaの音写。忍土・忍界の意。多くの衆生がさまざまな煩悩や痛苦を堪え忍びながら生きている所。憂き世、人間界。■仏経を書き-『日本霊異記』では「法華経を写し、講読し供養し、受くる所の苦を救はむ」と、経典名を出す。■しばし候へ-しばらくお待ちください。■汝が-「汝が」あるために、大王が直接広貴の妻に問いかけている構文であるかのように見えるが、「夫広貴が・・・問ひ給へば」は語り手の立場からの叙述文。従って「汝が」は不要な語。初めは直接話法で、「汝が夫広貴が申すやうは(しかじかなり。いかにすべき)と問ひ給へば」というふうに語ろうとしたのが、途中から間接話法によじれたものとみておく。■申すやうを-申し分について。■げに-いかにも。■経仏-仏教に同じ。仏教経典のこと。巻第六ノ五話に「経仏の営み(読経による供養)などしけるに」の例が見える。これを「経文と仏像」と解するのは誤り。■とく-早く。■弔ふべきなり-弔わなければならないぞ。
■これはいづく、誰(だれ)がのたまふぞとも知らず-ここがどこで、誰が自分と話を交した相手なのかということも知らない。新大系が指摘するように、これは広貴の仏教に対する無知無関心、不信心を示す。いかにも亡妻の供養を行わなかった人物にふさわしい物言い。■座-書陵部本では「庭」、すなわち裁きが行われた場所とする。■玉の-立派な。■ゐさせ給ひて-おいでになられて。■沙汰して-採決をして。■いみじくおぼつかなく覚えければ-たいそう心もとなく思われたので。■帰し遣はしたるにはあらずや-帰してやったのではないか。■計らざるに-思いがけないことに。■本国-元の国。生者の世界、娑婆。■いかにおはします人の仰(おほ)せとも-どういうお方の仰せとも。■きはめていぶせく-たいそう気がかりで。釈然とせず。■まかり帰り候はんことの-帰って行きますことが。■不覚なり-迂闊である。■閻浮提(えんぶだい)-巨大な閻浮樹(蒲桃の樹木)の生えている州(陸地)、の意で、世界の中心にそびえ立つとされる須弥山(しゅみせん)の南方にある州。ヒマラヤ山系を須弥山に見立てると、その南方にあって閻浮樹のの茂る自国を、古代インド人は閻浮提(えんぶだい)と称した。閻浮提は、三辺がそれぞれ二千由旬(ゆじゅん)、残りの一辺が三・由旬で、インド亜大陸のことを示している。(一由旬は七~九マイル)後には中国、日本などをも含めた人間界全体さらには現世をさす語となった。■さは-それでは。■地蔵にこそおはしましけれ-地蔵でいらっしゃったのだ。■仕らば-お仕えすれば。■まぬかるべきにこそあめれ-まぬかれることができるのであろうと。■日本の法華経記-書名からすると、鎮源撰の『大日本法華経験記』(長久年間<1040~44>成立)をさすように思われるが、同書には本話は見えない。『日本霊異記』との取り違えか。