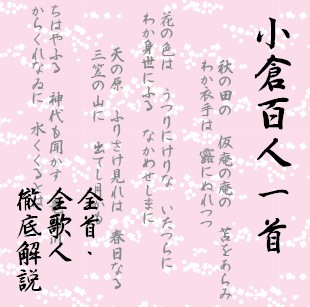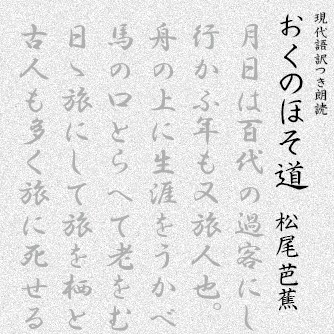宇治拾遺物語 8-4 敏行朝臣(としゆきあそん)の事
原文
これも今は昔、敏行(としゆき)といふ歌よみは手をよく書きたれば、これかれがいふに随(したが)ひて法華経を二百部ばかり書き奉りたりけり。かかる程に、にはかに死にけり。我は死ぬるぞとも思はぬに、にはかにからめて引き張り率(ゐ)て行けば、我ばかりの人を、おほやけと申すとも、かくせさせ給ふべきか、心得ぬわざかなと思ひて、からめて行く人に、「これはいかなる事ぞ。何事の過(あやまち)によりかくばかりの目をば見るぞ」と問へば、「いさ、我は知らず。『たしかに召して来(こ)』と、仰(おほ)せを承りて率(ゐ)て参るなり。そこは法華経や書き奉りたる」と問へば、「しかじか書き奉りたり」といへば、「我がためにはいくらか書きたる」といへば、「その事の愁(うれ)へ出(い)で来(き)て、沙汰(さた)のあらんずるにこそあめれ」とばかりいひて、異事(ことごと)もいはで行く程に、あさましく人の向ふべくもなく、恐ろしといへばおろかなる者の、眼を見れば電光のやうにひらめき、口は炎(ほむら)などのやうに恐ろしき気色(けしき)したる軍(いくさ)の、鎧兜(よろひかぶと)着て、えもいはぬ馬に乗り続きて、二百人ばかりあひたり。見るに肝(きも)惑ひ、倒(たふ)れ伏しぬべき心地すれども、吾(われ)にもあらず引き立てられて行く。
さてこの軍は先立ちて往(い)ぬ。我からめて行く人に、「あれはいかなる軍ぞ」と問へば、「え知らぬか。これこそ汝に径あつらへて書かせたる者どもの、その功徳によりて天にも生れ、極楽にも参り、また人に生れ返るとも、よき身とも生るべかりしが、汝がその経書き奉るとて、魚をも食ひ、女にも触れて、清まはる事もなくて、心をば女のもとに置きて書き奉りたれば、その功徳のかなはずして、かくいかう武(たけ)き身に生れて、汝を妬(ねた)がりて、『呼びて給はらん。その仇(あた)報ぜん』と愁へ申せば、この度(たび)は道理にて召さるべき度(たび)にあらねども、この愁へによりて召さるるなり」といふに、身も切るるやうに心もしみ凍(こほ)りて、これを聞くに死ぬべき心地す。
「さて我をばいかにせんとて、かくは申すぞ」と問へば、「おろかにも問ふかな。その持ちたりつる太刀(たち)、刀にて、汝が身はまづ二百に斬(き)り裂きて、おのおの一切づつ取りてんとす。その二百の切(きれ)に汝が心も分れて、切(きれ)ごとに心のありて、責められんに随(したが)ひて、悲しくわびしき目を見んずるぞかし。堪へがたき事たとへん方(かた)あらんやは」といふ。「さてその事をば、いかにしてか助かるべき」といへば、「さらに我も心も及ばず。まして助かるべき力はあるべきにあらず」といふに、歩み空なし。
また行けば、大(おほ)きなる川あり。その水を見れば、濃くすりたる墨の色にて流れたり。あやしき水の色かなと見て、「これはいかなる水なれば、墨の色なるぞ」と問へば、「知らずや。これこそ汝が書き奉りたる法華経の墨の、かく流るるよ」といふ。「それはいかなれば、かく川に流るるぞ」と問ふに、「心のよくまことをいたして清く書き奉りたる経は、さながら王宮に納められぬ。汝が書き奉りたるやうに、心きたなく、身けがらはしうて書き奉りたる経は、広き野辺に捨て置きたれば、その墨の雨に濡(ぬ)れて、かく川に流るるなり。この川は汝が書き奉りたる経の墨の川なり」といふに、いとど恐ろしともおろかなり。
「さても、この事はいかにして助かるべき事ある。教へて助け給へ」と泣く泣くいへば、「いとほしけれども、よろしき罪ならばこそは助かるべき方(かた)をも構へめ、これは心も及び、口にても述ぶべきやうもなき罪なれば、いかがせん」といふに、ともかくもいふべき方(かた)なうて行く程に、恐ろしげなるもの走りあひて、「遅く率(ゐ)て参る」と戒(いまし)めいへば、それを聞きて、さげ立てて率(ゐ)て参りぬ。大きなる門に、わがやうに引き張られ、また頸枷(くびかし)などいふ物をはげられて、結(ゆ)ひからめられて、堪えがたげなる目ども見たる者どもの、数も知らず、十方より出(い)で来(き)たり。
集りて門に所なく入り満ちたり。門より見いるれば、あひたりつる軍(いくさ)ども、目をいからかし、舌なめづりをして、我を見つけて、「とく率(ゐ)て来(こ)かし」と思ひたる気色(けしき)にて立ちさまよふを見るに、いとど土も踏まれず。「さてもさても、いかにし侍らんとする」といへば、その控へたる者、「四巻経書き奉らんといふ願をおこせ」とみそかにいへば、今門入る程に、この科(とが)は四巻経書き、供養してあがはんといふ願をおこしつ。
さて入りて、庁の前に引き据(す)ゑつ。事沙汰(ことさた)する人、「彼は敏行か」と問へば、「さに侍り」と、この付きたる者答ふ。「愁(うれ)へども頻(しき)りなるものを、など遅くは参りつるぞ」といへば、「召し取りたるまま、滞(とどこほ)りなく率(ゐ)て参り候ふ」といふ。「娑婆世界(しやばせかい)にて何事かせし」と問はるれば、「仕りたる事もなし。人のあつらへに随(したが)ひて、法華経を二百部書き奉りて侍りつる」と答ふ。
それを聞きて、汝は、もと受けたる所の命は今しばらくあるべけれども、その経書き奉りし事の、けがらはしく清からで書きたる愁(うれ)への出で来て、からめられぬるなり。すみやかに愁(うれ)へ申す者どもに出(いだ)し賜(た)びて、彼らが思ひのままにせさすべきなり」とある時に、ありつる軍(いくさ)ども、悦(よろこ)べる気色(けしき)にて請(う)け取らんとする時に、わななくわななく、「四巻経書き、供養せんと申す願の候ふを、その事をなんいまだ遂げ候はぬに召され候ひぬれば、この罪重く、いとどあらがふ方(かた)候はぬなり」と申せば、この沙汰する人聞き驚きて、「さる事やはある。誠ならば不便(ふびん)なりける事かな。帳を引きて見よ」といへば、また人、大きなる文を取り出でて、ひくひく見るに、我がせし事どもを一事も落とさず記(しる)しつけたる中に、罪の事のみありて功徳の事一つもなし。この門入りつる程におこしつる願なれば、奥の果てに記されにけり。文(ふみ)引き果てて、今はとする時に、「さる事侍り。この奥にこそ記されて侍れ」と申し上げければ、「さてはいと不便な事なり。この度(たび)の暇(いとま)をば許し給(た)びて、その願遂げさせて、ともかくもあるべき事なり」と定められければ、この目をいからかして、吾(われ)をとく得んと手をねぶりつる軍ども失(う)せにけり。「たしかに娑婆世界に帰りて、その願必ず遂げさせよ」とて許さるると思ふ程に、生き返りにけり。
妻子泣き合ひてありける二日といふに、夢の覚めたる心地して、目を見あけたりければ、「生き返りたり」とて悦びて、湯飲ませなどするにぞ、「さは、我は死にたりけるにこそありけれ」と心得て、勘(かんが)へられつる事ども、ありつる有様、願を起こしてその力にて許されつる事など、明らかなる鏡に向ひたらんやうに覚えければ、いつしか我が力付きて清まはりて、心清く四巻経書書き供養し奉らんと思ひけり。やうやう日比経(ひごろへ)、比(ころ)過ぎて、例のやうに心地もなりにければ、いつしか、四巻経書書き奉るべき紙、経師(きやうじ)にうち継(つ)がせ、け掛けさせて、書き奉らんと思ひけるが、なほもとの心の色めかしう、経仏の方(かた)に心のいたらざりければ、この女のもとに行き、あの女懸想(けさう)し、いかでよき歌詠(よ)まんなど思ひける程に、暇(いとま)なくて、はかなく年月過ぎて、経をも書き奉らで、この受けたりける齢(よはひ)、限りにやなりにけん。遂(つひ)に失せにけり。
その後一二年ばかり隔てて、紀友則(きのとものり)といふ歌よみの夢に見えけるやう、この敏行(としゆき)と覚(おぼ)しき者にあひたれば、敏行とは思へども、さま、かたち、たとふべき方(かた)もなく、あさましく恐ろしうゆゆげにて、現(うつつ)にも語りし事をいひて、「四巻経書き奉らんといふ願によりて、しばらくの命を助けて返されたりしかども、なほ心のおろかに怠りて、その経を書かずして遂に失せにし罪によりて、たとふべき方(かた)もなき苦を受けてなんあるを、もし哀(あは)れと思ひ給はば、その紙尋ね取りて、三井寺にそれがしといふ僧にあつらへて書き供養せさせて給(た)べ」といひて、大(おほ)きなる声をあげて泣き叫ぶと見て、汗水(あせみず)になりて驚きて、明くるや遅きと、その料紙尋ね取りて、やがて三井寺に行きて、夢に見えつる僧のもとへ行きたれば、僧見つけて、「うれしき事かな。只今人を参らせん。みづからにても参りて申さんと思ふ事のありつるに、かくおはしましたる事のうれしさ」といへば、まづ我が見つる夢をば語らで、「何事ぞ」と問へば、「今宵の夢に故敏行朝臣の見え給へるなり。四巻経書き奉るべかりしを、心の怠りに、え書き供養し奉らずなりにしその罪によりて、きはまりなき苦を受くるを、その料紙は御前のもとになん。その紙尋ね取りて四巻経書き供養し奉れ。事のやうは御前に問ひ奉れとありつる。大きなる声を放ちて叫び泣き給ふと見つる」と語るに、哀れなる事おろかならず。さし向ひて、さめざめと二人(ふたり)泣きて、「我もしかじか夢を見て、その紙を尋ね取りて、ここに持ちて侍り」といひて取らするに、いみじう哀れがりて、この僧誠をいたして手づからみづから書き供養し奉りて後、また二人が夢に、この功徳によりて堪へがたき苦少し免れたる由(よし)、心地よげにて、形もはじめには変りてよかりけりとなん見けり。
現代語訳
これも今は昔、敏行と言う歌人は、文字を上手に書いたので、誰れかれが注文するのに従って、法華経を二百部ばかり書き奉っているうちに、急に死んでしまった。自分は死ぬのだとは思わないのに、急に捕らえられて引き立てられてゆくので、自分のような無実の人間を天皇であってもこのようになさってよいだろうか、わけのわからないことだなと思って、捕らえて行く人に、「これはどういうことか。何の過ちで、このようなひどい目に遭うのか」と尋ねると、「さあ、自分にはわからん。『必ず召し連れて来い』という仰せを承って、連れて行くのだ。あなたは法華経を書いたか」と聞くので、「こうこう書き上げた」と答える。すると、「そなた自身のためにはどれほど書いたか」と聞くので、「自分のためというわけではない。ただ、人が書かせるのでそれに従って二百部程も書いたと思う」と言うと、「その事で訴えがあって、裁きがあるということらしい」とだけ言って、また他の事は何も言わずに歩いて行く。途中、不気味な感じで面と向い合っていられそうもない、恐ろしいという形容では言い尽せないような者で、目を見ると稲妻のようにきらめいており、口は火炎のように真っ赤で恐ろしい様子をした兵士どもが、鎧兜を着て何とも奇怪な馬に乗り続き、二百人ほどいるのに出会った。見ると心惑い、倒れてしまいそうな心地がするが、心も上の空な気持ちで引き立てられて行く。
さて、この兵隊たちは先に立って行ってしまった。自分を捕らえて行く人に、「あれはどういう兵士どもか」と問うと、「分らないのか。これこそおまえに経を頼んで書かせた者たちが、その功徳に寄って天上界にも生れ、極楽へも参り、再び人間に生れ返るとも、よい人間に生れるはずのものであった。それを、おまえが経を書いたとき、魚を食い、女にも手を出して、精進潔斎する事もなく不浄の身で写経に携わるという罪を犯し、心を女に奪われ、心を込めず経を書いたので、その功徳がかなわず、このようにいかめしく猛々しい身に生れたのだ。それで、お前を恨めしがって、『呼んで下さい。この恨みを晴らしたい』と訴えるので、この度は、召されるはずの理屈に合った時期ではないのだが、召されるのだ」と言う。それを聞いて敏行は、身を切られるように心も凍りついて、息も止まりそうな気持になる。
「それで私をどしようと、このように訴えたのか」と問うと、「問うまでもない事。その持っている太刀、刀で、お前の身体を二百に斬り裂いて、それぞれ必ず一切れづつ取ろうというのだ。その二百の切身にお前の心も分れて、それぞれに心があり、責めさいなまれるにつれて、悲しくつらい目を見ることになろうぞ。その堪えがたい事は例えようもないだろう」と言う。「それでは、その事からどうしたら助かる事ができるのか」と言うと、「まったく私にも考えつかない。それくらいだからましておまえにその責め苦に堪えて助かる力などあるはずがない」と言うので、歩む足も地につかない。
さらに行くと、大きな川がある。その水を見ると、濃くすった墨の色のような水が流れていた。不思議な水の色だなと見て、「これはどういった水で、墨の色をしているのか」と問うと、「分らないのか。これこそお前が書写した法華経の墨がこのように流れているのよ」と言う。「それがどうすればこのように川に流れているのか」と問うと、「精進潔斎して慎んで書写した経典は、おおかたは閻魔王宮に納められたのだ。お前が書いたように、心が汚れており、汚らわしい身体を以て書いた経は、広い野辺に捨て置いたので、その墨が雨に濡れて、このように川に流れだしたのだ。この川はお前が書いた経の墨の川である」と言うので、いよいよその恐ろしさといったらない。。
「では、この事から助かるにはどうしたらよいのか。教えて助けて下さい」と泣く泣く言うと、可哀想だが普通の罪なら助かる方法もあるだろうが、これは、想像を絶し、形容しようもない甚だしい重罪だから、どうにもならない」と言うので、もう何も言いようもなくて進むうちに、恐ろしそうな者が走り寄って来て、「遅かったぞ、連れて来るのが」と叱咤すると、獄卒はそれを聞いて敏行を吊り上げて連れて行った。大きな門に自分と同じように引いて来られ、また首枷(くびかせ)などという物をはめられて、ぐるぐる巻きに縛られ、堪えられそうもない苦しい目に遭っている者どもが、数知れず、方々から集まって出て来た。
集まって門内に隙間なくいっぱいに入っている。門から中を見ると、さっき出会った兵士たちが、目をいからかし、舌なめづりをして、自分を見つけて、「さっさと連れて来ないか」と思った様子でうろついている。それを見ると、いよいよ足が地につかない。「さてもさても、どうしたものでしょう」と言うと、敏行を引き押さえている獄卒が、「四巻経をお書き申し上げるという願を立てよ」と密かに言うので、ちょうど門を入ろうとするときに、この罪を四巻経を書写し、供養して償おうという願を立てた。
さて門を入って庁の前に引き据えられた。裁きをする人(閻魔大王)が、「彼が敏行か」と問うと、「さようでございます」とこの敏行に付き添って来た獄卒が答える。「訴えがたびたび重なるのに、なぜ遅れて参ったのか」と言うと、「召し取ってすぐに引き連れて参りました」と言う。「人間世界ではどのような善行をしたのか」と問われると、「これといってたいしたこともありません。人の依頼に従って、法華経を二百部書き申し上げました」と答える。それを聞いて大王は、「お前は、もともと授けられた命は今しばらくあるはずだが、その経を書き写したやり方が、汚らわしく清浄ではなかった事で訴えが起こり、捕らえられたのだ。すぐに訴えを起こした者どもにお前の身柄を渡してやって、彼らの思いのままにさせるがよかろう」と言う時、先ほど出会った異様に恐ろしげな馬上の武装兵どもが喜んだ様子で敏行の身柄を請け取ろうとした。その時、敏行はぶるぶる震えながら、「四巻経を書写し、供養し申し上げる願を立てましたが、その事をいまだ為し遂げていないのに召されましたので、この罪は重く、まったく抗弁しようもありません」と言うと、大王はそれを聞いて、「そういう事実があるのか。事実なら気の毒なことだ。帳簿を開いて見よ」と言うと、別の人が大きな帳簿つづりを開いて、めくりめくりながら見ると、自分がした事などを一つも漏らさず記述した中に、罪の事ばかりは書いてあるが功徳の事に関する記述は一つもない。この門をくぐった時に立てた願なので、その事は最後に記されていた。これで終わりとする時に、「それに関する記述が最後に記されております」と申し上げたので、「それは実に気の毒な事だ。今回は許して暇を与え、その願を遂げさせたうえでどうとでもするがよかろう」と裁定を下された。すると、この目を怒らかして自分をすぐに得ようと手を舐って待ち構えていた兵士どもは一瞬に消え失せてしまった。「間違いなく娑婆世界に帰って、その願必ず遂げよ」と言って、許されたと思ったとたん、敏行は生き返ったのであった。
妻子が泣き合っていた死後二日目に、夢が覚めたような心地になって敏行が目をあけると、妻子が、「生き返った」と言って喜び、お湯など飲ませるなどすると、「さては自分は死んでいたのであった」と納得して、冥途で問いただされたことのあれやこれや、見聞してきた冥途の様子、願を立ててその力で許された事など、みな明るい鏡に向っているようにはっきりと思いだした。いつか、そのうちに自分の体力が回復して、精進潔斎して、心清く四巻経を書写し、供養し申し上げようと思った。ようやく何日かがたち、何か月かが過ぎて、気分も平生のようになったので、四巻経を書き上げるべき紙を経師に継がせ、罫線を引かせて早く書き上げようと思った。しかしもともとの心は色好みで、経や仏の方に気持ちが向かず、この女のもとに行き、あの女に思いをかけ、どうやってよい歌を詠もうかなどと思っているうちに、経を書く暇も無くなり、むなしく年月が過ぎ、経も書き上げないまま、与えられていた寿命も尽き、遂に死んでしまった。
その後一、二年ばかり経って、敏行は紀友則という歌人の夢に現れた。この敏行と思われる者に会うと、敏行とは思われるが、その様子や姿はたとえようもなくひどく恐ろしく不吉な感じであった。生前にも語っていたことを述べて、「四巻経書き申し上げるという願によって、しばらくの命を与えられてこの世に帰されたのだが、なおも愚かな心が残っており、その経を書かずにとうとう死んでしまうことになった。その罪で、例えようもない苦痛を受けているのだが、もし哀れと思われるなら、経を書くために自分が用意したその紙を捜しだして、三井寺に居るこれこれという僧に頼んで書写供養させてほしい」と言い、大きな声で泣き叫ぶのを見て汗びっしょりになって目が覚めた。そこで、夜が明けるを待ちかねて、その料紙を捜しだし、すぐに三井寺に行き夢に見えた僧のもとへ行くと、僧が見つけて、「ありがたいことです。只今使いを差し向けましょう。自分から参って話そうと思っていた事があったのですが、このようにお出でいただいてなんとありがたいこと」と言う。それでまず、友則は、自分の見た夢の事は話さず、「どうなされたのか」と問うと、「今宵の夢に故敏行朝臣がお見えになったのです。四巻経を書き申し上げるべきところ、気持が緩み、書き供養申し上げる事ができなかった。その罪で限りない苦痛を受けているが、書くべき料紙はきっとあなたの所にあります。その料紙を捜しだして四巻経を書写供養してください。詳しい事情はあなたにお聞きくださいとのことでした。大きな声で泣き叫んでおられると見ました」と語る。それを聞くとその哀れな事は 尋常ではない。二人は向きあってさめざめと泣き、友則が、「私も同じような夢を見て、その紙を捜しだし、ここに持っております」と言って、差し出すと、その僧はひどく哀れがって、誠実に自ら書写供養し申し上げた。その後、また二人の夢に、敏行が現れ、「この功徳によって堪えがたい苦痛を少し免れました」と、心地よさそうに語った。顔つきもはじめ見たときよりは変ってよくなっているようであったという。
語句
■敏行-藤原敏行。本話と同文話の『今昔』巻一四-二九話は橘敏行とするが、紀友則との関係及び書家としての声価の不明な点から、橘氏説は採らない。鞍察使富士麿の子。蔵人頭を経て、寛平九年(897)近江権守、右兵衛督、『古今集』以下に二十八首入集している歌人。能書家として知られ、『江談抄』第三に、村上天皇がわが朝の書の上手を問うたのに対して小野道風が「空海、敏行」の名前を挙げた話が見える。没年は延喜元年(901)、一説に同七年。■手をよく書きたれば-能書家であったために。文字を上手に書いたために。■これかれがいふに随(したが)ひて-誰かれの注文に従って。■法華経-大乗経典の一つ。釈迦が霊鷲山(りやうじせん)で行った説法を記録した、諸大乗経典の中でも最も比喩の多い文学的表現に富み、高遠な法を説くとされるもの。わが国では、鳩摩羅什(くまらじゆう)漢訳の『妙法蓮華経』八巻二十八品が最もよく普及した。■二百部-『今昔』では「六十部許」とする。『法華経』全巻を一部と勘定する。■からめて引き張りて-捕らえて引っ張って。■率て行けば-連れてゆくので。■我ばかりの人を-自分のような無実の人間を。■おほやけと申すとも-天皇であっても。■かくさせ給ふべきか-このようになさってよいだろうか。■心得ぬわざかなと-わけのわからないことだなと。■目をば見るぞ-ひどい目にあうのか。■いさ-さあ。■そこは-あなたは。■法華経や書き奉りたる-法華経をお書き申したか。■しかじか-こうこう。■我がためには-そなた自身のためには。■その事の愁(うれ)へ出(い)で来(き)て-その二百部程も書いたという事について訴えが起こって。■沙汰(さた)のあらんずるにこそあめれ-裁きがあるらしいようだぞ。■異事も言はで-ほかの事も言わないで。■あさましく人の向ふべくもなく-不気味な感じで面と向い合っていられそうもない。■恐ろしといへばおろかなる者の-恐ろしいという形容では言い尽くせないような者で。■口は炎(ほむら)などのやうに恐ろしき気色(けしき)したる軍(いくさ)の-口は燃え盛る炎のように真っ赤で恐ろしい様子をした兵隊が。■えもいはぬ馬-何とも奇怪な馬。『今昔』では「鬼ノ如クナル馬」。■肝惑ひ-心が惑い。■吾(われ)にもあらず-夢うつつの気持ちで。心にもなく。
■え知らぬか-分らないのか。■あつらへて-頼んで。■その功徳-『法華経』を書写させた善行の功徳。「功徳」はよい転生の果報を期待し得る積善の功。■天-以下に「極楽」、「人(にんげん)」とあるので、ここは六道の天上界。■生るべかりしが-生れるはずであたのが。■極楽-西方十万億土のかなたにあるとされる阿弥陀仏の安楽浄土。■また人に生れ返るとも-再び人間としてこの世に生れ変って来るにしても。■清まはる事もなくて-(魚食・女犯の戒律を守らず)精進潔斎することもなく、不浄の身で写経に携わるという罪を犯したことをさす。■いかう武き身-いかつく猛々しい身。はげしく荒々しうふるまう者。■妬がって-恨めしがって。■呼びて給はらん-呼んで下さい。■その仇報ぜん-その恨みを晴らしたい。この結果への仕返しをしたい。■愁へ申せば-お訴え申すので。■道理にて召さるる度にあらねども-人間としての寿命が尽きてこの冥土に呼び迎えられる順番に当たっているわけではないが。■心もしみ凍りて-「しみ凍る」は「凍み凍る」で、「凍る」の強調形。心もすっかり凍りつく思いで。凍りついて。
■二百-冒頭の『法華経』二百部の書写と対応する。敏行の身体を二百切れし、彼の「心」もその二百切れの中に入っていて、それぞれが別人によって責められるはずだという獄卒の説明は、要するに敏行が通常の二百倍の責め苦を受けることになるということを、感覚に訴えることをねらった具体的で独特な表現。■取りてんとす-必ず手に入れようというのだ。■見んずるぞかし-見ることになろうぞ。■たとへん方(かた)あらんやは-たとようがないだろう。■さらに我も~あるべきにあらず-全く私にも考えがつかない。それくらいだから、ましておまえに、その責め苦に堪えて助かる力などあるはずがない(絶望的だ)。■歩む空なし-歩む足も地につかない。心も虚ろな状態での歩行ぶり。
■清く書き奉りたる経は-精進潔斎して慎んで書写した経典は。本書第一話でも不浄の説法を戒めているが、マハーバーラタの「ナラ王物語」にも、ニシャダ王が小用の後、手と口はすすいだが、両足の浄めをせぬまま朝夕の勤めをしたために、カリ王という悪玉にとり憑かれた例が見える。■さながら王宮に納められぬ-そのまま大切に閻魔王宮に納められるのだ。『今昔』は「竜宮」(海中の竜王の宮殿)とする。■広き野辺-閻魔王宮にいたる途中にある冥途の広大な野原。■よろしき罪-一通りの、並み普通の罪なのであれば。「よろし」は、まあまあの、普通の程度の、の意。■口にても述ぶべきやうもなき-(罪の程度が)想像を絶し、形容を絶した甚だしいものであることを言う。■いふべき方なくて-言うべき言葉を失って。何も言うことができなくなって。■さげ立てて-吊り上げて。
■いちど土も踏まれず-まるで足が地につかない。■四巻-曇無讖(どんむしん)の漢訳した四巻十八品の『金剛明経』の異称。唐の義浄訳の十巻本に対していう。■控えたるもの-引き押さえている者。■みそかに-ひそかに。■今門入る程に-ちょうど門を入るときに。■科(とが)-罪。■あがはん-つぐなおうと。
■庁-閻魔庁の庁舎。■事沙汰する人-裁きをする人が。閻魔大王を指す。■さに侍り-さようでございます。■この付きたる者-この敏行に付き添っている獄卒。敏行にとっては恩人になる。前出の「その控へたる者」に同じ。■愁へどもしきりなるものを-訴えがたびたびかさなるのに。■など-どうして。■滞(とどこほ)りなく率(ゐ)て参り候ふ-すぐさま連れて参ったのです。■娑婆世界-六道のうちの人間界。この世。すなわち敏行が生前において。■何事かせし-どんなことをしたか。善根となる何事かを。■仕りたる事もなし-これといってたいしたこともありません。
■もと受けたる所の命-人間に生れた時に与えられていた本来の寿命。■あるべけれども-あるはずであるが。■からめられぬるなり-逮捕されたのである。■出(いだ)し賜(た)びて-敏行の身柄を引き渡してやって。■ありつる軍(いくさ)ども-先ほど出会った異様に恐ろしげな馬上の武装兵ども。■わななくわななく-ぶるぶる震えながら。■この罪重く-この不浄の身での『法華経』書写という罪過が重いままに残る事になって。■いとどあらがふ方(かた)候はぬなり-まるで抗弁する余地はありません、私は大変きびしく不利な立場に立たされています。■さる事-「四巻経」によって供養しようと願を立てた事実。■不便なりけることかな-かわいそうなことだな。■帳-帳簿、いわゆる閻魔帳。死者の娑婆における善悪一切の行動が細大漏らさず記録されているとされる。■引きて-開いて。■文-書類の綴り。帳簿。■引く引く-繰り広げながら。■今はとする時に-もうこれで終りと、帳簿を閉じようとする時に。■さては-そうならば。「四巻経」を書写して供養すると願を立てたことが事実であったとすれば。■この度(たび)の暇(いとま)をば許し給(た)びて-今回一度娑婆へ帰って書写供養をするための時間を許し与えて。■その願遂げさせて-願を遂げさせたうえで。■ともかくもあるべき事なり-どのように処分すればよいかを決めればよいことである。■手をねぶりつる軍ども-手をなめながら今や遅しと待ち構えていた兵隊どもは。
■二日といふに-死後二日目という時に。■湯飲ませなどするにぞ-死者だった敏行の空腹を癒し、体を温めるために、枕辺に居た家族の者がお湯を飲ませたりしたので。■「さは、我は死にたりけるにこそありけれ」と心得て-「さては自分は死んでいたのであった」と納得して。■勘(かんが)へられつる事ども-(冥途で)問いただされたことのあれやこれや。■ありつる有様-見聞してきた冥途の様子。■覚えければ-はっきりと思いだしたので。■いつしか我が力付きて清まはりて-いつか、そのうちに自分の体力が回復して、精進潔斎して。■やうやう日比経(ひごろへ)、比(ころ)過ぎて-ようやく何日かがたち、何か月かが過ぎて。■例のやうに心地もなりにければ-ふだんのような気分にもなったので。■経師(きやうじ)-古くは経巻を書写する職人をいった。ここは経巻の表具師。■うち継がせ、け掛けさせて-用紙をつなぎ合せ、罫(けい)を引かせて(書写の用意を整えて)、「罫」は文字の行間の境界線。■なほもとの心の色めかしう-やはりもともとの心が色好みで。■至らざりければ-ゆかなかったので。■懸想-思いを懸ける事。心を傾ける事。■いかで-何とかして。■はかなく-むなしく。書写も供養も何もしないままに。■この受けたりける齢(よはひ)-敏行に与えられていた寿命。
■紀友則-紀有友の子。生没年未詳。貫之の従兄弟。歌人。延喜四年(904)、大内記。『古今集』選者の一人。三十六歌仙の一人。『古今集』哀傷に次のようにあり、敏行との親交ぶりがうかがわれる。「藤原敏行朝臣の身まかりける時に、よみてかの家につかはしける紀友則/寝ても見ゆ寝でも見えけりおほかたは空蝉の世ぞ夢にはありける」。■覚しき-思われる。■たとうべき方もなく-たとえようもなく。■ゆゆしげにて-いまわしい様子で。■現にも語りし事-生前にも語っていた事。■その紙尋ね取りて-経を書くために自分が用意したその紙を捜しだして。■汗水になりて-びっしょりと汗をかいて目を覚まして。■みずからにても-急ぐので場合によっては私自身が参上して。■御前-敬称の代名詞。ここは友則の事を指す。■なん-きっとあります。書陵部本などには「なんあらん」とする。■事のやう-詳しい事情。事のいきさつ。■おろかならず-尋常ではない。並一通りではない。■手づからみづから-全く他人を煩わすことなくいっさい自分の手で。