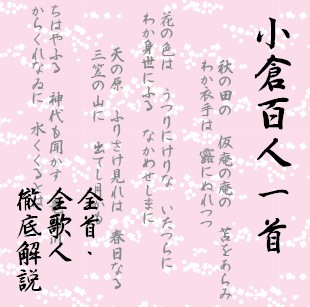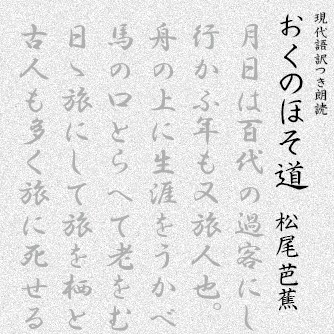宇治拾遺物語 9-1 滝口道則(たきぐちみちのり)、術を習ふ事
昔、陽成院(やうぜいゐん)位にておはしましける時、滝口道則(たきぐちみちのり)、宣旨(せんじ)を承り、陸奥(みちのく)へ下(くだ)る間(あひだ)、信濃国(しなののくに)ひくうといふ所に宿りぬ。郡(こほり)の司(つかさ)に宿をとれり。設(まう)けしてもてなして後(のち)、あるじの郡司は郎等(らうどう)引き具(ぐ)して出でぬ。いもねられざりければ、やはら起きて、たたずみ歩(あり)くに、見れば、屏風(びやうぶ)を立てまはして、畳など清げに敷き、火ともして、よろづ目安きやうにしつらひたり。空薫物(そらだきもの)するやらんと、香(かう)ばしき香しけり。いよいよ心にくく覚えてよく覗(のぞ)きて見れば、年廿七八ばかりなる女一人(ひとり)ありけり。みめことがら、姿、有様、殊(こと)にいみじかりけるが、ただ一人臥(ふ)したり。
見るままに、ただあるべき心地せず。あたりに人もなし。火は几帳(きちやう)の外(と)に灯してあれば、明(あか)くあり。さてこの道則思ふやう、よによにねんごろにもてなして、志ありつる郡司の妻を、うしろめたき心つかはん事いとほしけれど、この人の有様を見るに、「ただあらん事かなはじ」と思ひて、寄りて傍(かたは)らに臥すに、女、けにくくも驚かず、口おほひをして笑ひ臥したり。
いはん方(かた)なくうれしく覚えければ、長月(ながつき)十日比(ごろ)なれば衣(ころも)もあまた着ず、一襲(ひとかさね)ばかり男も女も着たり。香ばしき事限りなし。我が衣(きぬ)をば脱ぎて女の懐(ふところ)へ入るに、しばしは引き塞(ふた)ぐやうにしけれども、あながちにけにくからず懐に入れぬ。男の前の痒(かゆ)きやうなりければ、探りて見るに物なし。驚きあやしみて、よくよく探れども、頤(おとがひ)の髭(ひげ)を探るやうにて、すべて跡形(あとかた)なし。大(おほ)きに驚きて、この女のめでたげなるも忘られぬ。この男探りて、あやしみくるめくに、女、少しほほゑみてありければ、いよいよ心得ず覚えて、やはら起きて、我が寝所(ねどころ)へ帰りて探るに、さらになし。あさましくなりて、近く使ふ郎等を呼びて、かかるとはいはで、「ここにめでたき女あり。我も行きたりつるなり」といへば、悦(よろこ)びてこの男往(い)ぬれば、しばしありて、よによにあさましげにて、この男出(い)で来(き)たれば、これもさるなめりと思うて、また異男(ことをとこ)を勧めてやりつ。これもまたしばしありて出(い)で来(き)ぬ。空を仰ぎて、よに心得ぬ気色(けしき)にて帰りてけり。かくのごとく七八人まで郎等(らうどう)をやるに、同じ気色に見ゆ。
かくする程に、夜も更(ふ)けぬれば、道則(みちのり)思ふやう、「宵(よひ)にあるじのいみじうもてなしつるをうれしと思ひつれども、かく心得ずあさましき事のあれば、とく出でん」と思ひて、いまだ明け果てざるに急ぎて出づれば、七八町行く程に、後(うし)ろより呼ばひて馬を馳(は)せて来(く)る者あり。走りつきて、白き紙に包みたる物を差し上げて持(も)て来(く)。馬を控えて待てば、ありつる宿に通ひしつる郎等なり。「これは何ぞ」と問へば、「これ、郡司の参らせよと候(さぶら)ふ物にて候ふ。かかる物をば、いかで捨ててはおはし候ふぞ。形(かた)のごとく御設(まう)けして候へども、御いそぎに、これをさへ落させ給ひてけり。されば拾ひ集めて参らせ候ふ」といへば、「いで、何(なに)ぞ」とて取りて見れば、松茸(まつたけ)を包み集めたるやうにてある物、九つあり。あさましく覚えて、八人の郎等、とりどりあやしみをなして見るに、まことに九つの物あり。一度にさつと失(う)せぬ。さて、使(つかひ)はやがて馬を馳せて帰りぬ。その折、我が身より始めて、郎等どもみな、「ありあり」といひけり。
さて陸奥(みちのく)にて金(かね)受け取りて帰る時、また信濃(しなの)のありし郡司のもとへ行きて宿りぬ。さて、郡司に金、馬、鷲(わし)の羽(は)など多く取らす。郡司よによに悦(よろこ)びて、「これはいかに思(おぼ)して、かくはし給ふぞ」といひければ、近く寄りていふやう、「かたはらいたき申し事なれども、初めこれに参りて候ひし時、あやしき事の候ひしは、いかなる事にか」といふに、郡司、物を多く得てありければ、さりがたく思ひてありのままにいふ。「それは若く候ひし時、この国の奥の郡(こほり)に候ひし郡司の、年よりて候ひしが、妻の若く候ひしに、忍びてまかり寄りて候ひしかば、かくのごとく失せてありしに、あやしく思ひて、その郡司にねんごろに志を尽して習ひて候ふなり。もし習はんと思し召さば、この度(たび)はおほやけの御使(つかひ)なり。すみやかに上(のぼ)り給ひて、またわざと下(くだ)り給ひて習ひ給へ」といひければ、その契(ちぎ)りをなして上(のぼ)りて、金など参らせて、また暇(いとま)を申して下(くだ)りぬ。
郡司にさるべき物など持ちて下(くだ)りて取らすれば、郡司大に悦びて、心の及ばん限りは教へんと思ひて、「これは、おぼろげの心にて習ふ事にては候(さぶら)はず。七日水を浴(あ)み、精進(しやうじん)をして習ふ事なり」といふ。そのままに清まはりて、その日になりて、ただ二人(ふたり)連れて深き山に入りぬ。大(おほ)きなる河の流るるほとりに行きて、さまざまの事どもを、えもいはず罪深き誓言(せいごん)ども立てさせけり。その郡司は水上へ入りぬ。「その川上より流れ来(こ)ん物を、いかにもいかにも鬼にてもあれ、何(なに)にてもあれ、抱(いだ)け」といひて行きぬ。
しばしばかりありて、水上の方(かた)より雨降り風吹きて、暗くなり、水まさる。しばしありて、川上より頭一抱(かしらひといだ)きばかりなる大蛇(だいじや)の、目は金椀(かなまり)を入れたるやうにて、背中は紺青(こんじやう)を塗りたるやうに、首の下は紅(くれなゐ)のやうにて見ゆるに、「まづど来ん物を抱け」といひつれども、せん方(かた)なく恐ろしくて草の中に伏しぬ。しばしありて郡司来たりて、「いかに取り給ひつや」といひければ、「かうかう覚えつれば、取らぬなり」といひければ、「かく口惜しき事かな。さてはこの事はえ習ひ給はじ」といひて、「今一度試みん」といひてまた入りぬ。しばしばかりありて、やをばかりなる猪(ゐ)のししの出(
い)で来(き)て、石をはらはらと砕けば、火きらきらと出づ。毛をいららかして走りてかかる。せん方(かた)なく恐ろしけれども、「これをさへ」と思ひ切りて、走り寄りて抱きて見れば、朽木(くちき)の三尺ばかりあるを抱きたり。妬(ねた)く悔(くや)しき事限りなし。「初めのもかかる者にてこそありけれ。などか抱かざりけん」と思ふ程に、郡司来たりぬ。「いかに」と問へば、「かうかう」といひければ、「前の物失ひ給ふ事はえ習ひ給はずなりぬ。さて、異事(ことごと)の、はかなき物を物になす事は習ひぬめり。さればそれを教へん」とて、教へられて帰り上(のぼ)りぬ。口惜しき事限りなし。大内(おほうち)に参りて、滝口どものはきたる沓(くつ)どもを、あらがひをして皆犬子になして走らせ、古き藁沓(わらぐつ)を三尺ばかりなる鯉(こひ)になして、台板(だいばん)の上に躍(をど)らする事などをしけり。御門(みかど)、この由(よし)を聞し召して、黒戸の方(かた)に召して習はせ給ひけり。御几帳(みきちやう)の上より賀茂祭など渡し給ひけり。
現代語訳
昔、陽成院が御位についておられた時、滝口道則は宣旨を承り、陸奥へ下ったが、途中、信濃国ひくうという所で泊まることになり、そこの郡司の家に宿をとった。郡司はご馳走をして道則をもてなした後、郎等どもを引き連れて出て行った。道則はなかなか寝付けなかったので、そっと起きて、ぶらぶら歩いているうちに、ふと見ると、屏風を立てめぐらし、畳などを小ぎれいに敷き、火をともして、万事気持ち良く整えられている。どこで焚いているのか分らないが香を焚いているらしく、ほのかに香りが漂っている。ますます心にくく思ってよく覗いて見ると、年のころ二十七八くらいの女が一人いた。顔だち、人品、姿、様子などの格別に美しい人がたった一人で寝ていた。
それを見るや、だまって見過ごす気持にはなれない。あたりには人もいない。灯火が几帳の外に灯してあるので、明るい。そこで、この道則が思うには、「はなはだ厚くもてなしてくれて、自分たちに深い好意を示してくれたあの郡司の妻に対して、後ろ暗いやましい気持ちを抱くのは気の毒ではあるが、この女の様子を見ると、「このまま黙っていることはできない」と思い、寄って傍に寝ると、女は憎らしいくらいに驚かず、袖で口をおおって笑いながら寝ている。
言いようもなくうれしく思った。九月十日ごろなので厚着もせず、男も女も一重の衣を着ていた。限りなく香ばしい。男は自分の着物を脱いで女の懐に入ろうとすると、女はしばらく肌を隠すようにしたが、強いて拒むようなそぶりを見せるわけでもなく、懐に入れた。その時に、男は、前の方が痒くなったので探って見るが一物がない。驚き、不思議に思って、よくよく探って見るが、顎鬚(あごひげ)を探っているようできれいさっぱりない。たいそう驚いて、この女のすぐれて美しいことも頭から離れてしまった。この男が探ってあわてふためくのを見て、女が、少し微笑んでいたので、ますますわけが分らず、そっと起きて、自分の寝所へ戻って探って見るがやはり跡形もない。情無くなり、近くに召し使っている郎等を呼んで、こういうふうだとは言わずに、「ここにとても美しい女がいる。自分も行ってみた」と言うと、喜んで、この男が出て行くと、しばらくしてから、はなはだあきれたような顔つきでこの男が帰って来たので、「これもやはりそうだったんだな」と、また違う男を勧めてやった。この男もしばらくして戻って来たが、空を仰いでまことに訳が分からないという様子で帰って来た。このように七、八人まで家来をやったが皆同じ様子に見えた。
こうしているうちに夜も更けたので、「宵の時分にはあるじのたいそうな持てなしを喜んだが、こんなわけの分からぬおかしな事が起こった場所なので、早く出て行こう」と思って、まだ夜も明けないのに急いで出立したが、七、八町行くうちに、後から繰り返し呼びかけながら馬を馳せて来る者がいる。走り終わって、白い紙に包んだ物を差し上げて持って来る。馬を控えさせて待っていると、昨晩宿泊した郡司の家に仕える郎等である。「これは何か」と問うと、「これは、主人の郡司が客人たちにお届けせよと申す物でございます。こんな大事な物を、どうして捨てておいでになりますか。型どおり朝食の準備をしておりましたのですが、お急ぎのあまり、これまでも落としておいででした。それで、拾い集めてお届けに参ったのでございます」と、言う。「さあ、何だろう」と取って見ると、松茸を包み集めたように男の陽物が九つある。びっくりして、八人の郎等が代わる代わる不思議そうに見ると、本当に九つの陽物がある。すると、その陽物は一度にさっと消え失せてしまった。使いの者はやがて馬を馳せて帰って行った。その時、自分を始めとして郎等どもはみな、「あるある」と言った。
さて、道則は陸奥で砂金を受け取って帰る時、また信濃の例の郡司のもとへ行って宿をとった。それから郡司に砂金、馬、鷲の羽根などをたくさん与えた。郡司は非常に喜んで、「これはまた、どうしてこんなにして下さるのです」と言ったので、近寄って、「恥ずかしい話ではありますが、最初ここに参った時、不思議な事があったのはどういうことですか」と言うと、郡司はたくさん物をいただいているので、断わり難く思って正直に答える。「それはまだ私が若うございましたころ、この国の奥にいた郡司が年老いておりましたが、その妻が若うございまして、そこへ忍んで通っておりましたところ、あのように一物がなくなってしまいましたので、不思議に思って、その郡司にねんごろにお願いして、その秘密を習ったのです。もし、あなたも習おうと思われるなら、この度は朝廷からのお使いです。早く京にお上りになって、また改めてお下りになってお習い下さい」と言ったので、その約束をして、京に上り、砂金などを届けて、また改めてお暇をいただいて下った。
郡司に相当の謝礼としての献上品を持って下り与えると、郡司は大いに喜び、出来る限りの事は教えようと思い、「これは、生半可な気持ちで習う事ではありません。七日間水浴びをし、ひたすら身を清めて習うことです」と言う。言われるままに、身を浄(きよ)め、その日になって、ただ二人連れだって山に入って行った。大きな川が流れる辺に行って、色々な事をして、言う事もはばかられる仏法に対する罪深い誓いを立てさせて、郡司は水上の方へ向かった。「その川上から流れて来る物を何としても何としても鬼であれ何であれ抱きなさい」と言って行った。
しばらくして、水上の方から雨が降り、風が吹いて、暗くなり、水嵩(みずかさ)が増した。しばらくすると、川上から頭が一抱え程もある大蛇が現れた。目は金鞠を入れたように輝き、背中は紺青を塗ったようで、首から下は紅のように赤く見える。郡司は、「まず出て来る物を抱け」と言ったが、どうしようもなく恐ろしくて草の中に身を伏せた。しばらくして郡司が来て、「どうです。つかまえられましたか」と言ったので、「これこれで恐ろしかったので捕まえられなかった」と言うと、「それは残念な事。ではこれを習う事はできません」と言って、「もう一度やってみましょう」と言って、また川の中に入っていった。しばらくすると、八尺ほどもある猪が出て来て、石をばらばらと噛み砕いたので、火花がきらきらと出る。怒って、毛を逆立てて突進してくる。どうしようもなく恐ろしかったが、「この猪さえ抱けないようでは」と思い切って、走り寄って抱いて見ると、三尺ばかりの朽木を抱いている。しゃくにさわり悔しい事といったらない。「最初の物も、このよう物であったのか。どうして抱かなかったのだろうか」と思っていると、郡司がやって来た。「どうでしたか」と聞くので、「こうこうしかじか」と言ったので、「男の前の物を失う術はお習いできずに終った。しかし、それとは別のちょっとした物を何かに変える術は、習得できるでしょう。では、その術を教えましょう」と、その術を教えられて京へ帰った。悔しい事限りない。
その後、宮中に参り、言い争いをした時には、滝口の侍などの履いている沓などを、みな子犬にして走らせたり、古い藁草履(わらぞうり)を三尺くらいの鯉に変えて、台板の上で踊らせる事などをした。帝は、この話をお聞きになり、道則を黒戸の所へお呼びになって、この術をお習いになり、御几帳の上から賀茂祭の行列などをお渡しになられたという。
語句
■陽成院-第五十七代天皇(868-949)。清和天皇の皇子。貞観十八年(876)~元慶八年(884)在位。奇行の伝えが多い。■滝口道則-伝未詳。類話の『今昔』巻二〇-一○話では「道範」。「滝口」は、清涼殿の東北の御溝水(みかわみず)の落ち口(すなわち滝口)の近くに詰めていた、禁中警護の武士。■宣旨(せんじ)-天皇の命令書。■陸奥(みちのく)-東北地方のうち、秋田・山形県を除く地域にあたる陸奥国。■信濃国(しなののくに)-現在の長野県。■ひくう-『大日本地名辞書』の指摘によれば、「いがら(育良、伊賀良)」の誤りか。とすれば飯田市内。■郡の司-郡司。国司を補佐する、地方豪族の中から選任された終身官。■いもねざりければ-なぜか寝付かれなかったので。■たたずみ歩くに-時々立ち止まったりしながら、ぶらぶら歩きまわっていると。■畳-敷物・ござの類。ここは高麗縁(こうらいべり)などを施した上敷用のござを指す。■空薫物(そらだきもの)するやらんと香(かう)ばしき香しけり-どこでたいているのか分らないが、香をたいているらしく、ほのかに香りが漂っている。■年廿七八ばかりなる女-『今昔』は「年二十余許(ばかり)ノ女」とする。
■ただあるべき心地せず-そのまま黙って見過ごす気持になれない。■よによにねんごろに-はなはだ手厚く。■志ありつる郡司の妻を-自分たちに深い好意を示してくれたあの郡司の妻である人に対して。■うしろめたなき心つかはん事-気がとがめるような、よからぬ思いを抱くこと。「うしろめたなき心(後ろ暗い心)」は「うしろめたき心」に同じ。■いとほしけれど-申し訳ないことだが。気の毒ではあるけれども。■ただあらん事かなはじ-何もせずに引き下がる気にはなれない。■けにくくも-心得た様子で、あらがう態度も見せず、騒ぎたてもせずに。
■いはん方なくうれしく覚えければ-言いようもなくうれしい気分であり。女の迎え入れてくれそうな態度が、まことにもってうれしく思われたので、ためらわずその気になることができて。■長月十日-陰暦の九月十日。まだ暖かい時節。■一襲(ひとかさね)ばかり着たり-上下一対の一重の着衣だけをまとっていた。『今昔』は「紫苑色ノ綾ノ衣一重、濃キ袴ヲゾ着タリケル」とする。■しばしは引き塞ぐやうにしけれども-しばらくは着衣の前をふさぐように抵抗する様子を見せたが。■あながちにけにくからず-強く拒むような態度をとることもなく。■すべて跡形なし-きれいさっぱりない。■空を仰ぎて-空を仰いで。■よに心得ぬ気色にて-まったく合点のいかぬ顔つきで。
■かく心得ずあさましき事のあれば-このようなわけの分からない取り返しのつかない悔しい事が起こったりした場所なので。■呼ばひて-繰り返し呼びかけながら。「呼びて」に反復・継続の意を添える助動詞「ふ」のついたもの。■ありつる宿-前夜宿泊した宿。郡司の館。■通ひしつる-御膳を運んで給仕した。『今昔』は「物取て食ハセツル郎等也ケリ」とする。■郡司の参らせよと候ふ物にて候ふ-主人の郡司が、客人たちにお届けせよと申します物でございます。以下、「候ふ」調で一貫している丁寧な物言い。■形のごとく御設けして候へども-型どおりに朝食のご用意をしておりましたのですが。「形のごとく」は、たいしたものでがありませんが、という謙遜(けんそん)の意。■いで、何ぞ-さあ、何だろう。■松茸-『今昔』は「松茸を裹集(つつみあつめ)タル如ニシテ、男ノ「魔羅」九ツ有リ」■一度にさつと失せぬ-「魔羅」が術によって一瞬のうちにそれぞれの持ち主の体に戻ったことを暗示する。■ありあり-あるある。後ろめたい行動によって失ったために、その事実と落胆の思いを表だって口外できずにいただけに、それが戻ってきたことを確認できた喜びは大きく、この歓喜の叫び声となった。
■金-道則の使命は陸奥産出の砂金や馬を陸奥の郡司から受け取り、都へ運搬する事であった。■金、馬、鷲の羽-いずれも陸奥の特産品。「鷲の羽」は矢羽の材料としての逸品。■よによに-「世に(非常に)」を重ねて強調した言い方。■かたはらいたき申し事なれども-気恥ずかしいような話ではありますが(話し相手の妻に手だししようとしてのしくじりであったという羞恥心があっての物言い)。■さりがたく-拒みにくく、断わり難く。■おほやけの御使いなり-朝廷の公務を帯びた使者である。■またわざと-その目的のためにまた改めて。
■さるべき物-相当の謝礼としての献上品。■そのままに清まはりて-その時からただちに精進潔斎をして。■えもいはず罪深き誓言-まことにたいへんに罰当たりな誓いの言葉。■いかにもいかにも-何としても何としても。必ず必ず。「抱け」にかかるきわめてしっこく強調された形容語。■鬼にてもあれ、何にてもあれ-鬼であろうが何であろうが。これも「抱け」にかかる。つまり、郡司は「ともかく抱いて受け止めよ」と重ねて指示した。
■一抱きばかりなる-ひとかかえもあるような巨大な。■金椀(かなまり)-金属製の椀。目玉が大きく不気味に恐ろしく輝いている様。■いかに取り給ひつや-どうでした、取り押えましたか。■この事-道則が一番習いたかった摩羅を奪い取る術を指す。■やをばかりなる-八尺ほどもある。「やを」は八尺の誤写か。とされる。■はらはらと砕けば-ばらばらに噛み砕くと。■毛をいらかして走りかかる-怒って、毛を逆立てながら突進して来る。■これをさへ-(最前、大蛇を抱き止めずに大事な術を習得しそこなったばかりなのに)この猪をさえ抱けなくては(何の術も習得できずに終わってしまうだろう。そうなっては、わざわざここへ来たことが無駄になってしまう)。■前の物-「摩羅」を指す。■はかなき物を物になす事は習ひぬめり-ちょっとした物を何かに変える術は、習得できるでしょう。
■大内-内裏、宮中。■あらがひをして-言い争いをした時には。■黒戸-黒戸の御所。清涼殿の北、滝口の陣の西にある細長い部屋。