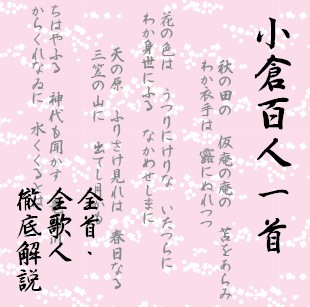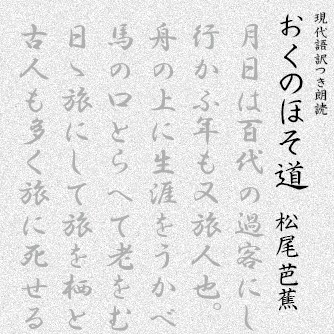宇治拾遺物語 10-6 吾妻人(あづまびと)、生贄(いけにへ)をとどむる事
今は昔、山陽道美作国(みまさかのくに)に中山(ちゅうさん)、高野(かうや)と申す神おはします。高野は蛇(くちなは)、中山は猿丸にてなんおはする。その神、年ごとの祭に必ず生贄(いけにへ)を奉る。人の女(むすめ)のかたちよく、髪長く、色白く、身なりをかしげに、姿らうたげたるをぞ求めて奉りける。昔より今にいたるまでその祭怠り侍らず。それにある人の女(むすめ)、生贄にさし当てられにけり。親ども泣き悲しむこと限りなし。人の親子となることは前(さき)の世の契(ちぎ)りなりければ、あやしきをだにもおろそかにやは思ふ。ましてやよろづにめでたければ、身にもまさりて おろかならず思へども、さりとて逃(のが)るべからねば、嘆(なげ)きながら月日を過(すぐ)す程に、やうやう命つづまるを、親子とあひ見ん事今いくばくならずと思ふにつけて、日を数へて明け暮れはただねをのみ泣く。
かかる程に、あづまの人の、狩といふ事をのみ役(やく)として、猪(ゐ)のししといふものの腹立ち叱りたるは、いと恐ろしきものなり、それをだに何(なに)とも思ひたらず、心に任せて殺し取り食ふ事を役とする者の、いみじう身の力強く、心猛(たけ)く、むくつけき荒武者の、おのづから出(い)で来(き)て、そのわたりに立ちめぐる程に、この女(むすめ)の父母のもとに来にけり。
物語するついでに、女の父のいふやう、「おのれ、女(むすめ)のただ一人(ひとり)侍るをなん、かうかうの生贄にさし当てられ侍れば、思ひ暮し、嘆き明かしてなん、月日を過し侍る。世にはかかる事も侍りけり。前(さき)の世にいかなる罪を作りてこの国に生れて、かかる日を見侍るらん。かの女子(をなご)も、『心にもあらず、あさましき死をし侍りなんずるかな』と申す。いとあはれに悲しう侍るなり。さるは、おのれが女(むすめ)とも申さじ、いみじう美しげに侍るなり」といへば、あづまの人、「さてその人は今は死に給ひなんずる人にこそおはすれ。人は命にまさる事なし。身のためにこそ神も恐ろしけれ。この度(たび)の生贄を出(いだ)さずして、その女君をみづからに預け給ふべし。死に給はんも同じ事にこそおはすれ。いかでかただ一人持ち奉り給へらん御女(むすめ)を、目の前に生きながら膾(なます)につくり、切り広げさせては見給はん。ゆゆしかるべき事なり。さる目見給はんも同じ事なり。ただその君を我に預け給へ」と、ねんごろにいひければ、「げに目(ま)の前にゆゆしきさまにて死なんを見んよりは」とて取らせつ。
かくてあづま人、この女のもとに行きて見れば、かたち姿をかしげなり。愛敬(あいきやう)めでたし。物思ひたる姿にて寄りふして手習(てならひ)をするに、涙の袖(そで)の上にかかりて濡(ぬ)れたり。かかる程に、人のけはひのすれば、髪を顔にふりかくるを見れば、髪も濡れ、顔も涙に洗はれて、思ひ入りたるさまなるに、人の来たれば、いとどつつましげに思ひたるけはひして、少しそば向きたる姿、まことにらうたげなり。およそ気高(けだか)くしなじなしう、をかしげなる事、田舎(ゐなか)人の子といふべからず。あづま人これを見るに、かなしき事いはん方(かた)なし。
されば、「いかにもいかにも我が身亡(な)くならばなれ、ただこれにかはりなん」と思ひて、この女の父母にいふやう、「思ひ構ふる事こそ侍れ。もしこの君の御事によりて滅びなどし給はば、苦しとや思(おぼ)さるべき」と問へば、「このために、みづからはいたづらにもならばなれ、さらに苦しからず。生きても何(なに)にかはし侍らんずる。ただ思(おぼ)されんままに、いかにもいかにもし給へ」といらふれば、「さらば、この御祭の御清めするなりとて、しめ引きめぐらして、いかにもいかにも人な寄せ給ひそ。またこれにみづから侍りと、な人にゆめゆめ知らせ給ひそ」といふ。さて日比籠(ひごろこも)りゐて、この女房と思ひ住む事いみじ。
かかる程に、年比(としごろ)山に使ひ習はしたる犬の、いみじき中(なか)にかしこきを二つ選(え)りて、それに生きたる猿丸を捕へて、明け暮れは、やくやくと食ひ殺させて習はす。さらぬだに猿丸と犬とは敵(かたき)なるに、いとかうのみ習はせば、猿を見ては躍(をど)りかかりて食ひ殺す事限りなし。さて明け暮れはいらなき太刀(たち)を磨(みが)き、刀を研(と)ぎ、剣(つるぎ)を設(まう)けつつ、ただこの女(め)の君と言草(ことぐさ)にするやう、「あはれ、前(さき)の世にいかなる契(ちぎ)りをして、御命にかはりていたづらになり侍りなんとすらん。されど御かはりと思へば、命はさらに惜(を)しからず。ただ別れ聞えなんずと思ひ給ふるが、いと心細くあはれなる」などいへば、女も、「まことに、いかなる人のかくおはして、思ひ物し給ふにか」と言ひ続けられて、悲しうあはれなる事いみじ。
さて過ぎゆく程に、その祭の日になりて、宮司(みやづかさ)より始め、万(よろづ)の人々こぞり集りて、迎へにののしり来て、新しき長櫃(ながびつ)をこの女のゐたる所にさし入れていふやう、「例のやうにこれに入れて、その生贄(いけにへ)出(いだ)されよ」といへば、このあづま人、「ただこの度(たび)の事は、みづからの申さんままにし給へ」とて、この櫃(ひつ)にみそかに入り伏して、左右の側(そば)にこの犬どもを取り入れて、いふやう、「おのれら、この日比(ひごろ)いたはり飼ひつるかひありて、この度(たび)の我が命にかはれ。おのれらよ」といひて、かきなづれば、うちうめきて脇(わき)にかい添ひてみな伏しぬ。また、日比(ひごろ)研ぎ磨きつる太刀(たち)、刀、みな取り入れつ。さて櫃(ひつ)の蓋(ふた)を掩(おほ)ひて布して結(ゆ)ひて封つけて、我が女(むすめ)を入れたるやうに思はせて、さし出(いだ)したれば、鉾(ほこ)、榊(さかき)、鈴、鏡を振り合せて、先追(さきおひ)ののしりて持(も)て参るさま、いといみじ。さて、女これを聞くに、「我にかはりて、この男のかくして往(い)ぬるこそいとあはれなれと思ふに、また無為(ぶゐ)に事出(い)で来(こ)ば、我が親たちいかにおはせん」と、かたがたに嘆(なげ)きゐたり。されども父母のいふやうは、「身のためにこそ神も仏も恐ろしけれ。死ぬる事なれば、今は恐ろしき事もなし。同じ事を、かくてをなくなりなん。今は滅びんも苦しからず」と言ひゐたり。かくて生贄(いけにへ)を御社(やしろ)に持(も)て参り、神主祝詞(かんぬしのと)いみじく申して、神の御前(おまへ)の戸をあけて、こおの長櫃(ながびつ)をさし入れて、戸をもとのやうにさして、それより外(と)の方(かた)に、宮司(みやつかさ)を始め、かく次第次第の司ども、次第にみな並びゐたり。
さる程に、この櫃(ひつ)を刀の先してみそかに穴をあけて、あづま人見ければ、まことにえもいはず大(おほ)きなる猿の、長(たけ)七八尺ばかりなる、顔と尻(しり)とは赤くして、むしり綿を着たるやうにいらなく白きが、毛は生(お)ひあがりたるさまにて横座によりゐたり。次々の猿ども、左右(さう)に二百ばかり並みゐて、さまざまに顔を赤くなし、眉(まゆ)をあげ、声々に啼(な)き叫びののしる。いと大きなるまな板に、長やかなる包丁刀(はうちやうがたな)を具(ぐ)して置きたり。めぐりには、酢(す)、酒、塩入りたる瓶(かめ)などもなめりと見ゆる、あまた置きたり。
さてしばしばかりある程に、この横座にゐたるをけ猿寄り来て、長櫃の結緒(ゆひを)を解きて蓋をあけんとすれば、次第次第の猿どもみな寄らんとする程に、この男、「犬ども食(くら)へ。おのれ」といへば、二つの犬躍(をど)り出でて、中に大きなる猿を食ひて、うち伏せてひき張りて、食ひ殺さんとする程に、この男髪を乱りて、櫃(ひつ)より躍り出でて、氷のやうなる刀を抜きて、その猿をまな板の上に引き伏せて、首に刀を当てていふやうは、「おのれが、人の命を絶ち、その肉(しし)むらを食ひなどするものは、かくぞある。おのれら。承れ。たしかにしや首斬(き)りて、犬に飼ひてん」といへば、顔を赤くなして、目をしばたたきて、歯を真白にくひ出して、目より血の涙を流して、まことにあさましき顔つきして、手を摺り悲しめども、さらに許さずして、「おのれが、そこばくの多くの年比(としごろ)、人の子どもを食ひ、人の種を絶つかはりに、しや頭斬(き)りて捨てん事、只今にこそあめれ。おのれ、かみならば我を殺せ。さらに苦しからず」といひながら、さすがに首をばとみに斬りやらず。さる程に、この二つの犬どもに追はれて、多くの猿どもみな木の上に逃げ登り、惑ひ騒ぎ、叫びののしるに、山も響きて、地も返りぬべし。
かかる程に、一人の神主(かんぬし)に神憑(つ)きていふやう、「今日(けふ)より後、さらにさらにこの生贄(いけにへ)をせじ。長くとどめてん。人を殺す事、懲(こ)りとも懲りぬ。命を絶つ事、今より長くし侍らじ。また我をかくしつとて、この男とかくし、また今日(けふ)の生贄に当りつる人のゆかりをれうじ煩(わずら)はすべからず。あやまりて、その人の子孫の末々にいたるまで、我、守りとならん。ただとくとく、この度の我が命を乞い受けよ。いとかなし。我を助けよ」とのたまへば、宮司(みやづかさ)、神主より始めて、多くの人ども驚きをなして、みな社(やしろ)の内に入り立ちて、騒ぎあわてて手を摺りて、「ことわりおのづからさぞ侍る。ただ御神に許し給へ。御神もよくぞ仰(おほ)せらるる」といへるも、このあづま人、「さな許されそ。人の命を絶ち殺すものなれば、きやつに物のわびしさ知らせんと思ふなり。我が身こそあなれ、ただ殺されん苦しからず」といひてさらに許さず。
かかる程に、この猿の首は斬(き)り放たれぬと見れば、宮司(みやづかさ)も手惑(てまど)ひして、まことにすべき方(かた)なければ、いみじき誓言(ちかごと)どもを立てて祈り申して、「今より後(のち)はかかる事さらにさらにすべからず」など神もいへば、「さらばよしよし。今より後はかかる事なせそ」と言ひ含めて許しつ。さてそれより後は、すべて人を生贄(いけにへ)にせずなりにけり。
さて、その男家に帰りて、いみじう男女あひ思ひて、年比(としごろ)の妻夫(めをと)になりて過(す)ごしけり。男はもとより故(ゆゑ)ありける人の末なりければ、口惜(くちを)しからぬさまにて侍りけり。その後は、その国に猪、鹿をなん生贄にし侍りけるとぞ。
現代語訳
今は昔、山陽道美作国に中山、高野という神が祭られていた。高野の祭神は蛇、中山は猿でいらっしゃる。それぞれの神には毎年祭りの時、生贄を捧げていた。娘の中から、器量が良く、髪が長い、色の白い、体つきが端正で、可愛らしい姿の者を選りすぐって奉っていた。昔から今に至るまでその祭が取りやめになったことはない。ところで、ある人の娘が生贄に指名されてしまった。親は限りなく泣き悲しんだ。人の親になったり子になったりすることは、この世に生まれてくる前の世からの宿縁であるので、たとえ醜くかったり、とりたてて美点のないような子さえもなおざりには思いはしないものである。ましてやこの娘はすべてにすぐれた子だったので、我が身にも勝っていとおしく思うが、だからといって逃れる事はできないので、嘆きながら月日を過ごしていたが、だんだん娘の命はちぢまってくる。親子として合い見る事ができるのがもうしばらくと思うにつけて、残りの日を数えては明けても暮れてもただ声をあげて泣く。
こうしている時に東国の人で、狩だけを仕事にしており、例えば、猪が腹を立てて怒り狂うのは実に恐ろしいものだが、それさえ何とも思わず、心のままに殺し取って食うのを生業とする男で、たいそう力が強く、気性の激しい、恐ろしい荒武者が、たまたまめぐり来て、その辺をめぐり歩いているうちに、この娘の父母のもとに立ち寄った。
話のついでに、娘の父親が言うには、「私は、ただ一人の娘を、これこれの生贄として指名されておりますので、思い悩み、嘆き明かして月日を過ごしております。世の中にはこんなこともあるのです。前世にどんな罪を犯してこの世に生れ、こんな目にあっているのでしょう。娘も『心にもなく情ない死に方をすることになりそうです』と言う。まことにかわいそうで悲しいのです。このように無念を申しあげるのは、自分の娘だからいう身びいきから申すわけではございません。たいへん美しい子なのです」と言うと、東国の人が、「では、その人はもはや死なれることになっているお方なのですね。人の命に勝る物はございません。我が身のためにこそ神を恐れるのです。今度の生贄としては出さずに、娘御を私に預けられるべきです。死んだものと思えば同じ事ではありませんか。どうしてたった一人お持ちの娘御を、目の前で膾に作り、切り刻ませるわけにはまいりますまい。忌まわしく無残な事です。そんな目にお遭いになるのも同じ事です。ただその娘御を私にお預けください」」と熱心に言ったので、「いかにも、目の前で無残に死ぬのを見るよりは」と言って、娘を男に託すことにした。
こうして、東国の男が、この娘の所へ行って見ると、顔かたちや姿も美しく、魅力があってすばらしい。それがもの思いに耽った様子で、寄りかかって手習いをしていたが、涙が袖の上に落ちて濡れている。そのうちに、人の気配がするので、 髪を顔にふりかけてうつむくのを見ると、髪も濡れ、顔も涙に洗われて沈み込んでいる様子であるが、人が来たので、いっそう気恥ずかしそうな気配で、少し横を向いた姿は、まことに可愛らしい。およそ気高く上品なその美しさは、田舎の娘とは言えず、男はこれを見るにつけ、いとしい事は言いようもない。
「このうえは、わが身などはもう死ぬなら死んでもかまわぬ。ただこの娘の身代わりになろう」と思い、この娘の父母に向って、「一つ計略があります。もし娘さんの事でこの家が滅びるようなことになったら、辛(つら)いと思われるでしょうか」と聞くと、「このために自分は役にも立たないで死ぬなら死んでもかまわない。いっこうにさしつかえない。どうせ生きていても何になりましょう。ただあなたのお考えになるとおりにどうなりともしてください」と答えるので、「それでは、この祭りのお清めをするのだと言って、注連縄を引き巡らせて、どんなことがあっても人を近寄らせないでください。またここに私がいることを人には絶対言わないでください」と言う。そこで、男は何日もそこに籠って、この女とたいそう仲睦まじく暮らしていた。
こうしているうちに、長年山で使い慣れている犬で、立派な働きをする犬の中から、さらにすぐれている賢い犬を二匹選び出し、それに生きた猿を捕まえて与え、仕事としてもっぱら食い殺す訓練をした。そうでなくても、昔から猿と犬とは不仲であるのに、ただもうこうしたことだけに慣れさせたから、猿を見ては躍りかかって容赦なく食い殺すのであった。一方、男は毎日鋭い太刀を磨き、刀を研ぎ、剣を準備しながら、ただこの女に向って口癖のように言う。「ああ、前世でどんな約束をしてあなたのお命に代わって死のうという事になったのでしょう。しかしあなたの身代わりと思えば、命は少しも惜しくはありません。ただお別れするのかと思いますと、それがとても心細くつらいのです」などと言うので、女も、「まこと、あなたをおいて誰がこうしておいでになって、私に思いをかけ、身代わりに立ってくださるでしょうか」と言い続け、たいへん悲しく哀れな様子なのである。
こうして時が経ち、その祭りの日になって、宮司を始めいろんな人が集まって、生贄の娘を迎えに来て騒ぐ。新しい長櫃を娘のいた場所に差し入れて、「いつものようにこれに入れて生贄をさしだされよ」と言う。この東国の男は、「ただ今度の事については、私の言うとおりにしてくだされ」と言うと、櫃の中に秘かに入り屈んで、左右にこの犬たちを抱き入れ、「おまえら。この私が長年大切に飼ってきたかいを見せて、このたびの私の命に代れ。おまえら」と言って、なでると、犬たちはうめいて脇に寄り添い、皆身を伏せた。また常日頃研ぎ磨いてきた太刀、刀、みな取り入れた。それから櫃の蓋を被せ、布を巻いて縛って封印をして、自分の娘を入れたように思わせて、さし出したので、鉾、榊、鈴、鏡を振り合わせて先払いをして大騒ぎで運んで行く様子は、まことに物々しい。さて女がこれを聞いて、「私に代わってこの男がこうして行くことは本当に気の毒だと思うのだが、また長年の土地の慣習を犯した結果として、さぞかしひどい断罪をこうむるのではあるまいか、そうなったら、自分の親たちはどうなさることか」と、あれこれと考えては嘆いていた。しかし、父母は、「我が身のためにこそ神も仏も恐ろしいものだ。どうせ死ぬのであればもう何も恐ろしい事はない。どうしたって同じ事なのだからこうしてあの東国の男のやり方にまかせて、死ぬなら死んでしまおう。今となっては滅びたとしても辛いとは思わない」と言って落ち着いていた。こうして生贄を御社に運び、神主が祝詞をたいそうに奏上し、神の御前の戸を開けて、この長櫃をさし入れて、もとのように戸を閉めて、そこから外の方に、宮司を始めとしてしかるべく次々と役人たちが、順番にみな並んでいった。
そうしているうちに、東国の男がこの櫃に刀の先を使って秘かに穴をあけて、外を見ると、まことに何とも言えないくらい大きな猿が、身の丈は七八尺ほどもあり、顔と尻は赤く、むしり綿を着たようにはなはだしくきわだって白いのが、毛は逆立って生えているようなのが上座に坐っている。次々の猿どもが、左右に二百匹ばかり並び、それぞれ顔を赤くして、眉を吊りあげ、声々にやかましく鳴き叫んでいる。たいそう大きなまな板の上に長々とした包丁を添えて置いてある。そのまわりには、酢、酒、塩の入った瓶かと見えるものがたくさん置いてある。
さて少し時間がたつと、横座に陣取っていた大猿が寄って来て、長櫃の結紐を解いて蓋を開けようとすると、次々と連座している猿どもがみな寄って来る。そこで、この男が、「犬ども食らえ、おまえら」と言うと、二匹の犬は長櫃から躍り出て、中でも大きな猿にかみついて、打倒して左右に引っ張り合って食い殺そうとする。その時、男は髪を振り乱して櫃から飛び出し、氷のように冷たく光る刀を抜いて、その猿をまな板の上に引き伏せ、その首に刀を当てて言う。「おまえが人の命を絶ち、その肉を食らいなどした報いはこれだ。おのれら、聞け。必ずそっ首斬り落して犬に食わせてやるぞ」と言うと、大猿は顔を真っ赤にして、目をしばたき、歯を真っ白に剥き出して、目からは血の涙を流し、まこと情ない顔つきをして、手を摺り合わせて悲しむが、男は許そうとはしない。「おのれが何年にもわたる長い間、人の子どもを食い、人の命を絶った代償に、今こそそのそっ首を切り捨てる時が来たようだ。おのれが神だというなら私を殺してみろ。殺されたってどうって事はないぞ」と言いながら、そうは言ってもやはり、大猿の首をすぐには斬り落さない。そうしているうちに、この二匹の犬に追われて、多くの猿どもはみな木の上に逃げ登り、あわて騒ぎ、叫びわめくので、山も響き、大地もひっくり返りそうである。
こうしていると、一人の神主に神が乗り移って言うには、「今日から後は、もう決してこの生贄は取るまい。人を殺す事は本当に懲り懲りした。命を絶つ事は、今からは永久にしないようにしよう。また自分をこうしたからといって、この男をとやかくし、また今日の生贄に割り当てられた人の親類の人を捕らえて悩まし報復したりなどは決してしない。今までの行為を改めて、その人の子々孫々に至るまで、自分が守り神となるであろう。ただ一刻も早く、この度のわしの命乞いを聞き届けてくれ。まことにせつない。わしを助けよ」とおっしゃるので、宮司、神主を始め多くの人たちを驚き、みな社の中に入って立ち、騒ぎあわてて手をこすって、「あなたの言われる道理は言うまでもなくその通りであります。ただ相手が神様であるという事に免じて許してください。神様もよく謝っておられます」と言うのだが、この東国の男は、「そう簡単に許すことはできん。人の命を絶ち殺したのであれば、あやつに殺される者の辛さ、悲痛な気持ちを教えてやろうと思う。我が身は今は無事であるけれどもわが身はどうなってもかまわない」といって決して許そうとしない。
こうしているうちに、猿の首が斬り落されそうに見えるので、宮司もあわてふためき、まったく手の出しようもないため、たいそうな誓いの言葉をあれこれと祈った。「今から後は、この様な事は決して決していたしません」などと神も言うので、「それならばよいよい。今から先はこんなことはするでないぞ」と言い含めて許してやった。さてそれから後は、まったく人を生贄にしないことになった。
それから、男は家に帰り、たいそう仲むつましく、長年夫婦となって過した。男は当然、由緒ある人の子孫であり、世間からおとしめられないような人物であった。その後、その国では猪や鹿といった動物を生贄にするようになったということだ。。
語句
■山陽道美作国-中国山脈の南側(瀬戸内海側)の国々。■中山-岡山県津山市一宮にある中山大明神。南宮(なんぐう)とも。天文二年(1533)の尼子氏の乱で社殿は焼亡。主祭神は鏡作命(かがみつくちのみこと)であるが、大己貴命(おおなむちのみこと)((大国主命(おおくにぬしのみこと))・瓊々杵命(ににぎのみこと)が合祀されている。■高野(かうや)-津山市二宮にある高野明神。■生贄(いけにへ)-生きたまま供え物として神に捧げる動物。ここは人身御供(ひとみごくう)。『今昔』巻二六-七話では、「国人の未婚の娘」の中から選ばれたとする。■かたちよく云々-以下、当時に於ける「美女」の要件が列挙される。「猿丸」は食欲をそそる対象として美女を指定していた事になる。なお、『今昔』には、さらに、「此ハ今年ノ祭ノ日被差(さされ)ヌレバ、其日ヨリ一年ノ間ニ養ヒ肥シテゾ、次ノ年ノ祭ニハ立ケリ」と、住人たちにはもう一つの義務が慣例になっていた事が見える。■をかしげに-きれいで。■らうたげなるを-かわいらしいのを。■前の世の契りなりければ-この世に生まれてくる前の世からの宿縁であるので。■あやしきをだにもおろそかにやは思ふ-たとい醜かったり、とりたてて美点がないような子でさえもなおざりには思いはしないものである。■身にもまさりて-自分の身命以上に。■やうやう命つづまるを-生贄にされる日が近づいて、だんだん娘の命が残り少なくなってきたために。■今いくばくならず-もはや幾日もない。■ねをのみ泣く-声をあげて泣いていた。「ね」は「哭」で、泣く声。
■あづま-「あづま」は東国、ここは陸奥を含まない、東海、東山両道の範囲をさす程度の使われ方か。■役として-仕事にして。生業にして。■腹立ち叱りたるは-腹を立てて怒っている状態は。凶暴になっている時は。■むくつけき-不気味で恐ろしげな。■おのづから出で来て-たまたまめぐり来て。
■前の世に-先にも「前の世の契りなりければ」と見え、この話には前世因果観が底流している。■あさましき死をし侍りなんずるかな-情ない死に方をいたすことになりそうなのです。悔しさを込めた物言い。■さるは-このように無念な思いを申し上げるのは。■おのれが女とも申さじ-自分の娘だとの身びいきで申すわけではありません。■今は死に給ひなんずる人にこそおはすれ-もはや死なれることになっているお方なのですね。死を免れ得ない立場の人間であるとの確認をとるための言葉。娘を亡き者と思って自分に預けよ、と言いだすための伏線。■命にまさる事なし-『今昔』では、この後に「亦、人ノ財ニ為物(するもの)子ニ贈ル物無」と、続く。■身のためにこそ神も恐ろしけれ-命を失いたくないからこそ神を恐れるのだ。『今昔』は仏神モ命ノ為ニコソ怖シケレ、子ノ為ニコソ身モ惜シケレ」とする。■膾(なます)-『和名抄』に「細切宍也」とあるように、魚・肉などを細く薄く切りきざんだもの。■ゆゆしかるべき事-忌まわしく無残なこと。
■思ひ入りたるさまなるに-もの思いに沈んでいるように見受けられたが。■人の来たれば-誰かがやって来たので。■いとどつつましげに思ひたるけはひして-自分の心中を察知されはしないかと、たいへん気恥ずかしそうにしている様子で。
■亡くならばなれ-死ぬのであれば死んでもかまわない。どうなってもいい。■これに代わりなん-娘の身代わりになろう。娘に代わって死のう。■滅びなどし給はば-あなたがたの御一家が滅びるようなことにおなりになれば。■いたづらににもならばなれ-役にも立たないで死ぬならばそれでもかまわない。■何にかはし侍らんずる-何になりましょうか。■思されんままに-お考えになるとおりに。■いかにもいかにもし給へ-どうなりともして下さい。■いらふれば-答えるので。■さらば-それでは。■引きめぐらして-引き回して。■いかにもいかにも-どんなことがあっても。■人な寄せ給ひそ-人を寄せないでください。■これにみづから侍ると-ここに私がおりますと。■な人にゆめゆめ知らせ給ひそ-けっして人にお知らせなさいますな。■さて-そこで。■日比-何日も。■思ひ住む-仲良く暮らす。
■いみじき中にかしこきを-立派な働きをする犬の中から、さらにすぐれている賢い犬を。■やくやくと-「役々と」で仕事として、もっぱらに、の意。■さらぬだに-そうでなくても。■猿丸と犬とは敵(かたき)なるに-昔から猿と犬とは不仲であるのに。■いらなき太刀-鋭い太刀。太刀は大ぶりの刀。「大刀和名太刀、小刀加太奈」(和名抄)。■剣(つるぎ)-両刃の刀をさす事が多い。■言草(ことぐさ)-決まって口にする話題。話の種。■前の世にいかなる契(ちぎ)りをして-前出のようにここでも前世の因縁が関心の種となっている。この世での意想外の出来事の展開に合理的な筋道を見つけたい思いの現れ。■別れ聞えなんずと思ひ給ふるが-あなたとお別れいたすことになろうと思いますことが。「給ふる」は謙譲の補助動詞。■いかなる人のかくおはして、思ひ物し給ふにか-あなたをおいて誰がこうしておいでになって、私に思いをかけ、身代りに立ってくださるでしょうか。
■宮司(みやづかさ)-神事を主催する神官。神官の長。■長櫃-縦長の櫃(ひつ)。■おのれら-おまえら。きさまたち。■おのれらよ-『今昔』のこの箇所には、男が犬に呼びかけ、言い聞かせる言葉は見えない。■かきなづれば-なでると。■布して結ひて封つけて-布を巻いて縛って封印をして。■鉾(ほこ)-長い木の柄の先に両刃の剣のついた鎗状の武器。ここでは、榊の枝葉、鈴、鏡とともに御輿の先に立って進む先駆けの者たちの持つ祭具の一つ。■無為(ぶゐ)に-(思いがけなく)たまたま。■我が親たちいかにおはせん-その不意の事態になったら、自分の親たちはどういうことにおなりになることだろうか。長年の土地の慣習を犯した結果としてひどい断罪をこうむることになるのではあるまいか。■かたがたに-あれこれとさまざまに。■死ぬる事なれば-書陵部本など「死ぬる君の事なれば」。■同じ事を-どうしたって同じ事なのだから。■かくてをなくなりなん-こうしてあの東国の男のやり方にまかせて、死ぬなら死んでしまおう。「を」は強意の助詞。■祝辞(のりと)-神に奏上する言葉。一般には神の徳をたたえ、誓願の主旨を述べ、恩恵を請うという内容のもの。■御前の戸-『今昔』は瑞籬(みづかき)の戸。■次第次第の-『書陵部本』など、「次々の司ども」。
■いらなく白きが-はなはだしくきわだって白いのが。■生ひあがりたるさまにて-逆立って。■横座-上座。頭目、首領などの座る席。■包丁刀-料理用の刀。長さ二十五センチほどで剣形の普通のものよりもずっと大ぶりのものであろう。■あまた置きたり-『今昔』には、この後に、「人ノ鹿ナドヲ下シテ食ンズル様也」とあって、この話の伝承者たちの間では、生贄の娘は薄切りにされて食われるものと想像していたらしいことがうかがえる。
■をけ猿-大猿。年功を経たボス猿。■次第次第の-書陵本など、「つぎつぎの」。■おのれ-①犬に向ってけしかけている語。さあ、おまえ。②猿どもに向って激して叫びかけている語。この野郎。①②の両義にとれるが、『今昔』では「男俄ニ出テ、犬ニ噉(くへ)ヲレ噉(くへ)ヲレト云ヘバ」とすることから、①に解しておく。■ひき張りて-二匹の犬がかみついて、左右に引っ張り合って。■肉(しし)むら-肉%E5%8F%A2(肉塊)。ここは肉そのものをいう。■しや-卑しめののしっていう気持を添える接頭語。■しや首-がん首。そっ首。■犬に飼ひてん-犬に食わせてしまうぞ。■顔を赤くなして-以下、赤い顔、白い歯、しばたたく目など、大猿の特徴点に焦点を合せながら、恐怖におののく顔面の懸命な様相が活写される。■そこばくの多くの年比-何年にもわたる長い間。■只今にこそあめれ-今その時が来たようだ。■おのれ、かみならば我を殺せ-お前が本当に神だというのであれば、俺を殺してみせろ。■さらに苦しからず-殺されたって、どうってことはないぞ。■さすがに-そうは言ってもやはり、大猿の首をすぐには斬り落さない。■地も返りぬべし-大地も反転しそうである。
■神憑きて-神画がとり憑いて。神が乗り移って。■長くとどめてん-末長く、将来に渡って停止したい。■懲りとも懲りん-本当に懲り懲りした。■れうじ煩わすべからず-「%E6%8E%95(れう)じ(捉えて)」、危害を加えるようなことはしない。■あやまりて-今までの行為を改めて、の意から、危害を加えるどころか、返って反対に、逆に。■ことわりおのづからさぞ侍る-あなたの言われる道理は言うまでもなくそのとうりであります。「おのづから」は、当然に、無論のこと、の意。■御神に-相手が神様であるということに免じて。■さな許されそ-そのように簡単に許してはならぬ。桃本、京本などは「さなすかされそ」。■物のわびしさ-殺される者のつらさ、悲痛な気持ち。■我が身こそあなれ-「あなれ」は「あるなれ」で、我が身は(今は)無事であるけれども。
■斬り放たれぬ-今にも斬り落されてしまいそうだ。■さらにすべからず-決して決していたしません。
■故ありける人の末なりければ-氏素性の豊かな人の末裔であったので。男は単なる粗野な風来坊ではなく、美女を妻にできる選ばれた者であったことを読者に納得させるための条件づけ。