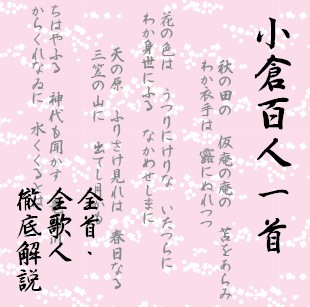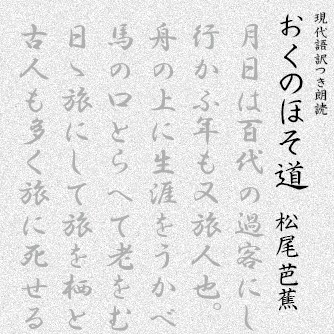宇治拾遺物語 11-4 河内守頼信(よりのぶ)、平忠恒(たひらのただつね)を攻むる事
昔、河内守頼信上野守(よりのぶかうづけのかみ)にてありし時、坂東(ばんどう)に平忠恒(たひらのただつね)といふ兵(つはもの)ありき。仰せらるる事なきがごとくにする、討たんとて、多くの軍(いくさ)起して、かれがすみかの方へ行き向かふに、岩海(いはうみ)の遥(はる)かにさし入りたる向ひに、家を造りてゐたり。この岩海をまはるものならば、七八日にてめぐるべし。すぐに渡らば、その日の中に攻めつべければ、忠恒、渡りの船どもをみな取り隠してけり。されば渡るべきやうもなし。
浜ばたにうち立ちて、この浜のままにめぐるべきにこそあれと、兵ども思ひたるに、上野守いふやう、「この海のままに廻りて寄せば、日比(ひごろへ)経なん。その間に逃げもし、また寄せられぬ構へもせられなん。今日(けほ)のうちに寄せて攻めんこそ、あのやつは存じの外(ほか)にして、あわて惑はんずれ。しかるに、舟どもはみな取り隠したる、いかがはすべき」と、軍どもに問はれけるに、軍ども、「さらに渡し給ふべきやうなし。まはりてこそ寄せさせ給ふべく候へ」と申しければ、この軍どもの中に、さりとも、この道知りたる者はあるらん。頼信は、坂東方はこの度こそ初めて見れ。されども我が家の伝えにて、聞き置きたる事あり。この海中には、堤のやうにて広さ一丈ばかりして、すぐに渡りたる道あるなり。深さは馬の大腹に立つと聞く。この程にこそその道は当たりたるらめ。さりとも、この多くの軍どもの中に知りたるもあるらん。さらば先に立ちて渡せ。頼信続きて渡さん」とて、馬をかき早めて寄りければ、知りたる者にやありけん、四五騎ばかり、馬を海にうちおろして、ただ渡りに渡りければ、それにつきて五六百騎ばかりの軍(いくさ)ども渡しけり。まことに馬の太腹に立ちて渡る。
多くの兵どもの中に、ただ三人ばかりぞこの道は知りたりける。残りは「露も知らざりけり。聞く事だにもなかりけり。しかるに、この守殿(かうどの)、この国をばこれこそ始めてにておはするに、我らはこれの重大の者どもにてあるに、聞きだにもせず、知らぬに、かく知り給へるは、げに人にすぐれたる兵(つはもの)の道かな」と皆ささやき、怖(お)ぢて、渡り行く程に、忠恒は、「海をまはりてぞ寄せ給はんずらん、舟はみな取り隠したれば、浅道をば我ばかりこそ知りたれ。すぐにはえ渡り給はじ。浜をまはり給はん間には、とかくもし、逃げもしてん。左右(さう)なくは、え攻め給はじ」と思ひて、心静かに軍揃へてゐたるに、家のめぐりなる郎等(らうどう)、あわて走り来て曰く、「上野殿(かうづけどの)は、この海の中に浅き道の候ひけるより多くの軍を引き具して、すでにここへ来給ひぬ。いかがせさせ給はん」とわななき声にて、あわてていひければ、忠恒、かねての支度(したく)に違(たが)ひて、「我すでに攻められなんず。かやうにしたて奉らん」といひて、たちまちに名簿(みやうぶ)を書きて文挟(ふみばさ)みにはさみてさしあげて、小舟に郎等一人乗せて持たせて、迎へて、参らせたりければ、守殿(かうどの)見て、かの名簿を受け取らせて曰く、「かやうに名簿に怠文(おこたりぶみ)を添へて出(いだ)す。すでに来たれるなり。さればあながちに攻(せ)むべきにあらず」とて、この文を取りて、馬を引き返しければ、軍どもみな帰りけり。その後(のち)より、いとど守殿をば、「殊にすぐれて、いみじき人におはします」と、いよいよいはれ給ひけり。
現代語訳
昔、河内守頼信が上野守だった時、関東に平忠恒という武士がいた。国司の命ぜられることをないがしろにして自分の好き勝手に振舞うので、これを討伐しようとして大軍を起し、彼の住処の方角へ向かったが、忠恒は内海のはるか向こうの入り江の対岸に家を造っていた。この内海をまわれば、七八日はかかるであろう。それで、まっすぐに渡れば、その日のうちに攻められるはずなので、忠恒は渡りの船などをみな取り隠してしまった。それで渡る術(すべ)もない。
この海辺に立って、この浜を回って行くべきだろうと兵たちは思った。しかし、上野守は、「この海を回って攻めるには日数がいる。その間に逃げたり、また、攻められないような構えも出来よう。今日のうちに攻め寄せれば、あやつは予想外にあわてふためくことだろう。しかし、舟どもはみな隠してしまった。どうすべきか」と兵たちに聞かれると、兵たちが、「とてもまっすぐに渡る方法はありません。ぐるっと迂回してお攻めになるべきです」と申し上げたので、「この兵たちの中に、そうはいっても特別な道を知っている者がいるであろう。頼信は、関東は初めて見るのだ。しかし、我が家での言い伝えで聞いている事がある。この海中には堤のよな広さ一丈ほどの、すぐに渡れる道があるという。深さは馬の太腹位に水がつく位だと聞いている。このあたりがきっとその道に当るであろう。それにしても、この大軍の中にはそれを知っている者もいるであろう。いたらその者が先に立って馬を渡せ。頼信はそれに続いて渡ろうぞ」と言って、馬をあおり、速歩になって水際に走り寄った。すると、道を知っている者であろうか、四五騎ほどが、馬を水に乗り入れ、どんどん渡って行ったので、その後について五六百騎ばかりの兵たちが騎馬を渡した。まこと、馬の太腹まで水につかりながら渡ったのだった。
多くの兵士たちの中で実は三人だけがこの道を知っていた。残りは、「まったく知らなかった。聞いたこともなかった。しかし、この上野守殿は、この国へはそれこそ始めて来られたが、我らはこの土地に何代も住み続けている人間であるのに、聞いたことさえなく、知らないのに、このようにご存知であるのは、実に優れた武将の器よ」と、皆はささやきながら、恐れいって渡って行った。忠恒は、「海を回って攻めて来られるだろう。舟はみな取り隠したことだし、浅瀬の道は自分だけが知っているのだ。まっすぐに渡って来られることはできまい。浜を回っておられる間に、あれこれ準備もし、逃げもしよう。たやすくはお攻めになれまい」と思ってのんびりと軍勢を揃えていた。そこへ家の周りにいた家来が、あわてて走って来て、「上野殿は、この海の中にありました浅瀬の道を通って大軍を引き連れて、すでにここに到着されました。どうなさいますか」と、震え声で、あわてて報告した。忠恒は、かねての作戦計画とは違って「わしはもう攻め落とされそうだ。こうしてさしあげよう」と言って、すぐに名簿を書いて、文挟みに挟み、さしあげて、小舟に配下の兵一人を乗せて持たせて、先方からの使いを出迎えてお渡しした。それを上野守は見て、この名札を受け取らせ、「このように名簿とともに降伏状を添えて出している。すでにこうして降参してきているのだ。無理やり攻める必要もなかろう」と、この文を受け取って、騎馬を引き返したので、兵隊たちもみな帰って行った。そのことがあってから、上野守殿は、「たいそう優れて、立派な方でおいでになる」とますます高く評判されるようになった。
語句
■頼信-源頼信(968~1048)。一説には康平三年(1060)没。多田満仲の子、頼光、頼親の弟。藤原道長に仕え、伊勢(三重県)・相模(神奈川県)・美濃(岐阜県南部)など数々の諸国の守を歴任、鎮守府将軍。長元三年~四年(1030~31)、忠恒の乱を鎮定。■坂東-関東地方。東国。■平忠恒-一般には忠常(?~1031)武蔵押領使。長元年六月、前上野介平忠常は、上総国府を占拠、さらに安房(千葉県南部)の国守を殺害して反乱、検非違使平直方、中原成通らの追討軍には抵抗したが、同四年四月、頼通には戦わずして投降、上洛の途上、美濃で病死した。■仰せらるること-上司の命ぜられることを。■なきがごとくにする-ないがしろにする。■仰せらるる事なきがごとくにする-『今昔』巻二五-九話には「上総下総ヲ皆我ママニ進退シテ、公事(クジ)ニモ不為(せざ)リケリ。亦、常陸守ノ仰ヌル事ヲモ、事ニ触レテ忽緒(いるかせ)ニシケリ」と具体的に見える。■討たんとて-長元三年九月二日、六月から追討に随っていた平直方らに代って、頼信は坂東の諸国司とともに忠恒討伐の命を受ける。■かれがすみか-忠恒の私宅は、海岸ではなく、実際には下総国(千葉県)香取郡の椿湖(周囲約40キロメートル、現在は湖跡のみ)湖畔にあった。■すぐに渡らば-一直線に渡るならば。■攻めつべければ-攻めたとすれば。「べけれ」は推量の助動詞「べし」の已然形。■岩海(がんかい)-大きな角ばった巨礫で覆われた地域で,巨礫は高地の平坦な地域で激しい霜の作用で形成されたもの。しかし、この岩海の解釈をそのまま適用すると、不自然な文脈となるので、ここは小学館の訳に合わせて「内海」とした。
■存じの外-思いがけず。案外。予想外。■軍どもに-配下の兵士たちに。■さらに渡し給ふべきやうなし-騎馬で海をお渡りになる方法はまったくありません。■この道-以下に頼通が語ってみせる幅一丈(約3メ-トル)ほどの堤上の浅瀬。■あるなり-あるということである。■深さは馬の太腹に立つ-馬の前足の付け根(肩)までの高さが五尺(約150センチ)であることから計算すれば、太腹が水にもぐらない深さは三尺未満(約80~90センチ程度)ということになろう。■この程にこそ-このあたりにこそきっと。■さりとも-そうであったとしても。この海の中を馬で渡るのは容易ではないとはいうものの。■馬をかき早めて寄りければ-馬をあおり、速歩になって水際に近づくと。
■露も知らざりけり-ここから軍兵たちのささやきの言葉ととることにする。■この守殿-「この上野守殿」の略。■これの重代の者どもにてあるに-この土地に何代も住み続けている人間であるのに。■怖じて-頼信が、他国の地勢についての家伝の情報を持ち、それを大胆にも果敢に生かしてしまう神技の武将である事に、畏怖を覚えて。■海をまはりてぞ云々-以下、忠恒の頼信軍の進撃についての予測と対応の目算。■すぐにはえ渡り給はじ-まっすぐに渡海してくることはできまい。■とかくもし、逃げもしてん-十分な時間があるはずだから、あれこれ用意もし、逃げ出す事もできよう。■左右なくは-容易には。たやすくは。■仕度(したく)-心用意。または作戦計画。■かやうにしたて奉らん-こうして(名札を書いて)さしあげよう。■名簿(みやうぶ)-家来として服従することを誓う証拠を示す名札。■文挟み-目上の人に書状を奉る場合の用具。長さ1.5メートルほどの白木の棒の先端に鳥口(とりぐち)という金具のついたもの。その嘴(くちばし)状の部分に書状を挟む。細竹の先に割れ目を入れて代用する場合もある。■怠文(おこたりぶみ)-謝罪状。ここは降伏状。■すでに来たれるなり-すでにこうして降参してきているのだ。