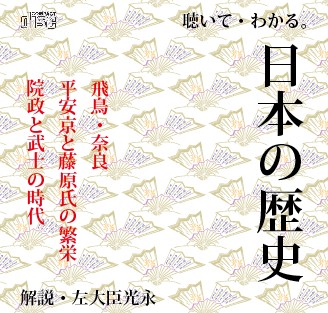花伝第六 花修
原文
花伝第六 花修(くわしゆ)に云はく
一、能の本を書く事、この道の命なり。極めたる才学の力なけれども、ただ、工(たく)みによりて、よき能にはなるものなり。
大かたの風体、序破急の段に見えたり。ことさら、脇の申楽(さるがく)、本説(ほんぜつ)正しくて、開口(かいこ)より、その謂(いは)れと、やがて人の知るごとくならんずる来歴を書くべし。さのみに細かなる風体を尽くさずとも、大かたのかかり直(すぐ)に下(くだ)りたらんが、指寄(さしよ)り花ばなとあるやうに、脇の申楽をば書くべし。
また、番数(ばんかず)に至りぬれば、いかにもいかにも、言葉・風体を尽くして、細かに書くべし。
仮令(けりやう)、名所・旧跡の題目ならば、その所によりたらんずる詩歌の、言葉の耳近からんを、能の詰め所に寄すべし。
為手(して)の言葉にも風情にもかからざらん所には、肝要の言葉をば載すべからず。なにとしても、見物衆(けんぶつしゆ)は、見る所も聞く所も、上手をならでは心にかけず。さるほどに、棟梁(とうりやう)の面白き言葉・振り、目にさえぎり、心に浮かめば、見聞く人、すなはち感を催すなり。これ、第一、能を作る手立てなり。
ただ、優しくて、理(ことわり)のすなはちに聞こゆるやうならんずる、詩歌の言葉を取るべし。優しき言葉を振りに合はすれば、ふしぎに、おのづから、人体も幽玄の風情になるものなり。硬(こは)りたる言葉は、振りに応ぜず。しかあれども、硬き言葉の耳遠きが、またよき所あるべし。それは、本木(もとぎ)の人体によりて似合ふべし。漢家・本朝の来歴に従って心得分くべし。ただ、卑しく俗なる言葉、風体悪き能になるものなり。
しかれば、よき能と申すは、本説正しく、めづらしき風体にて、詰め所(どころ)ありて、かかり幽玄ならんを、第一とすべし。風体はめづらしからねども、わづらはしくもなく、直に下(くだ)りたるが、面白き所あらんを、第二とすべし。これは大よその定めなり。ただ、能はひと風情、上手の手にかかり、便りだにあらば、面白かるべし。番数を尽くし、日を重ぬれば、たとひ悪き能も、めづらしくし替えし替え色取れば、面白く見ゆべし。されば、能は、ただ、時分・入れ場なり。悪き能とて捨つべからず。為手の心づかひなるべし。
ただし、ここに様(やう)あり。善悪(ぜんなく)にすまじき能あるべし。
いかなる物まねなればとて、仮令、老尼・姥(うば)・老僧(ろうそう)などの形にて、さのみは狂ひ怒る事あるべからず。又、怒れる人体にて、幽玄の物まね、これ同じ。これを、まことのえせ能、きやうさうとは申すべし。この心、二の巻の物狂(ものぐるひ)の段に申したり。
また、一さいの事(じ)に、相応なくば成就あるべからず。
よき本木の能を、上手のしたらんが、しかも出(い)で来(き)たらんを、相応とは申すべし。されば、よき能を上手のせん事、などか出(い)で来(き)ざらんと、、皆人思ひ慣れたれども、不思議に、出で来(こ)ぬ事あるものなり。これを目利きは見分けて、為手の咎(とが)のなき事を知れども、ただ大かたの人は、能も悪く、為手もそれほどにはなしと見るなり。そもそも、よき能を上手のせん事、なにとて出で来ぬやらんと工夫するに、もし、時分の陰陽の和(くわ)せぬ所か。または花の公案なきゆゑか。不審はなほ残れり。
現代語訳
第六 花修に言う
一、能の脚本を書く事が、この道にとって何よりも大切な生命ともいえるものだ。能の脚本を書くには、たとえ、優れた学識の力が無くても、ただひたすら原作の欠点を直していい作品に直していく工夫を重ねることによっていい作品が生まれることになる。
およその申楽の芸風は、『花伝』問答条々の「序破急」の段に述べている。特に、最初の脇能(わきのう)は、典拠が正しく、曲の最初の部分から、あぁ、あの話かとすぐに見物人にわかるような筋の話を書くべきだ。あまり手の込んだ演技の工夫を色々やらずに、作品全体の流れがまっすぐでわかりやすく、最初の部分から華やかであるように、第一番目用の能を書くのが良い。また、番組が進んでその日の山場になるときの出し物としては、出来るかぎり詞章や演技に工夫を尽くし、細部まで念入りに書かなければならない。
例えば、名所・旧跡にちなみの題目ならば、その場所に縁のあるような詩歌で、耳慣れた文句のものを、作品の急所に集めるがよい。為手のせりふにも所作にも関係ないようなところには、大事な言葉を配してはならない。どうあっても、見物している人たちは、見るのも聞くのも上手な花形役者以外には目もくれないものだ。だから、主役の面白いせりふや所作が視野に入り、心に響けば、それを見聞した人は、すぐに感動するのだ。このように為手の演技に名文句を集中させることが、能を作るための、最も大切な方法である。
要するに優しくて、意味がすぐにわかるような詩歌の文句を引用せよ。優しい言葉を所作に合わせれば、不思議と、自然と主人公の演技も優美なものになるのである。とはいうものの、堅い言葉では動作を合わせられないが、聞きなれていない硬い言葉が良い場合もある。それは、典拠となった作品の主人公の性格や特質によるのであろう。中国風か和風かによっても使い分ける必要があろう。ただ、卑しく俗っぽい台詞を用いると、演技までもが下品な能になってしまうから使ってはいけない。
こういうわけで、良い能というのは典拠が正しく、山場があり、能の作品性において、優美なことを第一とすべきだ。作品の趣は平凡だが、作為が過ぎてごたごたした印象になる事なく、直線的にすらすらと進行するわかりやすい筋書になっていることをその次とすべきだ。これは、だいたいの目安だ。
要するに、能というものは、演技一つでも、上手な為手の手で演出替えができるような手がかりのある脚本であれば面白いものになるであろう。上演演目が多くなったり、興業日数が続く場合には、たとえ面白くない能と言えども目新しく演出を替えていけば、面白く見えてくるものだ。要するに能というものは、ただ、それを演じるにふさわしい時と演じる曲の組み合わせ次第なのだ。悪い能だからといって、捨てたものではない。能を生かすも殺すも、為手の工夫一つだ。
ただし、ここに問題がある。どうなことがあっても決して演じてはならない能というのもある。どんなに写実的に演じるからといって、例えば、老尼・姥・老僧などの姿で、むやみに荒々しく狂乱することがあってはならない。また、鬼人のような荒々しい役柄で、優美な演技というのもこれまた良くない。これを正真正銘の贋物能(にせもののう)、訳のわからぬ駄作というべきであろう。このことは、第二巻「物学条々」の「物狂」の段で説明したところだ。
また、すべての事に釣り合いということが無ければ成功はおぼつかないであろう。出所正しい作品の能を、上手な役者が演じ、しかも成功すれば、相応というものだ。では、良い能を上手が演じたのに成功しないことがあろうかと、人は皆、思い込んでいるけれども、不思議なことに、うまくいかないということがあるものだ。
そのことを鑑識眼のある観客は見抜いて、必ずしも役者に問題があったのではないことはわかっているのだけれど、一方ほとんどの人は、作品も駄作で、役者も大したことはないと見るのである。そもそも、良い能を上手な役者が演じて、どうしてうまくいかないのかと考えるに、あるいはその時の陰陽の和合が不調であったのか、または、役者の側に花を咲かせる工夫がなかったのか、なお疑問が残るのだ。
語句
■能の本-能の台本。■才学-学識・学問の実力。■大かたの風体-能の作風の目安。■序破急-「問答条々」第二問答を指す。■本説正しくて-典拠(話・小説・論文などのよりどころとなる確かな文献。出典。)が正統的な文学作品であること。■開古(かいこ)-曲の始まりの部分。■その謂れ-能の典拠となる説話・物語。■細かなる風体-具体的な演技上の工夫。精細な物まねわざ。■大かたのかかり直(すぐ)に下りたらん-作品全体の流れが素直でわかりやすい事をいう。必ずしも祝言能であることを意味しない。■指寄り-ここは一曲の始まりの事。■番数に至りぬれば-演目の数が重なってその日の興業の山場になる事。■言葉・風体を尽くして-名句を散りばめるなど表現を工夫し、技どころも盛り込むこと。■仮令-もし…だとしても。仮に。よしんば。たとえ。■名所・旧跡の題目-歌枕などの由緒ある土地にちなみの曲趣。■耳近からん-よく知られた作品。■詰め所に寄す-山場に集めること。■風情-型どころで見せる所作。■肝要の言葉-作品の主題と関わる大事な文句。名文句。■上手-棟梁の為手の事。■棟梁-一座の指導者で、常に能の為手を勤める花形役者。■振り-動作。■理-詩章のこと。■幽玄の風情-優美な動作。具体的には歌舞の演技をいうのであろう。■硬(こは)りたる言葉-固い、こわばった言葉。漢語などの類を指すか。■耳遠き-聞き慣れないこと。■本木-典拠となった作品の主人公の性格や特質。■漢家・本朝-典拠が中国の物語りか、日本の物語かということ。■しかれば-語調を転じる接続詞。さて。ところで。■めづらしき風体-新鮮味のある能柄・作品性。■かかり-ここは「能のかかり」のことで、能の姿、作品性をいう。■わづらわしくもなく-作為が過ぎてごたごたした印象になることなく。■直に下りたる-直線的にすらすら進行するわかりやすい筋書きをいう。■上手の手にかかり、便りだに-「上手の手にかかる便り」の誤記であろう。作柄ではなく演出の工夫をいう。■めづらしくし替へし替へし-目新しく演出を替えていくこと。■善悪にすまじき-どうあろうとも。■いかなる・・・あるべからず-結びが「あるべきか」となるところを「あるべからず」と語調を強めた文章。■狂ひ怒る-荒々しく狂乱の演技をすること。■えせ能-贋物の能。能とは名ばかりの駄作。■きゃうさう-狂草。独善的で訳のわからない能をののしる言葉か。「狂草」。■物狂の段-『風姿花伝』第二物学条々の物狂のこと。■相応なくば-諸条件がすべて揃うこと。■成就-成功。■為手の咎も云々-作者ではなく役者に注目したいいかた。■時分の陰陽-「問答条々」第一問答に詳説。■花の公案-「問答条々」第九問答に詳説。なお、「別紙口伝」第七条・第八条でこの問題に結論が示される。
原文
花伝第六 花修(くわしゆ)に云はく
一、作者の思ひ分くべき事あり。ひたすら静かなる本木の音曲(おんぎよく)ばかりなると、また、舞・はたらきのみなるとは、ひと向きなれば、書きよきものなり。音曲にてはたらく能あるべし。これ一大事なり。真実面白しと感をなすは、これなり。聞く所は耳近(みみちか)に、面白き言葉にて、節(ふし)のかかりよくて、文字移りの美しく続きたらんが、ことさら、風情(ふぜい)を持ちたる詰めをたしなみて書くべし。この数々相応する所にて、諸人一同に感をなすなり。
さるほどに、細かに知るべき事あり。風情を博士(はかせ)にて音曲をする為手は、初心の所なり。音曲よりはたらきの生ずるは、功入りたるゆゑなり。音曲は聞く所、風体は見る所なり。一さいの事(じ)は、いはれを道にしてこそ、よろづの風情(ふぜい)にはなるべき理(ことわり)なれ。いはれをあらはすは言葉なり。さるほどに、音曲は体なり。風情は用(ゆう)なり。しかれば、音曲よりはたらきの生ずるは、順なり。はたらきにて音曲をするは、逆なり。諸道・諸事において、順・逆とこそ下(くだ)るべけれ。逆・順とはあるべからず。かへすがへす、音曲の言葉の便りをもて、風体を色取り給ふべきなり。これ、音曲・はたらき一心になる稽古なり。
さるほどに、能を書く所にまた工夫あり。音曲よりはたらきを生じさせんがため、書く所をば、風情を本(ほん)に書くべし。風情を本に書きて、さてその言葉を謡(うた)ふ時には、風情おのずから生ずべし。しかれば、書く所をば、風情を先立てて、しかも謡(うたひ)の節・かかりよきやうにたしなむべし。さて、当座の芸能に至る時は、また、音曲を先とすべし。かやうにたしなみて、功入りぬれば、謡ふも風情、舞ふも音曲になりて、万曲一心たる達者となるべし。これまた、作者の高名なり。
現代語訳
一、作者として認識しておくことがある。まったく動きの少ない題材で、謡を聞かせるばかりの曲や、反対に舞やはたらきからのみなっている曲は、趣向が一面的なので書きやすい。これに反して、謡に合わせて所作を演じる能というのがあろう。これが書くのも大変に難しいのだ。事実、面白いと観客に感動を与えるのは、このような作品だ。耳慣れた面白い言葉に、旋律が心地よく、しかも美しく構成されているような文句で、特に、見せ場となる演技を内包するような山場を考慮して書くべきであろう。こういう、すべての諸条件が揃ったところで、全観客が等しく感動するのだ。
そこで、なお具体的に心得ておかねばならぬ事がある。所作を基準にして謡をする役者は、未熟者である。謡から所作が生まれ出るというのは、年功を重ねて初めてできるのだ。謡は耳から入る情報、所作は目から入る情報である。さて、全ての事は、意味に導かれてこそ、あらゆる所作が生まれでてくるのである。意味を表すのは言葉である。であるから、謡は主であり、所作は従である。それで、謡から所作が生まれるのは順である。これとは逆に所作を見て、謡を起こすのは逆である。あらゆる方面、あらゆる事柄において、順から逆へという言い方で秩序立てるはずであろう。逆・順とは言わないであろう。必ずや謡の文句をよりどころとして、所作を作られるがよい。これこそが、謡と所作とが一体となるための稽古である。
そこで、能を書く際にまた工夫が必要となる。謡より演技を生まれされるために、執筆に際しては、演技を基本にして書かなければならない。演技を基本にして作品を書けば、その詞章を謡うときには、演技が自然と生まれ出てこよう。以上のごとく、書くときに、まづ演技を先に立てて、しかも、謡の節まわしや曲趣が面白いように工夫せねばならない。そうして実際の舞台で能を演じるときは、また、謡を先に考えるがよい。このように勤めて、年功を重ねれば、謡から美しい所作が生まれ、舞はまた謡と一体化することによって、あらゆる面白さを一つに融合した上手になろう。こうした舞台が実現するのも、作者の名誉なのである。
語句
■静かなる本木-動きの少ない題材で、謡の聞かせどころがあるばかりの能。■舞・はたらき-舞踊的所作と物まね的な所作。■ひと向き-聴覚的趣向か視覚的趣向か、どちらか一方のみであること。■音曲にてはたらく能-謡に基づいて演技する能。■節-旋律。■文字移り-詞章の韻律。言葉の連なり具合。■風情を持ちたる詰め-見せ所となる演技を内包するような山場。「風情」は所作の意。■博士-基準。■初心の所-初心の境地。未熟な段階。■風体-能の姿の意で用いるか。「風情」の誤記の可能性もある。■いはれを道にして-言葉の意味に導かれて、あらゆる演技が生じる、の意。■・・・は体なり、・・・は用なり-「体・用」は事物の本体と作用、原理と作用を意味する漢語。ここは主従の意味に採用する。『至花道』の体用説が本来の用法に近い。■順・逆-正統的なものと応用的なもの。「順・逆」という言い方で物事の正しい秩序を表すという意味であろう。■色取り給ふ-近親者に対する親しみを表す言い回しで、本篇の他の部分にも見られる。弟四郎に宛てた秘伝であることを意識したためであろう。■音曲・はたらき一心になる-謡と所作とが一体となること。■風情を本に書くべし-所作を念頭において作詞すること。■おのづから生ずべし-謡の文句により動作が説明されるので、わかりやすい演技になること。■よきやうにたしなむべし-たんに作曲・旋律が美しいことをいうのではなく、所作と相応させるように作曲せよというのであろう。■当座の芸能に至る時は-実際の上演に際しては。■万曲一心-あらゆる能の面白さが一つになることで、具体的には「音曲・はたらき一心」と同意。
原文
花伝第六 花修(くわしゆ)に云はく
一、能に、強き・幽玄、弱き・荒きを知る事。大かたは見えたる事なれば、たやすきやうなれども、真実これを知らぬによりて、弱く、荒き為手多し。
まづ、一さいの物まねに、偽る所にて、荒くも弱くもなると知るべし。この境、よきほどの工夫にては紛るべし。よくよく、心底を分けて案じ納むべき事なり。
まづ、弱かるべき事を強くするには、偽りなれば、これ荒きなり。強かるべき事に強きは、これ強きなり。荒きにはあらず。もし、強かるべき事を幽玄にせんとて、物まねに足らずば、幽玄にはなくて、これ弱きなり。さるほどに、ただ物まねにまかせて、その物になり入りて、偽りなくば、荒くも弱くもあるまじきなり。
また、強かるべき理(ことわり)過ぎて強きは、ことさら荒きなり。幽玄の風体よりなほ優しくせんとせば、これ、ことさら弱きなり。
この分け目をよくよく見るに、幽玄と強きとは、別にあるものと心得るゆゑに、迷ふなり。この二つは、そのものの体にあり。たとへば、人においては、女御(にようご)・更衣(かうい)、または遊女(いうじよ)・好色(かうしよく)・美男(びなん)、草木には花の類(たぐひ)、かやうの数々は、その形幽玄のものなり。また、あるいは、武士(もののふ)・荒夷(あらえびす)、あるいは鬼・神、草木にも松・杉、かやうの数々の類は、強きものと申すべきか。かやうの万物の品々を、よくし似せたらんは、幽玄の物まねは幽玄になり、強きはおのづから強かるべし。この分け目をば宛てがはずして、ただ幽玄にせんとばかり心得て、物まねおろそかなれば、それに似ず。似ぬをば知らで、幽玄にするぞと思ふ心、これ弱きなり。
されば、遊女・美男などの物まねをよく似せたならば、おのづから幽玄なるべし。ただ、似せんとばかり思ふべし。また、強き事をも、よく似せたらんは、おのづから強かるべし。
ただし、心得べき事あり。力なく、この道は見所(けんじよ)を本にするわざなれば、その当世当世の風儀にて、幽玄をもてあそぶ見物衆(けんぶつしゆ)の前にては、強き方をば、少し物まねにはづるるとも、幽玄の方へは遣(や)らせ給ふべし。
この工夫をもて、作者また心得べき事あり。いかにも、申楽の本木には、幽玄ならん人体、まして心・言葉をも優しからんを、たしなみて書くべし。それに偽りなくば、おのづから幽玄の為手と見ゆべし。幽玄の理を知り極めぬれば、おのれと強き所をも知るべし。されば、一さいの似せ事(ごと)をよく似すれば、よそ目に危(あやう)き所なし。危からぬは強きなり。
しかれば、ちちとある言葉の響きにも、「靡(なび)き」「臥(ふ)す」「帰る」「寄る」などいふ言葉は、やはらかなれば、おのづから余情(よせい)になるやうなり。「落つる」「崩(くづ)るる」「破るる」「転(まる)ぶ」など申すは、強き響きなれば、振りも強かるべし。
さるほどに、強き・幽玄と申すは、別にあるものにあらず、ただ物まねの直(すぐ)なる所、弱き・荒きは、物まねにはづるる所と知るべし。
この宛てがひをもて、作者も、発端(ほつたん)の句、一声(いつせい)・和歌などに、人体の物まねによりて、いかにも幽玄なる余情・便りを求むる所に、荒き言葉を書き入れ、思ひの外(ほか)にいりほがなる梵語(ぼんご)・漢音(かんおん)などを載(の)せたらんは、作者のひが事なり。さだめて、言葉のままに風情をせば、人体に似合はぬ所あるべし。ただし、堪能(かんのう)の人は、この違ひ目を心得て、興(けう)がる故実(こしつ)にて、なだらかなるやうにしなすべし。それは為手の高名なり。作者のひが事は逃(のが)るべからず。また、作者は心得て書けども、もし為手の心なからんに至りては、沙汰(さた)の外なるべし。これはかくのごとし。
また能によりて、さして細かに言葉・義理にかからで、大やうにすべき能あるべし。さやうの能をば、直(すぐ)に舞ひ謡(うた)ひ、振りをもするするとなだらかにすべし。かやうなる能をまた細かにするは、下手のわざなり。これまた能の下(さが)る所と知るべし。しかれば、よき言葉・余情を求むるも、義理・詰め所のなくてはかなはぬ能に至りての事なり。直なる能には、たとひ幽玄の人体にて硬(こは)き言葉を謡ふとも、音曲のかかりだに確(たし)やかならば、これ、よかるべし。これ、すなはち、能の本様(ほんやう)と心得べき事なり。ただ、かへすがへす、かやうの条々を極め尽して、さて大やうにするならでは、能の庭訓(ていきん)あるべからず。
現代語訳
一、能においては、強い能、幽玄な能、弱い能、荒々しい能の区別を認識すべきことについて。たいていは舞台で見えている事なので、簡単に区別できるように思えるが、実際にはその区分がわからず、弱く、荒々しい能を演じる役者が多い。
まず、どうして弱く、荒いのかというと、すべての物まねを本当に似せていないから、荒くなったり弱くなったりするのだと知れ。強く幽玄な能を演じるコツを飲み込むにはいいかげんな工夫ではダメである。よくよく心底から考察し、納得すべきことである。
まず、弱々しく演じるべきところを、強く演じるのは、正確に似せていないからで、これは強いのではなく荒いのである。強く演じるべきところを強く演じるのは、これこそ、強い演技というものである。それは荒いのではない。もし、強く演じなければならないところを優しく美しくしようとして、あまり似ていなければ、幽玄ではなく弱いということになる。したがって、ただ、役柄の本質どおりに、その役になりきって演じ、よく似ていれば、荒くもなく弱くもない芸ということになる。
また、強く演じるべき役において、度を過ぎて強く演じるのは、特別荒い芸になる。幽玄な所作に比べて、もっと優しく見せようとすると、これも、特に弱い芸になるのだ。
この違いをよく見比べると、幽玄とか強いとかいうものが、その物から離れて別の物であると思うから迷うのだ。この二つは、もともと、物まねの対象に備わっているものだ。例えば、人においては、貴女・更衣のような最高貴族の女性、または遊女・好色・美男であり、草木においては花の類の事である。このような種々の物は、その姿は優雅で美しいものである。また、武士や荒夷あるいは鬼・神など、そのほか草木にも松や杉といったような種類の類は強いものと言うべきであろうか。このような種々の品々を、よく知り、よく似せて演技すれば、幽玄な物まねは幽玄になり、強い物まねはおのずと強い演技になるであろう。この違いを理解せず、ただ何でも幽玄に美しく演じようとばかり考えて、肝心の物まねがいい加減になると、似ても似つかぬものになる。似てもいないのにそれがわからず、幽玄に美しく演じようとする能が、「弱い能」なのだ。
遊女や美男などの物まねを上手に似せて演じれば、自然と幽玄で美しい能となるであろう。ひたすら「似せよう」とのみ考えるべきである。また、「強き」演技についても忠実に似せたならば、自然と強い演技になるであろう。
但し、心得ておくべきことがある。致し方ない事だが、この申楽という分野は観客本意の仕事であるから、その時代時代のはやりにより、幽玄な芸を愛好する観客たちの前では強い演技の場合、少しばかり物まねの趣旨に外れたとしても、演技を優美で美しく見せる傾向を強めた方がいいであろう。
こうした工夫をふまえて、作者としても認識しておくべきことがある。それは幽玄を好む観客の為には、なるべく、申楽の題材に、幽玄な性格の主人公を見つけ、とりわけ心情も文句も優しいようなものを書くべきである。それを忠実に似せて演じることができれば、おのずと幽玄な役者に見えるものだ。幽玄に見せる演技の道理を理解し極めれば、おのずから、強い演技の境地をも知ることができよう。それゆえ、すべての物まねを忠実に似せることができれば、客観的に見て安定感があって危なっかしところはなくなるであろう。安定して見ていられる芸は強いというものだ。
そこで、ちょっとした言葉の響きにも、「靡き」「臥す」「帰る」「寄る」などという言葉は、ものやわらかな印象なので、おのずとそれに伴う所作も優雅で幽玄になるように思われる。「落ちる」「崩れる」「破れる」「転ぶ」などという言葉は、響きが強いので、それに伴う所作も自然と強いものになるであろう。
こう考えてみると、、強い・幽玄というのは、物まねの対象とは別に存在しているのではない。要するに、物まねを正確に演じた結果なのであり、弱い・荒いというのは、物まねの本旨に外れたやり方の結果だと心得べきである。
これを理解したうえで、作者も、為手登場直後の冒頭の句とか、一声や和歌などの大事なところで、主人公の演技に応じて、できるだけ優美な所作とか、演技のきっかけとなる言葉を集めなければならぬ場合に、荒々しい文句を書き込んだり、とんでもないうがちすぎの経文や漢語などを書き加えてしまうのは、作者の間違いである。
そういう詞章は、必ずや、言葉通りに所作を演じれば、優美な人体に不相応な結果になるであろう。しかし、優れた役者は、この見当違いを悟って、不釣り合いでないように演じてこなしてしまうであろう。その場合は役者の名誉であって、作者の落ち度であることに変わりはない。また逆に、作者はそれを心得て書いてあるのに、役者に先に述べたような心得がなければ、まったく、お話にならないのである。以上である。
また、能によっては、言葉やその意味にこだわらず、おおらかに演じた方がいい場合がある。そのような能については、素直に歌い、かつ、舞い、演技をよどみなく滑らかに、自然に演じるがよい。このような能まで、脚本どうりに細かにやるのは、下手な役者だ。こういうのは能が下手なせいだと思うがよい。
要するに、名文句やそれに伴う美しい所作を求めるのも、言葉の面白さや山場というものがなくてはならないような能の場合である。素直でおおらかな能の場合は、たとえ、優雅な主人公役で堅苦しい言葉を使おうとも謡の旋律がしっかりしてさえいれば、これも、いい能と言えるだろう。これが、すなわち、能の本来の姿と心得るべきことである。ただ、残念なことに、いままで述べたような項目を稽古工夫し尽した上で、おおらかに演じるというのでなくては、今までの能についての教えも無意味になってしまうのだ。
語句
■強き・幽玄・弱き・荒き-「花修」執筆当時の世阿弥周辺で、父観阿弥以来定評のあった鬼能(強き能)と近江猿楽犬王の歌舞能(幽玄能)とが両立していたことを示す論。「問答条々」第七問答に本条の説が投影する。■弱き・荒き-物まねの本質を理解しない、力不足の役者の例として掲げる。■よきほどの工夫-いい加減な工夫。■心底を分けて案じ納む-心底から納得して。■弱かるべきこと-これは「幽玄」に近い。■強気なり-物まねの対象が「強き」(鬼能的)であるばかりでなく、演技のあり方がしっかりしている意も兼ねる。■幽玄に-美しく優美な芸。舞踊的演技を指すか。■物まねに足らずば-「物まね似たらずば」とも読める。■物まねにまかせて-役柄の本質通りに。■その物になり入りて-役になり切ること。■また-以下は、やり過ぎの例。■女御-貴女の代表。■遊女-白拍子などの歌舞を演じる女性とともに、優雅な女性(優女)の意味をも含むのが世阿弥時代の一般的用法。■好色-美女の事。■草木-草木の精がシテの能もあるが、ここはたんに植物のイメージを比喩的に例示したもの。■宛てが外して-物まね対象の本質に演技を対応させない事。■荒蝦-蛮族。■わざ-仕事。■その当世当世の風儀-その時々の観客の好み。幽玄風愛好の風が一般化しつつあったことを思わせる発言。■幽玄をもてあそぶ見物衆-幽玄な芸を喜ぶ観客。■申楽の本木には云々-以下、幽玄能制作の必要性を力説。■ちちとある-ちょっとした。■余情-「風情」と同じく所作の事。■別にあるものにあらず-個別の演技としてあるわけではない。■この宛てがひをもて-強い対象と幽玄な対象の演じ分け。■発端の句-登場直後の謡。一声もその一つ。■一声(いつせい)-シテ登場の段や舞の段の前後などで歌い上げる朗誦調の謡。■人体の物まね-役柄にふさわしい演技。「物まねの人体」と同じ。■便り-詞章上の工夫。■いりほが-1 和歌・俳諧などで、あまり技巧を加えすぎて味わいをそこなうこと。2 詮索しすぎて真実から外れること。うがちすぎ。■梵語(ぼんご)・漢音(かんおん)-陀羅尼などの経文や漢字音。実際に中国種の能には漢字音の語彙を多く含むのが世阿弥作品の特色。■ひが事-落ち度。■風情をせば-演技をしたら。■堪能の人-優れた役者。■興-意外な工夫。面白い思い付き。■これはかくのごとし-ここで段落を置くつもりで記した文言であろう。■言葉・義理にかからで-言い回しの面白さや見せ場が不可欠な、ひねったところのある能ではない。堂々たる作風の能。■振りを云々-ここは舞踊的な所作以外の者まね的な表意の所作を言うか。■するするとなだらかに-滞る事が無く滑らかな様。■細かに-克明に写実的に演じること。■音曲-謡の旋律。■確やか-しっかりしていること。■本様-本来のあり方。■能の庭訓-能について本条で述べた教えのこと。
原文
花伝第六 花修(くわしゆ)に云はく
一、能のよき悪(あ)しきにつけて、為手(して)の位(くらゐ)によりて、相応の所を知るべきなり。
文字・風体を求めずして、大やうなる能の、本説ことに正しくて、大きに位の上(あが)れる能あるべし。かやうなる能は、見所(みどころ)さほど細かになき事あり。これには、よきほどの上手も似合はぬ事あり。たとひ、これに相応するほどの無上の上手なりとも、また、目利き・大所(たいしよ)にてなくば、よく出で来る事あるべからず。これ、能の位、為手の位、目利き、在所、時分、ことごとく相応せずば、出で来る事は左右(さう)なくあるまじきなり。
また、小さき能の、さしたる本説にてはなけれども、幽玄なるが、細々(ほそぼそ)としたる能あり。これは、初心の為手にも似合ふものなり。在所も、自然(しぜん)、片辺(かたほと)りの神事、夜などの庭(には)に相応すべし。よきほどの見手(みて)も、能の為手も、これに迷ひて、自然、田舎(でんじや)・小所(せうしよ)の庭にて面白ければ、その心馴(な)らひにて、押い出だしたる大所、貴人(きにん)の御前(おんまへ)などにて、あるいはひいき興業(こうぎやう)して、思ひの外に能悪(わる)ければ、為手にも名を折らせ、われも面目なき事あるものなり。
しかれば、かやうなる品々(しなじな)、所々(しょしよ)を限らで、甲乙(かふおつ)なからんほどの為手ならでは、無上の花を極めたる上手とは申すべからず。さるほどに、いかなる座敷にも相応するほどの上手に至りては、是非なし。
また、為手によりて、上手ほどは能を知らぬ為手もあり。能よりは能を知るもあり。貴所(きしょ)・大所などにて、上手なれども、能をし違(ちが)へ、遅々(ちち)のあるは、能を知らぬがゆゑなり。
また、それほどに達者にもなく、物少(ものずく)ななる為手の、申さば初心なるが、大庭(おほには)にても花失(う)せず、諸人の褒美(ほうび)いや増しにて、さのみにむらのなからんは、為手よりも能を知りたるゆゑなるべし。
さるほどに、この両様の為手を、とりどりに申す事あり。しかれども、貴所・大庭などにて、あまねく能のよからんは、名望長久なるべし。さあらんにとりては、上手の、達者ほどは我が能を知らざらんよりは、少し足らぬ為手なりとも、能を知りたらんは、一座建立(こんりふ)の棟梁(とうりやう)には勝(まさ)るべきか。
能を知りたる為手は、我が手柄の足らぬ所をも知るゆゑに、大事の能に、かなはぬ事をば斟酌(しんしゃく)して、得たる風体ばかりを先立てて、仕立(したて)よければ、見所(けんじよ)の褒美かならずあるべし。さて、かなはぬ所をば、小所・片辺りの能にし習ふべし。
かやうに稽古すれば、かなはぬ所も、功(こう)入れば、自然自然にかなふ時分あるべし。さるほどに、つひには、能に嵩(かさ)も出で来、垢(あか)も落ちて、いよいよ名望も一座も繁昌(はんじやう)する時は、さだめて、年行くまで花は残るべし。これ、初心より能を知るゆゑなり。能を知る心にて、公案を尽くして見ば、花の種(たね)を知るべし。しかれども、この両様は、あまねく人の心ごころにて、勝負をば定め給ふべし。
花修(くわしゆ) 已上(いじやう)
此条々、心ざしの芸人より外は、一見(いつけん)をも許すべからず。
世阿(花押)
現代語訳
能の脚本の良し悪しがあるが、役者の芸の実力に応じて、どの程度の物が釣り合うかということを考えねばならない。
文飾や派手な演技を追求せず、具体的な見せ場や聞かせどころのない能において、典拠がきわめて権威のある文学作品で、大いにその格付けが高い能というものがあるであろう。このような作品は、具体的な見せ場はそれほどない場合がある。これには、かなり上手な役者でも適合しない場合がある。例え、これに適合するほどの最高に上手な役者といえども目の利く観客が居て、しかも晴れの舞台でもなければ、うまく成功することは決してない。こうした例では、作品性、役者の芸格、鑑識眼のある観客、上演の場所と時期、といた諸条件がすべて整わなければ、滅多に成功することはない。
これに反して、こじんまりした能で、大した文学作品に由来するものではないが、優雅で美しく、繊細な印象の能があるものだ。こういうのは、若い未熟な役者にふさわしい。演能の場所も当然、辺鄙な田舎の村祭りや夜間の演能など、いずれもこじんまりした催しで演じる能だ。そういうところでうまくいくと、よほどの目利きの観客も上演する役者も、、偶然、田舎やこじんまりした私的な催しの場で成功を収めただけで、それがどこでもうまくいくというふうに、これを勘違いし、特に目をかけ引き立てて、晴れの舞台や貴人の御前の能などで演能させ、期待外れの不出来で、役者の評判を落とし、自分も面目丸つぶれになるということがある。
要するに、こういった作品性や演能場所のさまざまに影響されず、常に優れた舞台を演じるほどの役者でないと、最高の花を極めた名人とは言えないだ。だから、どんな座敷での演能にも適合できるほどの名人であれば何も言うことはない。
しかし、役者によっては、わざが上手な割には能がどういうものかということを知らない者もいる。逆にわざの割には能の本質をわきまえている者もいる。貴人の御前や晴れの舞台などで、わざはうまいが演出や選曲を誤り、失敗することがあるのは、能がなんたるかをわきまえないからだ。
また、それほどわざ優れているわけでもなく、出し物が少ない役者、いうなれば未熟者が晴れの舞台でも花を失わず、観客の称賛をあび、それほど、出来不出来の差が無いのは、役者としての腕前以上に、能の本質をわきまえているからである。
そこで、この二種類の役者のどちらが優れているかの評価は、人により千差万別である。しかしながら、貴人の御前や晴れの舞台などで、いつも上手に能を演じる事が出来る役者は、その名声を永く保つことができる。そうだとすると、腕達者でも自分の能についての見識がないよりは、少し技量が不足する役者であっても、自分の技量について理解している役者の方が一座を成り立たせる花形の座長としては優れているであろう。
能の何たるかを知っている役者は、自分の技量不足を知っているから、大切な催しに際して、できないことはさしひかえて、得意な芸ばかりを演じ、出来が良ければ観客はきっと褒めるであろう。そのうえで、不得手な演目を、小規模な催しや地方でやってみて稽古するがよい。。
このようにして鍛錬すれば、不得手な演目でも、修練を積んで次第に上手にできるようにもなる。そうするうちに、ついには、能の芸域も広がり、洗練され、いよいよ、名声もあがり、一座も繁昌するようになれば、きっと老後まで芸の魅力は保たれるであろう。そうなるのは、未熟な頃から能の何たるかを知っているからだ。能に対する見識によって、工夫を重ねていけば花を咲かせるもとの種がなんであるかを知ることができるであろう。けれども、この両様は人の好き好きで、あまねく人それぞれで評価されるがよいであろう。
花修 以上
この花修で述べた項目は、芸道に深く志を持つ能役者以外には、たとえ一目でも見せてはならない。
世阿弥(花押)
語句
■能のよき・悪しきにつけて云々-作品の良し悪しと役者の芸位との関連について述べる。■文字・風体を求めずして-文飾や派手な演技を追求しないことをいう。■大やうなる能-堂々とした能。具体的な見せ場や聞かせどころのない能。■本説ことに正しく-典拠がきわめて権威のある文学作品であること。■大所-晴れの大舞台。大庭と同じ。■出で来る-成功する。■左右なく-簡単に。軽率に。滅多に。■在所-土地。興業の行われる場所。■小さき能-小品の能。■幽玄なるが-幽玄能が能の理想とされる以前の認識を反映した言い方か。■細々としたる能-繊細な印象の能。■自然-自ずと。■片辺りの神事、夜などの-辺鄙な田舎の村祭りや夜間の演能など、いずれも小規模な催しの例。■庭-演能場。■自然-ここは「偶然」の意。■小所の庭-小規模な、私的な催しの場。■押し出だしたる-堂々たる。■ひいき興業-特定の役者を引き立てるための興業。■名を折らせ-恥をかかせ。■甲乙-優劣。■無上の花-真の花。■上手ほどは能を知らぬ-自分の能の技量にふさわしい見識のないこと。■能よりは能を知る-役者としての力量以上に能について見識を持っていること。■遅々のある-後れを取ること。選曲・演出を誤り、失敗すること。■物少ななる-芸域が狭く、上演項目が少ないこと。■むら-出来、不出来の差。具体的には不出来の例がないこと。■とりどりに申す-技量と見識との優劣をそれぞれに評価すること。■貴所-貴人の邸宅。「貴人の御前」と同じ。■大庭-晴れの舞台。■名望-世間の名声。■さあらんにとりては-そのような結果よりどちらかを選ぶとすれば、の意。■一座建立の棟梁-一座を成り立たせる花形の座長。■我が手柄-自分の技量。具体的には得意演目の数や内容をいうか。■大事の能-大切な催し、貴所・大所の能。■かなはぬ事-自分には無理な出し物を避けること。■仕立て-能の演出。■習ふ-演じることによって稽古すること。■功入れば-年季が入ると。習熟すると。■能に嵩も出で-芸域が広がること。■垢も落ちて-洗練されて。■名望も一座も繁昌-「名望も得、一座も繁昌する」をつづめた言い方。■初心より能を知る-若いころから能の何たるかを知っていること。■能を知る心にて、公案を尽して-能についての見識を持っているその精神で工夫を尽くせば。■この両様は-見識と技量のどちらを優先するかは。■勝負をば定め給ふべし-弟に与えた書であることと一体の、親しみを込めた文書か。■心ざしの芸人より外は云々-一子相伝といった秘伝ではない事を示す文言。
備考・補足
<参考文献>
・風姿花伝・三道 現代語訳付き 世阿弥・竹本幹夫訳注
・花伝書(風姿花伝) 世阿弥編 川瀬一馬校注、現代語訳
・風姿花伝 世阿弥編 野上豊一郎・西尾実校訂
・現代語訳 風姿花伝 世阿弥著 水野聡訳
・風姿花伝 世阿弥 現代語訳:夏川賀央
次の章「風姿花伝 奥義に云はく」