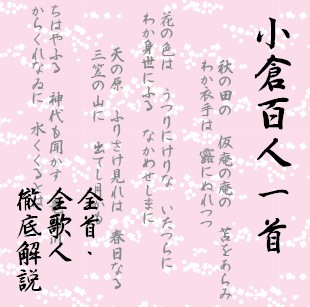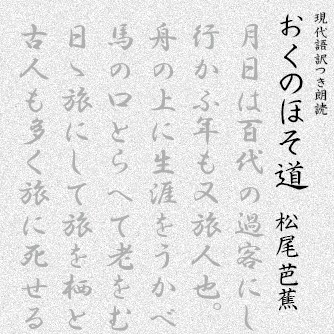くらもちの皇子と蓬莱の玉の枝
■『竹取物語』の全朗読を無料ダウンロードする
■【古典・歴史】メールマガジン
YOUTUBEで配信中
≪くらもちの皇子とその謀略≫
くらもちの皇子(みこ)は、こころたばかりある人にて、朝廷(おほやけ)には、「筑紫(つくし)の国(くに)に湯(ゆ)あみにまからむ」とて暇(いとま)申して、かぐや姫の家には、「玉の枝取りになむまかる」といはせて、下りたまふに、仕(つか)うまつるべき人々、みな難波(なには)まで御送りしける。
皇子、「いと忍びて」とのたまわせて、人もあまた率(ゐ)ておはしまさず。近(ちこ)う仕うまつるかぎりしていでたまひぬ。御送りの人々、見たてまつり送りて帰りぬ。
「おはしましぬ」と人には見えたまひて、三日ばかりありて、漕(こ)ぎ帰りたまひぬ。
かねて、事(こと)みな仰(おほ)せたりければ、その時、一(いち)の宝(たから)なりける鍛冶工匠(かぢたくみ)六人を召し取りて、たはやすく人寄り来(く)まじき家を作りて、竈(かまど)を三重(みへ)にしこめて、工匠らを入れたまひつつ、皇子(みこ)も同じ所に籠(こも)りたまひて、領(し)らせたまひたるかぎり十六所(そ)をかみに、蔵(くら)をあげて、玉の枝を作りたまふ。
かぐや姫ののたまふに違(たが)はず作りいでつ。
いとかしこくたばかりて、難波(なには)にみそかに持(も)ていでぬ。
「船に乗りて帰り来(き)にけり」と殿(との)に告げやりて、いといたく苦しがりたるさましてゐたまヘリ。迎へに人多く参りたり。
玉の枝をば長櫃(ながびつ)に入れて、物おほいて持ちて参る。
いつか聞きけむ、「くらもちの皇子(みこ)は優曇華(うどんぐゑ)の花持ちて上(のぼ)りたまへり」とののしりけり。
これをかぐや姫聞きて、我はこの皇子に負けぬべしと、胸つぶれて思ひけり。
現代語訳
くらもちの皇子は、はかりごとに長じた人で、朝廷には、「病気治療のため筑紫へ温泉に入りに行きます」と言って、休暇をもらいながら、かぐや姫には「玉の枝を取りにまいります」と家来に伝言させて都を下るのに、彼に仕える人々は皆、難波まで見送りをした。
皇子は、忍びの旅ということで、人もそれほどたくさんは連れていかなかった。
身近に使えるものだけを選んで出立した。見送りの人たちは見送りが終わった後、京へ帰って行った。
「このように出発なさった」と人には見られるようにしておかれて、三日ほど経ってから、船を漕いで帰っていらっしゃった。
かねて、計画を命令しておかれたので、その時、その当時一流の鍛冶工匠六人を、召し寄せ、簡単には人が寄り付けない家を作って、竈の囲いを三重にしつらえ、秘密を守るため厳重な警戒。
工匠らをその家に入れながら、皇子自身も同じところに籠って、所領の荘園すべて十六か所をはじめ蔵の全財産を投じて球の枝をお作りになる。
このようにして、かぐや姫のおっしゃるとおり、寸分違わず作り上げてしまった。
大変上手に計略をめぐらし、難波の浦にこっそり、持ち出した。
「船に乗って帰ってきましたよ」と自分の殿に報告にやり、とても苦しがっている風を装いすわっていらっしゃる。
たくさんの人たちが迎えに来た。
玉の枝を長櫃に入れ、覆いをかぶせて都へ持って帰る。
いつ聞いたのか、人々は、「くらもちの皇子は優曇華の花を持って都へ上って行かれたよ」と大声で騒ぐ。
これをかぐや姫が聞きつけて、「この皇子には負けてしまったかもしれない」と、胸がつぶれるように思い悩んでいた。
語句
■こころたばかりある人-はかりごとに長じた人。■筑紫(つくし)の国(くに)に-筑紫の大宰府(現在の福岡県太宰府市)近くの武雄温泉は『万葉集』の時代からあった。■いはせて-使者に連絡させて ■難波(なには)-今の大阪市から尼崎市にかけての海岸。淀川の河口 ■見えたまひて-お見せになって。「見え」は本来受身で「人に見られる」の意。■一の宝-第一の。最高の。 ■湯あみに云々-温泉に入って病気の治療をすること ■、見たてまつり送りて-「見送る」の謙譲語。 ■人には見へたまひて-「見え」は人から見られる意。≪くらもちの皇子、いつわりの苦労談を語る(1)≫
かかるほどに、門(かど)を叩(たた)きて、「くらもちの皇子おはしたり」と告(つ)ぐ。
「旅の御姿ながらおはしたり」といへば、あひたてまつる。
皇子ののたまはく、「命を捨ててかの玉の枝持ちて来たるとて、かぐや姫に見せたてまつりたまへ」といへば、翁(おきな)持ちて入(い)りたり。この玉の枝に、文ぞつけたりける。
いたづらに身はなしつとも玉の枝(え)を手折(たを)らでさらに帰らざらまし
これをもあはれとも見でをるに、たけとりの翁、走り入りて、いはく、「この皇子に申したまひし蓬莱の玉の枝を、一つの所あやまたず持(も)ておはしませり。何をもちて、とかく申すべき。旅の御姿ながら、わが御家(おほんいえ)へも寄りたまはずしておはしましたり。はや、この皇子にあひ仕(つか)うまつりたまへ」といふに、物もいはず、頬杖(つらづゑ)をつきて、いみじく嘆(なげ)かしげに思ひたり。
現代語訳
こうしているうちに、くらもちの皇子の従者が、門を叩いて、「くらもちの皇子がいらっしゃいました」とかぐや姫に告げる。
「旅姿のままおいでになりましたよ」と言うのでじいさんがお会い申し上げる。
皇子が、「命を捨てるほどの苦労をして、あの玉の枝を持って帰ってきたのでかぐや姫にお見せください」とおっしゃるので、じいさんがそれを持って、かぐや姫の部屋に入った。
この玉の枝に合わせて皇子はかぐや姫への文を託したのである。その歌は、
いたづらに身はなしつとも玉の枝(え)を手折(たを)らでさらに帰らざらまし
(危機に会ってわが身はむなしくなりはてても、ご依頼の玉の枝を手折らずに帰ってくるということはけっしてしなかったでしょう)
玉の枝はもちろん、この歌をも、心を打つ歌とは思わないでいると、竹とりの爺さんが走って姫の部屋ん入ってきて、言うには、「あなたがこの皇子に申し上げなさった蓬莱の玉の枝を、一点の違いもない形で持っていらっしゃった。
いまはもう、どういう理由であれこれ申せましょうか。
しかも、旅のご服装のままで、ご自身のお宅にも寄らずにいらっしゃったのです。
はやく、この皇子の妻としてお仕え申し上げなさい」と言うので、姫はもう物も言わず、頬杖をつく姿で、たいそう嘆かわしそうに物思いに沈んでいる。
語句
■かかるほどに-こうしているうちに ■いたづらに身は…-「身をいたづらに成す」で成語。破滅する。■さらに-「さらに」は、「ただに」となっている本が多い。「さらに」なら絶対に帰らないだろうの意。「ただに」なら「手ぶらでは帰らないだろう」の意になる。「まし」は、事実に反する仮想。実際は帰ってきたのであるが、玉の枝が入手できない時は帰って来ないと言っている。■いみじ-(程度が)はなはだしい。なみなみでない。たいそう。■頬杖をつく-思案して思い沈むときの動作≪くらもちの皇子、いつわりの苦労談を語る(2)≫
この皇子、「今さへ、なにかといふべからず」といふままに、縁(えん)に這(は)ひのぼりたまひぬ。
翁(おきな)理(ことわり)に思ふ。
「この国に見えぬ玉の枝なり。このたびは、いかでか辞(いな)びまうさむ。人ざまもよき人におはす」などいひゐたり。
かぐや姫のいふやう、「親ののたまふことをひたぶるに辞(いな)びまうさむことのいとほしさに」と、取りがたき物を、かくあさましく持(も)て来(く)ることを、ねたく思ふ。
翁は閨(ねや)のうち、しつらひなどす。
翁、皇子に申すやう、「いかなる所にかこの木はさぶらひけむ。あやしくうるはしくめでたき物にも」と申す。
皇子、答へてのたまはく、「一昨々年(さをととし)の二月(きさらぎ)の十日ごろに、難波(なには)より船に乗りて、海の中にいでて、行(い)かむ方(かた)も知らずおぼえしかど、思ふこと成(な)らで世(よ)の中に生きて何かせむと思ひしかば、ただ、むなしき風にまかせて歩(あり)く。
命(いのち)死なばいかがはせむ、生きてあらむかぎりかく歩きて、蓬莱(ほうらい)といふらむ山にあふやと、海に漕(こ)ぎただよひ歩きて、我(わ)が国のうちを離れて歩きまかりしに、ある時は、浪(なみ)荒れつつ海の底にも入りぬべく、ある時には、風につけて知らぬ国に吹き寄せられて、鬼(おに)のやうなるものいで来(き)て、殺さむとしき。
現代語訳
この皇子は、「いまとなってまで、あれこれ言うべきではない」と言いながら、縁(えん)に(は)這い上がられました。
じいさんはもっともだと思っている。
「これは日本では見ることができない玉の枝です。もう、今度はどうしてお断り申せましょうか。
人柄も良い方でいらっしゃる」などと爺さんは言って、姫の前に座っている。
かぐや姫の言うには、「親がおっしゃることを、ひたすらにお断り申し上げることが気の毒ゆえ、あのように申しましたのに」と、取ることが難しいものであるのに、このように意外なほどにちゃんと持ってきたことをいまいましく思う。
じいさんは、すっかりその気になって、寝室の中を片付けなどしている。
爺さんが、皇子に申し上げるには、「この木はどんな所にございましたのでしょうか。不思議なほど麗しく、すばらしいものでございますね」と申し上げる。
皇子が答えておっしゃるには、「一昨々年(さをととし)の二月(きさらぎ)の十日ごろに、難波から船に乗って、海上に出て、目的とする方向すらわからぬほど心細く思ったが、『自分の思うことが成就できないで、世の中に生きていてもしかたがない』と思ったので、ひたすらに、どちらに吹くかわかりもしない風に任せて航行しました。
『命がなくなればしかたないが、生きている限りはこのように航海を続け、いつかは蓬莱とかいう山に会うだろうよ』と思い、海を漕ぎ漂って、わが日本の領海を離れていきましたところ、あるときは、浪の荒れが続いて海底に沈みそうになり、あるときは、風の方向のままに知らぬ国に吹き寄せられ、鬼のような怪物が目の前に立ち現れて、私を殺そうとしました。
語句
■言うままに-言いながら ■辞(いな)ぶ-断る。承知しない。いやがる。■ひたぶるに-いちずである。ひたすら。むやみである。■いとほし-気の毒だの意。じいさんがかわいそうだから結婚の意志はないのに難題を出したと後悔している。■あさましく-意外なことに ■さぶらふ-「あり」「居(を)り」の謙譲語。ございます。あります。■めでたき物にも-「めでたきものにもあるかな」の意。■海の中-海の真ん中。海中の意ではない。■ども-逆説の確定条件。ガ・ケレドモ■むなしき風-どちらから吹く風でもそれにまかせて ■歩(あり)く-足で歩くとは限らない。行動することすべてを言う語。■蓬莱といふらむ-「らむ」は推量。自分でその存在を確かめていないからである。■浪荒れつつ-「つつ」は反復の意。何度の荒れたのである。≪くらもちの皇子、いつわりの苦労談を語る(3)≫
ある時には、来(き)し方(かた)行(ゆ)く末(すゑ)も知らず、海にまぎれむとしき。
ある時には、糧(かて)つきて、草の根を食物(くひもの)としき。
ある時は、いはむ方(かた)なくむくつけげなる物(もの)来(き)て、食ひかからむとしき。
ある時には、海の貝を取りて命をつぐ。
旅の空に、助けたまふべき人もなき所に、いろいろの病(やまひ)をして、行(ゆ)く方(かた)そらもおぼえず。
船の行(ゆ)くにまかせて、海に漂(ただよ)ひて、五百日といふ辰(たつ)の時ばかりに、海のなかに、はつかに山見ゆ。
船の楫(かぢ)をなむ迫(せ)めて見る。
海の上にただよへる山、いと大きにてあり。
その山のさま、高く、うるはし。
これや我(わ)が求むる山ならむと思ひて、さすがに恐ろしくおぼえて、山のめぐりをさしめぐらして、二三日ばかり、見歩(あり)くに、天人のよそほひしたる女、山の中よりいで来(き)て、銀(しろかね)の金鋺(かなまる)を持(も)ちて、水を汲(く)み歩(あり)く。
これを見て、船より下(お)りて、「この山の名を何とか申す」と問ふ。
女、答へていはく、『これは蓬莱の山なり』と答ふ。
これを聞くに、嬉しきことかぎりなし。
この女、『かくのたまふは誰(たれ)ぞ』と問ふ、『我が名はうかんるり』といひて、ふと、山の中に入りぬ。
現代語訳
ある時にはまた、海上で方向を失い、後(あと)も先もわからなくなり、そのまま海で行方不明になりそうになりました。
ある時には、食糧が尽き果て、偶然上陸した島で草の根を取って食糧にしました。
またある時は、言いようもなく気味悪い妖怪が出現して、私に食いかかろうとしました。
またある時は、海の貝を取って命をつないだこともあります。
旅の道中で、助けてくださる人もない所であるのに、種々の病気をして、行く方向までもさだかではなくなりました。
こんな調子で、ただ船の行くのにまかせて海上を漂流していましたが、海に出て五百日目という日の午前八時ごろに、海上にかすかに山が見えます。
船の楫(かじ)を島に近づけるように操作して、それを見る。
海上にただよっているその山はたいそう大きい。
そして、その山のようすは高くうるわしい。
『これこそ私が求めている山であろう』と思ってうれしくはあるが、やはり恐ろしく思われて、山の周囲を漕ぎまわらせて、二、三日ほど、ようすを見ながら航行させていますと、天人の服装をした女が、山中から出てきて、銀の椀を持って水を汲み歩いています。
これを見て、船からおりて、『この山の名はなんと申しますか』とたずねる。
女が答えて言うには、『これは蓬莱の山です』と答えます。
これを聞いたとき、うれしさはかぎりない。
『このようにおっしゃるあなたはだれですか』と問うと、この女は『私の名はうかんるり』と言って、すうっと山の中に入ってしまいます。
語句
■いわむ方なく-言いようもなく ■むくつけし-薄気味が悪い。無気味である。■そら-助詞「すら」と同じ。漢文訓読系の男性語。■まかりしに-「まかり」は聞き手の前で自分の「行く」という行動をへりくだっていうときに用いる。■はつかに-かすかに。ほのかに ■ふと-[副詞]すばやく。すぐに。さっと。たちまち
≪くらもちの皇子、いつわりの苦労談を語る(4)≫
その山、見るに、さらに登るべきやうなし。
その山のそばひらをめぐれば、世(よ)の中になき花の木どもたてり。
金(こがね)、銀(しろかね)、瑠璃色(るりいろ)の水、山より流れいでたり。
それには、色々の玉の橋わたせり。そのあたりに照(て)り輝(かかや)く木ども立てり。
その中に、この取りて持ちてまうで来(き)たりしはいとわろかりしかども、のたまひしに違(たが)わましかばと、この花を折(を)りてまうで来(き)たるなり。
山はかぎりなくおもしろし。
世にたとふべきにあらざりしかど、この枝を折りてしかば、さらに心もとなくて、船に乗りて、追風(おひかぜ)吹きて、四百余日になむ、まうで来(き)にし。
大願力(だいぐわんりき)にや。
難波(なにわ)より、昨日(きのふ)なむ都(みやこ)のまうで来(き)つる。
さらに、潮(しほ)に濡(ぬ)れたる衣(きぬ)だに脱ぎかへなでなむ、こちまうで来(き)つる」とのたまへば、翁、聞きて、うち嘆きてよめる、
くれたけのよよのたけとり野山にもさやはわびしきふしをのみ見し
これを、皇子聞きて、「ここらの日ごろ思ひわびはべりつる心は、今日(けふ)なむ落(お)ちゐぬる」とのたまひて、返し、
我(わ)が袂(たもと)今日かわければわびしさの千種(ちぐさ)の数も忘られぬべし
とのたまふ。
現代語訳
その山は、見ると、まったく登る手段がないほどに険しい。
その山の側面をめぐってゆくと、この世の物とも思えぬ花の木が多く立っている。
金色、銀色、瑠璃色の水が、山から流れ出ている。
その川には色々な色の玉で作った橋が渡してあり、橋の近傍に照り輝く木々がたっている。
その中で、ここにいま持参したのは、たいそう劣っていたのですが、せっかくよいのを取ってきても、あなたのおっしゃたのにぴったりでなければ困るだろうと思いまして、この花を折って持参したのです。
山はかぎりなくすばらしい。
世の中に例えるものが無いのだけれど、この枝を折ってしまいましたので、ただもう落ち着かなく、船に乗って追い風が吹いて、四百余日で帰って参りました。
ほんとうに仏の大願力のおかげでありましょうか。
昨日、難波から都へ帰参したのです。
そのうえ、潮で濡れた衣をも着替えもしないで、こちらに直接参上しました」とおっしゃると、じいさんが、これを聞いて、嘆息して詠んだ、その歌は、
くれたけのよよのたけとり野山にもさやはわびしきふしをのみ見し
(長い年月竹取りをし、年老いたこの竹取りですが、野山での竹を取る生活でも、こんなに苦しい目ばかりを見たことはございませんよ)
これを聞いて皇子は、「長い間苦しく思っていました心は、今日その言葉を聞いて、すっかり落ち着きました」とおっしゃって、返し、
我(わ)が袂(たもと)今日かわければわびしさの千種(ちぐさ)の数も忘られぬべし
(今まで海水や涙で濡れていた私の袂は、望みを叶えた今日、すっかり乾いたので、これまでの数々の辛苦も自然に忘れてしまうことでしょう)
とおっしゃる。
語句
■そばひら-[名詞]-かたわら。側面。■色々の-色彩豊かな ■まうで来-「来る」の謙譲語。参上する。うかがう。■大願力-阿弥陀仏の衆生の成仏を願う心が生み出した力。あるいは、単に神仏に願をかけた、その結果としての力。 ■衣(きぬ)-「きぬ」が日常語であるのに対して、「衣」は歌語である。■うち嘆く-嘆息する。ため息をついて嘆く。■くれたけの-「よよ」の枕詞。「よ」は竹の節と節との間の部分。その「よ」を二つ重ねて、「よよ」と言い、同時に「世々」の意味を表す。「長い年月」の意。■ここら-[副詞]-数量の多いさま。こんなに多く。たくさん■わびはべる-「わび」は「つらいと思う」「思い嘆く」で「はべる」はおります。ございます(丁寧語)≪工匠の訴えにより万事は露見(1)≫
かかるほどに、男(をのこ)ども六人、つられて、庭にいでたり。
一人の男、文挟(ふんばさ)みに文(ふみ)をはさみて、申す、「内匠寮(たくみづかさ)の工匠(たくみ)、あやべの内麻呂(うちまろ)申(もう)さく、玉の木を作り仕(つか)うまつりしこと、五穀(ごこく)を断(た)ちて、千余日に力(ちから)をつくしたること、すくなからず。
しかるに、禄(ろく)いまだ賜(たま)はらず。
これを賜ひて、わろき家子(けこ)に賜はせむ」といひて、ささげたり。
たけとりの翁(おきな)、この工匠らが申すことは何ごとぞとかたぶきをり。
皇子(みこ)は、我にもあらぬ気色にて、肝(きも)消えゐたまへり。
これをかぐや姫聞きて、「この奉る文を取れ」といひて、見れば、文に申しけるよう、皇子(みこ)の君(きみ)、千日、いやしき工匠らと、もろともに、同じところに隠れゐたまひて、かしこき玉の枝(えだ)を作らせたまひて、官(つかさ)も賜はむと仰(おほ)せたまひき。
これをこのごろ案ずるに、御使とおはしますべきかぐや姫の要(えう)じたまふべきなりけりとうけたまはりて。
この宮(みや)より賜はらむ。
と申して、「賜はるべきなり」といふを、聞きて、かぐや姫、暮るるままに思ひわびつる心地(ここち)、笑ひさかえて、翁を呼びとりていふやう、「まこと蓬莱の木かとこそ思ひつれ。かくあさましきそらごとにてありければ、はや返(かへ)したまへ」といへば、翁答(こた)ふ、「さだかに作らせたる物と聞きつれば、返さむこと、いとやすし」と、うなづきをり。
現代語訳
こうしているうちに、労働者が六人、連れだって、庭にあらわれた。
一人の男が、文挟みに文をはさんで訴えるには、「内匠寮(たくみづかさ)の工匠(たくみ)、あやべの内麻呂が申し上げます。
玉の木を作るのに、五穀を断って神仏に祈りながら千日余り力を尽くして頑張りましたが、いまだに、謝礼をいただけません。
謝礼をいただいて、貧しい弟子に与えたいのです」と文挟みを捧げた。
竹取りのじいさんは、この工匠たちは何を言わんとしているのかと首をかしげて、不思議がり、じっと座っている。
皇子は茫然自失のていで、肝をつぶしてすわっていらっしゃる。
これをかぐや姫が聞いて、「この工匠が差し出している文を取れ」と言って、取らせて、見ると、その文で訴えていることは、
皇子の君は、千日の間、身分の低い匠たちとごいっしょに、同じところに隠れ住み、りっぱな玉の枝を作らせなさって、できあがったら官職を下さろうとおっしゃいました。
このことをこのごろになって考えてみますと、ご側室としていらっしゃるはずのかぐや姫が必要となさっているのだったよと承知いたしまして。
ですから代わりに、このお邸からいただきたいのです。
と上申書に書いてあって、口でも、「当然いただくべきです」と言っているのを、聞いて、かぐや姫は、日が暮れるにしたがって、「皇子と契らねばならぬのか」と思い悩み、苦しんでいた心が、愉快になって、晴れ晴れしく笑って、じいさんを呼び寄せて言うには、「ほんとうに蓬莱の木かしらと思っていましたよ。けれど、このように意外な偽りごとだったのですから、早くお返ししてください」と言うと、じいさんが答えるには、「たしかに、作らせたものだと私も聞きましたので、お返しすることは、いとも簡単です」とうなずいて控えている。
語句
■男(をのこ)-「をとこ」ではなく「をのこ」であるのに注意。「をのこ」は「仕えている男」の意。■文挟み-細い竹の先を二つに割って貴人への書状を挟むようにしたもの。■内匠寮(たくみづかさ)-中務省に属し、金銀工・玉石帯工・鋳工・銅鉄工など多くの工匠がいて、調度の制作・装飾などを行った。■あやべの内麻呂-中国系の帰化人めいた姓名。■さく-(動詞の連用形の下について、その動作によって)思いをはらす■五穀(ごこく)を断(た)ち-米・麦・粟(あわ)・黍(きび)・豆を断ち、神仏に祈願しての意。■かたぶきをり-首をかしげて不思議がっている。(翁はそんなことはないと確信している)■我にもあらず-唖然としている。
■肝消ゆ-ひどく驚く。肝がつぶれる。■「この奉る文を取れ」といひて-「いひて」は召使に命じたのである。■賜はせむ-「賜ふ」に敬意を高める助動詩「す」が付いたもの。お与えになる。■をり-じっと座っている。控えているの意。軽い蔑視の気持ちを込めて用いる。■御使-使い人。召し人。北の方ではなく実の周りの世話をする一段下の待遇の妻。かぐや姫は皇子の正室となる身分ではなっかたのだ。■宮-竹取りの翁の邸を、宮と称しているのに注意。りっぱな建物なので、宮の語源の御屋の意で用いられている。■暮るるままに云々-同衾(どうきん)しなければならぬ夜が近づくのを恐れていた。■笑ひさかえて-明るく笑って
■つれ-完了の助動詞「つ」の已然形 ■さだか-はっきりしているさま。確実なさま。■あさましい-意外な ■そらごと-うそ。いつわり。作り事。
≪工匠の訴えにより万事は露見(2)≫
かぐや姫の心ゆきはてて、ありつる歌の返し、
まことかと聞きて見つれば言(こと)の葉を(は)かざれる玉の枝にぞありける
といひて、玉の枝も返しつ。
たけとりの翁(おきな)さばかり語らひつるが、さすがにおぼえて眠(ねぶ)りをり。皇子(みこ)は立つもはした、ゐるもはしたにて、ゐたまへり。日の暮れぬれば、すべりいでたまひぬ。
かの愁訴(うれへ)せし工匠(たくみ)をば、かぐや姫呼びすゑて、「嬉(うれ)しき人どもなり」といひて、禄(ろく)いと多く取らせたまふ。
工匠らいみじくよろこびて、「思ひつるやうにもあるかな」といひて、帰る。
道(みち)にて、くらもちの皇子(みこ)、血の流るるまで打(ちょう)ぜさせたまふ。
禄得(え)し甲斐(かひ)もなく、みな取り捨てさせたまひてければ、逃げうせにけり。
かくて、この皇子(みこ)は、「一生(いっしょう)の恥(はぢ)、これ過ぐるはあらじ。女(をんな)を得ずなりぬるのみにあらず、天下(てんか)の人の、見思(おも)はむことのはづかしきこと」とのたまひて、ただ一所(ひとところ)、深き山へ入りたまひぬ。宮司(みやつかさ)、さぶらふ人々、みな手を分(わか)ちて求めたてまつれども、御死(おほんし)にもやしたまひけむ、え見つけたてまつらずなりぬ。
皇子の、御供(おほんとも)に隠したまはむとて、年ごろ見えたまはざりけるなりけり。これをなむ、「たまさかに」とはいひはじめける。
現代語訳
かぐや姫の心はすっかり晴れて、さっきの皇子の歌の返歌として、
まことかと聞きて見つれば言(こと)の葉を(は)かざれる玉の枝にぞありける
(本当の玉の枝かと思い、皇子の話をよく聞き、また、玉の枝をよく見ましたところが、金(こがね)の葉ならぬ、言(こと)の葉で飾り立てた偽りの玉の枝でございましたよ)
と言って、歌とともに玉の枝も返してしまった。
いっぽう、竹取りのじいさんは、あれほどまで皇子と意気投合していたことが、だまされていたのだから仕方が無いとは思うものの具合が悪く、眠ったような顔をして座っている。
当の皇子は、立つのも落ち着かず、座っているのもきまりが悪いという様子で、座っておられる。
そして、日が暮れたので、これ幸いと、こっそり抜け出してしまわれた。
あの訴えた工匠を、かぐや姫が呼んで、庭に控えさせ、「うれしい人たちですよ」と言って、ご褒美をたいそう多くお与えになる。
工匠どもはたいそう喜んで、「期待していたとおりだった」と言って、帰る。
その帰り道で、くらもちの皇子が、工匠たちを血が流れるまで、打擲(ちょうちゃく)させなさる。
工匠たちは褒美を得た甲斐もなく、皇子がみな取りあげて、捨てさせなさったので、無一文になって逃げ失せてしまった。
さて、この皇子は、「生涯において、これ以上の恥はなかろう。女を自分のものにできなくなったばかりでなく、世間の人が、自分を見、いろいろと思うのが恥ずかしいことだ」とおっしゃって、ただ一人で、深い山中に入ってしまわれた。
お邸の執事やお仕えしている人々が、みな手分けをして、おさがし申し上げたが、あるいはお亡くなりにでもなったのだろうか、見つけ申しあげぬままになってしまった。
それは、皇子が恥ずかしくて、ご家来の前から自分の姿をお隠しになろうと思って、何年もの間、姿をお見せにならないのであった。
そののち、何年もたって、ひょっこりと姿をお見せになったのだろうか、この玉の枝事件を起こりとして、「たまさかに」という言葉を、言い始めるようになったのである。
語句
■心ゆきはてる-すっかり気が晴れる。■ありつる-先ほどの。さっきの。前述の。■さばかり-それほど。それくらい。その程度。■さすがに-そうはいってもやはり。それでもやはり。■いみじく-たいそう。たいへん。 ■はした-「形容動詞」はしたなりの語幹。落ち着かない。■一生の恥-生涯で最大の恥。■辷(すべ)る-そっと席をはずす。退く。■天下(てんか)の-仏教語に由来した語。「てんげ」と読むという説もある。■宮司-皇子の邸宅の執事。 ■さぶらふ人々-家来たち。■もや-「や」は疑問の係助詞。これに「も」がつくと、疑念の意が強まる。ひょっとしたらお亡くなりになったのだろうか。