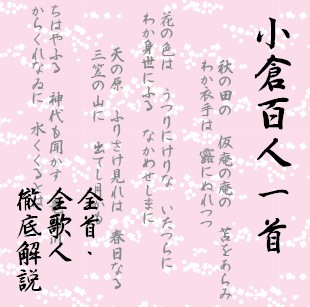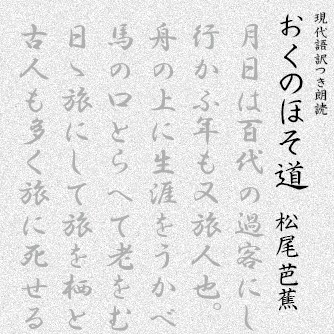帝、竹取りの翁に使いを出し昇天を確かめる
■『竹取物語』の全朗読を無料ダウンロードする
■【古典・歴史】メールマガジン
YOUTUBEで配信中
このことを、帝(みかど)、聞(きこ)しめして、たけとりが家に、御使(おほんつかひ)つかはせたまふ。御使に、たけとりいであひて、泣くことかぎりなし。このことを嘆くに、鬚(ひげ)も白く、腰もかがまり、目もただれにけり。翁、今年(ことし)は五十(いそじ)ばかりなりけれども、物思ひには、かた時になむ、老(お)いになりにけると見ゆ。
御使、仰(おほ)せごととて、翁にいはく、「『いと心苦しく物思ふなるはまことか』と仰せたまふ」。
たけとり、泣く泣く申す。「この十五日になむ、月の都より、かぐや姫の迎へにまうで来(く)なる。尊く問はせたまふ。この十五日は、人々賜(たま)はりて、月の都の人まうで来(こ)ば、捕へさせむ」と申す。御使、帰り参りて、翁の有様申して、奏しつることども申すを、聞(きこ)しめして、のたまふ、「一目(ひとめ)見たまひし御心(みこころ)にだに忘れたまはぬに、明(あ)け暮(く)れ見慣(みな)れたるかぐや姫をやりて、いかが思ふべき」。
現代語訳
このことを帝がお聞きになられて、たけとりの家へ使いをお出しになられた。爺さんは御使者に会い、いつまでも泣いている。このことを嘆くのが原因で、爺さんは鬚も白くなり、腰も曲り、そのうえ目もただれてしまった。じいさんは今年で五十近くであったけれども、かぐや姫と別れる苦しみのために、瞬時に老けてしまったように見える。
勅使、帝の仰せごとであるとして、じいさんに言うには、「たいそう気の毒に、物思いにふけっているというのは本当か」とおっしゃる。
たけとりのじいさんが泣く泣く申しあげる。「この十五日に、月の都から、かぐや姫を迎えるために参り来るとのことです。恐れ多くもお訊ねくださいました。この十五日には、ご家来をお遣わしいただき、月の都人が参り来たなら、捕らえさせとう存じます」と申しあげる。
勅使、帰参して、じいさんのようすを帝にご報告なさいます。また、じいさんの依頼事を申しあげますと、それをお聞きになり、おっしゃいます。「人目見ただけの心にも忘れることができないのに、明け暮れ見慣れているかぐや姫を月にやったら、翁はどう思うだろうか」。
語句
■このことを嘆くに-「このこと」は姫昇天のこと。 ■五十ばかり-「いそ」は五十。「ばかり」は、ぐらい、ほどの意。「ち」は「一つ」、「二つ」の「つ」と同じで、序数詞。翁の年齢は、前の「貴公子たちの求婚」のところは「年七十(ななそじ)に余りぬ」とあって相違している。■もの思ふには-「に」は、時を示す格助詞。この上に「時」を補って訳すとよい。心苦しく-見ているとこちらが心苦しくなる意で、「気の毒に」と訳す。■物思ふなるは-「なる」は伝聞。世間の噂を聞くに、物思うということだがそれはの意。次の「まうで来なる」の「なる」も同じく伝聞。 ■たふとく問わせたまふ-ひとつの慣用表現で、「よくぞ聞いてくださいました」の意。■帰り参りて-「参る」は、宮中に参内する意で、「まかる」の反対語。 ■奏しつることども-翁が帝にといって奏上したことなど、の意。帝には「奏す」、皇后・皇太子には「啓(けい)す」という。■一目見たまひし御心-「たまひ」「御」のように、天皇の場合は、ご自身に尊敬語を用いられる。これを「自称敬語」とか「自尊敬語」と呼ぶ。帝は以前に姫に求婚したため、一度お会いになっていて、ここはそれを「一目見たまひし…」と仰せになっているのである。■やりては-「やる」は行かせる、手放してやるの意。■いかが思ふべき-「いかが…べき」は副詞の呼応。簡単文。
≪帝、かぐや姫の昇天をはばもうと兵をだす≫
かの十五日、司々(つかさつかさ)に仰(おほ)せて、勅使(ちょくし)、中将高野(ちゅうじゃうたかの)のおほくにという人を指(さ)して、六衛(ろくゑ)の司(つかさ)あはせて、二千人の人を、たけとりが家につかはす。家にまかりて、築地(ついぢ)の上に千人、屋(や)の上に千人、家の人々多かりけるにあはせて、あける隙(ひま)もなく守らす。この守る人々も、弓矢を帯(たい)してをり。屋の内には、媼(おうな)どもを、番(ばん)に下りて守らす。
媼、塗籠(ぬりごめ)の内に、かぐや姫を抱(いだ)かへてをり。翁も、塗籠の戸鎖(さ)して、戸口にをり。翁のいはく、「かばかりまもる所に、天の人にも負けむや」といひて、屋の上にをる人々にいはく、「つゆも、物(もの)、空に駆けらば、ふと射殺(いころ)したまへ」。守る人々のいはく、「かばかりして守る所に、かはほり一つだにあらば、まづ射殺(いころ)して、外にさらさむと思ひはべる」といふ。翁、これを聞きて、たのもしがりをり。
これを聞きて、かぐや姫いふ。「鎖(さ)し籠(こ)めて、守り戦ふべきしたくみをしたりとも、あの国の人をえ戦はぬなり。弓矢して射られじ。かく鎖し籠めてありとも、かの国の人来(こ)ば、みなあきなむとす。あひ戦はむとすとも、かの国の人来(き)なば、猛き心つかふ人も、よもあらじ」。
翁のいうやう、「御迎へに来(こ)む人をば、長き爪して、まなこをつかみつぶさむ。さが髪(かみ)をとりて、かなぐり落とさむ。さが尻(しり)をかきいでて、ここらの朝廷人(おほやけびと)に見せて、恥(はぢ)を見せむ」と腹立ちをり。
かぐや姫のいはく、「声高(こわだか)になのたまひそ。屋の上にをる人どもの聞くに、いとまさなし。いますかりつる心ざしどもを、思ひも知らで、まかりなむずることの口惜しうはべりけり。長き契りのなかりければ、ほどなくまかりぬべきなめりと思ひ、悲しくはべるなり。親たちのかへりみを、いささかだに仕うまつらでまからむ道もやすくもあるまじきに、日ごろも、いでゐて、今年(ことし)ばかりの暇(いとま)を申しつれど、さらにゆるされぬによりてなむ、かく思ひ嘆きはべる。
御心(みこころ)をのみ惑(まと)はして去りなむことの悲しく堪(た)へがたくはべるなり。かの都(みやこ)の人は、いとけうらに、老(お)いをせずなむ。思ふこともなくはべるなり。さる所へまからむずるも、いみじくはべらず。老ひおとろへたるさまを見たてまつらざらむこそ恋しからめ」といへば、翁(おきな)、「胸いたきこと、なのたまひそ。うるはしき姿したる使(つかひ)にも、障(さは)らじ」と、ねたみをり。
現代語訳
その十五日に、帝は、それぞれの役所にご命令になられて、勅使に、中将高野大国を任命して六衛の役所合わせて二千人の人を、竹取りの家に派遣される。家に到着して、竹取りのじいさんの家の土堀の上に千人、建物の上に千人、じいさんの家の使用人などがもともと多かったのにあわせて、あいている隙間もないほどに守らせる。この使用人たちも兵士と同じく弓矢を持って武装している。その一部を建物の上からおろし、建物の中では、当番として、おんなたちを守らせる。
ばあさんは、塗籠の中で、かぐや姫を抱え、じっと座っている。じいさんも、塗籠の戸に鍵をかけて、戸口に座っている。じいさんが言うには、「こんなふうに守っているのだから、天の人にも負けるはずがない」と言って、建物の上にいる人々に言うには、「ちょっとでも、物が空を飛んだら、さっと射殺してくだされ」。守る人々が言うには、「このようにして守っている所で、蝙蝠一匹なりともいたならば、まっさきに射殺して、みせしめとして外にさらしてやろうと思っていますよ」と言う。爺さんはこれを聞き、頼もしく思いながら控えている。
これを聞いて、かぐや姫が言う、「戸を閉めて、守り戦う準備をしたところで、あの月の国の人と戦うことはできません。弓矢をもってしても射ることができないでしょう。このように、鍵をかけていても、あの月の国の人が来たなら、みなしぜんにあいてしまうでしょう。戦い合おうとしても、あの国の人が来たならば、勇猛心を振るう人も、まさかありますまい」。
じいさんが言うことには、「お迎えに来る人を、長い爪をもって、目の玉をつかみつぶしてやろう。そいつの髪をつかんで、かなぐり落としてやろう。そいつの尻をまくりだして、ここらに居る朝廷の人に見せて、恥をかかせてやろう」と腹を立てて、座っている。
かぐや姫の言うには、「大きな声でおっしゃいますな。建物の上に居る人たちが聞いたら、たいそうみっとみないことですよ。あなた様方のこれまでのご愛情をわきまえもせず、出て行ってしまうことが残念でございます。前世からの宿縁が無かったために、このように、まもなく、出て行かなければならないのだと思い、悲しんでいるのです。両親へのお世話を、少しも、いたさないまま出かけてしまう道中であれば、当然、安らかではありますまいから、日ごろも、縁側に出て、月の国の王に、せめて今年だけでもと、休暇の延長をお願いしましたが、まったく許されず、このように、嘆き悲しんでいるのでございます。
ご両親様の御心ばかりを惑わせて去ってしまうことが、悲しくて堪えがたいのでございます。あの都の人は、とてもすばらしく、老いもいたしません。また、悩み事もないのです。でも、そのような所へ行こうとしていますのも、いまの私にはうれしくはありません。ご両親の老い衰えなさるようすを見てさし上げられないとしたら、それこそ後髪を引かれる思いでしょう」
「胸が痛くなるようなことをおっしゃいますな」どんなに立派な姿をした天の使者が来ても差しさわりはないでしょうから」と恨み怒っている。
語句
■かの-すでに話題に上ったものごとをさす。その。例の。■指す-任命する ■中将-他の参考文献には「少将」とある。だが、後で4か所出てくる「中将」と同一人物と考えられるので、ここも「中将」と改めた。「中将」を「少将」と誤写した例、あるいは「少将」を「中将」と誤写した例は、数多い。中将は近衛府の中将。なお、高野氏は宝亀年中(七七〇~七八一)に和(やまと)氏が改姓したもの。ほかの登場人物のように天武・持統・文武の時代と異なるが、やはり古い時代に活躍した一族ではある。■六衛-令制では、五衛府(衛門府、左右衛士府、左右兵衛府)であったが、元明天皇の慶雲四年(七〇七)授刀舎人寮がおかれ、六衛府の基礎が作られた。しかし、そこの役人は授刀頭などと呼ばれていて、ここに言う「少将」などという呼称はない。聖武天皇の神亀五年(七二八)に置かれた中衛府は大将・少将などがあり、近衛府が誕生した天平神護元年(七六五)以前にも「少将」とか「六衛府」という呼称はあったことになる。なお、平安時代の六衛府は左右の近衛府、左右の衛門府、左右の兵衛府。これが定められたのは、弘仁二年(八一一)十一月であるから、『竹取物語』が成立したのはそれ以後だという。■媼ども-底本「女ども」。「媼」は本来「おむな」だったので、「女」と表記された。■番に下りて-番人として屋根などから降りて守らせる。
■塗籠-周囲を壁で塗り込め、明り取りの窓と出入り口しかない部屋。物置などに用いる。 ■抱かへてをり-「いだく」に上代に使われた継続の助動詞「ふ」がついてできた「いだかふ」だと説かれるが、その「ふ」は四段活用。ここは、下二段型の活用であり、不審。■つゆも-副詞の形。ちょっとでも。 ■かはほり-こうもり(蝙蝠)の古称。
■あきなむとす-「あきなむ」を強めたもの。 ■人を-「たたか(戦)ふは語源的に「叩(たた)く」の未然形に継続の助動詞「ふ」が接続したものであるから、「…をたたく」「…をたたかふ」でよい。■来なば-「な」は完了の助動詞「ぬ」の未然形。「ば」がついて仮定。■よも-副詞。「じ」と呼応して、「まさか…あるまい」の意。
■さが-そいつの。
■まさなし(正無し)-無作法だ。聞き苦しい。■いますかり-「あり」の尊敬語。■つる-完了の助動詞「つ」の連体形。■いましかりつる心ざし-今までのご愛情。■長き契りの-この世に長くごいっしょするという前世からの宿縁が無いので。■かへりみ-(願み)。世話をすること。■やすくもあるまじきに-心安らかでなかろうゆえに。■いとま-休暇。天へ帰ることを猶予してほしいと。■さらに-あとに打消しを伴い「まったく…ない」の意。
■老いをせずなむ-「老いをせずなむある」の約。■思ふこともなく-物思いもない。悩み事もない。■さる所-「いとけうらに、老いもせず」「思ふこともない」月の都に。■まからむずる-「まからむとする」の略。「まかる」は「行く」の謙譲語。「翁」を尊んだ言い方。■いみじく-たんに程度のはなはだしいことを表す場合が多いが、ここでは、本義に近い、「喜ばしい」「嬉しい」の意。■恋し-悲しの誤写ともとれるが? ■と言ひて-ここで文が終止しないのは不自然である。別の本には、この次に「泣く」という語があるので、本来はそのような語があったと思われる。■うるはし-端麗な中国風の美しさの形容に用いられる。天人は中国風のイメージの服装をしていたのだろう。 ■ねたむ-現代語と異なり、「恨み怒る」こと。
≪迎えの天人来たり、かぐや姫昇天≫
かかるほどに、宵(よひ)うちすぎて、子(ね)の時ばかりに、家のあたり、昼(ひる)の明(あか)さにも過ぎて、光(ひか)りたり。望月(もちづき)の明さを十(とを)合(あは)せたるばかりにて、在(あ)る人の毛の穴さへ見ゆるほどなり。大空より、人、雲に乗りて下(お)り来(き)て、土より五尺ばかり上がりたるほどに立ち連ねたり。内外(うちと)なる人の心ども、物におそはるるやうにて、あひ戦はむ心もなかりけり。からうじて、思ひ起こして、弓矢をとりたてむとすれども、手に力もなくなりて、萎(な)えかかりたる、中(なか)に、心さかしき者、念(ねん)じて射(い)むとすれども、ほかざまへいきければ、荒れも戦はで、心地(ここち)ただ痴(し)れに痴(し)れて、まもりあへり。
立てる人どもは、装束(さうぞく)のきよらなること物にも似ず。飛ぶ車一つ具(ぐ)したり。羅蓋(らがい)さしたり。その中に、王(わう)とおぼしき人、家に、「みやつこまろ、まうで来(こ)」といふに、孟(たけ)く思ひつるみやつこまろも、物に酔(ゑ)ひたる心地して、うつぶしに伏(ふ)せり。
いはく、「汝(なんぢ)、幼(をさな)き人。いささかなる功徳(くどく)を、翁つくりけるによりて、汝(なんぢ)が助けにとて、かた時のほどとてくだししを、そこらの年ごろ、そこらの黄金(こがね)賜(たま)ひて、身を変へたるがごとなりにたり。かぐや姫は罪をつくりたまへりければ、かく賤(いや)しきおのれがもとに、しばしおはしつるなり。罪の限(かぎ)りはてぬれば、かく迎ふるを、翁は泣き嘆く。あたはぬことなり。はや返したてまつれ」といふ。
翁答へて申す、「かぐや姫をやしなひたてまつること二十余年になりぬ。『かた時』とのたまふに、あやしくなりはべりぬ。また異所(ことどころ)にかぐや姫と申す人ぞおはしますらむ」といふ。「ここにおはするかぐや姫は、重き病(やまひ)をしたまへば、えいでおはしますまじ」と申せば、その返りごとはなくて、屋の上に飛ぶ車を寄せて、「いざ、かぐや姫、穢(きたな)き所に、いかでか久しくおはせむ」といふ。立て籠めたる所の戸、すなはちあきにあきぬ。格子(かくし)どもも、人はなくしてあきぬ。媼(おうな)抱(いだ)きてゐたるかぐや姫、外(と)にいでぬ。えとどむまじければ、たださし仰(あふ)ぎて泣きをり。
たけとり心惑ひて泣き伏せる所に寄りて、かぐや姫いふ、「ここにも、心にもあらでかくまかるに、のぼらむをだに見送りたまへ」といへども、「なにしに、悲しきに、見送りたてまつらむ。我を、いかにせよとて、捨ててはのぼりたまふぞ。具して率ておはせね」と、泣きて伏せれば、御心惑ひぬ。「文を書きおきてまからむ。恋しからむをりをり、取りいでて見たまへ」とて、うち泣きて書く言葉は、
この国に生まれぬるとならば、嘆かせたてまつらむほどまで侍(はべ)らん。過ぎ別れぬること、かへすがへす本意(ほい)なくこそおぼえはべれ。
脱ぎ置く衣(きぬ)を形見(かたみ)と見たまへ。月のいでたらむ夜(よ)は、見おこせたまへ。見捨てたてまつりてまかる、空よりも落ちぬべき心地する。と、書き置く。
天人(てんにん)の中に、持たせたる箱あり。天(あま)の羽衣入(はごろもい)れり。またあるは、不死(ふし)の薬(くすり)入れり。一人の天人いふ、「壺(つぼ)なる御薬たてまつれ。穢(きたな)き所の物きこしめしたれば、御心地悪(あ)しからむものぞ」とて、持(も)て寄りたれば、いささかなめたまひて、すこし、形見とて、脱ぎ置く衣(きぬ)に包まむとすれば、在(あ)る天人包ませず。御衣(みぞ)をとりいでて着せむとす。
その時に、かぐや姫、「しばし待て」といふ。「衣(きぬ)着せつる人は、心異(こと)になるなりといふ。物一言(ひとこと)いひ置くべきことありけり」といひて、文(ふみ)書く。天人、「遅し」と心もとながりたまふ。
かぐや姫、「物知らぬこと、なのたまひそ」とて、いみじく静かに、朝廷(おほやけ)に御文奉(たてまつ)りたまふ。あわてぬさまなり。かくあまたの人を賜(たま)ひて、とどめさせたまへど、許さぬ迎へまうで来(き)て、取り率(ゐ)てまかりぬれば、口惜しく悲しきこと。宮仕(みやづか)へ仕(つか)うまつらずなりぬるも、かくわづらはしき身にてはべれば。心得(こころえ)ず思(おぼ)しめされつらめども。心強くうけたまはらずなりにしこと、なめげなるものに思しめしとどめられぬるなむ、心にとまりはべりぬる。
とて、今はとて天の羽衣着るをりぞ君をあはれと思ひいでける
とて、壺(つぼ)の薬そへて、頭中将(とうのちゅうじゃう)呼び寄せて奉らす。
中将に、天人とりて伝ふ。中将とりつれば、ふと天の羽衣うち着せたてまつりつれば、翁を、いとほし、かなしと思しつることも失せぬ。この衣着つる人は、物思ひなくなりにければ、車に乗りて、百人ばかり天人具(ぐ)してのぼりぬ。
現代語訳
こうしているうちに、宵も過ぎ、夜中の十二時ごろになると、家の周辺が、昼の明るさ以上に光り輝いた。満月の明るさを十も合わせた明るさで、そこに居る人の毛穴さえ見えるほどであった。大空から、人が、雲に乗って降りて来て、地面から五尺ほどあがった所に立ち並んだ。それを見て、家の内外に居る人たちは、物の怪に襲われたような気持ちになって、戦い合おうというような心もなくなったのである。かろうじて、思い起こし、弓を立て、矢をつがえようとするが、手の力もなくなり、だらっとしている。その中で気丈な者が、我慢して射ようとするが、的外れの方向へ飛んでいくので、荒々しく戦うこともなく、気持ちがぼんやりとして、ただ、お互いに顔を見合わせるばかりであった。
地上から五尺ほども上に立っている人たちは、その衣装のすばらしいこと、たとえようもない。飛ぶ車を一つ、ともなっている。その車には、薄絹を張った天蓋がさしかけてある。その中の王と思われる人が、家に向かって、「造麿呂(みやつこまろ)出てこい」と言うのに、猛々しく構えていたじいさんも、何かに酔ったようになって、うつぶせに伏してしまった。
天人の王の言うには、「汝、未熟者よ。わずかばかりの善行を、お前が為したことによって、お前の助けにしようとして、わずかな間と思って、姫を下界に下したのだが、長い年月の間、たくさんの黄金(こがね)を賜って、お前は生まれ変わったように金持ちになった。かぐや姫は天上で罪をなされたので、このように賤しいお前の所にしばらくいらっしゃったのである。姫は罪の償いの期間が終わったので、こうしてお迎えするのをお前は泣き悲しむ。が泣き騒いでも今更どうすることもできないのだ。早く姫を出し申せ」と言う。
じいさんが答えて申しあげるには、「かぐや姫を養い育てて二十余年が過ぎました。『わずかな時間』とおっしゃいましたので、疑わしくなりました。また別の所にかぐや姫という申す人がいらっしゃるのでしょうよ」と言う。「ここにいらっしゃるかぐや姫は重い病気にかかっていらっしゃるので、外にお出にはなれないでしょう」と申しあげると、それへの返事はなく、建物の上に飛ぶ車を寄せて、「さあ!かぐや姫、こんな穢れたところに、どうして、長い間いらっしゃるのですか」と言う。姫を閉じ込めてあった塗籠の戸も、即座にすべてが開いてしまう。閉じてあった格子なども、人があけないのにしぜんにあいてしまう。ばあさんが抱いていたかぐや姫も外に出てしまう。とどめることができないので、ばあさんは、ただそれを仰ぎ見て泣いている。
竹取りのじいさんが、心を乱して泣き伏している所に寄って、かぐや姫が言う、「私自身も心ならずも、このように行ってしまうのですから、せめて昇天するのを見送ってください」と言うが、じいさんは、「なんのためにお見送り申しあげるのですか、悲しいので、見送りすることはできません。私を、いったいどうせよというつもりで、捨てて昇天なさるのですか。一緒に連れて行ってください」と泣いて、伏しているので、かぐや姫の御心は乱れてしまう。かぐや姫は「書置きをしてお暇(いとま)しましょう。私を恋しく思い出されたとき取り出して読んでください」と言って、泣きながら書く言葉は、
私が、この人間の国に生まれたのならば、ご両親を嘆かせ奉らぬ時まで、ずっとお仕えすることもできましょう。ほんとに去って別れてしまうことは、かえすがえ すも不本意に思われます。脱いでおく私の着物を形見としていつまでもご覧ください。月が出た夜は、私の住む月をそちらから見てください。それにしても、ご両 親を見捨て申し上げるような形で出て行ってしまうのは苦しく、空から落ちそうな気がいたします。
と書き置きをする。
天人の中の一人に持たせてある箱がある。その中には天の羽衣が入っている。また、別の箱には不死の薬が入っている。一人の天人が言うには、「壺に入っている薬をお飲みください。穢い地上の物をお召し上がりになられたので、ご気分が悪いことでしょうよ」と言って、薬を持って傍に寄ると、姫は少しお舐めになって、少しの薬を形見として、脱いで残しておく着物に包もうとすると、そこにいる天人が包ませない。天の羽衣を取り出して、姫に着せようとする。
その時に、かぐや姫が、「しばらく待て」と言う。「天の羽衣を着た人は、心が、常の人とは変わってしまうということです。一言(ひとこと)言っておかねばならぬことがあるのでした」と言って手紙を書く。天人が「遅い」といっていらいらなさる。かぐや姫は「わからぬことをおっしゃるな」と言って、はなはだ静かに、帝にお手紙を書き申しあげる。あわてず落ち着いたようすである。
このように、たくさんのご家来をお遣わしいただき、私をお留めなされようとなされましたが、避けられない迎えが参り、私を捕らえて連れてゆきますことゆえ、口惜しく悲しいことです。おそばにお仕え申しあげられなくなってしまいましたのも、このように常人とは異なった面倒な身の上ゆえのことです。わけのわからぬこととお思いになられたことでしょうが、私が強情に命令にしたがわなかったことにつき、無礼な奴めとお心におとどめなさっていることが、今も心残りになっております。と書いて、
今はとて天の羽衣着るをりぞ君をあはれと思ひいでける
(今はもうこれまでと、天の羽衣を着るときになり、あなた様のことをしみじみとおもいだしているのでございます。)
と歌をつけくわえて、その手紙に、壺の中に入った不老の薬を添えて、頭中将を呼び寄せて、帝に献上させる。まず、かぐや姫の手元から天人が受け取って、中将に手渡す。中将が壺を受け取ったので、天人が、かぐや姫にさっと天の羽衣を着せてさしあげると、じいさんを、「気の毒だ、不憫だ」と思っていた思いも消えてしまった。この天の羽衣を着た人は、物思いが消滅してしまうので、そのまま飛ぶ車に乗って、百人ほどの天人を引き連れて月の世界へ昇ってしまう。
語句
■かかるほどに-「かかる」は「かく・ある」の詰まった形。「ほどに」は時間の経過を示す語。■子の時-午前零時を中心とした二時間。 ■望月-陰暦の十五日に出る満月。とくに仲秋の満月。■明さ-形容詞「明(あか)し」の語幹に、接尾語「さ」がついてできた名詞。「高さ」「強さ」などと同じ。■ 五尺-約150センチメートル ■内外なる人-「なる」は所在を示す。「内」には、竹取りの翁と夫婦と召使の女たちが居り、「外」には、武装した二千の軍勢と家人たちが「あけるひまもなく」守備についているのである。■物におそはるるようにて-「もの」は「物の怪(もののけ)」の「物」で、精霊をさす語。ここは、うなされるような気持ちになる意。■あひ戦はむ-「あひ」は出会っての意。ただし、接頭語とする説もある。■思ひ起こして-「思ひ」を「奮い起こして」の意。■弓矢をとり立てむ-弓を手にとって立て、それに矢をつがえようとするの意。■萎えかかりたり-「萎(な)ゆ」はヤ行下二段活用で、草木などがしおれる胃。「かかる」は物に寄りかかるの意。■心さかしきもの-「さかし」は①かしこい、②しっかりしている、などの意。ここは②の例。 ■念じて-「念ず」は、①我慢する、②祈る、などの意。ここは、①の例。 ■ほかざま-的外れの方向。そっぽ。■あれも戦はで-「あれ」は「荒れ」で荒々しく振る舞う、の意。■ただ痴れに痴れて-「ただ」は、ひたすら、ひたむきに、の意。「しれ」は、魂がうつろになってぼんやりすること。格助詞「に」を間に同じ動詞を重ねると、動詞の意味を強調する。「ただ開(あ)きに開きぬ」と同じ。■まもりあへり-「まもる」は、「目(ま)」・守(も)る」で、人が互いに見つめ合う意。守備の人々が互いに見つめ合うとする説と、天人たちを見つめるとする説があるが、ここでは前者を採った。 ■うつぶしに伏す-うつぶせになる。
■羅蓋-「羅」は薄絹。羅を円形に張り、周囲に房などをつけ、貴人の後ろからさしかける豪華な日よけ傘。 ■その中に-「その車の中に」と解く説と、「立てる人どもの中に」と解く説とがあるが、ここでは、「その車の中に」とする。■王と思しき人-月からの使者一行の長官で、月世界の王ではない。「おぼしき」といっているのは、天人界のことであるから、地上の人間にはよくわからないという意を表す。
■まうで来-「まうで」は「参り出で」のつまった語。 ■孟く-勇猛に。たけだけしく。■汝、幼き人-「汝」と「幼き人」は同格。ともに竹取りの翁に対する呼びかけ。「幼き人」は、心をさなき愚かな人の意。一説には、「幼き人」を「かぐや姫」ととり、「幼き人(ソレヲ)…下ししを」と続く文脈だとするものもある。
■功徳-仏教語で、善行の意。 ■下ししを-天上界から姫を下したがの意。「を」は逆説の意の接続助詞。■そこらの-「ここだ」「ここだく」「そこら」などは皆、同じ意味の副詞で、①数の多い、②程度のはなはだしい、などの意。
■金たまひて-「たまひ」は「お与えになる」の尊敬語動詞。黄金を天が翁にお与えになる、の意。■身を変えたるがごと-「ごと」は「ごとく」に同じ。翁が百万長者になったことをさす。■罪の限り-罪の償いをするのに必要な期間。罪の期限。別に「罪のありったけ」とする説もある。■あたはぬことなり-姫をいつまでも留めておこうとしても、それは不可能なことだ、の意。道理に合わないことだ、の意とする説もある。■かた時とのたまふに-天上の時間と地上の時間の相違する矛盾を追及。天人の言葉尻を捕らえて抗弁するのである。
■ここ-「ここ」は自称。自分自身。■なにしに-なんのために。「見送りたてまつらむ」に続く。■具して率(ゐ)ておはせね-一緒に連れて行ってください、の意。■御心-かぐや姫の心。■過ぎ別れぬる-滞在期間が過ぎて別れること。■本意なくこそ-意のままでない心苦しさを感じております。しかし、どうしようもありません、の意。「こそ…已然形」の結びは、逆説的余情で、「…デハアルケレド」という気持ちを表す。■見おこせたまへ-かぐや姫はすでに天上にいる気持ちで発言している。「見おこす」は、視線を自分の方へ送ってよこす。■まかる、空よりも-この「まかる」は連体形。下に体言「事」が省略されているが主格になっている。■心地する-「心地する」で連体形。連帯止めによる余情表現。
■天の羽衣-天上の人として天に昇るために必要な衣装。羽衣説話の根幹となる重要な小道具。■御薬たてまつれ-この「たてまつれ」は飲むことの意。かなり強い敬語。■きこしめたければ-これも強度の敬語。食べること。 ■取り率て-「取り」は、無理やり連れてゆくようすを表す。■壺の薬添えて-壺に入っている薬を手紙に添えて。■頭中将-「頭」は蔵人所の頭を兼ねた近衛中将。 ■奉らす-天皇にたてまつらせる。■天人とりて伝ふーかぐや姫の周りはすでに天人に囲まれているのである。■ふと-さっと。すばやく。■ふと天の羽衣うち着せたてまつれば-かたわらにいた天人が。■かなし-現代語と違って、「いとおしい」「不憫だ」の意。
-