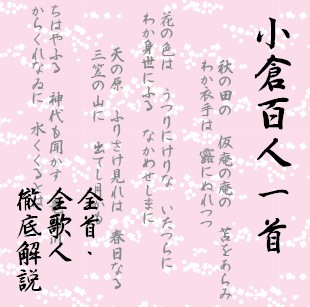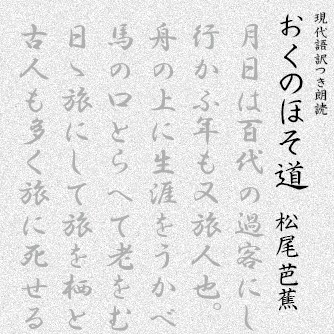石上(いそのかみ)の中納言と燕(つばくらめ)の子安貝(こやすがい)
■『竹取物語』の全朗読を無料ダウンロードする
■【古典・歴史】メールマガジン
YOUTUBEで配信中
≪石上の中納言、燕の子安貝を取らんと計画≫
中納言石上麿足(ちゅうなごんいそのかみのまろたり)の、家に使はるる男(をのこ)どものもとに、「燕(つばくらめ)の、巣(す)くひたらば告げよ」とのたまふを、うけたまはりて、「何(なに)の用(よう)にかあらむ」と申す。
答へてのたまふやう、「燕の持(も)たる子安貝(こやすがひ)を取らむ料(れう)なり」とのたまふ。男ども、答へて申す、「燕をあまた殺して見るだにも、腹(はら)になき物なり。ただし、子をうむ時なむ、いかでかいだすらむ、侍(はべ)んなる」と申す。「人だに見れば、失(う)せぬ」と申す。
また、人の申すやう、「大炊寮(おほひづかさ)の飯炊(いひかし)く屋(や)の棟(むね)に、つかの穴ごとに、燕は巣をくひはべる。それに、まめならむ男ども率(ゐ)てまかりて、足座(あぐら)を結(ゆ)ひあげて、うかがはせむに、そこらの燕(つばくらめ)子うまざらむやは。さてこそ、取らしめたまはめ」と申す。
中納言よろこびたまひて、「をかしきことにもあるかな。もつともえ知らざりけり。興(きょう)あること申したり」とのたまひて、まめなる男ども二十人ばかりつかはして、麻柱(あななひ)にあげ据ゑられたり。
殿(との)より、使(つかひ)ひまなく賜(たま)はせて、「子安(こやす)の貝(かひ)取りたるか」と問はせたまふ。燕も、人のあまたのぼりゐたるに怖(お)じて巣にものぼり来(こ)ず。
かかる由(よし)の返(かへ)りごとを申したれば、聞きたまひて、「いかがすべき」と思(おぼ)しわづらふに、かの寮(つかさ)の官人(くゎんにん)くらつまろと申す翁(おきな)申すやう、「子安貝(こやすがひ)取らむと思(おぼ)しめさば、たばかりまうさむ」とて、御前(おほんまえ)に参りたれば、中納言、額(ひたひ)を合わせて向ひたまへり。
くらつまろが申すやう、「この燕の子安貝は、悪(あ)しくたばかりて取(と)らせたまふなり。さては、え取らせたまはじ。麻柱(あななひ)におどろおどろしく二十人の人ののぼりてはべれば、あれて寄りもうで来(こ)ず。せさせたまふべきやうは、この麻柱(あななひ)をこほちて、人みな退(しりぞ)きて、まめならむ人一人を、荒籠(あらこ)に乗せ据(す)ゑて、綱(つな)を構へて、鳥の子うまむ間(あひだ)に、綱を吊(つ)り上(あ)げさせて、ふと子安貝(こやすがひ)を取らせたまはむなむ、よかるべき」と申す。中納言(ちゅうなごん)のたまふやう、「いとよきことなり」とて、麻柱をこほち、人みな帰りまうで来(き)ぬ。
中納言、くらつまろにのたまはく、「燕(つばくらめ)は、いかなる時にか子うむと知りて、人をば上(あ)ぐべき」とのたまふ。くらつまろ申すやう、「燕(つばくらめ)子生まむとする時は、尾を捧(ささ)げて、七度(しちど)めぐりてなむ生み落とすめる。さて七度めぐらむをり、引きあげて、そのをり、子安貝は取らせたまへ」と申す。中納言よろこびたまひて、よろづの人にも知らせたまはで、みそかに寮(つかさ)にいまして、男どもの中にまじりて、夜を昼になして取らしめたまふ。
くらつまろのかく申すを、いといたくよろこびて、のたまふ、「ここに使はるる人にもなきに、願ひをかなふることのうれしさ」とのたまひて、御衣(みぞ)ぬぎてかたづけたまうつ。
「さらに、夜(よ)さり、この寮(つかさ)にもうで来(こ)」とのたまうて、つかはしつ。
現代語訳
中納言石上麿足(ちゅうなごんいそのかみのまろたり)が、その家に使われる家来たちのもとに、「燕が巣を作ったら知らせよ」とおっしゃるのを、うけたまわって、「何に使われるのですか」と申し上げる。
中納言が答えておっしゃるには、「燕が持っている子安貝(こやすがい)を取ろうとするためだ」とおっしゃる。
家来たちが答えて申し上げる。「燕をたくさん殺して見る時でさえ、その腹の中にはございません。ただし、子を産む時に、どうやってだすのでしょうか、腹に抱えているようでございます」と申し上げる。また、「人が少しでも見れば、なくなってしまいます」とも申し上げる。
また、他の人が申し上げるには、「大炊寮(おほひづかさ)の飯(めし)を炊(た)く建物の棟(むね)にある、束柱(つかばしら)の穴ごとに、燕は巣を作っております。そこに、忠実だと思われる家来たちを連れて行って、足場を高く組み、そこに上げて、のぞかせれば、たくさんの燕が子を産んでいるはずです。そのようにしてはじめて取らせることがおできになりましょう」と申しあげる。中納言は、お喜びになって、「おもしろい発言だなあ。少しも知らなかったよ。素晴らしいことを言ってくれた」とおっしゃって、忠実な家来たち二十人ほどを大炊寮につかわして、高い足場の上にのぼらせておかれた。
さて、中納言は、御殿から、使者をひっきりなしに派遣されて、「子安貝はとったか」とお聞かせになる。燕も、人が多数のぼっているのを怖がって、巣にも上がってこない。このような趣の返事を中納言に申しあげたところ、お聞きになられて、「どうしたらよいだろう」とお悩みになっているときに、その大炊寮の官人で、くらつまろという名の翁(おきな)が申しあげるには、「子安貝を取ろうお思ひならば作戦をさしあげましょう」と言って、御前に参上したので、中納言は、身分差を超えて直接お会いになり、額(ひたい)を合わせるようにして対面なさった。
くらつまろが申すには「いまの燕の子安貝の取り方は、悪い作戦で取っていらっしゃるようです。これでは、お取りになれないでしょう。高い足場に、仰々しく二十人もの人がのぼっていますから、燕は遠のき、そばへ寄ってこないのです。
私がお教えする、なさるべき方法は、この高い足場を壊し、人もみな退いて、忠実だと思われる人、一人を荒籠(あらこ)に乗せてすわらせ、すぐに綱を吊り上げることができるように、準備しておいて、鳥が子を産もうとしている間に、綱を吊り上げさせて、籠(こ)を上にあげて、さっと、子安貝をお取らせになるのがよいでしょう」と申しあげる。中納言(ちゅうなごん)がおっしゃるには、「たいへんよい方法だ」とおっしゃって、高い足場をこわし、家来の人々はみなお邸(やしき)へ帰ってきた。
中納言が、くらつまろにおっしゃるには、「燕は、いったいどのような時に子を産むと判断して、人を上にあげたらよいのか」とおっしゃる。くらつまろが申しあげるには、「燕が子を産もうとする時は、尾をさしあげ、七度まわって、卵を産み落とすようです。ですから、そのようにして七度まわるときに、綱のついた荒籠を引き上げて、その瞬間に、子安貝をお取らせなさいませ」と申しあげる。中納言は、お喜びになって、多くの人にはお知らせにならないで、ひそかに大炊寮(おおいづかさ)に出かけられて、家来たちの中にまじって昼夜兼行で、お取らせになる。
中納言は、くらつまろがこのように申しあげたのを、ほんとうにひどくお喜びになって、おっしゃるには、「私の邸で使われている人でもないのに、願いをかなえてくれるのは、ほんとうにうれしい」とおっしゃって、みずから着てこられたご衣装を脱いで褒美としてお与えになった。
「もう一度、夜になったころ、この大炊寮に出頭せよ」とおっしゃって、家へお帰しになる。
語句
■くふ(構ふ)-(鳥などが)巣を作る。■男(をのこ)-仕えている男たち■たら- 助動詞「たり」(完了)の未然形。■ば-(未然形に付いて)順接の仮定条件を表す。…(する)なら。…だったら。■にかあらむ-…であろうか。 [なりたち]断定の助動詞「なり」の連用形「に」+係助詞「か」+ラ変補助動詞「あり」の未然形「あら」+推量の助動詞「む」の連体形「む」[参考]ふつう、「何」という疑問を表す語があるときは「にかあらむ」のように「か」が用いられ、疑問を表す語がなければ「にやあらむ」のように「や」が用いられる。 ■「-やう」(動詞や助動詞の連用形に付いて)…のしかた。…のぐあい。■たる-タリ活用形容動詞の連体形の活用語尾。 ■れう(料)-ため。せい。わけ。
■はべんなる-動詞「あり」「居(を)り」の丁寧語。ございます。あります。おります。「なる」は伝聞の助動詞「なり」の連体形。■大炊寮-宮内省に属し、諸国から運んでくる米や雑穀を納め、かつ、分配する役所であるが、その名称からして、炊飯し分配するのも、その仕事であったのだろう。次にも飯炊く屋とある。■つか(束柱)-梁(はり)と棟木(むなぎ)との間や床の下などに立てる短い柱。束。■まめならむ-忠実な ■あぐら(足座)-高いところへのぼるために材木を組み立てた足場か? ■ゆう(結ふ)-組み立てる■そこら-多くの ■しめたまはめ-「しめ」は助動詞「しむ」の連用形。使役または尊敬の意を持つが、ここの場合はいづれとも解釈できる。
■もつとも-下に打消しの表現を伴って全然、少しもの意。■麻柱(あななひ)-高いところへのぼるための足場。助ける意の「あななふ」の連用型名詞。 ■くらつまろ-大炊寮の倉の番人、というような意味で、洒落て名付けたのであろう。石の鉢を求める人を石作の皇子としたのと同じである。 ■額を合わせて云々-中納言のような身分の高い人は、ふつう、くらつまろ程度の人と直接話をしないのだが、目的のためにはそんなことを言っていられなかったのである。■くらつまろが云々-「が」は「の」と違い、身分の低い者などを卑しめて言う場合に用いる格助詞。■あれて-離れる、遠ざかるの意。■おどろおどろしく-目を脅かすようなさま。おおげさだ。■こほちて-壊して。砕いて。鎌倉時代までは「コホチ」と清音で読んだ。■荒籠-粗く編んだ籠 ■綱を構へて-綱を準備して、綱を荒籠につけ、すぐに荒籠を引き上げられるように準備するのである。 ■まうで-「まうづ」は、身分の高い人の所へ行く意であるから、人々が中納言邸へ帰るのである。■七度めぐりて-燕が産卵の時に七度めぐるというのは作者の創作か。■みそかぬ-「ひそかに」に同じ。■夜を昼になして-夜も昼と同じように働く。■かたづけたまうつ-本来は衣を肩に掛けるという意味。高貴な方から恩賞として衣を賜った時、それを肩に掛けて排舞するのが当時の習いであったので、転じて衣を賜ること自体をいうようになった。貴人が自分の着ているものを脱いでそのまま与えるのは最高の恩賞なのである。■夜さり-「夜になったころ」の意。
≪中納言みずから子安貝を取らんとし、失敗≫
日暮(ひく)れぬれば、かの寮(つかさ)におはして見たまふに、まことに燕(つばくらめ)巣つくれり。くらつまろの申すやうに、尾浮(う)けてめぐるに、荒籠(あらこ)に人をのぼせて、吊り上げさせて、燕の巣に手をさし入(い)れさせてさぐるに、「物もなし」と申すに、中納言、「悪(あ)しくさぐれば、なきなり」と腹立(はらた)ちて、「誰(たれ)ばかりおぼえむに」とて、「我のぼりてさぐらむ」とのたまひて、籠(こ)に乗りて、吊られのぼりてうかがひたまへるに、燕(つばくらめ)尾をささげて、いたくめぐるに合わせて、手をささげてさぐりたまふに、手に平(ひら)める物さはる時に、「我、物にぎりたり。今はおろしてよ。翁、し得たり」とのたまへば、集りて、とくおろさむとて、綱を引きすぐして綱絶ゆるすなはちに、やしまの鼎(かなへ)の上に、のけざまに落ちたまへり。
人々あさましがりて、寄りて抱へたてまつれり。御目(おほんめ)は、白目(しらめ)にて臥(ふ)したまへり。人々、水をすくひ入れたてまつる。からうじて、生きい出(で)たまへるに、また、鼎の上より、手とり足とりして、下げおろしたてまつる。
からうじて、「御心地(みここち)いかが思(おぼ)さるる」と問へば、息の下にて、「物はすこしおぼゆれど、腰なむ動かれぬ。されど、子安貝(こやすがひ)を、ふと握(にぎ)り持(も)たれば、うれしくおぼゆるなり。まづ、紙燭(しそく)して来(こ)。この貝の顔見む」と御ぐしもたげて、御手を広げたまへるに、燕(つばくらめ)のまり置(お)ける古糞(ふるくそ)を握りたまへるなりけり。
それを、見たまひて、「あな、かひなのわざや」とのたまひけるよりぞ、思ふに違(たが)ふことをば、「かひなし」といひける。貝にもあらずと見たまひけるに、御心地も違(たが)ひて、唐櫃(からびつ)の蓋(ふた)の入れられたまふべくもあらず、御腰は折れにけり。中納言は、わらはげたるわざして止(や)むことを、人に聞かせじとしたまひけれど、それを病(やまひ)にて、いと弱くなりたまひにけり。
貝をえ取らずなりにけるよりも、人の聞き笑はむことを日にそへて思ひたまひければ、ただに病(や)み死ぬるよりも、人聞きはづかしくおぼえたまふなりけり。
これをかぐや姫聞きて、とぶらひにやる歌。年を経て浪立ち寄らぬ住の江のまつかひなしと聞くはまことか
とあるを、読みて聞かす。
いと弱き心に、頭(かしら)もたげて、人に紙を持たせて、苦しき心地(ここち)に、からうじて書きたまふ。かひはかくありけるものをわびはてて死ぬる命をすくひやはせぬ
と書きはつる、絶(た)え入(い)りたまひぬ。
これを聞きて、かぐや姫、すこしあはれとおぼしけり。それよりなむ、すこしうれしきことをば、「かひあり」とはいひける。
現代語訳
日が暮れたので、中納言は、例の大炊寮にいらっしゃって、ご覧になると、ほんとうに燕が巣を作っている。くらつまろが申しあげたように、尾を上へあげてまわっているので、家来を荒籠に乗せ、綱で吊り上げさせて、その家来に命じ、燕の巣に手を入れてさぐらせたが、「何もありません」と申し上げるので、中納言は、「さぐり方が悪いからないのだ」と腹を立て、「私以外の誰がわかろうか」と言い、
「私がのぼってさぐろう」とおっしゃって、籠に乗り、綱で吊り上げられて、巣の中をのぞきなさると、燕が尾を上へあげて、ひどくぐるぐるまわっている。それに合せて、手を差し出しておさぐりになると、手に平たい物がさわった。その瞬間、「わしは何かを握った。もうおろしてくれ。やったぜ、じいさん」とおっしゃるので、家来たちが集まって、早くおろそうとして、綱を引っ張りすぎて綱がなくなった瞬間に、八個の鼎(かなえ)の上に、あおむけにお落ちになった。
人々は、あきれて、そばに寄って、抱きかかえ申しあげる。見ると、中納言は、御目(め)は、白目(しろめ)の状態で倒れていらっしゃる。家来たちが、水をすくい入れて飲ませてさしあげる。
やっとのことで生き返られたので、また、鼎の上から、手とり足取りして、下げおろし申しあげる。
「ご気分はいかがでございますか」と問うと、やっとのことで、虫の息で、「意識はすこしあるが、腰が動かない。しかし、子安貝をさっと握って、そのまま持っているから、うれしく思っているのだ、まず、とにかく紙燭(しそく)をつけてこい。この貝の顔を見よう」と、御頭(かしら)をもたげて、御手を広げなさると、それは子安貝ではなく、燕(つばめ)がもらしてそのままあった古糞(ふるくそ)を握っていらっしゃるのであった。
中納言(ちゅうなごん)は、これをご覧になって、「ああ、貝がないことだ」、とおっしゃった時から、期待に反することを「かい(ひ)なし」と言うのである。
貝ではないと、それをご覧になったゆえに、いまではご気分もずっと悪くなり、唐櫃(からびつ)の蓋に中にお入りになれそうもないほど、御腰は折れてしまったのである。
中納言は、子供っぽいことをして、失敗に終わったことを、人に聞かせまいとなさっていたが、結局それが病のもとになって、たいそう衰弱してしまわれた。
貝を取ることができなくなったことよりも、他人がこの話を聞いて、笑うであろうことを、日がたつにつれてだんだんと気になさるようになったので、ただふつうに病気で死んでしまうよりも、外聞が恥ずかしいとお感じになるのであった。
このようすをかぐや姫が聞いて、お見舞いに送る歌、
年を経て浪立ち寄らぬ住の江のまつかひなしと聞くはまことか
(長らく、お立ちよりにもなりませんが、浪も立ち寄らない住吉の浜の松ならぬ、待つ甲斐もない、つまりあの貝もない、と噂に聞くのは、ほんとうでしょうか)
と書いてあるのを、おそばの家来が読んで聞かせる。
中納言は、たいそう気力は弱っていたが、頭をもたげて、人に紙を持たせて、苦しい気分で、やっとのことお書きになる。
かひはかくありけるものをわびはてて死ぬる命をすくひやはせぬ
(貴方は貝もないとおっしゃるが、このようにお見舞いをいただいた甲斐はありましたよ。この「甲斐」ならぬ「匙(かい)」で、苦しみぬいて死ぬ私の命をすくい取ってはくださいませんか)
と書き終えると、息が絶えてしまわれた。これを聞いて、かぐや姫は、すこし気の毒にお思いになった。そのことから、すこしうれしいことを「かい(ひ)あり」と言うようになったのである。
語句
■日暮れぬれば-完了の助動詞「ぬ」の已然形+確定の接続助詞「ば」。日が暮れたので。■まことに-くらつまろの言葉そのままに。「真言」の意か。必ず先に述べられている言葉を受ける。■「誰(たれ)ばかりおぼえむに」-誰だけが腕に覚えがあるのだろうか。誰もできはしない。「おぼえ」は「おぼゆ」の未然形。■ささぐ-高くあげる ■平める-自動詞「平らむ」の已然形に助動詞「り」の連体形がついたもの ■綱を引きすぐして綱絶ゆるすなはちに-引き上げている綱をゆるめるだけではもどかしく、反対側から引っ張ったので、綱がなくなって落ちてしまったのであろう。「すなはち」は即座に、同時にの意。■鼎(かなえ、てい)- 中国古代の器物の一種。土器、あるいは青銅器であり、竜山文化期に登場し、漢代まで用いられた。通常はなべ型の胴体に中空の足が3つつき、青銅器の場合には横木を通したり鉤で引っ掛けたりして運ぶための耳が1対つくが、殷代中期から西周代前期にかけて方鼎といって箱型の胴体に4本足がつくものが出現した。殷代、周代の青銅器の鼎には通常は饕餮紋などの細かい装飾の紋が刻まれており、しばしば銘文が刻まれる。鼎はもともとは肉、魚、穀物を煮炊きする土器として出現したが、同時に宗廟において祖先神を祀る際にいけにえの肉を煮るために用いられたことから礼器の地位に高められ、精巧に作られた青銅器の鼎は国家の君主や大臣などの権力の象徴として用いられた。■やしまの鼎-「八島の鼎」は八つの島、日本各地のかまどの神様を祭った、神具なのです。■あさましがる-驚きあきれる。びっくりする。 ■からうじて-「息の下」に続く。■ふと-素早い様子。さっと。■紙燭(しそく)-「ししよく」の直音的表記。長さ五十センチ、直径一センチぐらいに削った松の木の先の方に、油を塗って燃やす簡便な照明器具。元の方は紙が巻いてあったので、「紙燭(ししょく)」と書く。
■年を経て云々-かぐや姫の家に中納言が立ち寄る意と、住の江に浪が立ち寄せる意をかける。■住の江-大阪市住吉区住吉神社付近にあった入江。■まつかひなしと-「松」と「待つ」、「甲斐」と「貝」をかける。
■「かひなし」-「…した甲斐が無い」と「貝がない」の意をかけた表記。■匙(かい)-さじ。すくうもの。
■かひはかく云々-「かひ」に「甲斐(効)」を表面の意とし、裏に「匙」の意を持たせる。裏の意は、下句の「すくひやはせぬ」の部分に至って、顕在化する。「掬ふ(すくう)」は「匙」の縁語。表面の意味の「救ふ」をかける。「救いやはせぬ」は「救ってくれないのか、きっと救ってくださる」という反語的表現。だから「かひはかくありけるものを」が生きてくるのであり、後にでてくるようにかぐや姫も「すこしあはれ」と思ったのである。