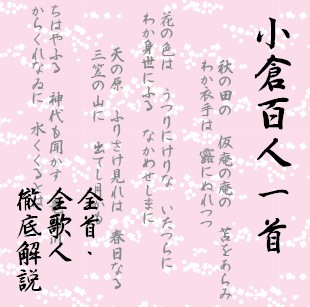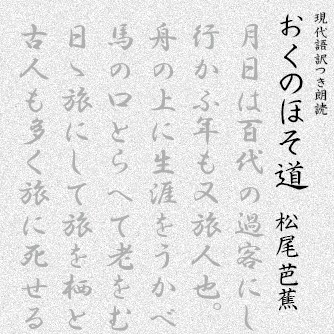青頭巾 二
さるに慈年(ことし)四月(うづき)の比(ころ)、かの童児(わらは)かりそめの病に臥(ふし)けるが、日を経(へ)ておもくなやみけるを痛(いた)みかなしませ給うて、国府(こくふ)の典薬のおもだたしきまで迎(むか)へ給へども、其のしるしもなく終(つひ)にむなしくなりぬ。ふところの璧(たま)をうばはれ、挿頭(かざし)の花を嵐にさそはれしおもひ、泣くに涙なく、叫ぶに声なく、あまりに嘆かせたまふままに、火に焼(やき)、土に葬(ほうむ)る事をもせで、臉(かほ)に臉をもたせ、手に手をとりくみて日を経(へ)給ふが、終(つひ)に心神(こころ)みだれ、生(いき)てありし日に違(たが)はず戯(たわふ)れつつも、其の肉の腐(くさ)り爛(ただる)るを吝(をし)みて、肉を吸(すひ)骨(ほね)を嘗(なめ)て、はた喫(くら)ひつくしぬ。
寺中の人々、『院主(ゐんじゆ)こそ鬼になり給ひるれ』と、連忙(あわただしく)逃(にげ)さりぬるのちは、夜々(よなよな)里に下りて人を驚殺(をど)し、或いは墓(はか)をあばきて腥々(なまなま)しき屍(かばね)を喫(くら)ふありさま、実(まこと)に鬼といふものは昔物がたりに聞きもしつれど、現(うつつ)にかくなり給ふを見て侍れ。されどいかがしてこれを征(せい)し得ん。只戸(いへ)ごとに暮をかぎりて堅(かた)く関(とざ)してあれば、近曾(このごろ)は国中へも聞えて人の往来(いきき)あへなくなり侍るなり。さるゆゑのありてこそ客僧をも過(あやま)りつるなり」とかたる。
快庵(くわいあん)この物がたりを聞かせ給うて、「世には不可思議(ふかしぎ)な事をもあるものかな。凡(およ)そ人とうまれて、仏菩薩の教(をしへ)の広大なるをもしらず、愚(おろか)なるまま、慳(かだま)しきままに世を終(をは)るものは、其の愛欲邪念の業障(ごふしよう)に欖(ひか)れて、或は故(もと)の形(かたち)をあらはして、恚(いかり)を報(むく)ひ、或は鬼となり蠎(みづち)となりて祟(たた)りをなすためし、往古(いにしへ)より今にいたるまで算(かぞ)ふるに尽(つき)しがたし。又人活(いき)ながらにして鬼に化するもあり。
楚王(そわう)の宮人は蛇(をろち)となり、王含(わうがん)が母は夜叉(やしや)となり、呉生(ごせい)が妻は蛾(が)となる。又いにしへある僧卑(あや)しき家に旅寝(たびね)せしに、其の夜雨風はげしく、灯(ともし)さへなきわびしさにいも寝られぬを、夜ふけて羊(ひつじ)の鳴(なく)こゑの聞えけるが、頃刻(しばらく)して僧のねふりをうかがひてしきりに嗅ぐものあり、僧異(あや)しと見て、枕におきたる禅杖(ぜんぢやう)をもてつよく撃(うち)ければ、大きに叫(さけ)んでそこにたふる。
この音に主(あるじ)の嫗(うば)なるもの灯(あかし)を照(てら)し来るに見れば、若き女の打ちたふれてぞありける。嫗泣(うばな)くなく命を乞(こ)ふ。いかがせん。捨てて其の家を出でしが、其ののち又たよりにつきて其の里を過ぎしに、田中に人多く集(つど)ひてものを見る。僧も立ちよりて『何なるぞ』と尋ねしに、里人いふ。『鬼に化した女を捉(とら)へて、今土に埋(うづ)むなり』とかたりしとなり。
現代語訳
ところが今年の四月ごろ、その少年がふとした病にかかり、日が経つにつれ重くなり苦しみ悶えるのを心痛して、国府の官医の中でも主だった名医を迎え、お診せになったけれども、その効験(かい)もなくとうとう死んでしまいました。懐中の玉を奪われ、飾りに頭に挿した花も嵐に奪われたような悲しみで、泣くにも涙は出ず、叫ぶにも声は出ず、あまりの嘆きようで、遺体を火葬したり、土葬したりもなさらず、抱きしめて、その顔に頬ずりし手を取り合ったまま、日を過ごす間に、とうとう精神に異常をきたし、生きていた時と同じように愛撫しつつも、其の肉が腐り爛れていくのを惜しんで、肉をしゃぶり、骨をなめて、最後には食い尽くしてしまったのです。
寺に住む人たちも魂消(たまげ)て、「お住職は鬼になってしまわれた」と、慌てふためいて逃げ去っててしまった後は、夜な夜な里に下りては人を襲って驚かせ、或いは新墓を暴いて生々しい死体の肉を食べる凄まじい有様というものは……鬼というものは昔物語には聞いてはいましたが、実に目の前で鬼になられるのを見てしまったのでございます。しかし、私どもに、どうやってこの浅ましい所業を止めさせることができましょうか。只どの家も暗くなって来たら家ごとに厳重に戸を閉ざしていますので、この頃は下野の国中にも噂が広がり、人の往来もなくなってしまいました。そのようなわけがありまして貴方様を見誤ってしまったのでございます」と語った。
快庵禅師はこの物語を聞かれて、「世の中には奇怪至極な話もあるものですな。およそ人の身と生まれながら仏菩薩の広大な教えも知らず、愚かなまま、捻くれた心のまま死んでいく者は、其の情欲、邪念という成仏の障害となるものに引きづられて、或いは、そのものの過去の本来の動物の形を表して恨みを報い、或いは、鬼となり大蛇となって祟りをなした例は、昔から今に至るまで数えられないほどである。又、人が活きながらにして鬼になる例もある。楚王の宮廷の女官は大蛇となり、王含の母は夜叉となり、呉生の妻は蛾となった。又、むかしある僧が卑賎な家に旅寝をしたときに、その夜は雨風が激しく、灯火もないわびしさに寝付けずにいるのに、夜がふけて羊の鳴き声のみが聞こえてきたが、しばらくして、僧が眠っているかどうかをうかがい、しきりに臭いを嗅ぐものがあった。僧は怪しんで、枕元に置いた禅杖をもってつよく撃ちすえると、大きな叫び声をあげてそこに倒れこんだ。この音に、主の老女が灯を照らして、来てみれば、若い女が倒れていた。老女は泣く泣く命乞いをする。いたし方もない。この事件はそのままにして家を出たが、後日、またついでがあって、其の里を通りかかると、田園(た)の中に人が多く集まっているのが見えた。僧も立ち寄って『何事ですか』と尋ねると、『鬼になった女を捕らえて、たった今土に埋めたところです』と里人が語ったということである。
語句
■愛でさせたまうて-女色を禁じられた仏門では少年が愛欲の対象となった。■さるに-しかるに。■慈-この。■かりそめの-ほんのちょっとした。■国府-古く国ごとに置かれた地方政庁。転じてその所在地を指し、また地名となった例が多い。■典薬-官医。■おもだたしき-重だった人。■ふところの玉を云々-正徳五年刊『艶道通鑑(えんどうつかん)』巻四の「懐の玉をうばわれ、手に持つ花を風に誘はれし思ひ、泣に涙なく、さけぶに声出ず」を利用した修辞。「玉」も「花」も、昔から深く愛するものの比喩として使われた。■挿頭(かざし)の花-髪や冠に飾りとして挿す花。■あまりに嘆かせ云々-「あまり別れの切なるによりて、火に焼き、土に埋るはざもせず、顔にかほをもたせ、手に手を取り組みて」(艶道通鑑巻四)による。■臉-目の下。頬の上。以下、抱擁や接吻などの愛撫のさまを示唆している。■戯れつつ-愛撫しながら。■鬼-ここは食人鬼をさす。■征-制の当て字。■近曾-近頃の意。■国中-下総国一帯に。■過(あやま)りつるなり-見誤る。■不可思議のこと-尋常には考えられないほどの奇怪な事件。■慳(かだま)しき-ねじ曲がった心。「慳(かだま)し」は「直(なほ)し」の反対語で、『雨月物語』を読むキーワードの一つ。■愛欲邪念-情欲、欲望。■業障-成仏の障害となる悪行。■欖(ひか)れて-とらえられ、ひきずられ、の意。■故の形-本来の動物の形。仏教の前世観を前提にしている。■恚(いかり)を報(むく)ひ-恨み怒ること。■宮人-宮廷に仕える女官。楚の荘王は細腰を愛したため、女官がこぞって減食し、餓死したものがあった。それを蛾と変じたとする伝説がある。■王含が云々-王含は武将として著名だが、その母も武勇にたけていた。実は狼の化身だったという伝説。■夜叉-インドから伝わる悪鬼の一種。■呉生が妻は云々-時代不明ながら、呉生の妻劉氏が夜叉となって生きながら鹿の肉を食べたという伝説。■卑しき-卑賎な。■いも-とても。■禅杖-禅僧が持つ短い杖。竹・木・葦で作られ、座禅の時、眠ればこれで打つ。
備考・補足
■『艶道通鑑』巻四をはじめ、『今昔物語集』巻十九・第二、『宇治拾遺物語』巻四第七など、この僧の愛童食肉の部分の原拠はすべて大江定基(後の円通大師)の挿話なのだが、それは日本では古くからあった愛する者の死体変相を観じて発心に至る発芯説話であった。ところがこの僧は、その醜い死体の変相にさえ、愛欲が打ち勝ってしまうのである。それが後出の「直くたくましき性」であろう。ここに愛欲の真髄が描かれる。
■「さるゆゑのありてこそ」と壮主は快庵に語るのだが、この導入部の構想は『水滸伝』第五回の構想を借りたものである。怪しまれた僧がその理由を知るかたちで、怪奇な事件の概略を紹介するという工夫が生きてくると同時に、一部の読者は、『水滸伝』のその部分(豪傑魯智深(ろちしん)の旅)のイメージを連想することになる。もちろん、快庵禅師は魯智深とは違うのだが、『雨月物語』の独自な小説としての奥行とイメージを創り出すことになる。
前の章「青頭巾 一」|次の章「青頭巾 三」
雨月物語 現代語訳つき朗読