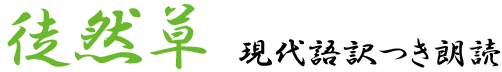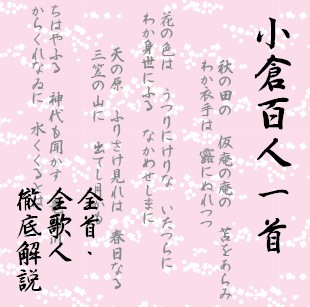第十九段 折節のうつりかはるこそ
■『徒然草』朗読音声の無料ダウンロード
【無料配信中】福沢諭吉の生涯
■【古典・歴史】YOUTUBEチャンネル
折節のうつりかはるこそ、ものごとにあはれなれ。
「もののあはれは秋こそまされ」と人ごとにいふめれど、それもさるものにて、今一きは心もうきたつものは、春の気色にこそあめれ。鳥の声などもことの外に春めきて、のどやかなる日影に、墻根の草萌えいづるころより、やや春ふかく霞みわたりて、花もやうやう気色だつほどこそあれ、折しも雨風うちつづきて、心あわたたしく散り過ぎぬ。青葉になり行くまで、よろづにただ心をのみぞ悩ます。花橘は名にこそ負へれ、なほ梅の匂ひにぞ、いにしへの事も立ちかへり恋しう思ひ出でらるる。山吹のきよげに、藤のおぼつかなきさましたる、すべて、思ひ捨てがたきこと多し。
▼音声が再生されます▼
口語訳
季節の移り変わりこそ、何事につけても味わい深いものである。
「もののあはれは秋がまさっている」と誰もが言うようだが、それも一理あるが、今ひときわ心浮き立つものは、春の風物でこそあるだろう。鳥の声なども格別に春めいて、のどかな日の光の中、垣根の草が萌え出す頃から、次第に春が深くなってきて霞がそこらじゅうに立ち込めて、花もだんだん色づいてくる、そんな折も折、雨風がうち続いて、心はせわしなく思ううちに散り過ぎてしまう。
青葉になり行くまで、何かにつけてひたすら人の心を悩ませる。花橘は昔を思い出させるよすがとして有名だが、それでもやはり梅の匂いにこそ、昔のことも今が昔に立ち返って恋しく思い出される。山吹が清らかに咲いているのも、藤の花房がおぼろにかすんでいる様も、すべて、思い捨てがたいことが多い。
語句
■折節 季節。 ■もののあはれは秋こそまされ 「春はただ花のひとへに咲くばかりもののあはれは秋ぞまされる」(拾遺集・雑下・読人しらず)。 ■さるもの 一理ある。道理がある。 ■あめれ 「あるめれ」の音便。あるようだ。あると思われる。 ■日影 日の光。 ■やや 次第に。 ■気色だつ 兆候が見える。花が咲き始める。 ■折しも。 まさにそんな折も折。間投助詞「し」+係助詞「も」で脅威。 ■心あはたたしく せわしなく。清音で読む。「ことならば咲かずやはあらぬ桜花見るわけさへにしづ心なし」(古今集・春下・紀貫之)、「ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ」(紀友則)の心。 ■花橘 昔を思い出すよすがとして歌や物語によく登場する。「五月まつ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」(古今・夏・読人知らず)、『和泉式部日記』の冒頭で、和泉式部と冷泉天皇第四皇子敦道親王の出会いのきっかけとなったことでも有名。『伊勢物語』にも花橘の歌に基づく章段がある。 ■名にこそ負へれ 有名だが。 ■梅の匂ひにぞ… 「人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける」(古今・春上・紀貫之)に基づき、梅の香を昔を思い出すきっかけとしている。 ■藤のおぼつかなきさま 藤の花房がぼうっとかすんでいる様。山吹のあざやかな色彩と、藤のおぼろな色彩を対比させたもの。
「灌仏会の比(ころ)、祭の比、若葉の、梢涼しげに茂りゆくほどこそ、世のあはれも、人の恋しさもまされ」と人のおほせられしこそ、げにさるものなれ。五月、あやめふく比、早苗とるころ、水鶏(くいな)のたたくなど、心ぼそからぬかは。六月(みなづき)の比、あやしき家に夕顔の白く見えて、蚊遣火(かやりび)ふすぶるもあはれなり。六月祓(みなづきばらえ)又をかし。
口語訳
「四月の灌仏会のころ、葵祭のころ、若葉の梢が涼しげに茂っていく頃こそ、世のあはれも、人恋しさも高まるものだ」と、ある人がおっしゃっていたが、まったくその通りだ。
五月、屋根にあやめを葺く端午の節句、六月の早苗を取って田植えするころ、水鶏(くいな)のたたく声など、心細くないことがあろうか。みすぼらしい家に夕顔の花が白く見えて、蚊遣火をいぶしているのも趣深い。六月の夏越の祓も味わいがある。
語句
■灌仏会 陰暦四月八日の釈迦誕生祭。「仏生会(ぶっしょうえ)」とも。釈迦の像の頭に香水をそそぐ。 ■祭 賀茂祭。陰暦四月中の酉の日に行われた。 ■あやめふく比 五月五日端午の節句の行事として、邪気払いのために屋根にあやめを葺いた。 ■早苗とる頃 稲の苗を苗代から出して田に植える。六月ごろのこと。 ■水鶏 水鳥の一で諸説あるがヒクイナ。「キョッキョッ」という声が戸を叩いているようなので「鳴く」ではなく「叩く」といわれる。田植えの時期の夕方から深夜にかけて哀愁ただよう声で「叩く」ので、恋愛感情を高めるものとされた。 ■あやしき家に夕顔の白く見えて 『源氏物語』夕顔の冒頭を思わせる。源氏の随身が荒れ果てた家に夕顔が白く咲いているのを見て源氏に言った。「かの白く咲けるをなむ、夕顔と申し侍る。花の名は人めきて、かうあやしき垣根になむ、咲き侍りける」 ■蚊遣火 蚊を追い払うために草などをいぶした。 ■ふすぶる いぶす。 ■六月祓 六月の晦日の日に水際で行われる行事。「夏越(なごし)の祓(はらえ)」とも。上賀茂神社・下賀茂神社が有名。茅の輪くぐりをして邪気を祓ったり、「人形(ひとがた)」とよばれる紙を衣類にこすりつけて邪気をうつし、水に流したりする。百人一首に「風そよぐならの小川の夕暮れはみそぎぞ夏のしるしなりける」(従二位家隆)が有名。
七夕まつるこそなまめかしけれ。やうやう夜寒(よさむ)になるほど、雁鳴きてくるころ、萩の下葉(したば)色づくほど、早稲田(わさだ)刈り干すなど、とり集めたる事は秋のみぞ多かる。又、野分(のわき)の朝(あした)こそをかしけれ。
言ひつづくれば、みな源氏物語・枕草子などにことふりにたれど、同じ事、又今さらに言はじとにもあらず。おぼしき事言はぬは腹ふくるるわざなれば、筆にまかせつつ、あぢきなきすさびにて、かつ破(や)り捨つべき物なれば、人の見るべきにもあらず。
口語訳
七夕をまつるのは、とても優雅なことだ。だんだん夜が寒くなってくる季節に、雁が鳴いて飛び渡ってくるころ、萩の下葉が黄色く色づく頃、早稲の田を刈り取って干しているのなど、趣深い事物は、秋ばかりに集中している。
また、野分の吹いた次の朝はとても情緒がある。
言い続ければ、みな源氏物語・枕草子などに語りつくされて今更というものだが、同じことをまた今一度絶対に言わないと決めているわけでもない。筆にまかせて書くものの、つまらない手すさびであり、すぐに破り捨てるべき物なので、人の見るようなものでもないのだ。
語句
■七夕 七月七日の夜。一年に一度だけ会うという牽牛・織女の二星をまつる行事。遣唐使によってもたらされた。乞巧奠(きこうでん)とも。 ■なまめかし 優雅だ。 ■やうやふ夜寒に 「夜を寒み衣かりがね鳴くなへに萩の下葉もうつろひにけり」(古今集・秋上・読人知らず) ■萩の下葉 萩の下のほうの葉。 ■早稲田刈り干す 早稲の田を刈り取って干す。 ■とり集めたる事 多くの(あはれな事が、秋に)集中しているさま。「白妙の衣打つ砧の音も、かなたこなたに聞きわたされ、空飛ぶ雁の声、取り集めて、忍びがたきこと多かり」(『源氏物語』夕顔) ■野分 晩秋から冬にかけて吹く強風。 ■ことふりにたれど 言古りにたれど。言い古されてしまっているが。松尾芭蕉『おくのほそ道』松島に「そもそもことふりにたれど…」。 ■おぼしき事言わぬは… 心に思っていることを言わないのは腹がふくれる思いなので。「おぼしきこと言わぬは、げにぞ腹ふくるる心地しける」(『大鏡』)古くからあったことわざと思われる。 ■あぢきなき つまらない。 ■筆にまかせつつ 筆にまかせて書くものの。「つつ」は逆説的ニュアンス。 ■かつ破り捨つべき すぐに破り捨てるべき。さて冬枯の気色こそ秋にはをさをさおとるまじけれ。汀の草に紅葉の散りとどまりて、霜いと白う置ける朝(あした)、遣水(やりみず)より烟(けぶり)の立つこそをかしけれ。年の暮れはてて、人ごとに急ぎあへる比(ころ)ぞ、又なくあはれなる。すさまじきものにして見る人もなき月の、寒けく澄める廿日(はつか)あまりの空こそ、心ぼそきものなれ。御仏名(おぶつみょう)・荷前(のさき)の使たつなどぞ、あはれにやんごとなき。公事(くじ)どもしげく、春のいそぎにとりかさねて催しおこなはるさまぞいみじきや。追儺(ついな)より四方拝(しほうはい)につづくこそ面白けれ。つごもりの夜(よ)、いたう暗きに、松どもともして、夜半(よなか)過ぐるまで人の門(かど)たたき、走りありきて、何事にかあらん、ことことしくののしりて、足を空に惑ふが、暁がたより、さすがに音なくなりぬるこそ、年の名残も心ぼそけれ。なき人の来る夜とて魂(たま)まつるわざは、この比(ごろ)都にはなきを、東(あずま)のかたには、なほする事にてありしこそあはれなりしか。
かくて明けゆく空の気色、昨日に変りたりとは見えねど、ひきかへめづらしき心地ぞする。大路(おおち)のさま、松立てわたしてはなやかにうれしげなるこそ、またあはれなれ。
口語訳
さて冬枯の気色こそ秋にほとんど劣らないだろう。水際の草に紅葉が散り留まって、霜がたいそう白く下りている朝、遣水から水蒸気が立っているのは大変趣深い。年も暮れてしまって、人は誰もお互いにあわただしい頃こそ、比べようもなく趣深い。殺風景で興ざめなものは、見る人も無い月が、寒々と澄んでいる十二月二十日過ぎの空こそ、心ぼそいものである。
宮中で諸仏の名を唱える御物名(おぶつみょう)・天皇や皇族の陵に諸国から献上された初穂を奉る勅使が立つのなどは、情緒深く高貴なものだ。
宮中の諸行事が、春の準備の忙しい時に重ねて行われるさまこそ、結構なことである。大晦日の追儺式から、元旦の朝の四方拝まで、一続きに行われるのは実に面白い。
大晦日の夜、たいへん暗い中に、松明をともして、夜半過ぎまで人の家の門を叩き、走り廻って、何事だろうか、大声で騒ぎ立て、足が地につかないほど走り廻るが、明け方には、やはり音もなくなってしまうのは、過ぎ去る年の名残も心細いことだ。
亡くなった人の霊魂が帰ってくる夜ということで魂を祭る行事は、このごろ都では行われないが、東国には、いまだに行うことがあるというのは、情緒深いことだ。
こうして明け行く空の気色。昨日に変わったとはみえないけれど、打って変わって実に清新な心地がするものだ。都大路のようすも、門松を家々に立てて華やかにうれしげなのこそ、趣深いものだ。
語句
■をさをさ ほとんど。 ■遣水 邸内に導き入れた細い水流。 ■すさまじきもの 殺風景で興冷めなもの。 ■御仏名 十二月十九日から三日間、清涼殿で諸仏の名を唱える行事。 ■荷前 のさき。十二月中旬に、諸国から献上された初穂を、天皇や皇室関係の陵に奉る勅使。 ■いみじ 結構なことである。 ■追儺 十二月晦日の夜、朝廷で行われる鬼やらいの儀式。 ■四方拝 元旦の寅の刻(午前四時)に清涼殿の庭で行われる儀式。天皇が北斗七星を拝して、天地四方の神々を拝する。村上天皇の代から清涼殿東庭で行われた。 ■松どもともして この風習は何なのか不明。大晦日の追儺式で、こういう習慣があったものか? ■ことことしくののしりて 大声で騒ぎ立て。 ■足を空に惑ふが 足が地面につかないほど、大急ぎで走り廻って。 ■ひきかへ うってかわって。 ■めずらしき 清新な。
メモ
■四季折々のよさ。枕草子を意識。